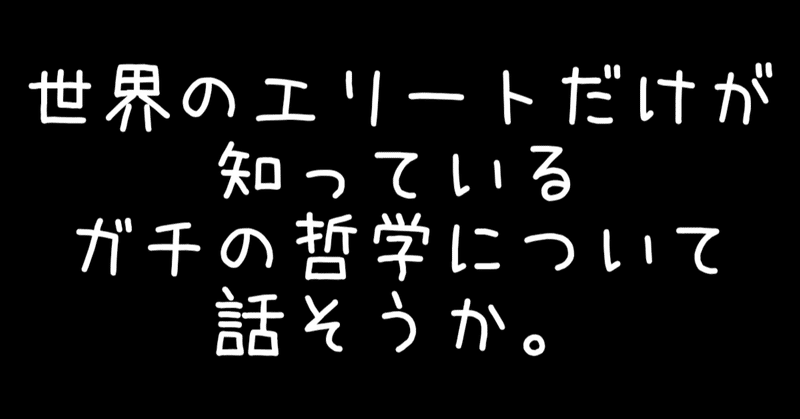
イデア論が不自然な世界をつくる
幻想を現実よりも大事にすることを、アイディアリズムIdealismといいます。『小学館ランダムハウス英和辞典 第1版』(小学館 1984年)は、Idealismを観念論、唯心論と訳しています。さらにむずかしい専門書などは、実在論と書いています。
誰が訳したのか知りませんが、実在もなかなか意地の悪い訳語ですね。実在、なんていわれても「はあ、そうですか」で終わってしまう。さらにタチの悪いことに、今度は実在で調べるとRealismなどと訳語がでてくる。もうなにがなにやら。なんでIdealism=実在=Realismなんてことになる?めちゃくちゃです。こういうことばっかだから、哲学は意味不明になるんですよ。けっして読み手がアタマ悪いわけではない。もともと訳されかたがめちゃくちゃなんです。
Idealism=実在の時点でわけわからんのに、今度は「いや!Realismなんだ!」と混乱に拍車をかけてくる。なんだそりゃ。Realというのは、もともとモノゴトの内容、性格、状態をあらわす単語です。「AはBだ」のときのBのことです。質のことです。Real=質です。このことはマルティン・ハイデガー(1889-1976)が証明しました。だからReal と実在は関係ありません。
だからここではRealのことなんか忘れてください。サクッと説明すると、実在(Idealism)とは、個体が幻想化した姿のことです。抽象しすぎてわかりづらいかもしれませんね。身近なとこでいえば、実在とは恋愛のことです。
人間の生殖行為は、性器に惹かれあった結果ではありません。恋する相手の肉体、タイプの顔立ち、笑顔だったり安らぎだったり、哀しみを共有したり、呼吸で浮き沈みする胸だったり、醸しだされた全体の雰囲気を美しさと呼んでひとつになりたいと願う。雰囲気なんてホントはどこにもないのに。あるのは性器だけなのに。
動物としては生殖だけが目的のはず。でもそんなことは考えたくない。雰囲気に惹かれて、美しさに惹かれて「ひとつになりたい」と願った以上、その美しさは存在する。愛している。愛の要素を個別に分解してしまえば、それはまたべつのものに変化する。たんなる部分の集合になってしまう。
そうじゃないんだ。たんなる部分の集合ではなくて、そのひと自体がそのひとの魅力なんだ。これが実在です。
愛は愛として、美しさは美しさとして存在する。全体としてのあなたを愛している。これが、アイディアリストidealistの主張です。「実在論者」という日本語訳からは全然見えてこない主張ですね。だからこういうところがイデア論のやっかいなところといいますか、それはそれでたしかにまちがっちゃいない。私だって人を性器で判断などしていません。雰囲気とか大事です。
さっき、たんなる部分の集合(=全部)ではなく雰囲気までふくめた全体。これが実在の特徴だといいました。
「全部」と「全体」はちがうんですよ。「全体」とは、雰囲気までふくめた幻想をしめすコトバなんです。実際に目のまえになくとも、ふくらんだ幻想がそこにあるならば、それを「全体」といいます。この全体が瓦解したときが、バブル崩壊。
いったん先物市場に出されたトウモロコシは、実体としての価値(=食料)からかけ離れた行動をとります。トウモロコシは巨額の投機の対象となって、ある者を富ませ、ある者を破滅させる金融のバケモノへと変貌します。これがトウモロコシが全体化した姿です。幻想によって究極にまで肥大化された姿。
いっぽう、「全部」は目のまえにある現実をしめします。八百屋にならんでいるトウモロコシのことですね。トウモロコシそのもの。幻想の余地がない。食べるだけ。全部と全体はちがう。そして全体は全部以上のもの。これがIdearism=実在の正体です。全体は、幻想化されることで全部以上なんです。この発想の源流こそプラトンです。
『西洋思想大事典 第4巻』p462(平凡社 1990年)
有機的統一にはもう一つの公式化が必要である。それは『全体は部分の総和以上のもの』という公式になって現代によく繰り返されているが、この格言の作者は不明である。だが、これときわめて近いことをプラトンは述べているー
『全部とは全体ではない』(『テアイテトス』204B)そして文脈から見れば、この『全部』とは部分の総和のことである。美学の問題としては、それは、孤立した断片をただ相互に付加してみたところで芸術作品が生まれるわけではなく、個々の部分をつなぐには全部を結合する一本の本質的連鎖が必要であることを意味する。
プラトンがめざしたのは全体。部分を越えて肥大化した幻想体です。恋愛も全体。あとで書きますが社会も全体です。どっちも幻想によって極端に肥大化されています。
恋愛も社会もプラトンが生みの親。どちらも幻想化の能力を持っている。しかしプラトンの執念はさらに次元を突き抜けていきます。幻想のそのさきへと到達します。全体という幻想すらも、じつは思い出なんです。なんの思い出?イデアの思い出です。
恋愛も社会も思い出なんです。原初の聖なるもの=イデアの思い出として、いまたまたま現代に降りてきているだけ。
ならばイデアとは?
三角形を描いてみてください。分度器をつかって、あるいは定規をつかって描いてみてください。描いてみて気づくけども、どんなに完璧をめざそうと奮闘しても、完璧な三角形など描けはしない。
どんなに完璧に見えても、微小な狂いがある。0,00001ミリの狂いが生じる。この狂いは、誰にもどうしようもない。完璧主義者が髪をふりみだして顕微鏡をつかってヒステリックに集中しても、微細の奥の奥の正確さは、はかりがたい。
だから人間とは完璧ではなくて、完璧な世界は、人間には触れられないところに存在する。人間はイデアを思い出しているに過ぎない。完璧な世界のおぼろげな思い出があるだけ。
だから完璧な世界=イデアの著述としての数学がある。もはやたんなる概念の数学だけがイデアにもっとも近い。「数式は美しい」なんていう人がいるけども、これがイデア論です。
だから、いま私が見ている夕陽に映える草木も完璧とはほど遠く、もろくも変わってしまう不完全な代替品。そこに滅びの美などない。不完全だから滅びる。滅びることのない、永遠の存在はただただ人には触れることのできないイデアだけ。現実を突き抜けたイデアだけが真・善・美。
だから滅びの夕陽など美しいはずがない。神聖さのため、どのようにも改変可能。べつに塗りつぶしたってかまわない。イデアに近づけるために塗りつぶせばいい。イデアは、自然よりも上位の神聖世界なんです。
自然よりも上位のイデア。これが哲学の中核です。そんなもの不自然に決まっています。
ここまで「自然」と「不自然」というコトバをなんとなく使ってますので、きちんと定義しておきましょう。自然というのは、たんに外界に広がる草木や昆虫などをしめすコトバではありません。
『反哲学入門』p59(木田元著 新潮文庫 2007年)
この「自然」という言葉が、もともとは「芽生える」「花開く」「生成する」といった意味の動詞phyesthaiから派生した言葉だというところからも、ソクラテス以前の思想家たちの時代のギリシア人がありとしあらゆるもの、つまり存在者の全体の真のあり方をどう考えていたかがうかがわれます。つまり、この時代のギリシア人は、すべてのものは生きて生成してきたと考えていたのです。これは、さっき丸山さんが「なる」という基本動詞で取り出したパターンと、かなり似通った発想でしょう。
これまで何度も繰りかえしてきましたが、プラトンが生成もしなければ消滅もしない<イデア>という超自然的な原理を設定してから後は、「自然」はそうした原理にのっとって形成されるたんなる材料・質料であり、たんなる物質つまりたんなる質料としての物に過ぎないという考え方が成立したわけです。
つまり、自然とは「なる」の状態のことです。上の引用文に丸山眞男のことを語っている部分があります。丸山氏は「なる」「うむ」「つくる」という3つの基本動詞が、人間がモノゴトを発想する際の基本パターンだといいます。そのうち「なる」という、ほおっておいても作動するこの世の原理のことを、自然と呼ぶのです。
「自然=なる」は連続する運動のこと、けっして分割できない、とまることのない流動のことです。そしてこっちが反哲学の立場です。プラトン以前の、古代の思想でもあります。たとえば最古のギリシア思想家タレスは「万物の根源は水だ」といいました。水という、けっして分割できない流動体を根源においているわけです。万物流転。欧米式の考えかたが幸いにもまだ浅い日本人には、スッと理解できる考え方でもあります。
いっぽう、哲学の立場は反自然です。こちらはまったく動きません。静止した世界観です。静止した絶対のイデアが、世界を「つくる」という発想こそ哲学です。のちのGodのことです。イデアやGodが自然よりも上位であるからこそ、「自然や世界をいくらでも改変可能だ」とする発想が生まれました。キリスト教圏からはじまった近代には、こちらの考えかたが濃厚です。そして、このことを不自然といいます。自然の「なる」を分断してアチコチにつぎはぎをするのが「不自然」であり、不自然こそが哲学の根本性格です。
第2回終わり(全20回)
次回「恋愛はカルト宗教〜神聖なモノはだいたいウソ〜」へつづく。
支援ありがとうございます。最高品質でお届けします。
