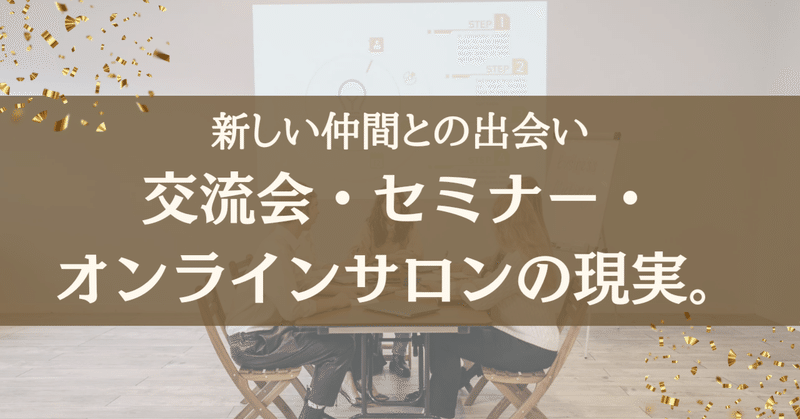
【新しい仲間を作る】交流会・セミナー・オンラインサロンの現実。
はじめに
こんにちは。あと2日で8月も終わるが、本州では30度を超える残暑が続く。

一方、北海道では秋雨前線のおかげか日中でも30度を切り、暑さのピークからは一件落着。だがしかし。

9月の初めには台風が日本列島に直撃。特に沖縄では気を付けないとならない。
北海道も秋雨前線とか言ってる割にはそこまで降っていない。
今回のテーマは「交流会・セミナー・オンラインサロンの現実」です。この後ゆっくりご覧ください。
人生において必要な人との関わりとは?
学生時代に必ず関わる友達
さて、ここから本題。まずは学生時代の話から。その話題には就学前の小さい子供も含みます。
まずは就学前。親や兄弟も世話が大変であること、自立を促すためにも保育園、または幼稚園に入るでしょう。お友達との関わりはここから始まる。
ごっこ遊びに遠足などの行事、その他集団生活において同年代の子と喧嘩したり、仲直りを繰り返しながら絆を深める。
それが卒園まで続く。
小学校に入るとまた別の仲間と関わることになるだろう。
次に小学生。ここから集団生活が本格化。授業もここから始まる。
朝は8:00くらいから登校。8:30くらいに朝の会を始めるところが多い。クラス全員の体調チェック、1日のスケジュール確認など先生から連絡事項が伝えられる。
朝はだいたいこの流れ。
8:45頃に授業を始める学校が多く、1コマ45分。その間に5~10分休憩がある。その間に準備をしたり、トイレを済ませたり。
小学校では中休みもあるので、その時間帯を使って友達と体を動かして遊んだり、会話をするなど3時間目が始まるまでに疲れた脳をリフレッシュ。

友達と関わる場面は他にもある。それは一体何かわかりますか?

正解は、給食の時間、並びに昼休み、掃除の時間です。
まず、給食と掃除について。給食当番については時間制限こそ設けられているものの、クラスの友達と協力して行うことの大切さ、自主的に動くことで味わえる達成感、約束を守ることがいかに大切かを学ぶことができる。
昼休みの場合は、中休みと同じように友達と会話したり、図書室で過ごすことが多い。
形は違えど、これらの時間で友達と交流するきっかけとなり、仲良くなることも多い。
また、放課後にはクラブ活動をする学校も多く、運動系や文化系、そのどちらかに入って1年間活動。
同じ趣味を持った仲間と仲良くなるきっかけにもなるでしょう。
とりあえず、小学校での関わり方はこんな感じ。
そして、中学生以降の部活動へと続き、義務教育を終えた高校、大学ではまた違った仲間と関わる。それまでには受験に合格しないとならない。
僕自身は、同じ発達障害を持った同期や先輩がいる高等養護学校に通っていたせいもあってか、給食は最後まで出た(他だと出ないことが多い)。
正直、学食を買って食べたり弁当を作ったりもしてみたかったが、今思えば浪費癖が激しく、お金の管理もそれほどできていなかったので、間違ってはいない気もする。
それも普通であれば、上記のような関わり方ができ、プライベートでも仲良くなれるはずなのに。
人の気持ちすら分からない僕に、同期と何を話せばよいのか。そればかりが頭によぎってモヤモヤする。

学生時代に関わるのは、学校のお友達や先生だが、他にも人と関われる場所はいくつかある。
例えば、僕の場合は「放課後デイサービス」や「音楽サークル」などが第3の居場所だった。
放課後デイサービスの場合、同じ発達障害を持ったお友達や愛情を注いで支援してくれる支援員。活動を通して仲良くなるきっかけを作ることができたのはとても良い思い出。

音楽サークルやその他習い事にも所属していたが、ピアノ以外はすべてやめてしまった。
中には塾に行く人もいるだろう。
学生のうちから第3の居場所を作っておいた方が良いよ、という話はこの後触れる。
社会に出ると上司に叱られることも多くなる
10年以上にわたる学生生活を満喫した後は、生活のために「働く」という大変な日々が待っている。
一般のサラリーマンにはそれが顕著に出ている。

また、社会人になると上司に叱られることも多くなる。でも、それは期待されているからではないか。僕はそう思います。
会社に入ったら歓送迎会にも参加し、人間関係を築く。それも一般常識だと言われてしまった。高校でも先生から教わっている。人との関わりを苦としないのならまだ、もっと別の形を作れないのだろうか。
極端な話、一人の方が集中できるのなら、1人部屋を作ってそこにデスクを置くとか。飲み会なら無理に誘わないとか。
ただ、どんな形であれ、人間関係を築くことが大事であることは確かに言えてる。
そんなこと言われたって…。障害を持っていなくとも、会社と自宅の往復でストレスを感じる人はいる。
まあ、飲み会なら会社での愚痴を吐きながらお酒を飲む。僕はそんなイメージが強い。いくら同僚であるとはいえ、こんなんだったら参加したくない。

「いっそのことなら転職すれば?」そんなことを言いたくなるけれど、基本的に長く会社に居続けないとならない。
ということで、前置きが長くなってしまったが、この後本題に入る。今回のテーマは「交流会・セミナー・オンラインサロンの現実」です。
それでは続きをご覧ください。
学校・仕事でのストレスを解消してくれる「第3の居場所」
さて、皆さんにとっての居場所は会社と学校、自宅以外に何を思い浮かべる?
僕は、「習い事」「SNS」「交流会」「セミナー」「オンラインサロン」などを思い浮かべます。
最近は「こくちーずプロ」というサービスから交流会・セミナーに申し込み、第3の居場所を自ら探しています。
新たな出会いを作る「交流会」「セミナー」「オンラインサロン」に秘められた現実
さて、ここからは交流会・セミナー、そしてオンラインサロンの現実を書いていきたいと思います。
まずは交流会について。僕が感じたのは、同じような趣味や目的を持った仲間が集まる場所だということ。
それが故に、初対面の参加者と気軽に話したり、主催者の話も聴ける貴重な場面にもなりうる。
しかし、連絡先を登録しておかないと疎遠になってしまうリスクもあるので注意が必要。

次にセミナーについて。これは成功者に直接出会い、話を聞く講演会の一つ。自分で調べる以上にノウハウを得られるため自己投資の1つでもある。
デメリットとしては、交流会と比較して参加者との交流機会が少なくなってしまうことを挙げる。

そして、最後に例として挙げるのがオンラインサロン。一方的な発信になってしまいがちなファンクラブとは違い、主宰、参加者双方が仲良く発信し合えるコミュニティの場となる。
もしかしたら参加者のみならず主宰者と仲良くなれるかも?!

だが、そんなオンラインサロンにも注意が必要な場面がある。同じ志を持った価値観の近いメンバーによるクローズドなコミュニティのため秘密を漏らしてはならないのだ。
チームを乱すなどもっての外だ(最悪の場合、強制退会も)。

グループの名前こそ出さないが、今回は例として「交流会」「セミナー」「オンラインサロン」の現実を正直に書かせてもらった。
第3の居場所は他にもSNSや習い事のサークルなどがあり、会社と自宅の往復だけでは体験しづらいような場所にも一歩踏み出すことができる。
そして、新しい仲間とも知り合える。こんなに幸せな場所って、そうないと思うわ。
おわりに
これまで単独での発信を続けてきた僕だったが、先月から交流会とセミナーに参加するようになった。それはなぜか。
自分の発達障害や難病を知ってもらうためには横のつながりも必要だという結論に至ったから。
先日、LGBTが集まる交流会の参加メンバーにInstagramのアカウントをフォローしていただき、現にストーリーズまで見ていただいている。
それは「当たり前」ではなく「ありがとう」。
自分のコンサートに来てくれるのだって、転んだ時「大丈夫かい?」なんて声をかけてくれるのも「ありがたい」事なんだ。
それが「大丈夫かい?」ではなく放っておく、中には笑う人もいるだろう。
だけど、もう、いつとは言わないし、誰とも言わないけど、交流会への参加を重ねて少しずつ忘れていくだろう。
価値観は違えど、横のつながりってやっぱり必要何だな。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
