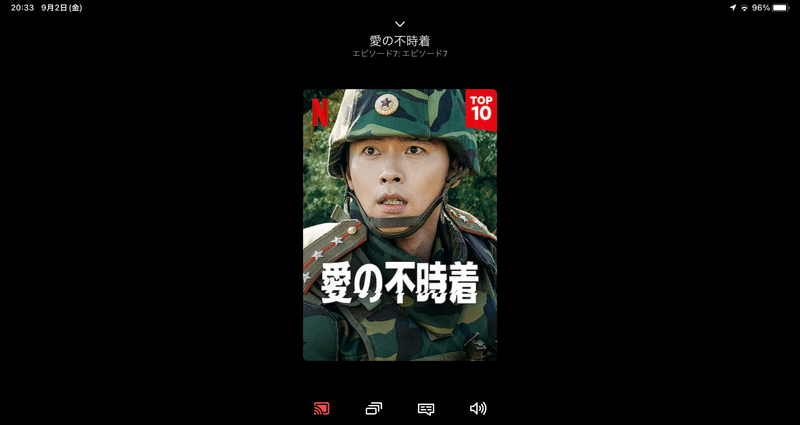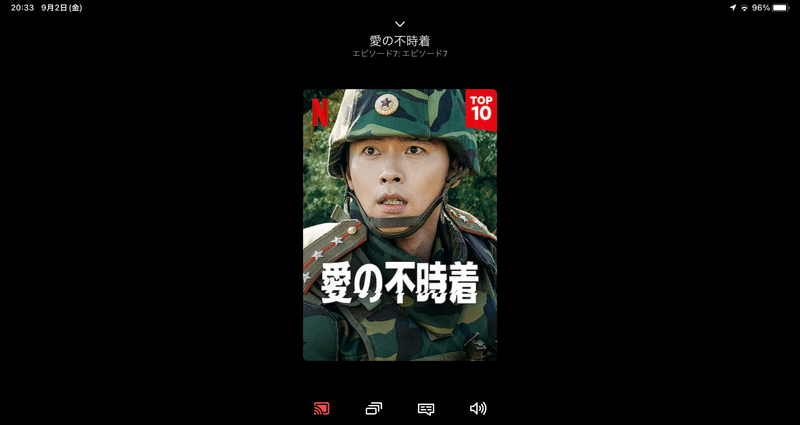「自由への手紙」(オードリー・タン[語り])を読むー「誰かが決めた『正しさ』はいらない」
若干35歳で台湾のデジタル担当大臣に就任し、今回のパンデミック対策でマスクの在庫確認ができるアプリを導入した人として名を馳せた。さらには、高いIQ指数(測定可能な測定値160)を持ち、学校教育は14歳で自主退学。そして自身はトランスジェンダーであることを公表している。
何から何まで我々とは違ったバックグラウンドを持つタン氏の自由論。でも読み終わって思ったことは、普段自分が感じていたこととおんなじだということである。ずっと自分が変だと感じたり不快に思っていたこと、もやもやして