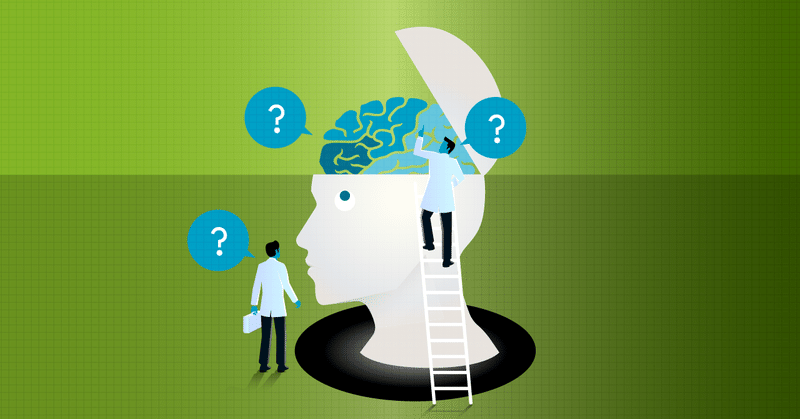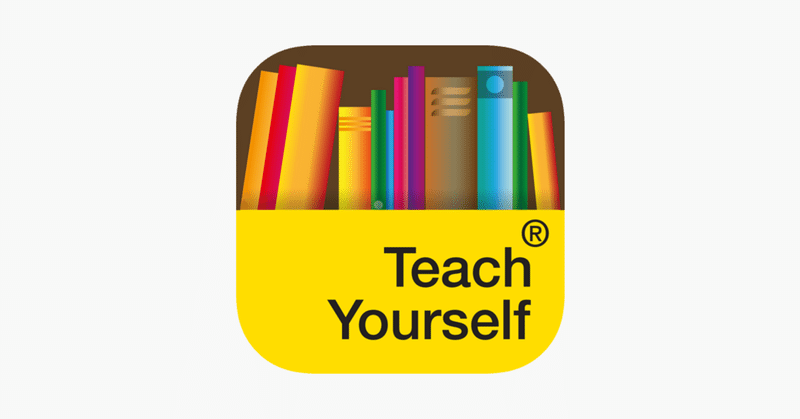- 運営しているクリエイター
#今日ときめいた言葉

今日ときめいた言葉144ー「生い立ちや信念や格好で切り捨てられたりしない、男か女でふるいにかけられない社会になることを私は心から願います」(朝ドラ「虎に翼」から)
ドラマの中でこの言葉を聞いた時、ちょっとウルッとしてしまった。今から86年も前、女性の立場がずっと困難だった時代にこのような意見表明をしたのだから。 でもさらに100年以上も前に大逆事件で逮捕された金子文子は、二十歳にも満たない年で以下のような意見表明をしている。享年23歳。 「私はかねて人間の平等ということを深く考えております。人間は人間として平等であらねばなりませぬ。そこには馬鹿もなければ、利口もない。強者もなければ、弱者もない。地上における自然的存在たる人間としての
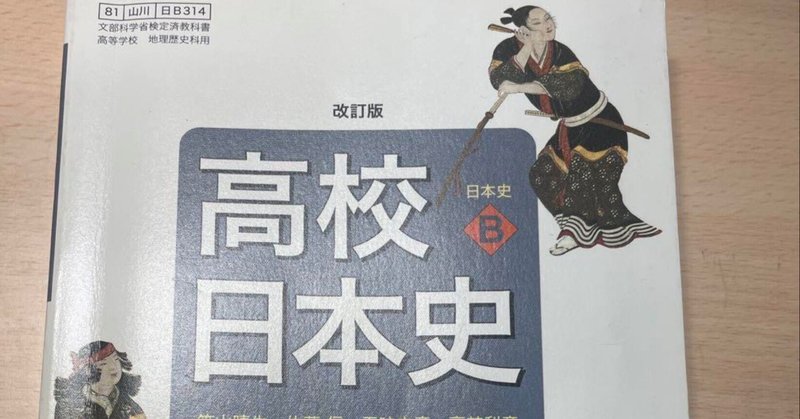
今日よみがえった言葉124ー「歴史の教科書はどうして縄文時代から始まるんでしょうね。近現代から始まってもいいと思うんですがね」
(タイトル写真は山川出版社のサイトから転載) 私の高校一年の時の地理の先生の言葉である。先生は日本史も世界史も教えていたが、一年生の我々が習ったのは地理であった。後で知ったのだが、郷土の歴史家で史跡や遺構の発掘などで著名な人物だったようだ。ちょっと前、戊辰戦争の戦場になった郷里の遺跡のことで新聞に載った記事を読んだことがある。 地理の授業もかなりユニークで、教科書中心ではなく先生が話すことの方が重要だった。試験についても「僕は試験はやらなくてもいいと思うんですけどね。でも

今日ときめいた言葉110ー”What do you mean they don’t nap?”「え、どういうこと。(学校では)皆んなお昼寝しないの?」😍😍
長女の第4子の3歳児がこのように叫んだ。彼女は保育園でキッチリお昼寝をさせられているから、当然姉や兄たちも学校でお昼寝をしているんだろうと信じていたらしい。自分がそうだから、他のみんなも同じだろうと思っていたところが笑える。だから学校ではお昼寝の時間がないと知って衝撃を受けたのだ。彼女にしてみれば、「なぜお昼寝しないのか」が大いに疑問だったのだろう。 日本のように「お兄ちゃん、お姉ちゃん」と言わずにfirst name で呼び合うことが長幼の意識をなくさせ、姉や兄を普通に呼