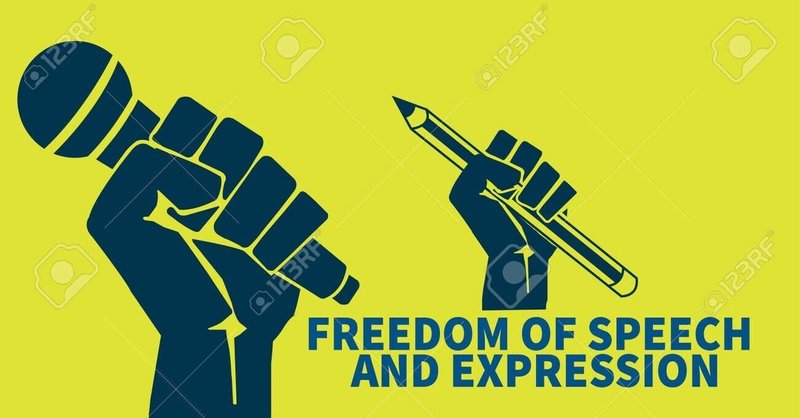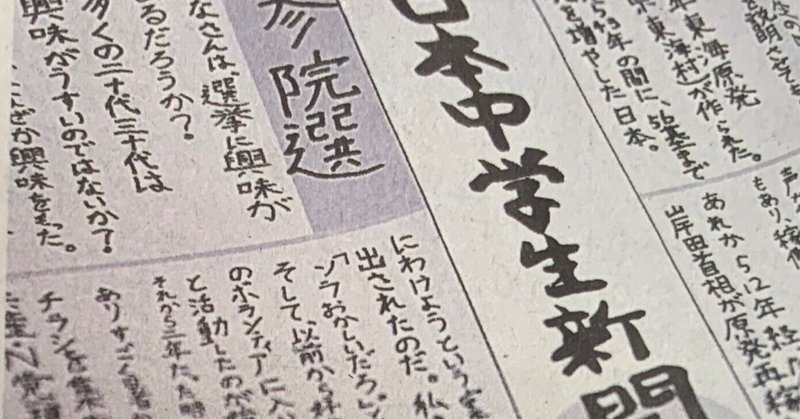- 運営しているクリエイター
#民主主義
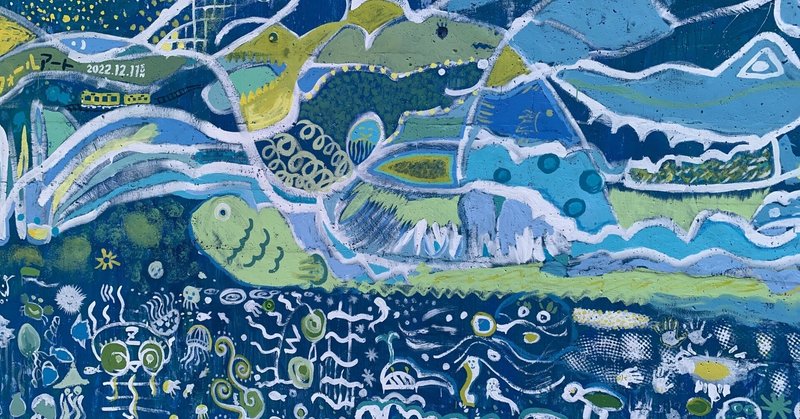
今日ときめいた言葉28ー「為政者と対峙するジャーナリズムは憲法が求める役割 鋭い追求こそが政治記者へのリスペクトをもたらす」
この言葉、ニューヨーク・タイムズの政治エディター、デイビッド・ハルブフィンガー氏の言葉だそうだ(2023年1月25日付 朝日新聞 論座の一推しから) 記事は続けて言う。氏がジャーナリズムの世界に入ったのは、 「『番犬(Watchdog)としての監視』が重要と考えたから。記者が取材源と親しくなり過ぎてへつらうリスクを指摘し、為政者に執拗に問いを重ねる『根性』がないなら『この仕事はやらないほうがいい』」と。 アメリカの民主主義への脅威が高まっているからこそ、番犬の役割もより