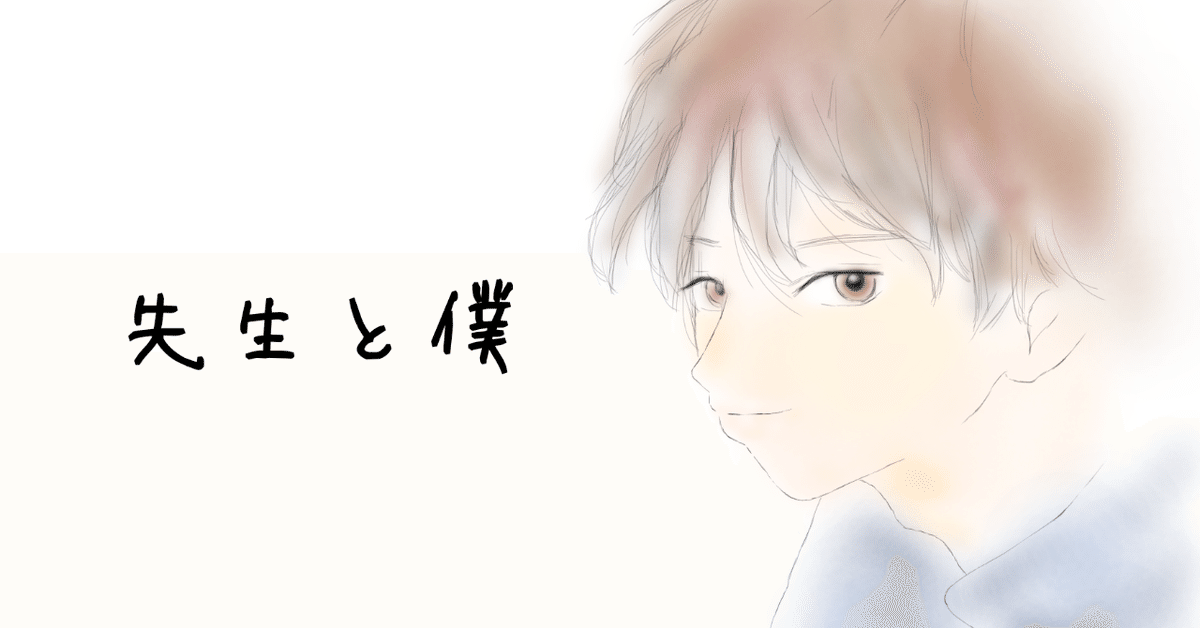
先生と僕(14)「ピチピチ先生」
樹の枝に小鳥が音符のように並んでいた。僕が窓を開けた瞬間、小鳥たちは飛び立ち、揺れた枝から雪の花弁が舞う。僕の後ろ手に隠し持ったずるさに気付かれたのかもしれない。雪の降った後の世界はあまりにも浄化されているので、隠し事はすぐに見透かされてしまうのだろう。
休み時間、僕は廊下の窓を開け、中庭を眺めていた。
雪の降り積もった中庭は、眩しく輝いている。春になれば、美しく咲き誇る桜の樹の枝に、白い雪の花が咲いていた。
そんな桜の樹の枝に、はらりと何かが落ちた。白いTシャツである。そして、陽の光で輝く眩いTシャツに駆け寄る者がいた。
「うおおおお」
体育教師の苫米地強先生である。彼はスーツの下にいつも白いTシャツを身に着けている。
先生は樹の枝にかかったTシャツに手を伸ばす。しかし、届かない。
「くそう!」
先生はジャケットを脱ぎ、白いTシャツ一枚になった。
Tシャツのサイズが小さすぎるのだろう。あまりにも肌に密着している。筋肉質の先生の身体の線が遠目にもわかるほどにピチピチだ。
「うおう!」
先生はTシャツに向かってジャンプする。もう少しで届きそうだ。
「うおお!」
先生はさらにジャンプする。ようやくTシャツに先生の手が触れた。もう少し。
「うおおお!」
先生はさらにジャンプ。ようやくTシャツをキャッチする。
「うおおおお!」
先生のピチピチのTシャツが張り裂け、あたりに雪のように舞った。
「おーい、なに見てるんだ」
通りかかった純也君が僕に声をかけた。
「中庭の景色を見てたんだ」
「そんなの見ておもしれーか」
やれやれとばかりに、純也君が窓から顔を出す。
純也君の頭に、張り裂けたTシャツの一片がはらりと載った。陽の光をはね返し、まるで雪の花弁のように、可憐な輝きを放つ。
僕は思わず、純也君の頭に触れてしまう。
「ごめんね、あまりにもきれいだったから」
To be continued.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
