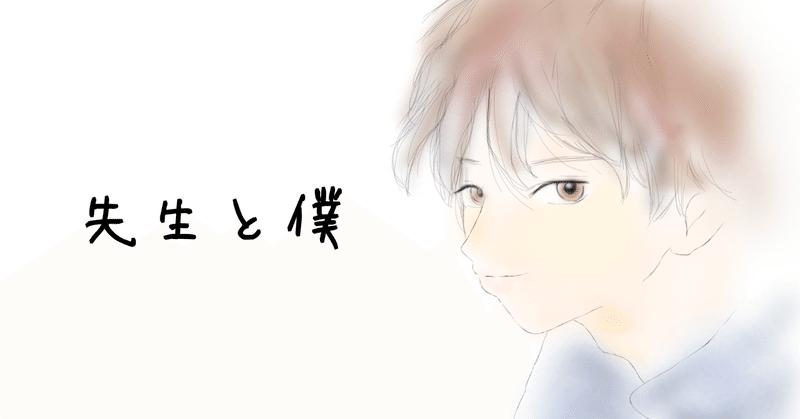
先生と僕(9)「眼力先生」
(8)←
教室は小さな世界だ。しかし僕達にとっては、偶然も運命と錯覚するほどの世界でもあった。錯覚は僕達に光や熱を与えるものの、無常に奪いもする。
小さな世界での正義なんて信じてはならない。だから、僕は太陽にくれてやった。
月明かりに輝く雪の中でなら、闇夜でも迷わない。真実が雪のように儚いのなら、熱くて眩しすぎる正義は不要だ。
二時間目は現国だ。授業開始のチャイムが鳴り、教室へ入って来たのは半田小五郎先生である。
「では、教科書の二十五ページを開いてください」
先生の眼力は凄まじい。見つめられれば恐怖で身体が動かなくなるほどである。僕達は目を合わせないようにして、教科書を開いた。
「間違いました、三十二ページを開いてください」
僕達は目を合わせないようにして、教科書を開いた。
「間違いました、四十五ページを開いてください」
僕達は目を合わせないようにして、教科書を開いた。
「いや、違う!」
先生が大声をあげたので、僕達はつい、顔をあげてしまった。
教壇で先生が頭を抱えている。
「何ページだっただろうか!」
悩み苦しむ先生が天井を見上げた後
「わかった!五十二ページだ!」
断言した先生の額には、第三の目が見開いていた。
「うわああああ」
僕達は恐怖のあまり一斉に教室を飛び出した。
廊下を走ってはならない。そんな正義は太陽にくれてやる。
教室を飛び出した僕らは、雪の積もった校庭へ避難した。
太陽の光を反射した雪の校庭は僕達の恐怖を一掃してくれる。雪玉をつくり、互いに投げ合い、雪合戦を始めた。子供の頃に戻ったように無邪気に笑いあう。
もしかしたら、先生は、僕達に笑顔を取り戻すために、あんなことをしたのかもしれない。
「雪合戦、楽しいな」
僕に話しかけたのは、後ろの席の純也君である。無口で不愛想な彼は、普段、近寄りがたい印象がある。しかし、雪まみれで笑顔を浮かべる彼は、まるで別人のようだった。光に溢れた校庭が、彼を変えてくれたのだろう。
「そうだね」
僕は答えながら、両手で雪をすくい、純也君の頭に落とした。
「おい、やめろよー」
純也君は笑いながら、僕に同じようなことをする。雪だらけになった僕達は、白い息を吐きながら、雪上に腰を下ろした。
純也君の髪には雪の結晶がのっている。太陽の光で輝いていたが、やがて雫となり消えてしまった。僕は、とっさに純也君の髪に触れてしまう。
「ごめんね、あまりにもきれいだったから」
To be continued.
→(10)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
