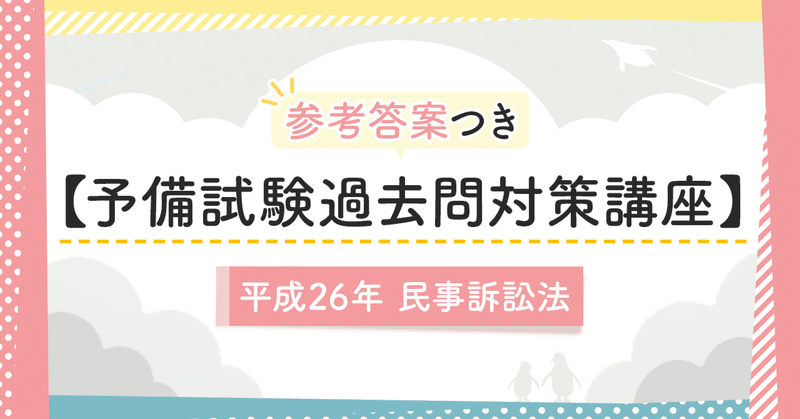
【予備試験過去問対策講座】平成26年民事訴訟法
はじめに
この記事は「予備試験過去問対策講座」講義記事です。
今回は、平成26民事訴訟法を題材に、実際に過去問を解く流れを思考過程から段階的に解説していきます。
予備試験民事訴訟法の思考方法
民事訴訟法では、問われている内容は一見シンプルであるため、何が問題となり得るのか分かりにくいという点に難しさがあります。
そこで、実際の問題の解説に入る前に、設問の内容に応じて民事訴訟法上のどのような概念を想起すべきかという考え方の一例を紹介します。
設問の分析は2つの視点から行います。
1つ目は、訴訟物、主張、立証レベルという民事訴訟法における三段階の基本構造です。まず、原告の主張する権利が訴訟物です。そして、訴訟物が認められるために必要な要件が主張レベルにおける要件事実であり、要件事実に対応する具体的事実である主要事実を推認させる証拠や間接事実が立証レベルの話に当たります。
訴訟物レベルでは、処分権主義が妥当します。つまり、何を請求するのか、という点は原告の意思に委ねられます。
主張レベルでは、弁論主義が妥当します。第1テーゼ(主張原則)により、当事者が訴訟上で主張した主要事実のみが裁判の判断の基礎とされます。また、第2テーゼ(自白法則)により、争いのない事実は自白が成立し、主張レベルで終わります。一方、争いのある事実は証拠調べが必要になるため、立証レベルの問題となります。
立証レベルでは、自由心証主義が妥当します。つまり、主張レベルと異なり、ある証拠方法を採用するかどうか、そして取り調べた証拠の証明力をどう評価するかは、原則として裁判所の自由な心証に委ねられます。
したがって、問題提起を正しくするためには、設問がどのレベルの議論をしているのか把握することが重要です。
2つ目の視点は、訴訟の進捗です。

上図は訴訟の進捗ごとに妥当する概念を記載したものですが、先ほどの三段階の基本構造は審理の進捗に対応しているため、概ね同じ構造になっていることが分かります。
この図をベースとして勉強した論点を適切な位置にマッピングしていくことで、初見の問題でも正しく設問を分析し、問題提起ができるようになります。
例えば、明示的一部請求訴訟は許されるか、という問いであれば、これは訴え提起の話であり、また訴訟物レベルの議論であるため、処分権主義に反しないか、という点を問題にすればよいことが分かります。
また、裁判所はある主要事実を認定できるか、という問いであれば、口頭弁論の話であり、主張レベルでは、当事者はその事実を主張しているか、そして相手方は自白しているか、という点が問題となり、立証レベルでは、裁判所は証拠調べの結果、その事実が存在するという心証を形成しているか、という点が問題になることが分かります。
平成26年民事訴訟法
では、実際の問題を解いていきます。
設問1
訴訟係属後に第三者を当該訴訟手続に関与させるための方法が問われています。
■複数の請求が扱われる場合
解答を考える前に、複数の請求が扱われる場合のパターンについて整理しておきます。
まず、請求が複数になるケースとしては、原告と被告は1人ずつで訴訟物が複数ある場合(請求の客観的複数)と、当事者の少なくとも一方が複数になっているかまたは第三者が登場する場合(請求の主観的複数)があり得ます。いずれの場合も、136条における「請求の併合」のための要件を充足することが必要とされています。
(請求の併合)
第百三十六条 数個の請求は、同種の訴訟手続による場合に限り、一の訴えですることができる。
請求の客観的複数には、原告が訴え提起時より数個の請求を立てる場合(原始的複数)のほか、訴えの変更(143条1項本文)、中間確認の訴え(145条1項本文)、反訴(146条1項本文)、弁論の併合(152条1項)により、訴訟手続中に複数になる場合(後発的複数)があります。
請求の主観的複数も同様に、原告または被告が訴え提起時より複数である場合(原始的複数)のほか、事後的に第三者が参加する場合(後発的複数)があります。このうち、当事者の一方が複数になる場合を共同訴訟(38条、40条1項)といいます。後発的に共同訴訟になる場合としては、共同訴訟参加(52条1項)、弁論の併合、(明文のない)訴えの主観的追加的併合が考えられます。また、係属中の訴訟に(原告または被告側ではない)第三の当事者が参加する場合として、独立当事者参加(47条1項)等があります。
請求の複数が扱われる場合
請求の客観的複数
原始的複数
後発的複数(訴えの変更、中間確認の訴え、反訴、弁論の併合)
請求の主観的複数
原始的複数
共同訴訟
後発的複数
共同訴訟(共同訴訟参加、弁論の併合、訴えの主観的追加的併合)
独立当事者参加
■訴訟承継
請求の主観的複数のうち後発的複数の場合において、独立当事者参加等の制度を利用して、訴訟の係属中に訴訟の目的物である権利または義務を承継した第三者が訴訟を引き継ぐ(または第三者に訴訟を引き継がせる)ための規定が訴訟承継です。口頭弁論終結後の承継人に対しては判決の効力が及ぶ(115条1項3号)一方で、口頭弁論終結前の第三者には及ばないことから、訴訟経済と公平の観点から定められています。
相続のような包括承継があった場合や、目的物の売買等の特定承継があった場合に検討が必要になりますが、ここでは後者の手続きに関して定めた49条以下を整理しておきます。
まず、訴訟の目的物である権利または義務を第三者が承継した場合において、そのことを承継人である第三者が自ら主張して訴訟へ参加するための規定が49条及び51条前段に定められている参加承継です。これは、独立当事者参加の手続きにより行われます。
次に、訴訟の目的物である権利または義務を第三者が承継した場合において、訴訟の原告または被告の申し立てにより第三者に訴訟を引き受けさせるための規定が50条及び51条後段に定められている引受承継です。こちらは同時審判申出の規定が準用されています。

■問題の解答
以上を踏まえ、設問1を検討していきます。
問われているのは、訴訟係属後に第三者を当該訴訟手続に関与させるための方法であることから、上記の分類でいえば、請求の主観的複数のうち後発的複数となるケースです。当該ケースが生じる原因のうち、原告のアクションがきっかけとなりうるものは以下の2つです。
弁論の併合
訴えの主観的追加的併合
※ 訴訟承継も問題になりそうですが、Wが乙建物を賃借したのは訴訟係属前の平成26年2月10日であることから、「訴訟の係属中…承継した」(50条)という要件を充足しません。
まず、Xは、Wに対して建物退去土地明渡請求訴訟を別訴として提起した上で、裁判所に弁論の併合(152条1項)を求めることが考えられます。
(口頭弁論の併合等)
第百五十二条 裁判所は、口頭弁論の制限、分離若しくは併合を命じ、又はその命令を取り消すことができる。
もっとも、弁論の併合は裁判所の裁量によってなされるものであることから、「本件訴訟の手続で併せて審理してもらいたい」というXの要望を確実に叶える方法とはいえません。
そこで、訴えの主観的追加的併合の可否を検討します。
訴えの主観的追加的併合とは、係属中の訴訟に第三者が当事者として参加し、または追加され、共同訴訟となる併合形態をいいます。必要的共同訴訟であれば、共同訴訟参加(52条1項)の手続きにより第三者は訴訟に参加することができますが、このような規定がない場合にも当事者または第三者主導による併合が認められるのかという点が問題となります。
判例(最判昭62.7.17)は、以下の理由を述べ、明文のない場合に原告が新たな被告を加えようとする訴えの主観的追加的併合を否定しています。
かかる併合を認める明文の規定がないのみでなく、これを認めた場合でも、新訴につき旧訴訟の訴訟状態を当然に利用することができるかどうかについては問題があり、必ずしも訴訟経済に適うものでもなく、かえって訴訟を複雑化させるという弊害も予想され、また軽率な提訴ないし濫訴が増えるおそれもあり、新訴の提起の時期いかんによっては訴訟の遅延を招きやすいことなどを勘案すれば、所論のいう追加的併合を認めるのは相当ではないからである。
論述の方針としては、この判例を引用して、本問の場合も同様の理由が妥当することから訴えの主観的追加的併合を認めないとすることが考えられます。もしくは、もう一歩踏み込んで、判例のいう訴訟不経済、訴訟の複雑化、濫訴の増加、及び訴訟の遅延といった弊害の生じるおそれがないのであれば、判例の趣旨は及ばず追加的併合が認められるという規範を定立し、当てはめを論じていくことも考えられます。
ここでは、本問特有の事情をより拾いやすい後者の構成を考えることにします。
Xの目的は乙建物の収去と甲土地の明渡しですが、本件訴訟の既判力はWには及ばないため、追加的併合が認められないとしてもWに対する別訴は必ず必要になります。その場合、両訴訟において同一不動産に対する明渡訴訟という点は共通しており、大部分の争点は共通すると考えられることから、同一手続による審理はむしろ訴訟経済に資するものであり、訴訟を複雑化させることもないと考えられます。
また、Xは、Wが乙建物を占有していることに気付かなかったために併合を求めるものであり、軽率な提訴といった指摘は当たらないことから、本ケースで併合を認めても濫訴の増加に繋がるとはいえません。
最後に、(問題文中の事情だけでははっきりとは分からないものの)XがWの占有に気付いたのは、本件訴訟の審理が大きく進んだ後というわけではないため、併合を認めWに弁論の機会を与えたとしても訴訟の著しい遅延には繋がらないといえます。
よって、本問においては判例の趣旨が妥当せず、訴えの主観的追加的併合が認められると結論付けられます。
設問2
設問1との前提条件の違いは、YがWに乙建物を賃貸した時期が訴訟係属後の平成26年5月10日であるという点です。①から③の記載の文言にもヒントがありますが、訴訟係属中に訴訟の目的物である土地明渡義務が承継されていることから、訴訟承継を検討すべきであると気づくことができます。
■①について
上記のとおりWは義務承継人に当たります。そして、Wは自ら訴訟参加していることから、義務承継人の参加承継(51条)のケースであることが分かります。
(義務承継人の訴訟参加及び権利承継人の訴訟引受け)
第五十一条 第四十七条から第四十九条までの規定は訴訟の係属中その訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したことを主張する第三者の訴訟参加について、前条の規定は訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である権利の全部又は一部を譲り受けた場合について準用する。
ここで、Yの陳述の持つ意味について考えます。Yは、AX間で本件売買契約が締結されたことを認めるという旨の陳述をしています。何となく自白に当たるのではないか、という点には気づくことができると思いますが、本問における重要なポイントであるため、しっかりと定義を思い出し、三段論法で認定できると良いでしょう。
自白とは、口頭弁論期日又は弁論準備期日における相手方の主張と一致する自己に不利益な事実を認める旨の陳述をいいます。
自己に不利益な事実とは、相手方が立証責任を負う事実のことを指します。本件訴訟の訴訟物は所有権に基づく返還請求権としての建物収去土地明渡請求であるため、Xの所有権を基礎づける事実は主要事実であり、Xが立証責任を負います。Yは、本件訴訟の口頭弁論期日において、上記事実を認める旨の陳述をしていることから、当該陳述は自白に当たります。
裁判上の自白が成立すると、禁反言の観点から原則として当事者は自白を撤回することができません。したがって、少なくともYはこの自白を撤回できないことになります。
そして、Wは、問題文にあるように、そもそもこの事実がないことを主張したいと考えています。つまり、義務承継人が参加承継した場合に、被承継人がした自白を撤回できるのか、という点が問題になっていることが分かります。
前述のとおり、訴訟承継の趣旨は、訴訟経済と公平性の確保にあります。仮に、承継人が承継時における被承継人の地位を引き継がないとすると、承継前に行われた審理を再度繰り返す必要性から訴訟不経済に繋がるだけでなく、相手方は承継人を相手に再度訴訟を追行せざるをえず、不公平な結果となりうる可能性もあります。一方で、承継前には、被承継人が訴訟の目的物について利害関係を有する当事者として訴訟追行をしていたことから、当該目的物を承継した承継人の手続保障は十分に代替されているといえます。
したがって、承継人は、承継時における被承継人の地位を引き継ぎ、その訴訟状態に拘束されてもやむを得ないと考えられます。
本問では、WはYの自白後に義務承継人として参加承継しているため、当該自白の内容に拘束されます。つまり、Yの陳述は、Wとの関係で、AX間で本件売買契約が締結された事実はなかったという主張を妨げる意義を持つことになります。
■②について
①と同様、義務承継人の参加承継のケースです。こちらでは、Wの参加後にYの自白がなされていることから、訴訟状態の承継は問題とならず、当事者間における訴訟行為の効力が問題となります。
ここで問われているのは条文操作のみです。義務承継人の参加承継を規定した51条により47条が準用されることから、47条4項が準用する40条1項が適用されます。
(独立当事者参加)
第四十七条
4 第四十条第一項から第三項までの規定は第一項の訴訟の当事者及び同項の規定によりその訴訟に参加した者について、第四十三条の規定は同項の規定による参加の申出について準用する。
(必要的共同訴訟)
第四十条 訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合一にのみ確定すべき場合には、その一人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生ずる。
そして、裁判上の自白は、「全員の利益」に繋がる行為ではないため、その効力を生じません。
したがって、Yの陳述は、Wとの関係で、AX間で本件売買契約が締結された事実はなかったという主張を妨げません。
■③について
①、②と異なり、Xの申し立てによりWに訴訟を引き受けさせる旨の決定がなされているため、義務承継人の引受承継(50条1項)のケースに当たります。
本問では50条3項が準用する41条1項が適用されます。
(義務承継人の訴訟引受け)
第五十条
3 第四十一条第一項及び第三項並びに前二条の規定は、第一項の規定により訴訟を引き受けさせる決定があった場合について準用する。
(同時審判の申出がある共同訴訟)
第四十一条 共同被告の一方に対する訴訟の目的である権利と共同被告の他方に対する訴訟の目的である権利とが法律上併存し得ない関係にある場合において、原告の申出があったときは、弁論及び裁判は、分離しないでしなければならない。
そして、同時審判申出共同訴訟も通常共同訴訟(38条)であることから、共同訴訟人独立の原則(39条)が妥当します。
(共同訴訟の要件)
第三十八条 訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき、又は同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づくときも、同様とする。
(共同訴訟人の地位)
第三十九条 共同訴訟人の一人の訴訟行為、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為及び共同訴訟人の一人について生じた事項は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。
本問でも、Yの陳述は、共同訴訟人であるWに対しては、W自身が援用しない限り何ら影響を及ぼしません。したがって、Yの陳述は、Wとの関係で、AX間で本件売買契約が締結された事実はなかったという主張を妨げません。
出題の趣旨
本問題について公表されている出題の趣旨は以下の通りです。
本問は,建物所有者に対する建物収去土地明渡請求訴訟の目的物である当該建物が訴訟係属前又は訴訟係属後に賃貸された場合について,これにより当該土地建物の占有を承継した賃借人が当該訴訟手続に関与するため又は当該賃借人を当該訴訟手続に関与させるための方法と,当該訴訟手続に関与することとなった当該賃借人に対して従前からの当事者である建物所有者が行った陳述の効果が及ぶか否かを問うものである。
設問1は,訴訟係属前に当該賃借人が当該土地建物の占有を承継した事案について,訴訟係属後に,原告の意思に基づき当該賃借人を当該訴訟手続に関与させるための方法を問うものであり,別訴提起・弁論の併合の方法によることや主観的追加的併合の許否等について検討することが求められる。
設問2は,訴訟係属後に当該賃借人が当該土地建物の占有を承継した事案について,①及び②では,賃借人すなわち義務承継人が参加承継することを前提として, 従前からの当事者が当該義務承継人の参加前(①)・参加後(②)にした陳述の当該義務承継人に対する効果を,③では,義務承継人に引受承継させることを前提として,従前からの当事者が当該義務承継人の引受け後にした陳述の当該義務承継人に対する効果を,それぞれ問うものである。
参考答案
以上の内容を反映した参考答案を添付します。
参考書籍
書き方講座記事のご案内
本noteでは、論文の書き方についてゼロから丁寧に解説した記事を公開しています。これから論文を書き始める方、論文の勉強方法に悩んでいる方はぜひご覧ください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
