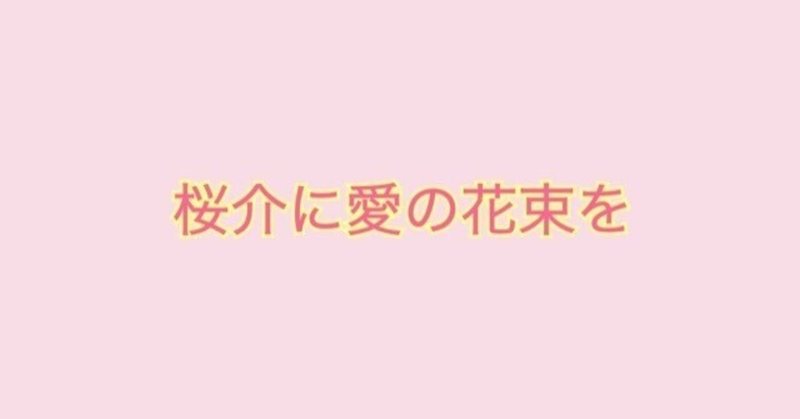
桜介に愛の花束を 20
雨の夜
「菜緒?」
しがみついて離れない私が濡れないように桜介は傘だけ拾って、片手で傘をさしながら、もう片方の手で抱き寄せてくれた。
「震えてる。風邪ひくよ」
「もう少し」
「うーん……ならうち、来る?」
「え?」
ドキッと心臓が跳ねてギュンと縮んだ。
「うち、いつも夜まで誰もいないから」
「うん」
「家に電話して」
「しなくてもいいよ、少しくらい」
「だーめ、ほら早く。あと亜美の家って口実もなしな。なんなら俺電話出るから」
「いいよ、そこまでしなくて」
私は会話を聞かれるのが恥ずかしくて桜介に背を向けながら家に電話した。
だけど電話に出たのは弟の慎二だった。親は二人とも夜まで帰ってこないと言われた。
そういえば朝そんなことを言ってた気がする。時間ギリギリに起きて慌てて家を出たから記憶が少しぼんやりしていた。
「はい、帰りコンビニでアイス買ってきて」
なんとも拍子抜けする。
「慎二ご飯は?」
「カレー作ってから行ったから。姉ちゃん食って帰るの? なら姉ちゃんの分も食っていい?」
「いいよ」
電話口の慎二の声はカレーを私の分も食べられることで弾んでた。もう一食食べられるって成長期の食欲は本当に恐ろしい。
「なんだって?」
「あ、親はうちもいないみたい。慎二はもうご飯食べたって」
「じゃあなんか食ってく? てかうちで食おうか」
「あ、うん」
コンビニでご飯を買って桜介の家へ向かった。
あまり家の場所も覚えてない。始めて来る家。だけど過去には何度が来ている。
過去に何度が来ているって表現はおかしいか。
未来に何度が来ている。の方が正しいかな。
お母さん、いつもいなかったな――。
雨と傘、それに加えもうすっかり夜に飲み込まれそうな暗さ。あとどのくらい歩けば着くのかも分からず一歩踏み出す度にドキドキと心臓は破裂しそうなくらいに激しく動いた。
「ここ」
コンビニでお弁当と飲み物を買って桜介の家に着いた。
桜介はお母さんと二人で暮らしてる。そして桜介は一人っ子だからいつもここに一人で帰ってる。
思えば私がいなくなってから桜介は一人でこの家に帰る時、どれだけ淋しい思いをしたんだろう。
それを想像したらまた胸がぎゅっと伸縮した。
「上がって」
桜介の家は無機質であまり生活感がない。
物は最低限だけ揃えられていて余計なものが一切ない。
それがまた淋しさを思い浮かばせた。
「適当に座って。てか初めてじゃないしな」
「うん、でも初めて」
「あぁ、そっか」
そう言って小さく笑った。
「はい、これ使って」
桜介に渡されたタオルで髪を拭いた。このタオルも桜介と同じ匂いがする。柔軟剤の匂いなんだから当たり前か。
「ドライヤーこっち」
「いいよ」
「風邪ひくから乾かしなよ」
そう言って洗面所に案内されて軽く髪の毛を乾かした。
「桜介?」
「んー?」
「桜介も濡れたよね」
「俺はもうほとんど乾いた」
「だーめ」
そう言って桜介を洗面所に呼び寄せると桜介の背後に立ってドライヤーをあてた。
「んー、ちょっと屈んで」
桜介の柔らかい猫みたいな毛を指で掬いながら風をあてた。
「サラサラだねー」
「んー?」
ドライヤーの音で聞こえなかったみたいで桜介が振り返った。
屈んで私より低い位置にいた桜介が振り返ると驚くほど顔が近かった。
「あっ、ごめん」
目が合って慌てて逸らしたら桜介も戸惑って顔を戻した。
「終わり、乾いたよ」
「ありがと、ご飯食べよ」
リビングに戻ってお弁当を広げた。
「ん、ちょっと温《ぬる》くなっちゃったかな」
コンビニで温めてもらったお弁当は少しその熱を下げていた。
「このお弁当さ、美味しかったのに今もうないよね」
「うん、改良されたみたいだけどあれまるで別もんだよな」
「もう食べられないから堪能しとこ」
この言葉を呟いたあと、このお弁当だけじゃなくて何もかも食べられないんだって気づいたけどそれを口にするのはやめた。
空気が暗くなるのを恐れたから。
「ごちそうさまでした」
「テレビ見る?」
「うん」
「雨やんだら送ってく」
雨やまないといいのに。
朝まで降り続けたらいいのに。
なんで私たちは子供なんだろう。大人だったら残された時間をずっと二人でいられるのに。
いつしか窓を弾いていた雨粒の音がしなくなって雨がやんだんだって気づいた。
だけど私はそれを口にしなかった。それどころかテレビを見ながら桜介にずっと話しかけ続けた。桜介が私を帰すのを忘れちゃえばいいのにと思って。
だけど時々チラチラと動く視線の先、時計の針が無情にも動き続けてたこと、ずっと気づいていた。
「じゃあ、そろそろ帰るか」
「うん」
手を繋いでそんなに長くはない距離を二人で歩いた。
家が近づくとどちらからともなくするりと解けた手。
「じゃあ」
「ああ」
「また明日」
「気をつけて」
「ここ私の家の前だよ?」
いつも言ってくれてた。私の家の前まで送ってくれてるのにそこで「気をつけて」って。その度いつも私は笑うの「ここ私の家の前だよ?」って。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

