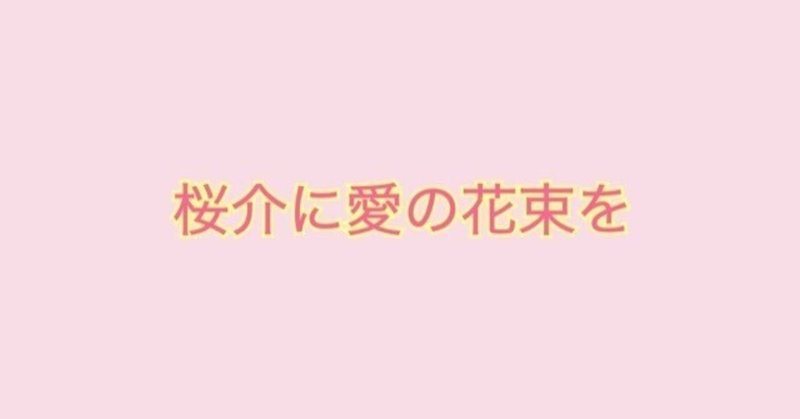
桜介に愛の花束を 33
ふたつの傘
「お待たせ」
「どこ行ってたの?」
「ふふ、なんか頼んだ?」
「まだ」
「じゃあ先に頼もうか」
メニューを見て私はホットココア、桜介はカフェラテを選んだ。
「桜介、手出して」
そう言うと桜介は不思議そうな顔をしながら、それでも素直に両手を出した。
右腕には時計がついてるから却下。右腕をそっと押し返した。
「なに?」
そして左腕にさっき買ったヘアゴムアクセをつけた。
「そこで売ってたの、欲しくなっちゃって、ケーキ代も浮いたし」
「え、それなら俺も用意したかった」
「いいのいいの……でも」
「ん?」
「私のも、あるんだ」
そう言ってそれを見せたら「貸して」って言われて、腕につけられた。
「やっぱり、こういうの、したくなっちゃうよね」
「我慢しなくていいのに」
そうだよね、分かるのになんで我慢しちゃうんだろう。
ドリンクが届いて店内の温かさとドリンクの温かさで顔が赤くなってきた。
特になにもしてないのに、あっという間に時間が過ぎていく。
学校の一時間と桜介と一緒にいる一時間てなんでこんなに体感が違うんだろう。
「そろそろ出よっか、暗くなってきた」
「うん、そうだね」
肯定の言葉を出してるのに、その表情は真逆だったのか、桜介はそんな私の顔を見てぷっと吹き出した。
「なにー?」
「いやー? 分かりやすいなーと思って」
確かに分かりやすいってよく言われるけど。
「亜美たちどうなったかな?」
「うまくいってると思うよ」
「そうだよね、大丈夫だよね。そろそろ冬休みだけど、どこか行ける?」
「あぁ、そうだな」
無理矢理話題を出してこの時間を引っ張ろうとしても限界がある。
周りを見渡せばカップルだらけ。いいな、大人は。今日はずっと一緒にいられるんだろうな、なんて思ってはまた顔に出てしまうと、慌てて悟られないように笑顔を作った。
「ありがとうございました」
店を出るともうすっかり暗くなっている空からふわりと真っ白な粒が降りてきた。
「あ、雪」
「どうりで寒いわけだ」
「雪だ! 雪だ!」
桜介は、はしゃぐように飛び出そうとした私の腕を取った。
「濡れるぞ」
「あ、うん、でも嬉しくない? 雪。降ったっけ? この年」
「記憶にないな……」
「ね、ないよね」
この世界は私たちが知ってる世界じゃないのかもしれない。
あの世界とは別の世界で、だからあの世界とは違うことが起きる。
それならばと少しの期待がむくむくと心の中に広がりそうになっては、突き落とされる前にと慌てて閉じ込めた。
今日のことも漫画にしよう。
この勢いじゃ積もらないだろうけど、話の中では積もって明日には一面銀色の世界が広がってるってことにしよう。
少しくらいのデフォルメは悪いことじゃないよね。
「傘、ないね」
「ちょっと待ってて、コンビニで買ってくる」
そう言って桜介はパーカーのフードを被って駆け出そうとした。
けど、駆け出すことは出来なかった。
私が腕を取ったからだ。
「どうしたの?」
傘がなければ帰れなくて、帰れなければ一緒にいられる。
そんな子供みたいな方程式を思い浮かべて桜介がコンビニに行くのを阻止した。
だけど桜介が困ったように笑ったからすぐにその腕をそっと離した。
そしたら桜介はもっと困ったような顔をした。
「どうしたのよ」
「なんでもない、傘買って帰ろ」
「ああ、買いに行くよ? いい?」
「いい。いい」
そう言うと桜介は一気に走り出した。
間もなく傘を二本買って出てきた。
一本でもよかったのに。
「はい」
「ありがとう」
まずは桜介の家へ向かった。
歩き出すと桜介は私の右手を繋いだ。
あ、傘二本あるからスムーズに手繋げるんだ。
桜介のアパートまで行って、明かりが漏れてたらお母さんが帰ってきてるから桜介とはお別れ。
明かりが消えてたら桜介と一緒にうちで夕ご飯を食べる。
元からこんな約束をしてをしていた。
地面を踏みしめるとザッと雪が鳴る。
その音がなんだかすごく心地よくて雪がありそうなところを見つけてはフラフラと踏みしめに行くと繋がれた手の先、桜介も連れ回されてることに気づき、思わず笑いながら手を離した。
「ごめんごめん、繋いでたの、忘れてた」
電気、点いてなかったらいいな。
でも、桜介にとっては電気は点いてる方がいいのかな。
なかなか会えないみたいだから。こんな日くらい一緒にいた方がいい。
角を曲がると桜介のアパートが見えてきた。二階の角部屋。
「あ、お母さんいるね」
明かりは点いてた。
「そうだな」
「じゃあ、ここで」
「いや、家までは送ってくよ」
「いいよ、そんなに遠くないし」
「暗いし、雪降ってるし送ってく」
「ありがとう」
結局うちまで送ってもらい、そのまま桜介は家に帰っていった。
「じゃ、気をつけて」
またそう言うから
「ここ私家の前だよ」
少し笑いながら、またそう返した。
家に入りすぐにお風呂に入った。体の芯が凍えるように寒くて限界が近かったからだ。
ゆっくりお風呂から上がるとパーティーの準備が出来ていた。
「あれ? 菜緒帰ってきてたの?」
「うん」
「姉ちゃん振られたのかよ」
「はぁ? んなわけないでしょ」
「桜介くんにこれ、渡そうと思ったのに」
そう言われて渡されたのはタッパーに入ったパーティーのご馳走の一部。
「わ、届けてくる」
「あんた湯冷めするじゃない、慎二、行ってやって」
「俺家知らないよ」
「髪乾かして行くから大丈夫」
「でも……夜遅いし、慎二と一緒に行って」
「えー、分かったよ」
髪の毛を軽く乾かして外に出た。
空はもうなにごともなかったかのようにその色を戻していた。
雪は積もらないとは分かってたけど、それでもこんなに早くやむなんて思わなかった。
「もうやんだんだ」
「でも寒いな」
「息が白いー」
こうやって慎二と桜介の家まで歩くなんて今までなかった。この良好な関係は本当によかったと思う。
「着いた」
「んー、じゃあ俺待ってる」
「行ってくるね」
駆け足で裏にある階段に向かった。
振り返り階段を上ろうとした瞬間
「ひゃっ」
驚いて変な声が出た。階段の一番下に人がいたからだ。
そしてそれはよくよく見たら桜介だったからだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

