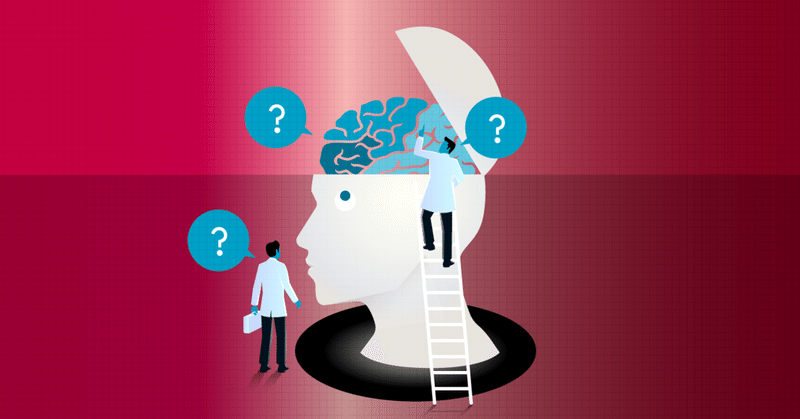
超短編小説|記憶を消した女
ある晴れた日のこと。小さな研究室で、二人の男たちは喜びの声をあげた。
「博士。完成しました」
「おぉ。とうとうできたか」
「誰か被験者になってくれませんかねぇ」
彼らは、政府の依頼で記憶を取り除く装置を開発していた。その機械がやっと完成したのだ。
これにより、日付と時間が分かれば、その期間の記憶を脳内から取り出すことができる。取り出された記憶は、装置の中にある試験管に保存される仕組みだ。
これがあれば、思い出したくない記憶を消すこともできるし、取り出した記憶を保管したり、中身を見ることもできる。
あとは、被験者を見つけるだけだった。もちろん、彼らが実験台になるわけにはいかない。なにしろ、彼らは天才科学者で、彼らのどちらかでも記憶が無くなってしまえば、今後の研究に支障をきたす恐れがあるからだ。
「博士。ポスターを貼って募集しますか?」
「だめだ。この実験は極秘だぞ」
この研究は政府の極秘プロジェクトだ。被験者といえど、一般市民に簡単に教えてしまってはいけない。
「ならば、我々はどうすればいいのでしょう?」
「政府の役人に聞いてみるよ」
博士はそう言って、ポケットから携帯電話を取り出し、電話をかけた。
「おひさしぶりです。例の件なのですが...」
数日後、研究室に被験者がやってきた。やってきたのは若い女性だった。話を聞くと、彼女には思い出したくない過去があった。知人の紹介でこの研究所を紹介されたらしい。女は、このチャンスを逃さまいと、わらにもすがる思いでやってきたのだ。
「思い出したくないのですが、言わなくてもいいですか?」
女は話を切り出した。
「大丈夫ですよ。日付と大まかな時間が分かれば、記憶は取り出せるので」
助手はそう言うと、机に置いてあった誓約書を取り出した。
「こちらの書類に記入して頂けますか?」
「分かりました」
書類には、「怪我や死亡した場合には一切の責任を負わない」とはっきり書かれていた。これは、はじめての人体実験だ。正直うまくいくかは未知数なのだ。
女は書類にゆっくりと目を通していた。最後まで読み終えると、覚悟を決めたかのように、「はぁ」と一息ついた。そして、ついに自分の名前を記入した。
助手は彼女から紙を受け取り、博士に渡した。
「いよいよだな」
「はい」
博士は、機械の前に立って、女から聞いた時間を入力する。
はじめての人体実験。成功するかは五分五分だ。でも、自信だけはある。これを作るのに10年もかかっているのだ。われわれの計算に狂いはない。
「ゴー、ゴー、ゴー」
すると、機械は激しく作動した。それから、30分ほど経っただろうか。とつぜん機械の音が鳴り止んだ。
「止まったぞ」
「終わったのでしょうか?」
機械を開けてみると、試験管には記憶のエキスが入っていた。
「成功だ」
「はい。では、処分しましょう」
すると、博士はにやりと笑いながら、助手に尋ねた。
「中身を見てみないか?」
「気になりますね」
博士は、試験管のエキスを機械に垂らした。そして、モニターのスイッチをつけた。すると、彼女の脳内の記憶が写った。
「悪かった。」
「ぜったいに許さない」
女はすごい形相で男に詰め寄っていた。見ると女の手には、包丁が握られている。
「じゃあ、なんでそんなことしたの?」
「いやぁ。悪かったよ。そんなつもりじゃなかったんだ」
すると、とつぜん警官たちが入ってきた。少なくとも、10人はいる。
「ご協力ありがとうございます。これで逮捕できます」
「逮捕ですか?」
二人は顔を合わせた。
「博士の研究のおかげで、あの女が殺人犯だと確信したのです」
「それはよかった」
女は手錠をかけられ、パトカーに運ばれた。しかし、彼女の頭にはハテナマークが浮かんでいる。それも無理はない。犯罪の記憶は頭から消し去られてしまったのだから。
警官たちのなかに、政府の役人の姿があった。
「博士。今回はありがとうございます」
「犯罪捜査のためだなんて聞いてないですよ」
「それは申し訳ない。でも、今日で時代は前に進んだ。博士は天才だ」
「いやぁ。天才だなんて」
博士は顔を赤らめて、照れていた。
「博士ひとつ聞きたいのですが」
「なんでしょう?」
「自白を引き出したいのですが、記憶は元に戻せますか?」
「残念ですが、それはできません」
サポートして頂いたお金で、好きなコーヒー豆を買います。応援があれば、日々の創作のやる気が出ます。
