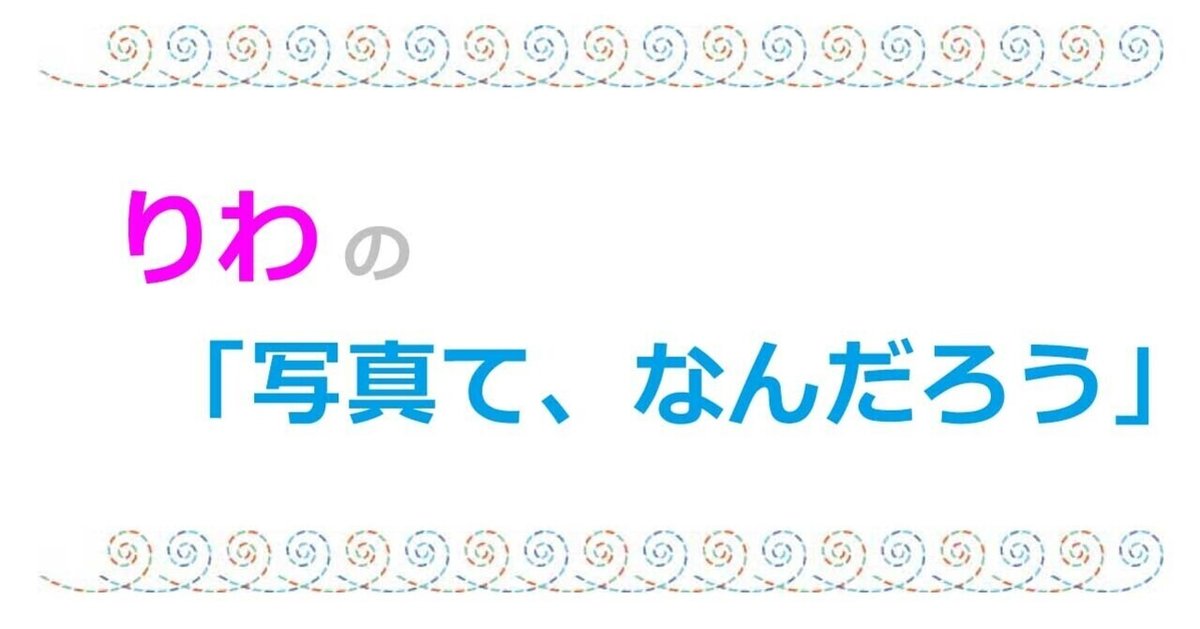
りわの「写真て、なんだろう」【第3話】
写真は動画に勝てるのか?
新築された千駄ヶ谷の国立競技場の横、これまたつい最近新築オープンしたオリンピックミュージアムの中で、大画面に映し出される動画に見入ったまままたしても私は呟いていた。。。
「私はなんで写真を撮るのだろう?」
9月にオープンしたオリンピックミュージアムの1階(無料)で大画面に見入っている。
画面には、過去の様々なオリンピックシーンや、競技をするアスリートの引いた動画やアップの動画が流されている。
躍動する筋肉、緊張している表情、滴る汗、しなやかなポーズ。
スタートと同時に飛び出すその肢体の動きがスローになりストップモーションになる、その動画のなめらかさ。
トラックを周回するアスリートを真上から映すと、人間は動く点になり、足元から伸びた影は意思を持った人間の様に見えてくる。
黒い影人間が、走る、跳ぶ、舞い踊る。
こんな撮り方もあるのかと感心する。。。そして思う。
状況のわかりやすさ、情報量の多さ、音響も付く。
今のインフラなら伝達スピードも一瞬、保管にかかる費用もさほどではない。
ドローンを使えば今までは不可能だった角度からも撮影できる。
動画って凄い!
メディアとして凄い可能性がある!
このままでは写真は動画に勝てないのでは?
ネス湖のネッシーの有名なフェイク写真。
あれだって動画だったならすぐ不自然さを指摘されただろう。
ぼけた写真が1枚きりしかなかったから、何十年も議論となった。
映画スターウォーズの1作目、R2-D2がルーク・スカイウォーカーに見せる有名なホログラム(映像メッセージ)「オビワン・ケノービ。あなただけが頼り」のシーンでも、ルークが心を動かしたのは、レイア姫の美しさもさることながら、動画だったことも影響が大きかったのではと思っている。
これがレイア姫の写真だけだったら、彼は命がけの冒険に乗り出しただろうか?
ともかく、動画の圧倒的な情報量に、将来写真は勝てるのだろうか?
まてまて、「勝てるか」という命題の立て方はちょっと違う。
動画の反対語は静止画であって、「写真」ではない。
将来写真は生き残れるか?という問いの立て方の方が適切だろうか。
というようなことをつらつら考えていたら、またしても奴が出た。
「着眼点としては悪くないかもだけど、答えはとっくに出てるでしょう?」
「でてる?。。。」
「写真と動画は、共存共栄に決まってるじゃない!」
「なんで決まってるの?」
「マンガだって、コミックとアニメーションは別物よ!」
「……それって例えになってる?」
「CDに駆逐されたレコードだって、いまだに愛好家がいるじゃない!」
「レコードはアンティークに片足つ込んでるんじゃぁ?」
「細かいわね。それなら逆説で行く? 写真のいいところを言ってみなさいよ!」
動画に勝る写真の魅力。。。
最初っからそこを考えればよかったことに、今更ながらに気が付く。
血の巡りが悪いことおびただしい。
「プリントしてしまえば、写真は見るのに電気も機器も不要。」
「ふんふん?」
「紙面の中でテキスタイル的デザインの美しさを楽しめる。部屋に飾れる。」
「なるほど。」
「情報が少ない分、想像の余地がある!」
「そうね!」
「つまり…動画は動画、写真は写真!」
「おおあたりぃぃぃ~~」
まるで千と千尋のワンシーンのように叫んで、奴は消えた。
結局そういう事なんだろうと思う。
精密画というジャンルは廃れたけど、写真技術が発達してなお、いまだ絵画の世界は健在だ。
トーキーが生まれ、映画という名の動画が発達しても、写真は毎日撮られている。
ポスターやパンフレット、雑誌の見開きの様に、むしろ補い合う形で利用されているのではないだろうか。
今では生活に深く根付き、記録媒体と共に、あって当たり前となっている写真。
一億総カメラマンになる日も近いのではないかとさえ思える。
どんなに動画が発達してユーチューバーが闊歩しようとも、写真には写真の良さがある。
お財布の中に、手帳の中に、スマホの中に、大切な人の写真を持ち歩きたい。
思い出の1ページを壁に飾りたい。
電気がなくたってへっちゃら。
本の中にだってこっそり隠せる。
そんなことを、一巡りしてやっと気が付いた日。
「私はなんで写真を撮るのだろう?」
それは、人生の旅の長い長~い記憶だから。かな。




写真・文:渡辺理和
渡辺理和(Riwa Watanabe)プロフィール
2018年から写真教室に参加中。
若い頃から写真に興味はあったものの、きちんと写真を撮ることを意識し出したのは、3年前に姪っ子にインスタグラムを教えてもらってから。
当初はコンパクトデジカメを使っていたが、2年ほど前に一眼レフの入門機を購入。
基礎講座に通い、入門者から初心者へジョブチェンジ。
さらに中級者を目指しレベルアップに励むも、返り討ちにあったりする。
主な撮影場所:ご近所、大きな公園、旅先など。撮影は時間&体力と相談なので、人だかりのできる有名スポットはほぼ無し。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
