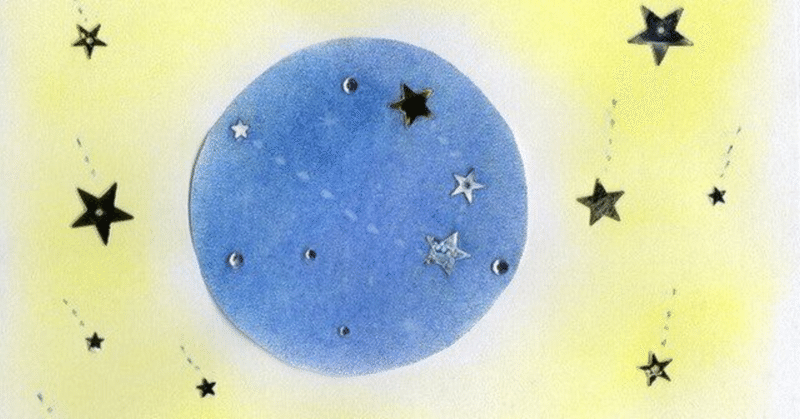
「地球儀を売る」【短編小説】
僕のうちはこの町に一つしかない地球儀屋さんを営んでいる。
地球儀を売るというのは、地球儀を売ったことがない人の想像する何倍も大変なことだ。僕自身、もちろんどこかの誰かに地球儀を売ったことなんてないから、つまりは僕の父さんと母さんは僕の想像する何倍も頑張っているということだ。
そんな二人の日々の頑張りに、一人っ子である僕は心から感謝しているし、二人を尊敬してもいる。けれど、だからといって僕も父さんのように地球儀を愛することができるかときかれると、僕は地球儀よりもアニメとか算数とかの方がだんぜん好きだ。
僕も、この年になるといろいろと将来のことを考える。
僕は大人になったら家業を継がねばならないのだろうか。僕はできればそれは避けたいと思う。地球儀を売るのは、地球儀に心から惚れこんだ父さんのような人にしか、とうていできなっこないからだ。
僕の周りの友達は、僕に比べるとまだまだのんきだ。
みんな、「将来の夢」をきかれると、「スポーツ選手」とか「歌手」だとか答える。小学校一年生だから仕方がないといえばそれまでなのだが、みんなもっと現実を見つめるべきだと僕は思う。僕だってみんなと同じ小学校一年生だ。
世の中、そんなに甘くはない。
僕はそのことを父さんから学んだ。
*
地球儀の売上は年々、減少傾向にある。
誰もがみんな地球を愛でた時代もあった。僕の父さんが地球儀を愛でるように。
しかし、今ではみんな地球そのものを知り尽くしてしまった。そして地球に飽きてしまった。それに地球儀なんか持っていなくても、パソコンを開けば地球に関する情報は誰でもいくらでも手に入れることができるのだ。
地球の形が、たとえばウミのご機嫌のようにころころと移ろいやすいものであれば、みんなに飽きられないですむのにと僕は思う。要するに地球はまじめすぎる。自分の殻に閉じこもってばかりいて、自分流のルールや法則にこだわりすぎる傾向がある。
少し前まではうちの地球儀はよく売れていたが、近頃ではめっきり相手にされなくなったと、父さんは溜息まじりに言う。
それでもうちは頑張っている方だと僕は思う。
近年の不況に重ねて、町の人口は年々減り続けている。駅前のパン屋さんはついこのあいだ潰れてしまったし、近所の八百屋さんも店を先日畳んだ。
そんななかで我が家はなんとか地球儀屋さんの暖簾を守り続けている。そのことが僕にとっては誇りであるし、小さくないプレッシャーでもある。
うちの地球儀屋さんが開業したのは、母さんいわく、もう三十年も昔のことだ。亡くなったおばあちゃんはもっと前だと言っていた。クラスメイトの土屋くんは、僕に、うちの家業は百年も前から続いていると言い、我が家をほめたたえる。みんな言うことがばらばらで、その根拠はどれもあいまいなものだ。
正確な年数はともかくとして、我が家が長いあいだ地球儀を作製し、それを売り続けてきたということは確かである。
*
父さんは少しでも多くの地球儀を売るために、これまでさまざまな努力と工夫を重ねてきた。その姿勢は子供の僕から見ても、たいへん涙ぐましいものであった。
たとえば父さんは、地球の北極点をまるでサイの角のように鋭く尖らせた画期的な形状の地球儀を生みだした。南半球はもとの球体のまま、北半球がきれいな円錐形をした地球だ。宇宙広しといえど、そんな形をした惑星は、父さんの仕事場にしか存在しないだろう。
はじめその新商品は、そのインパクトゆえに、かなりの数売れた。
しかし、その「尖った地球」のリリース以降、みんな性格が荒々しくなった。地球の尖った先端は人々の気を必要以上に引いてしまった。
地球の先っぽへと辿り着くために、死に物狂いで体を鍛えはじめた人がいた。するとそれに負けじとみんな体を鍛えはじめた。誰がいちばんはじめに北極点に辿り着くかで誰もが競い合うようになった。
そんな大衆を冷めた目で見る、いわゆる文化人とよばれる人たちが、
「カドを立てるな」
と言ってカンカンに怒りだした。その怒りは当然、地球に勝手にカドをこしらえた父さんに対して向けられたものだった。
僕は学校でずいぶんと肩身の狭い思いをした。地球の地平線はこんなにも開けているというのに。ここはなんて狭い世界なのだろう。
*
父さんは北半球の鋭く尖った地球儀の作製を中断し、今度はまさにシュールレアリスムというべき、筆舌に尽くしがたい奇妙奇天烈な形をした惑星を作りあげた。その表面は本来の地球とは比べものにならないほどでこぼこしていて、そこには無数の角(カド)と隅(スミ)が混在していた。
その地球上には、どんな生き物にとっても住みやすい場所が存在し、彼らはそれを地球のどこかに見つけだすことによって、誰とも競わず、争わず、のびのびと自由に生きてゆける――と、父さんは考えた。
しかし、競い合うことを忘れた生物たちは、自分こそスミに置けない存在だと心のなかで思うようになった。結果、みんな居場所をなくしてしまった。世界はたちまちギスギスした。その見た目はボコボコしていて、あいかわらず文化人たちはカンカンだった。
父さんは地球上にスミを作りすぎてしまったことを猛烈に反省した。
*
そんなあるとき、土星関連の仕事をしている土屋くんの父さんが、うちを訪ねてきて、父さんにある提案を持ちかけた。
それは、地球も土星のように輪っかをつけてみないか、というものだった。
土屋くんの父さんは、本業の傍ら、ネットで土星の輪っかを売るサービスをはじめ、大成功させていた。
「あんな輪っかなんか、誰が買うんだろうなあ」
と、父さんはなかばあきれたように言っていたが、そこには土屋くんのお父さんに対する羨望と嫉妬の気持ちが紛れこんでいたようだ。
父さんは悩みぬいたあげく、その話に乗った。
父さんは土屋くんの父さんから「輪っか」を安く売ってもらい、それを地球サイズに変更した。そして地球に合う色に輪っかを塗り替え、さらに輪の細部に僕には到底わからない微妙な調整と細工を施した。そうして「輪っかのある地球」を完成させた。
しかし、それが世に出ることはなかった。
僕は土屋家とのコラボレーションを楽しみにしていたし、今回の父さんの格別な熱の入れようを知っていたから、父さんのその挫折をひどく残念に思った。
「あなた、どうしてあきらめちゃったの?」
と母さんが声を落して父さんにたずねた。すると父さんは、
「あの輪っかは、地球には向いてないよ」
と今更のようなことを言った。
「次の地球儀をみんなが買えば、世界は良くなるんでしょ?」
と僕がたずねると、父さんは、
「どうせ、輪をかけて、悪くなるさ」
と今にも泣きだしそうな声で答えた。
僕もなぜだか泣きそうだった。今まさに溢れようとする涙は、父さんへの同情なのか、失望なのか、僕自身にはわからなかった。
*
そんな父さんの一番の理解者は、愛猫のウミだった。
父さんと母さんはときどき喧嘩することがあったが、父さんとウミはいつでも仲良しだった。
ウミはまさに海のような青い目をした白猫だ。
地球儀を作る父さんの膝の上がウミの特等席だった。作業に熱中する父さんに甘えるようにウミがミャアと鳴くと、父さんはその頭や体を優しい手つきで何度も撫でた。まるで完成したばかりの地球儀のつるつるした表面を撫でるように、優しく。
そんなウミが、このあいだ、うちを出ていってしまった。
朝から涼しい風の吹く土曜日のことだった。父さんがいくらウミの名前を呼んでも、ミャアと答える可愛い声は、狭いうちのなかに響かなかった。
「ウミは、地球を出ていってしまったんだ」
と父さんは落胆して言った。その落ち込みようは、「輪っかのある地球」の発売を断念したときよりも深く大きなものだった。
悲しみに打たれた父さんは、しばらくのあいだ店を開けなかった。
*
いくらかの日々が過ぎたあるとき、父さんは宇宙探査船の作製をはじめた。その探査船はもちろん、ウミを探しだし、我が家に連れて帰るためのものだ。
船ができあがるまでには長い時間がかかった。そのあいだ父さんは寝ることも食べることも忘れて、宇宙船作りに没頭した。その姿には鬼気迫るものがあった。
蒸し暑い初夏のある日、ついに完成した船は、じつに父さんらしい、細部にまでこだわりのつまった、見た目は派手でゴージャスだが、どこかぬくもりの感じられる優しいデザインの宇宙船だった。
その日、父さんは「やりきった」というような清々しい表情をしていた。
できたての船に乗り込む前の日の夜、父さんは僕を作業場に呼びだして、僕の頭を優しく撫でながら言った。
「しばらくのあいだ、うちを空けるから、母さんのこと、よろしくたのむぞ」
僕は静かに深くうなづいた。
「家業のことは、おまえが大人になってから考えればいい。せめて、このことだけは憶えておいておくれ。人には地球がなくてはならないし、地球儀だって、なくてはならない」
「父さん、僕も一緒に行くよ」
と僕は強い決意を声に表して言った。
「ありがとう。けれど、これは危険な旅だ。おまけにいつまで続くかわからない。おまえを連れて行くことはできないよ」
僕は泣いた。今度の涙は、さびしさに満ちた温かい涙だった。
*
父さんの出発の日が来た。
朝の光に照らしだされた宇宙船は、間近で見ると、とても大きくて神々しかった。ウミがこの船を見つけたら、立てた尻尾を小刻みに振って飛び乗ってくるに違いない。そして父さんの膝の上で、ミャアと可愛く鳴くだろう。
父さんの旅は、おそらくは宇宙の歴史のように長い旅になる。
しかし宇宙船の大きな窓からは、地球の姿が見えるはずだ。父さんは地球儀作りの腕に磨きをかけて帰ってくるだろう。母さんは確信をこめてそう言ったし、僕もそう思う。僕はなによりもそのことが楽しみなのだ。
ウミと父さんは、そのうちすぐに出会うだろう。暗い宇宙のなかで、ウミのきらきら輝く青い目は、ひときわ目立つだろうから。
(終)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
