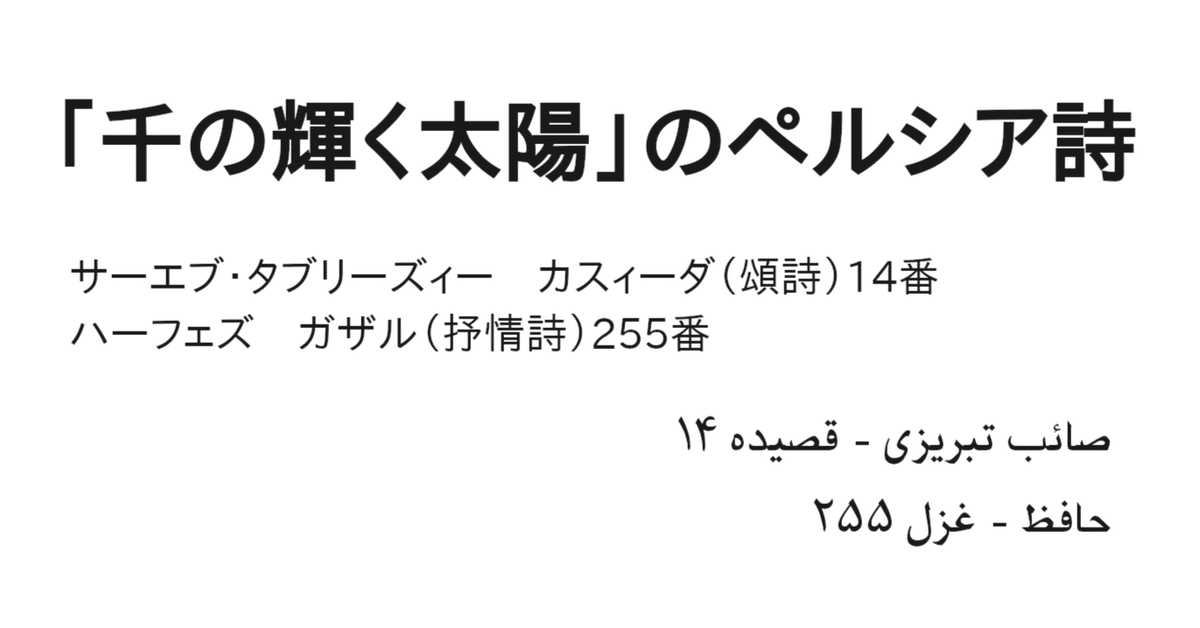
「千の輝く太陽」のペルシア詩
昨年末、アフガニスタン系のアメリカの作家カーレド・ホッセイニ(ハーレド・ホセイニー)の小説「千の輝く太陽」を読みました。アフガニスタンを生きる二人の女性、マリヤムとライラの物語。中盤以降は、涙でしばしば読むのが中断しました。私の表現力では、この物語の感想を的確に言うのは困難かもしれません。いずれにせよ、多くの人が読むべき物語だと思っています。
ところで、この「千の輝く太陽」にはいくつかの詩が出てきます。この拙文では、小説のタイトルの由来にもなっているサーエブ・タブリーズィーの詩と、物語の終盤に出てくるハーフェズの詩を紹介したいと思います。いずれもペルシア語(「千の輝く太陽」の文中では「ファルシ語」)の詩です。両詩人とも現在のイラン出身ですが、字訳はアフガニスタンのペルシア語(いわゆるダリー語)の発音風とすることにします。韻律は「V」を短、「_」を長とします。
なお、「千の輝く太陽」は原著は英語ですが、私が読んだのは今のところ日本語訳のみで、英語版は未確認であることをご了承ください。
サーエブ・タブリーズィー
サーエブ・タブリーズィー(صائب تبریزی / Saib Tabrizi)は、Wikipedia英語版によると1592年生まれの1676年没。故郷は名前のとおりタブリーズ(イラン北西部アーザルバーイジャーン地方の主都)で、イラン中部のイスファハーンで没したようです。
作中で引用され、小説のタイトルの由来にもなっているサーエブ・タブリーズィーの詩は、彼がカーブル(カブール)を訪れた時に詠んだカスィーダ(頌詩)14番の第9対句です。
حساب مه جبینان لب بامش که میداند
دو صد خورشید رو افتاده در هر پای دیوارش
Hesāb-e mah jabīnān-e lab-e bāmash ke mēdānad
Do sad khorshēd rū aftāda dar har pā-ye dīwārash
(韻律: V _ _ _ V _ _ _ V _ _ _ V _ _ _)
(カーブルの町の)屋根の縁にある月の眉の数を誰が知っているだろう
二百の太陽の顔がそれぞれの壁の下に隠れている
小説の原題は「A Thousand Splendid Suns」すなわち「1000の輝く太陽」ですが、ペルシア原文では上記のとおり「200の太陽」となっています。
現代のペルシア語では、アフガニスタンでは「200」をこの詩のようにدو صد(do sad)と言い、イランではدویست(devīst)という別の単語を使います。このような違いがサーエブ・タブリーズィーの時代にあったのかどうかは未把握ですが、もし当時既にこのような違いがあったとしたら、サーエブは「カーブル風の表現」であるدو صدを使うために200という数字を選んだのかもしれません。
一方、英語では200という数字に特別な意味合いは無いということもあってか、ハーレド・ホセイニーが参考にした英訳では「1000」と意訳されているようです。ペルシア語版Wikipediaによると英訳はDr. Josephine Barry Davisという人によるもののようで、「1000」とした訳のほかに「数百」とした訳もあるようです。
ハーフェズ
ハーフェズ(حافظ / Hafez)は史上最も有名なペルシア語詩人の一人。黒柳恒男「ハーフィズ詩集」によると1326年頃生まれの1390年頃没。シーラーズ(イラン中南部ファールス地方の主都)で生まれ生涯の大半をシーラーズで過ごしシーラーズで没しました。
作中で引用れているのは、ガザル(抒情詩)255番の第1対句および第6対句です。
یوسف گم گشته بازآید به کنعان غم مخور
کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور
ای دل ار سیل فنا بنیاد هستی برکند
چون تو را نوح است کشتیبان ز طوفان غم مخور
Yūsof-e gom gashta bāz āyad ba kan'ān gham makhor
Kolba-ye ahzān shawad rōzē golestān gham makhor
Ay del ar sēl-e fanā bonyād-e hastī bar konad
Chon to rā Nūh ast kashtībān ze tūfān gham makhor
(韻律: _ V _ _ _ V _ _ _ V _ _ _ V _)
道に迷ったヨセフは再びカナンに帰る。悲しむな。
悲しみのコルバ(小屋)はいつか花園になる。悲しむな。
心よ、もし消滅の洪水が存在を破壊するとしても、
ノアがお前を颱風から救う船長となる。悲しむな。
ハーフェズの詩の原文には、小説の中でしばしば登場するコルバ(کلبه/小屋)という単語が出てきます(作中の引用では「あばら屋」)。
詩の中のこの言葉を見るたびに、小説の中の情景が思い起こされ、涙が溢れてきます。しかし、直後の「花園になる」「悲しむな」という言葉に、それでも歩み続ける登場人物たち(そして我々)の進むべき道が要約されているように感じます。
詩の朗読
YouTubeにハーフェズのガザル255番の朗読(アフガニスタン音、英語字幕付き)がありました。
第1対句は0:08〜、第6対句は1:13〜です。
余談
ペルシア語版Wikipediaによると、「千の輝く太陽」は10以上のペルシア語訳が出ているようです。
参考
カーレド・ホッセイニ、土屋政雄訳「千の輝く太陽」(2014、早川書房)
ハーフィズ、黒柳恒男訳「ハーフィズ詩集」(昭51、東洋文庫)
https://allpoetry.com/poem/8541977-Kabul-by-Mirza-Muhammed-Ali-Saib
サポートをいただけるととても励みになります! 頂いたサポートで、外国語に触れる旅に出かけます!
