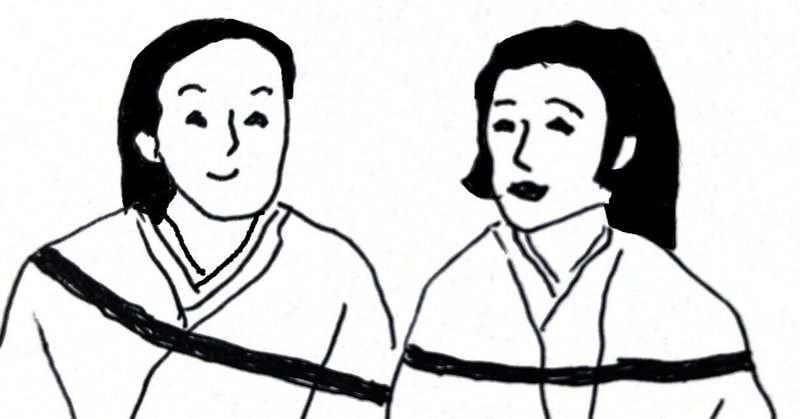
「光る君へ」溜まりに溜まったうろ覚えレビュー前半《第15話~17話》
うろ覚えレビューをかためてやる。
なんだよそれは、という方もいらっしゃるかもしれないが、ここ1ヶ月半ほどレビューできなかったのは、ひとえにあたしの力不足である。
仕事でテンパると他の余裕がなくなるのだ。ごめんなさい。
かためてやると、ますますうろ覚えになっちゃうのであるが。
ただ、このレビューは止まることはあっても辞めるつもりはないです。
では早速いってみよう。語ることは山程ある。
今回もドラマ中の名セリフをからめてみよう。
■第15話:おごれる者たち
父親の兼家の後継者として摂政の地位を得ることもできず、妻にも子にも捨てられた藤原道兼。以前彼について行くと言っていた藤原公任の屋敷に居座り、酒浸りの生活を送っていた。以前も道兼はまひろの父親の藤原為時の家に急にやってきたりしたが、わりと相手の都合は考えないのだ。しかし、そんな情けない生活をしている道兼に弟の道長が救いの手を差し伸べる。
「この道長がお支えしますがな。」
また道長の株があがった。優等生すぎる。
一方、道兼の兄で一条天皇の摂政・藤原道隆の横暴がエスカレート。彼に関係する人々が66人も位を上げた。政界のルールブックみたいな藤原実資も不満げだ。道隆の息子の藤原伊周も、『枕草子』の中に描かれたような好青年ぶりとは違って、ただの自信過剰なヤなやつである。道長との「弓比べ」の様子では、頭の中は自家の繁栄と関白の座狙いしかないことが丸わかりだった。矢は的を外れちゃったけどね。
15話であたしが特に注目したいのは、まひろがさわと一緒にでかけた近江国の石山寺詣で出会った人物。藤原兼家の妾であった藤原道綱の母だ。
『蜻蛉日記』の著者である道綱の母の言葉、
「日記を書くことで心の痛みを癒やしましてん。」
「書くことでおのれを悲しみから救ったっちゅーわけですねん。」
にまひろが感銘を受けた。これこそ間違いなくまひろが『源氏物語』を書く未来へ向かって張り巡らされる細やかな伏線のうちの1本である。

■第16話:華の影
今まで(今も)まひろとさわがなんで仲良しなんかちっともわからんかったけど、あの2人が合う気がしない。
友人と旅行に行って初めて相手の本当の姿がわかり、しんどくなったりすることがある。あたしにも苦い経験あるけどねー。
とにかくさわは、石山寺で会った藤原道綱の母とまひろとの『蜻蛉日記』についての会話についていけず、またお調子者の藤原道綱の夜這いの目的の女性とは、本当はまひろで、さわじゃなかったことが判明してずいぶんいじけてしまった。まひろが意地悪なわけではないけれど、2人にとってちょっと苦い旅となったようだ。
摂政の藤原道隆という人物は、14話あたりくらいまでそれほど悪人のイメージがなかった。だから彼の横暴な態度はどこか上滑りな、無理してる感が漂う。権力の頂点にあった道隆にとって、巷で流行る疫病で死んでいく民のことよりも、内裏の放火事件のほうがシリアスな問題らしい。
「光が強ぉーなったら影は濃ぃーなるやんけ」
つまり、権力を持つ者はそれなりに恨みも買うけどしゃーない、的なことを言ってのけた。
そんな兄を頼れない道長は、疫病に苦しむ庶民を助ける施設・悲田院の様子を自分で見に行こうと考える。
当然ながら、疫病が蔓延する場所に出かけるにはリスクがある。
それを、酒浸りの生活から道長に救われたあの道兼が引き止めていう。
「都の様子はわてが見て来たるわ。汚れ仕事はわての役目やさかいにな」。
いや、まじか。これだよ。この道兼は、ちょいちょい名言を吐く。
不良少年が雨に濡れる捨て猫に傘を差し掛けただけで「善人」へとステータスが爆上がりするように、ワルだった登場人物がちょっといいことすると、心がゆさぶられてしまう。ここは今回の目玉シーンの1つであった。

結局、道長も道兼と一緒に悲田院に向かう。
実はまひろも人手の足りない悲田院で看護を手伝っていた。
そんな彼女もついに疫病に感染して倒れるのだが、倒れた先は道長の腕の中だった。

道長に自宅まで送り届けてもらい、そのまま一晩看病してもらうことに。その間まひろは一度も目を覚まさなかったが、病気と格闘中の彼女に道長ってば、たいがい難しい質問を投げかける。
「生まれてきた意味な、もう見つかったん?」
「なんであそこにおってん?」
など。
特に1つ目の質問はドラマの根幹に関わる大切なものなんだが、Yes/Noで回答できない内容であり、病気でほぼ意識のない人にする質問ではない。
死にそうになってるのに、生まれてきた意味を考えるなど、ちょっと大変。
さらに道長はこうまひろに叫ぶ。
「往くなや。戻って来ぃーやぁ」
これはグッド。
死にそうだけど死んじゃ困る人には、こういう声がけこそ大切だ。
彼の献身的な看護の甲斐あって、後日まひろは回復する。
その点は心配してなかったけれども。
ききょうは、前話でついに「清少納言」の名を定子に与えられていた。
早速『枕草子』で非常に有名な「香炉峰の雪」のエピソードも登場。華やかな定子サロンを演出する逸話だ。
その後の定子たちの雪遊びの場面は、あたし的にはかなり好きだった。
庭木がクリスマスツリーみたいだったし。
ところで、なぜか「香炉峰」ってすぐに言葉が出てこないんですが。
いつもまず「回鍋肉」って心の中で言ってから、ちゃうちゃう、って思って「香炉峰」に着地する。
■第17話:うつろい
藤原道隆、死す。
水を飲みたがっていた場面があったから、飲水病、つまり糖尿病らしい。
酒好きだったので、酒のせいだとも言われる。
こうして時はうつろっていく。
一時は、さわとの交流が途絶えていたまひろだったが、さわがまひろにわびを入れにやってきた。さわは悪い人ではないのだ。好きではないが。
まひろの手紙から何かを学ぼうとしていた。
自分の手紙がさわの心を捉えたことを知ったまひろ。
「何を書きたいんか分からへん。せやけど、筆を取らずにいられへんねん」ひとり考える夜、彼女はそんな気持ちに気がついた。
そういうことは、ひとりの時にしか考えないものなのだ。
こうして、まひろがまた『源氏物語』へと歩を進める。
ちなみに偶然ではあるが、「何を書きたいんか分からへん」という状態は、まるで仕事中のあたしである。
さて、平安時代の女性というのも、現代と変わらずなかなか鋭い。
その①
道長の正妻である源倫子。昔は天然入ったお嬢様だったが、すっかり冷静沈着な大人となった。道長がまひろを一晩看病していたときのことを、夫の様子から感じ取る。
「殿のお心にはあてやなくて、明子様でもあらしまへんもう一人の誰かがいたはりますわ」。
お見通しである。いつかまひろと道長の関係がわかったらどうなるのか。
その②
清少納言はすっかり宮中での暮らしに慣れてきたのか、かつて関係のあった藤原斉信に冷たいこと、冷たいこと。
「自分の女みたいに言わんといてぇな。ねちねち聞くあんたほんまにいややわ」
かなりきっつい。身分の差を考えても、強気すぎるのではないだろうか。
だいじょぶ?
『枕草子』には、藤原斉信は次第に登場しなくなっていき、入れ替わるようにして藤原行成が登場する。

<後半へつづく>

