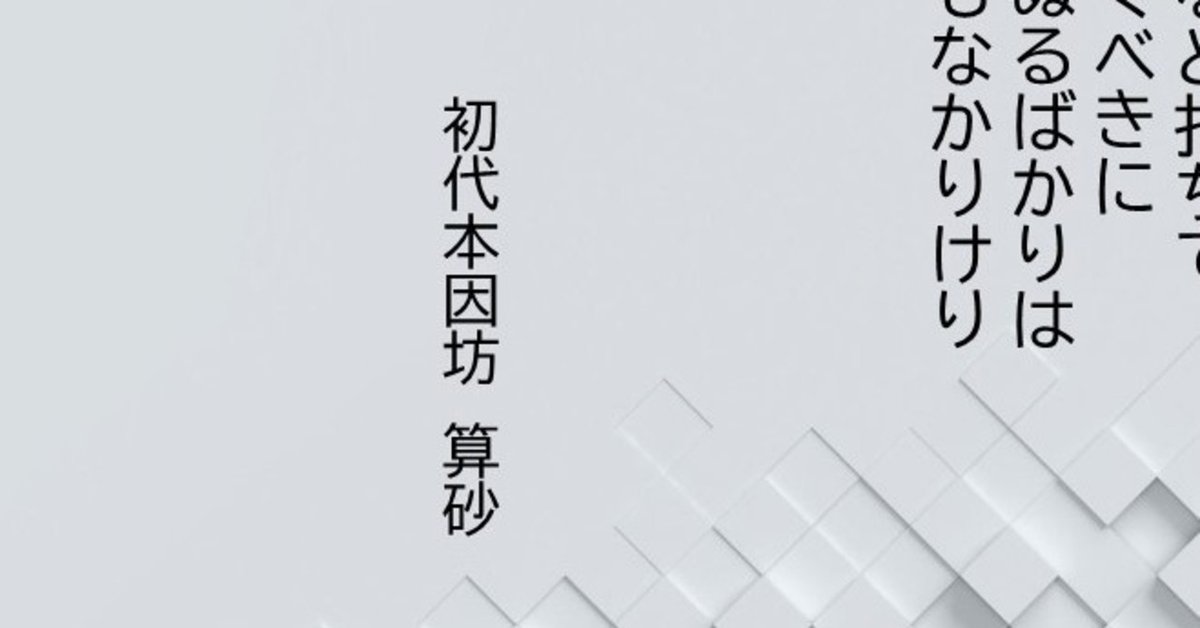
初代本因坊 算砂の辞世 戦国百人一首㉘
わが国最初の囲碁棋士、これが算砂(さんさ)(1559-1623)である。
将棋の名手でもあった。
戦国の三大英傑である織田信長、豊臣秀吉、徳川家康に囲碁を指導したという算砂が遺した辞世には、囲碁が登場せずにはいられなかった。
この世を去るというときに、算砂の辞世は笑いを誘う。

碁なりせば 劫(こう)など打ちて 生くべきを
死ぬるばかりは 手もなかりけり
もし囲碁であれば、死にそうな局面でも劫で粘って生きることもできるのに、自分が死ぬとなると打つ手がないものだ
辞世狂歌ともいうべき一首だ。
囲碁を知る人ならば、可笑し味が理解できるだろうが、ここで簡単にこの歌の「笑いどころ」を説明しよう。
*以下、囲碁くまブログさん https://igokuma.com/igo-rule5/ の画像をお借りして説明する。
「劫(コウ)」とは、囲碁用語である。
囲碁は石が1つだけ孤立している場合、上下左右に相手の石を置かれると、囲まれてしまった石は盤面から取り除かれてしまう。

だが、そのあとは今度は白黒逆転して、取られた黒があった場所にもう一度黒を置けば、白の碁石を取り除けるのだ。

つまり、お互いにこの方法で相手の碁石を取ろうとすれば、延々と同じ事が繰り返されるきりのないものになる。この状態を「劫」という。
「劫」とは囲碁用語だが、仏教用語でもある。
仏教では、無限ともいえるほどの長い時間の単位を意味する言葉が「劫」だ。つまり未来永劫(みらいえいごう)の「劫」なのだ。
そこで、局面でこの「劫」が生まれると、延々と同じことの繰り返しを避けるためのルールがある。
つまり、「劫」を取ったのが白ならば、黒はすぐに「劫」を取り返すのではなく、一手別の場所に打ってからでないと「劫」を取り返すことができない。別に打ってから取り返す。
反対も同じで、相手の白も一手を別に打ってからならば「劫」を取り返すことができる。
別の一手を打っていく間に局面は変わり、その間に
・相手の石を全部取る
・自分の石を取られないように守り切る
・打つ手がなくなる
・最後の「劫」の勝ち負けが勝負に結びつく
などで最終的な勝負が決まるのだ。
算砂は、そんな囲碁のルールをふまえてこの辞世を詠んだ。
「囲碁だったら、死にそうな石でも劫を作って粘って生かすチャンスを作れるというのに、死にそうな自分については打つ手がないよ・・・」
そうボヤいているのである。
「劫」の説明ばかりになってしまったが、辞世にまで囲碁を詠んだ算砂とは、スゴ腕の棋士というだけでなく、8歳の頃から出家した寂光寺塔頭本因坊の僧侶でもあった。
1611年には僧侶としての最高位「法印」に叙せられている。
信長が「名人なり」と称賛した。
また秀吉の御前で対局に勝ち抜いた算砂は扶持を与えられた。
家康にも招かれ、江戸幕府からも扶持をもらい、囲碁の家元本因坊家の始祖となった。
プロ中のプロである。
さて、1582年、本能寺の変で織田信長が明智光秀によって討たれた。
事件の前夜に算砂が信長によって本能寺に招かれ、彼の前で算砂のライバル囲碁棋士である利玄との対局を行っていたという逸話が残る。
それが本当の話ならば、織田信長の死は算砂にとって衝撃的なことだったに違いない。
