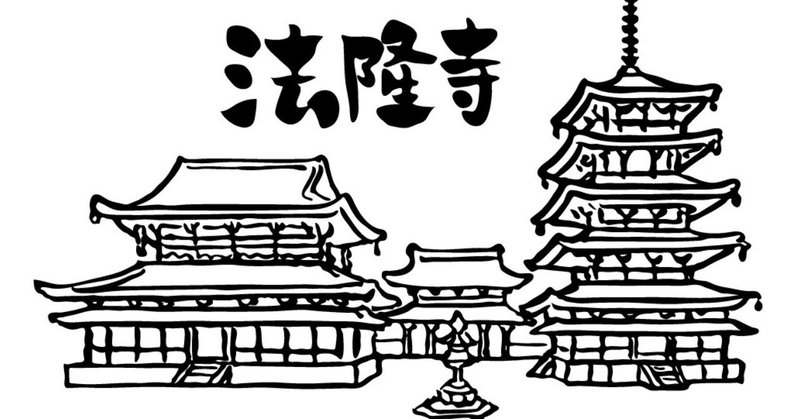
法隆寺にあるもう一つの世界最古 百万塔陀羅尼
ユネスコの世界遺産に登録されている法隆寺の建築群。西院伽藍は、現存する世界最古の木造建築群として今も多くの人々がその地へ足を運ぶ。実は、ここにもう一つの世界最古と呼ばれるものがある。それが国の重要文化財にも指定されている「百万塔陀羅尼」である。
百万塔陀羅尼とは何か
770年、称徳(しょうとく)天皇の発願によって100万基の小塔とその中に納められる経が作られた。これが百万塔陀羅尼である。陀羅尼とは経のことで、正式名は「無垢浄光大陀羅尼経」という。そしてこの経は、制作年代が明確なものとしては世界最古の印刷物なのだ。
百万塔陀羅尼製作の理由
【政治的背景】
奈良時代の末期。学識にすぐれた僧・道鏡は、女帝・孝謙太上天皇に取り入ったとされ、重用された。そのことを不満に思った太政大臣・藤原仲麻呂は、道鏡を排斥して政権を奪取するためのクーデター(恵美押勝の乱)を起こす。対立した2つの勢力は、お互いに多くの死者を出し、結局、藤原仲麻呂は斬殺されてしまった。仲麻呂側についていた淳仁天皇は位を剥奪されて流罪となった。そして、孝謙太上天皇は重祚(ちょうそ/退位した天皇が再度即位すること)し、称徳天皇となったのである。
【目的は死者の供養と平和祈願】
百万塔陀羅尼は、このクーデターで亡くなった多くの供養と平和祈願のために称徳天皇の勅願によって製作されたものである。約6年の歳月をかけて製作された100万基の小さな三重の塔にそれぞれ一つずつ100万の陀羅尼経を印刷して納められた。正確には、一万節塔(いちまんせっとう)一万基ごとに七重小塔が作られた。約50cmの高さのものを100個。
十万節塔(じゅうまんせっとう)十万基ごとに十三重小塔が作られた約60cmのものを10個。
そしてそれらは、当時の大寺院10ヶ寺にそれぞれ10万基ずつ奉納されたのである。
それらの寺とは、奈良の大安寺(だいあんじ)、元興寺(がんこうじ)、東大寺(とうだいじ)、西大寺(さいだいじ)、薬師寺(やくしじ)、興福寺(こうふくじ)、法隆寺(ほうりゅうじ)、川原寺(かわはらでら)、大阪の四天王寺(してんのうじ)、滋賀の崇福寺(すうふくじ)である。
そのうち現存する塔は、法隆寺に保存されていた4万5千基ほどのみで、陀羅尼経は約2千巻である。
塔と陀羅尼経をどうやって作ったのか
この塔と経のすごさは、ひとえにその膨大な数を5年半から6年で仕上げたことにある。塔をつくる工場も機械もなく、実に膨大な数の職人が手作業で塔作りに従事したと考えられる。
【こけしのように作った木製の塔】
木造の塔は、全体の高さが約21cmの三重の小塔だ。塔頂部に栓をするような形になっており、その栓を抜くと、中に5.4cmほどの幅の巻紙に書かれた経が入っている。塔の底は直径約10.5cmの円形である。
ろくろを使って製作されたこの塔は、いわばこけしを作るような要領で木を削って作られたものだ。
実は、塔の底に製作した職人の名前や製作年月が墨で記録されている。調査によると約2000基作るのに、200人近くの職人が参加したことが名前で確認されている。全部で100万基作ったのだから、ものすごいマンパワーが費やされたことが想像されるのだ。
【印刷された陀羅尼経】
塔に納められた陀羅尼経の経文にも自心印、根本、相輪、六度という4種類があり、それぞれ経文の長さが違う。最も長い根本陀羅尼経は、長さが約51.5cm、短いものは27.2cm。1列5文字整然と配置されており、これらはもちろん手書きではない。印刷物である。しかし、現在のところそれらが木版で印刷されたのか、銅版だったのかは明確には分かっていない。当時の印刷レベルでは木版だったと考えられるが、木版が100万部も摺れるほどの耐久性があったかについては疑問が残る。しかし、当時銅版が製作可能だったどうかも疑問なのだ。
おわりに
この百万塔陀羅尼こそが作成年月の明らかになったものとして、世界最古の印刷物である。世界遺産の法隆寺に眠っていた百万塔と陀羅尼経。当時の技術を駆使し、朝廷の威信をかけて作られたこれらは、日本の工芸技術、印刷技術の向上の歴史における一つのステップを印す大切な記念碑でもある。
