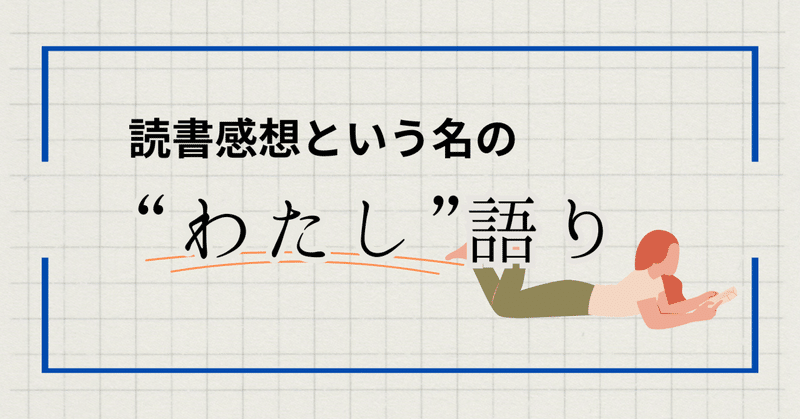
絶対に終電を逃さない女『シティガール未満』読書感想
◉前置き…読書という名の“わたし”語りとは、その名の通り、読んだ本について、思ったことなど自由に、とても自由に書いています。
⏩バックナンバー
時折私は、ビビッとくる本を求めて本屋をぷらぷら彷徨う。そして財布を開きため息をつく。また今度…と欲しいものリストに入れて本屋を立ち去る。そして思い出した時に、そうだ買ってしまおうとポチる。ネットでポチるのではなく、本屋で買えば良かったなと思いつつ。
本作もそんなビビッときた本の一つ。著者名もタイトルもいい。私は意図的に終電を逃すこともあるし、ボケボケして意図せずに終電を逃すこともある。更には、終電に乗り、駅員さんに起こされてハッとして降りたら終着駅だったりする。
ちなみに私は埼玉県生まれで、東京に対する憧憬は全くない。都心の人混みは昔から苦手であったが、20代後半にして都心に耐えられる体力がなくなったきたように思う今日この頃。都心に通える郊外の住宅地がやはり落ち着くなと、現在は区民ではなく市民として東京に住んでいる。
そんなどうでもいい話を本作の印象的な部分を引用しつつ語っていきたいと思う。
●歌舞伎町のサブカルキャバ嬢(p.56)
いわゆるサブカル的な前提知識を共有している若い女性なら、誰でもよかった。しかも場所は一杯数百円の安居酒屋とくれば、同じ歌舞伎町のキャバクラよりも遥かに安上がりで、私はいわばサブカルキャバ嬢だったというわけだ。
この感情は私も覚えがある。とある映画関係の仕事をしている男性と知り合い「こんな映画も知ってるの?若いのに何者?」と気に入られご飯に行くことに。少々嫌な予感もしたが、映画関係の記事を書き始めたばかりの私は、繋がりが欲しいという思いもあった。私も私で下心はあったわけだが…。
まあ、蓋を開けてみれば自分の仕事自慢ばかり。私が何か話せば、自分の話題に持っていってしまう。これは対話ではなく、接待だな。「あの映画も!凄いですね〜」と大袈裟に驚く。このような時私はシンバルを叩く猿の人形のような同じ動作を繰り返す人形になった気分になる。
とはいえ、接待と割り切ればまあ乗り越えられなくもない。しかし、接待となれば割に合わない接待はしたくない。そんなことを思う私だが、仕事の安月給のひもじさを補うためと社交性向上プロジェクトの一環(私が勝手に自分に課しているプロジェクトである)として始めたスナックバイトでは、給料をいただいているのに、この愛想のなさ、接客の下手さが許されていいものか…と定期的に落ち込んでいる。まあそんな話はいい。
●渋谷PARCOとオルガン坂(p.74)
他人と容姿の美醜を競わされるコンテストからも。自分の外見を美しいと思えるまでクリアできないゲームからも、早く降りたいと願いながら、完全には降りられていないのだ。
●渋谷スクランブル交差点(p.101)
ナンパされた話をすると、自慢だと解釈されることが往々にしてある。ナンパなんて若い女なら誰でもされる、本物の美人はナンパされない、などといったマウンティングがおまけで付いてくることも多い。(〜中略〜)「自虐風自慢」だと言われてしまう世の中である。
長年のもやもやを見事言語化してくれたと、嬉しくて涙が出るような言葉であった。私の場合、年子の姉と外見を幼少期から比べられ続けていた。外見に対する呪縛から逃れられないのは身内による視線と植え付けられた外見至上主義によるものが大きい。
私にとっておしゃれはいつしか無難を身に纏って自分の存在を消すためのものになっていた。目立つことから逃げることで視線から逃れたかった。そして、大きくなるにつれ、無難な可愛さを纏うことでキャッチやナンパに声をかけられるようになった。
そしてナンパを自虐風自慢ととられてしまう風潮も分かる!と大きく頷く。外国の方に道を聞かれ、拙い英語で話しながら、自分も同じ方に向かうので途中まで行きますよと歩いていると、何故か路地裏に連れられ、道案内ではなくナンパであったことに気づいた時は身の危険を感じた。
怖かったと親に言うと、「俺だったら外国人の女に声かけられてナンパされたら嬉しいけどな」とニヤニヤしていた父の言葉に怒りが込み上げる。男性より女性の方が体格的に勝てないと恐怖を感じる瞬間は比較的多いのではないだろうか。父はきっとそんな経験がない。その上、ナンパは女性として認識されている証で、そんなものは交わしてナンボだと思っている人間である。いつまでも理解し合えない溝を感じつつも、負けるのは癪なので、言い返してしまう私は子供だろうか。
また、メイクをせずジーンズを履いて街中を歩いていると声をかけられなくなる。しかし、私はそんなにファッションやメイクにこだわりがあるわけでも、好きなわけでもないが…それらは私なりの武装であって、メイクをせずに街中を出歩くことはどこか頼りないのである。メイクをして、納得できる服を身に纏って都会へ繰り出したいのだ。しかしそれがナンパしやすいちょろさと見られてしまうのが悔しくて仕方ない。
●御茶ノ水 神田川の桜(p.137)
集団生活を強いられない大学生活を送る中で新学期の不安が薄れつつあったことも手伝って、この日を境に、桜を見ると素直に綺麗だと思えるようになったのだった。
思えば私も桜が好きではなかった。というよりも春が嫌いであった。友達が少ない私はクラス替えが近づくにつれ憂鬱が増すし、別れのセンチメンタルも、新学期のそわそわした空気の馴染めなさも、社交的な友人を恨めしく思うのも何もかも嫌いだった。
大学生の頃はまさにインスタ映えが世界を牛耳っていた。桜を撮るという行為自体が映えを意識していると思われるのが嫌という変な逆張り。そんな自意識も抜けてきたのが社会人になったここ数年ではないかと気づいた。そうか、気付かぬ間に私も素直に桜を綺麗だと思えるようになっていた。
●原宿 TOGAの靴(p.177)
本を出せたら死んでもいい。
一番ずきゅーんとやられた言葉かもしれない。私は何がきっかけなのかもよく分からないが、本が好きで自然と私は本を出すのだと思っている。実現していないが、いつかするんじゃないと希望的観測のような確信のようなものを感じている。
そのために何かしているかというと何もしていないが、今の時代はnoteもそうであるし、SNSの発達で文章を書いて発表することのハードルはかなり下がっている。ある程度の承認欲求は満たされてしまうという。商業出版はそう簡単にできるものではないのだけれど。
最後に
言いたいことは一通り言ったが、総じて何を言っているのか、何が言いたいのかは、正直自分でもよく分からない。しかし、読んで共感したことを誰かに言いたくなるのがエッセイと言うものだと私は思っている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
