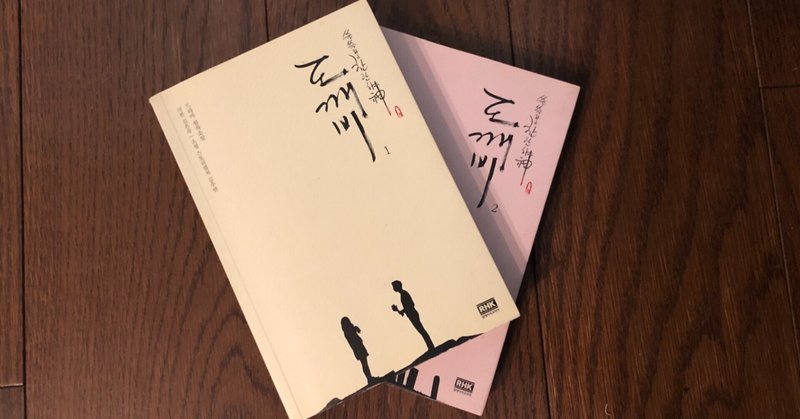
【韓国文化研究者の韓国ドラマ考察】「トッケビ」第3回:見えない文化を考える
このドラマの面白さは、韓国の宗教文化・説話と現代的ラブロマンスのフュージョンにあります。今回は、(トッケビの花嫁としての)「運命」、(前世からの)「因縁(縁)」といった韓国ドラマ的な要素が、「記憶」というキーワードによって見事に編み上げられている点について考察します。
※ネタバレあります。
ドラマ「トッケビ」と「記憶」の問題:見えない文化の考察
「記憶し続けるトッケビ」と「記憶を失くした死神」は、後半で「記憶」における立場が逆転します。死神は「自分に関する記憶を取り戻し」、トッケビは全ての人の中で「自分に関する記憶を失い」ます。記憶し続けようと必死に願ったウンタクでさえも「トッケビの記憶」を失くしますが、前世の「記憶」を取り戻したサニーは、全てを「記憶」にとどめます。「記憶」は、このドラマのキーワードであることに間違いありません。
韓国ドラマと「記憶」といえば、冬ソナ以来、韓国ドラマ「あるある」なのですが、事故や病気などによる記憶喪失といった単調なものではなく、ストーリーと記憶とが複雑に絡み合い、登場人物それぞれが記憶にまつわり異なる状況に置かれるところが、シナリオのとてつもない進化を感じます。
韓国ドラマの「記憶」問題は、ドラマをドラマチックにするうえで単に都合が良いというだけでなく、韓国社会が大切にしている「価値観」であるようにも思えます。韓国で起きた歴史的な事件、事故は、それを忘れまいとする試みやイベント、行事などで記憶され続けています。
3・1節、光復節(8・15)は政府主催で記念式典が行われ、4・16のセウォル号沈没事故追悼や5・18(光州民主化闘争)、8・14慰安婦メモリアルデーにも、ろうそく集会や追悼イベントが行われ、遺族だけでなく市民も参加しています。これらのイベントで訴えているメッセージは「いつまでも忘れない」です。慰安婦の話題が混じっているので「いつまでも憎しみを抱き続けるのか」と誤解されそうですが、「いつまでも忘れない」のは「憎しみ」のことではなく、「私の人生とは関係のない人々だけれど、彼らが生きていた証しを私は忘れないように努力する」という意味です。
つまり韓国人が、ひときわ歴史的な記憶を大事にしているからということではなく、むしろノンポリも多く個人主義が加速する中、「自分と関係のない人の話」と切り捨てるのではなく、社会の「記憶」を風化させないよう、皆で大切に守り育もうとしているように感じます。そんな社会的な感覚が、「記憶」をテーマにしたドラマを作らせているとも言えるのではないでしょうか。
「見えない文化」を知る難しさ
文化には、衣食住といった「見えるもの」と、価値観やこだわりといった「見えないもの」とがあります。「見えるもの」は伝わりやすいですが、「見えないもの」は自分の中にある美学や価値基準で相手を判断してしまうため、うまく伝わらないばかりか、誤解につながることも多いです。
韓国の文脈でよく登場する「反日」。これは、非常に誤解の多い「見えない文化」の一つです。韓国での「日本」のイメージは、日本での「韓国」のイメージにくらべて、かなり重層的で広がりがあります。漫画やグルメといった大衆文化、平和憲法を持つ民主的で平和主義の国家、カメラや電子機器などの世界的技術国、戦前にはアジアを侵略した帝国主義国家…。これらが一体となって、「日本」というイメージができています。こうした中、解放後の韓国人にとって譲れない美学(見えない文化)となっているのが、「戦前の日本帝国主義の歴史を肯定してはならない」です。これは、戦前に大日本帝国を肯定して暮らしてきた(暮らしてこざるを得なかった)内省に基づいており、この点では「大日本帝国は良いこともした」と肯定することは美学に反します。でも、日本のイメージは戦前の問題だけで作られているわけではありません。
「反日」という「見えない文化」を知ったとき、日本社会は「韓国人は日本を嫌っている」と単純に捉えたようですが、韓国にとっての日本は、「好きか嫌いか」といったシンプルな二択の世界で捉えられるものではありません。韓国の中での日本情報と、日本の中での韓国情報とでは、量質ともに、今でも格段の差があります。(当然韓国の方が上ですよね。日本の韓国情報はびっくりするぐらい薄いですから)こうした情報格差も、両国の対日・対韓認識に大きな差を生んでいると考えられます。少ない情報から単線的な対韓認識を持つ日本人が、たくさんの情報から重層的な対日認識を持つ韓国人を見た時に生まれる認知バイアスが、日韓問題を複雑にしている要因の一つであると思うのです。日本人である自分が韓国をシンプルに捉えているからといって、韓国人も日本をシンプルに捉えていると思い込んでしまっているのです。
長年寄り添った夫婦が、パートナーのことを好きか嫌いかを一言で答えられないように、「見えない文化」の中身は非常に複雑です。内田樹先生もブログで書いていましたが、異文化を理解するときには、「複雑なものは複雑なままに」捉える必要があります。白黒論といった安易な単純化や、自分の持つ美学や視点からでのみ理解することは、相手への無理解につながる危険な行為なのです。KPOPアイドルの日本観だって同じですね。アイドルビジネスの側面だとか、歴史認識における美学もあるでしょうが、アイドルと日本のファンダムとの関係が、互いの人生になくてはならない「かけがえのない存在」であることもまた事実なのです。
ということで、話がそれましたが、「トッケビ」ネタはまだまだあるので、また別の機会に。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
