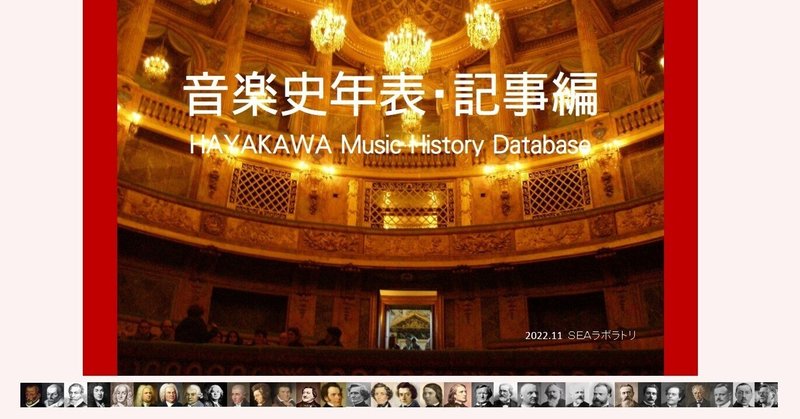
音楽史・記事編133.リストの創作史・ロマン派の大作曲家
古典派期からロマン派期の時代にイタリア人のパガニーニはバイオリンのヴィルトゥオーソとして一世を風靡していましたが、ロマン派期に登場したリストはピアノのヴィルトゥオーソとしてヨーロッパを席巻し、同時代に生まれたショパン、シューマンとともにロマン派の大作曲家となります。

〇リスト創作史の難しさ
今回のリストの創作史にあたり、本音楽史年表データベースに掲載しているリストの主要な約200作品から、さらに約1000作品への増補を試みていますが、リストの作品分類はたいへん難しく困難であり、リストの作品群の淵となりそうです。リストは36歳までヨーロッパ各地でピアノの名人的演奏で人気を得ていました。そのため作曲の目的は演奏会での演奏のためであり、同じ曲においてもピアノ独奏稿、連弾稿、2台のピアノ稿など多数残しており、しかも次々改訂を行い決定稿というものを残さず、常に即興的にピアノ演奏を行っていたようで、従って、文献により作曲年はまちまちであり、創作の過程の把握を難しくしています。
また、リストの作品番号の問題も大きく、エヴェレット・ヘルム著・野本由紀夫訳の大作曲家リスト(1)によれば、重要なリストの作品目録は5つあり、最も重要なものがラーベ(R**)の作品表であり次いで重要な作品表はサール(S**)のものであるとされています。本編では福田弥著・人と作品シリーズ「リスト」(2)に掲載のニュー・グローヴ音楽事典第2版による作品表(ABC順に分類)を使用していますが、リスト創作史における一番の問題は作品を特定すべき統一的作品番号が一般に利用されていない点にあるように思われます。最近のインターネットのyoutubeの検索により作品番号が特定されていれば容易に指定する楽曲を聴くことができるようになりました。例えば、ベートーヴェンの交響曲第9番の「歓喜の主題」の原曲と思われるモーツァルトのオッフェルトリウム「ミセリ・コルディアス・ドミニ」を聴こうと思えば、モーツァルトのケッヘル番号K.222を「mozart k222」と入力すれば容易に聞くことができます。しかし、リストの作品の場合、例えばリストがワーグナーの死去に伴い作曲した「リヒャルト・ワーグナーの墓に」のオルガン独奏版を聴こうとしたとき、ニュー・グローヴ作品番号E38を「liszt e38」と入力しても検索は不能であり、方法としてはサール作品番号S267を「liszt s267」と入力する必要があるわけですが、現在の文献ではニュー・グローヴ作品番号とサール作品番号の対比表は見当たらず(現在、ニュー・グローヴ音楽事典(原典)第2版の作品表を手配中です)、従って今回リストの年度別分類別作品集計を行ったものの、本編である音楽史年表データベースへの増補公開については、サール番号との対比が可能となった作品から順次、両作品番号を併記し公開することとします。
さらに、リストの創作史を難しくしている宗教音楽に触れておきます。リストはカトリックでありながら、ワイマールではプロテスタントのドイツ語の歌詞による宗教的合唱曲として旧約聖書の詩編に付曲しています。しかし、ローマに移って下位の聖職者に叙階されてからはラテン語の歌詞の詩編を作曲しています。当時政治的には神聖同盟により異なる宗派の融和が行われていたというものの、多くのリストの宗教的作品について題名によって歌詞の言語を類推するしかない状況となっており、リストの創作の解明を難しくしています。また、リストの大作であるオラトリオ「キリスト」はラテン語典礼によって作曲されており、このカトリックの宗教曲をプロテスタント地域のワイマールで作曲していたことが、ワーグナーとの軋轢を生んだ一因とも見られます。なお、ワーグナーの宗教観は歌劇「ローエングリン」と舞台神聖祝典劇「パルジファル」に現れており、聖杯の騎士ローエングリンの父を扱った「パルジファル」ではキリスト教の聖句「聖金曜日」が現れることから、聖杯の神がゲルマン民族由来の神ではなくキリスト教に関係しているのではと思わせられます。
〇リストとショパン、シューマン、後のブラームス・・・ロマン派のピアニスト
ショパンとシューマンは1810年に生まれ、リストは翌年の1811年に生まれており、ロマン派を代表する3人はいずれもピアノ音楽に関わっています。ポーランドに生まれたショパンはパリに移り、音楽史に残るピアノの傑作を残し「ピアノの詩人」と呼ばれています。ドイツのプロテスタントの家庭に生まれたシューマンはピアニストを目指したものの過酷な練習により右手を痛め作曲家に転身し、ドイツロマン派の申し子のようにピアノ作品の傑作を作曲し、ドイツロマン派を代表するピアノ協奏曲を作曲します。オーストリーとハンガリーにまたがるエステルハージ家の領内に生まれたリストは、バイオリンのパガニーニの影響を受け、自らは超人的なピアノのヴィルトゥオーソとしてヨーロッパを席巻し、ワイマールの宮廷楽長になると管弦楽の標題音楽である「交響詩」の様式を創始し、イタリアでは僧門に入り宗教音楽を作曲しロマン派の大作曲家となっています。一般にカトリックの聖職者は結婚を禁じられ独身を通しますが、リストに対する叙階は下位のものであり、この位では妻帯も可能であったとされます。
リストは1年先輩のショパンとシューマンには敬意を持っていたようで、ショパンの12の練習曲を愛奏しており、またシューマンの妻のクララとは共演を行い、シューマンとの結婚にあたっては「パガニーニによる超絶技巧練習曲」全6曲をクララに献呈しています。また、リストは演奏会でシューマンのピアノ曲を演奏し、ワイマールではシューマンの歌劇「ゲノフェーファ」の上演を行っています。しかし、リストとクララはともにピアノの名手でありながらその後は疎遠になっています。クララはリストとワーグナーが掲げる「新ドイツ主義」に対抗する反ワーグナー派のウィーンの批評家ハンスリック率いるブラームスと親しかったからと思われます。

ショパン、シューマン、リスト、ブラームスの創作史の年代をそろえて並べてみます。ショパンは短い生涯を通じてピアノ音楽の作曲を続け、シューマンは当初はピアノ音楽の作曲を集中して行い、クララとの結婚後は声楽曲、交響曲などの管弦楽曲、室内楽、歌劇や宗教曲など多彩な分野の作曲を行っています。そしてリストは36歳まではピアノのヴィルトゥオーソとしての活動とピアノ曲の作曲を中心に行い、ワイマールの宮廷楽長になると管弦楽曲やこれまで演奏で蓄積してきたピアノ曲も含めて幻想曲などに譜面化し、また宗教曲の作曲を行っています。
リストはヨーロッパ中の多くの作曲家の作品のピアノ編曲やトランスクリプションと呼ばれる編曲作品を手掛けています。モーツァルトやベッリーニ、ドニゼッティ、マイヤーベーアのオペラやワーグナーのオペラやヴェルディのオペラに及び、管弦楽曲編曲ではベートーヴェンの交響曲全曲やベルリオーズの幻想交響曲、バッハのオルガン曲からメンデルスゾーンの歌曲、フランスのサン=サーンスやシューベルト、シューマン、ウェーバーの歌曲など多岐にわたりその数は膨大です。これらは演奏会で演奏されたばかりではなく、印刷譜は広く家庭に拡散し、現代において管弦楽曲をLPやCDなどにより家庭で鑑賞するように、家庭のピアノ演奏で鑑賞されたものと見られます。1830年、ベートーヴェンが亡くなってから3年後にゲーテはメンデルスゾーンのピアノ演奏で交響曲第5番第1楽章を聴いており、次の感想が残されています・・・「これは感動させるなんてもんじゃない。・・・まったくとてつもない!今にも家が崩れ落ちそうだ」・・・(3)。メンデルスゾーンのピアノ演奏は年代からリスト版ではないと思われますが、リストの編曲は管弦楽の臨場感をみごとに伝えており、リストの多くの名曲の編曲は音楽普及に多大な貢献をしたことが伺えます。
〇リスト、交響詩様式を生み出しロマン派の大作曲家となる
リストはパリでベルリオーズの幻想交響曲の初演に立ち会っていますが、おそらくベルリオーズの途方もない巨大な音楽に度肝を抜かれた思いをしたにちがいありません。この時期、リストはピアノ演奏を中心に活動を行っており管弦楽に対する知識も乏しいなかで、それでも未完の革命交響曲作曲にチャレンジしています。リストは1848年ワイマールの宮廷楽長となりいろいろな管弦楽曲を指揮するようになり、管弦楽曲作曲法を習得して行き、1852年にはフランスからベルリオーズを招きベルリオーズ週間と題した音楽祭を催し、そして音楽史に残る交響詩「レ・プレリュード」を作曲し、その総譜の前文で交響詩の意義について述べています。描写音楽としては古くはヴィヴァルディの「四季」があげられ、ベートーヴェンの田園交響曲を経て、交響曲第9番の第4楽章に至ってはもはや音楽と詩は深く融合し、単に詩を描写するだけではなく詩の持つ意義を音楽に表した「歓喜の歌」に交響詩の原点があるのかもしれません。
〇リストと宗教、ワーグナーとの軋轢と和解
リストはドレスデンで革命運動に参加し逃亡してきたワーグナーをワイマールで匿い資金援助を行い、ワーグナーとは良好な関係を築きますが、やがて関係が悪化します。リストはワイマールで宗派の異なるウクライナの裕福な貴族の夫との離婚問題を抱えたカトリーヌ・ヴィトゲンシュタイン侯爵夫人を伴侶としていましたが、プロテスタントであるワーグナーとカトリックであるリストとは宗教的価値観に相違があったようにみられます。しかも、前の伴侶であったマリー・ダグー夫人との間の次女コジマが夫である名指揮者ビューローのもとを離れ、ワーグナーと駆け落ちするに及んで、とうとうワーグナーとの間は決裂したようです。そもそもリストはヴィルトゥオーソとして現代のアイドルのようにもてはやされ、パリのサロン界の女王マリー・ダグー伯爵夫人はリストを愛人としていました。長女のブランディーヌはスイスで生まれ、次女のコジマはイタリアで生まれています。しかし、ワイマールで出会ったカトリーヌ・ヴィトゲンシュタイン侯爵夫人は本気でリストとの結婚を考えていたようで、侯爵夫人を名乗っていたもののすでにプロテスタントの夫とは離婚し夫はすでに再婚しており、カトリックのカトリーヌは離婚を禁ずるローマ教皇庁に対し離婚を認めるように掛け合ったりしています。しかし、前夫との間の子の遺産相続問題で結局はリストとの再婚はあきらめたようです。
1872年、ワーグナーと妻のコジマはワイマールのリストを訪問し和解しています。高齢となったリストをいたわった結果かもしれません。リストはこの後、バイロイトも訪れるようになり1876年にはバイロイト祝祭大劇場で4夜にわたって行われたワーグナーの楽劇「ニーベルングの指輪」初演に立ち会っています。この時期、リストはローマ、ワイマール、ブダペストを数ヶ月ごとに回り、各地で音楽活動を行い、ハンガリーのブダペストでは音楽院院長に就任するなど、各地で大作曲家として敬愛され幸福な晩年を送っています。
【音楽史年表より】
1811年10/22、リスト(0)
フランツ・リスト、ハンガリー国境近くの現オーストリアのライディングに生まれる。(4)
1840年9/12、リスト(28)、ピアノのためのパガニーニによる超絶技巧練習曲A52、S140
パガニーニが1820年に出版した24の奇想曲Op.1からの6曲とバイオリン協奏曲第2番の終楽章からのピアノ編曲。40年9/12のロベルト・シューマンとクララ・ヴィークの結婚を記念してクララに献呈される。(2)
1851年、リスト(39)、ピアノのための「ハンガリー狂詩曲」第1番から第15番A132の1~15、S244
自らの祖国をハンガリーであると考えていたリストは、生涯を通じてハンガリーにかかわる素材を使った作品を残した。中でも最も知られているのが、ワイマール時代の15曲と晩年の4曲を合わせた19曲からなるハンガリー狂詩曲であろう。(2)
1854年2/23、リスト(42)、交響詩「前奏曲」(レ・プレリュード)G3、S97
ワイマールの宮廷管弦楽団の基金募集音楽会でリスト自身の指揮で初演される。(4)
1855年2/17、リスト(43)、ピアノ協奏曲第1番変ホ長調H4、S124
ワイマールでベルリオーズ指揮、リスト自身のピアノ独奏で初演される。すでに1832年にはスケッチが行われていたと考えられるが、ひと通り完成をみたのは1835年であり、このときは3楽章であった。39年の改訂で1楽章構成となり、49年の改訂では曲名が交響的協奏曲となりトライアングルが用いられた。53年にも改訂され、55年2/17に初演された。57年に初版が出版され作曲家のリトルフに献呈される。華麗な名技性が展開される一方で、大きな形式的枠組みのなかに、リスト特有の主題変容、激しい転調、半音階的書法が一貫して認められる。主題はそれぞれ最後に再現され、多楽章構成をとソナタ形式を融合しようという斬新な試みであり、そこにスケルツォ楽章を追加することで協奏曲の4楽章化も図られている。(2)
1856年8/31、リスト(44)、荘厳ミサ曲(グランのミサ)I2、S9
ハンガリーのブダペストの北西約40kmのエステルゴム(グラン)のバジリカの献堂式で初演される。リスト最大のミサ曲で、この作品に対する喝采と、初演が国費によってなされたことなどから、リストは宗教音楽の作曲を天職と思うまでに至った。リスト交響詩やピアノ・ソナタにおいて独自の境地を開いた革新的な手法と、保守的な表現を重んじるミサ曲の伝統手法が融合、昇華した傑作である。(2)
1873年5/29、リスト(61)、オラトリオ「キリスト」I7、S3
ワイマールのプロテスタントのヘルダー教会で、リストの指揮で全曲初演が行われる。ワーグナーとコジマが初演に出席する。救世主イエスの降誕から復活までを描いたリスト畢生の大作、1853年頃から構想を練り、62年に本格的に着手されたと考えられる。中断をはさみ、一通りの完成をみたのは66年であった。全14曲から構成され、アリアやレチタティーヴォといったオペラ風の楽曲は含まない。第12曲はヴェルディの作品とともに19世紀屈指のスターバト・マーテルに数えられる。1872年出版される。(2)
1886年7/31、リスト(74)
フランツ・リスト、23時半にバイロイトで死去する。(2)
【参考文献】
1.エヴェレット・ヘルム著・野本由紀夫訳、大作曲家 リスト(音楽之友社)
2.福田弥著、作曲家・人と作品 リスト(音楽之友社)
3.青木やよひ著、ゲーテとベートーヴェン(平凡社)
4.最新名曲解説全集(音楽之友社)
SEAラボラトリ
作曲家検索(約200名)、作曲家別作品検索(作品数約7000曲)、音楽史年表検索(項目数約15000ステップ)で構成される音楽史年表データベースにリンクします。お好きな作曲家、作品、音楽史年表をご自由に検索ください。
音楽史年表記事編・目次へ
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
