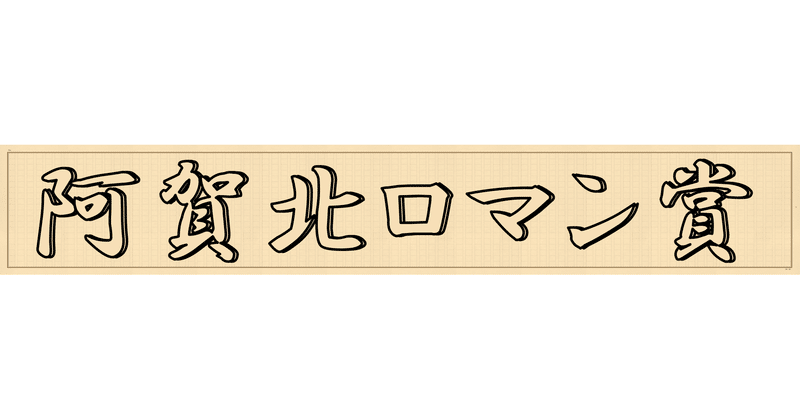
第九回阿賀北ロマン賞受賞作 小説部門 大賞『世界の余白』七瀬瑛
この記事は新潟県の阿賀北エリアの魅力を小説で伝えてきた阿賀北ロマン賞の受賞作を紹介するものです。以下は七瀬瑛さんが執筆された第9回阿賀北ロマン賞小説部門受賞作です。2020年より阿賀北ロマン賞は阿賀北ノベルジャムにフォーマットを新たにし、再スタートしています。<詳しくはこちら>公式サイト
小説創作ハッカソン「NovelJam(ノベルジャム)」初の地方開催を企画・運営しています。「阿賀北の小説 チームで創作 敬和学園大が初開催 筆者と編集者、デザイナー募集へ」 (新潟日報)→ https://niigata-nippo.co.jp/news/local/20200708554292.html
『世界の余白』七瀬瑛
私が高原さんと出会ったのは、一年ほど前のことだった。大学を卒業し、両親が阿賀野で営んでいる小さな旅館で働き始めて間もない頃だった。当時の私には仕事に対する熱意はもちろん、故郷に対する特別な思い入れはほとんどと言っていいほどなかった。都会で生きていけないことがわかっていたから、仕方なく地元で暮らすことを選んだのだから。
都会に出て働いてみたい――いや、私は都会で働くんだと思っていた時期が、私にもあった。華やかで、欲しいものがなんでも揃う『都会』という場所に憧れていたのだ。だから、東京で開かれるインターンや会社説明会に参加したこともあった。
だが、駄目だった。ぴりぴりとしたせわしない都会の空気に、馴染むことができなかったのだ。都会を歩いていると、突然、言いようのない寂しさに襲われる。周りにたくさん人がいるのに、一人ぼっちで大通りを歩いているような気がして心がすっと冷えていく。胸をかきむしりたくなるような、嫌な痛みが心をじわりと蝕んでいく。
ここは、おまえみたいなやつが来る場所じゃない。街そのものから、そう言われているような気がして怖かった。だから私は、地元で働く道を選んだのだ。
それでも、都会に対する憧れが完全になくなったわけではない。都心からはるばるやって来たお客さんを眺めながら、彼らが暮らす明るくて賑やかな街に思いを馳せることも多々あった。
そういうとき、私は決まって同じ疑問と対峙する。彼らはどうして、わざわざこんなところに来るんだろう――と。ここは自慢できるものなんて雪の量くらいしかない街なのに、どうして。この旅館に泊まりにくるお客さんは冬にぐっと数が減るから、雪ではない何かを目当てにやってくる人も多いのだろうが、目的が何であれ、やはり、都会からわざわざ田舎にやって来る理由が分からない。
だから、一月の下旬に、それも二週間のロングステイの予約が入ったと聞いたときには驚いた。
「高原さんとおっしゃる方だよ。冬の阿賀野を見て、記事を書くって言ってたなあ」
「記事」
怪訝そうな顔をした私をよそに、そう、と父は頷いた。
「トラベルライター、って言うらしいぞ。メールには、旅人みたいなもんだって書いてあったかな」
初めて耳にする職業だった。あちこちを旅して、そこで見たものや聞いたもののことを記事にする仕事だそうだ。
トラベルライター。旅人。父から聞いた単語を咀嚼するうちに、私の中でイメージだけが好き勝手に成長していった。旅人というくらいだから、登山家が背負っているような大きくて重そうな荷物を背負っているのだろう。長年の経験と苦労が滲む皺だらけの顔。長旅に耐える頑丈な身体に、ぼさぼさの髭を蓄えている。風雨に晒された服は、あちこち破れてぼろぼろになっていることだろう。
結論から言うと、一月下旬の月曜日、吹きすさぶ吹雪の向こうから現れた旅人――高原さんは、イメージとはまるで違う男だった。
防寒着はもちろん、その下に着ている服も破れてなどいなかったし、ぼさぼさの髭も生えていない。特別頑丈そうな身体つきというわけでもない。なにより、高原さんは随分若かった。私より年上であることは間違いないけれど、だからといってそう歳が離れているようには見えなかった。唯一、彼が背負っている大きな荷物だけは予想通りの見た目をしていたけれど。
「さすが、豪雪地の名は伊達じゃない。ちょっと甘く見てました」
そう言って雪を払う高原さんの言葉には、不思議な訛りがあった。言葉の輪郭が溶けているような、丸く柔らかな訛りが。
「あのう」
控えめに声をかけてみたが、雪を払うことに夢中なのか、高原さんは気付かない。
「あの」
思いの外、大きな声が出た。自分の声に身を縮めた私の前で、一瞬遅れて高原さんが顔を上げた。
「あの その、雪はあまり降らない地域のご出身ですか」
「いや、僕は岐阜の北部、飛騨地方の出身です。雪は積もるんですが、さすがにこれほど積もるようなことはありませんでしたね。でも、寒さや雪には慣れていますよ。――あんまり、雪に慣れていないように見えますか」
「い、いえ、そういうわけでは ただ、少し訛ってらっしゃるので、もしかしたらと思って」
すると、ああ、と言いながら高原さんは両方の耳を指してみせた。
「僕、耳が聞こえないんですよ」
「えっ」
「ですから、誰かと話をするときは相手の口の動きをよく見るんです。もちろん、アナウンスやラジオの内容は聞き取れませんけどね。僕、昔はちょっとだけ耳が聞こえていたんですよ」
特発性両側性感音難聴。
高原さんが口にしたのは、呪文のような言葉だった。
「小学生の頃、そういう病気だと診断されましてね。僕の場合、中学を卒業した直後に急激に聴力が落ちて、大学生のときにほとんど何も聞こえない状態になりました。――生まれつき聞こえなかったわけではないので、聞こえなくても喋ることはできるんです」
よくある質問に対する答えを一足飛びに与えられた形になって、私は高原さんに渡すはずの居室の鍵を握りしめたまま固まってしまった。ぽかんと口を開けたまま凍りついた私は、高原さんの笑い声を聞いてはっとする。慌てて鍵を渡し、しどろもどろになりつつ宿泊の説明をする私を前に、高原さんは何度も頷きながら事務的で一方的な会話に耳を傾けてくれた。
「な、何かありましたらフロントまでお越しください。私、中村と申します」
「中村さん」
ナカムラサン、と繰り返してから、高原さんはふわりと笑顔を浮かべた。
「では、中村さん。これから二週間、どうぞよろしくお願いします」
高原さんの朝は早い。火曜日、水曜日は午前八時、木曜日は午前七時三十分。金曜日以降に至っては午前七時にはフロント前に姿を現すようになっていた。
高原さんは、いつも重そうなリュックを背負っている。一体何を持ち歩いているのか知らないが、たいして重くないのか、あるいはその重さにも慣れているのか、高原さんは軽い足取りで出かけてゆき、踊るようなステップを踏みながら帰ってくる。
宿泊者は高原さんだけだったから、洗濯や食事の準備、部屋の掃除を含め仕事は午前中に片付いてしまう。だから、高原さんが帰ってきそうな頃合いを見計らってカウンターに座り、帰ってきた高原さんにおかえりと声をかけることが私の日課になった。もちろん、高原さんが入ってきた瞬間に声をかけるのではない。彼と目を合わせてから、口を開くのだ。高原さんが、私の声を『見る』ことができるように。
ただいま、と返す高原さんは、たいてい全身雪まみれになっている。彼が初めて街に繰り出していった火曜日は、特に酷かった。
「立派な雪の壁ができていました。あと、あれは融雪パイプというのかな。とても便利だけど、たまに元気のいいやつがいるから気をつけないといけませんね。それに、雪の下に隠れている大きな水たまり――落とし穴みたいでびっくりしました」
その落とし穴にはまったのか、高原さんのズボンは足首のあたりまでぐっしょりと水に濡れていた。雪まみれになって歩くのがそんなに楽しかったのかな、と思ったけれど、もちろんそんなことを尋ねる勇気はない。脱いだ靴の底を上に向けて壁に立てかけながら、高原さんは再び口を開いた。
「僕はね、最低二日は同じ場所に足を運ぶと決めているんです。人が溢れかえっている東京でも、凍てつくシベリアの大雪原でも」
「何もない場所でも、ですか」
「何もない場所 」
高原さんはほんの少しだけ目を見開いてから、そっと首を左右に振った。
「それはきっと、何もないと思っているだけです。別の場所と比べて、あそこにあるものがここにはないと言っているだけですよ」
「でも」
思わず、私は声を上げた。それって、要するに何もないってことだ。その証拠に、東京にある華やかさが、阿賀野にはない。大きなショッピングモールや、流行と人が交差する音が聞こえてきそうなビル群もない。
だから、私は都会に憧れた。だけど、私は都会に溶け込めなかった。人混みの中をさまよい、にぎやかな空気に弾かれ、何千何万という人の中で苦い孤独感を味わっただけだった。粉々に砕けた憧れの欠片は、敗北感に似た重い澱となって今も私の胸の底に沈んでいる。だから今でも、代わり映えしない退屈な毎日の中で錆びついてしまった時間が、都会に行けば息を吹き返すような気がしてならないのだ。絶対に、そんなことは起こり得ないとわかっているはずなのに。
とらわれているのだ。田舎に。阿賀野に。私は、この何もない土地にとらわれたまま生きていかなければならないのだ。
そう思った瞬間、目の前を黒い影が横切った。黒い影の正体は、高原さんの手のひらだった。はっと息を呑んだ私の前で、悪戯っ子のような笑顔をたたえた高原さんが重たそうなリュックをひょいと背負っていた。
「何もない場所なんて、どこにもありませんよ」
翌日も、高原さんは嬉々とした表情を浮かべて阿賀野の街へ出かけて行った。
「中村さん、見てください」
旅館に帰ってくるが早いか、高原さんは雪を払うのもそこそこにカメラの画面を見せてくれた。そこには、うっすらと霧のかかった山の姿が映し出されていた。雪がみっしりと積もっているせいで、木々が白く輝いて見える。凛とした冬の空気を切り取った写真の中で、山は薄青色の光を帯びている。見慣れた風景のはずなのに、画面越しに見る阿賀野の山は別世界の名山みたいに見えた。世界に灰色のフィルムがかけられて、あらゆるものが色を失い、冷え切ってしまうのが冬という季節だと思っていたのに――冬の世界が、こんなに鮮やかな色を纏うことがあるなんて。
「きれい」
すごいです、と呟くと、高原さんは笑いながら首を横に振った。
「すごいのは、僕じゃなくて阿賀野の山です。僕は、目の前にあるものの一部を撮ることしかできません」
「でも、こんなきれいな色をした山を見たのは初めてです」
「自然も生き物ですからね。人と同じで、毎日同じ顔をしているわけじゃありません。だから、まずはじっと眺めるんです。それから、よく考える。不思議に思ったことについてあれこれ調べたり、興味を持ったものに近づいてみたりする。それが終わったら、大きく深呼吸をするんです。心の中に生まれた先入観や、勝手な思い込みをリセットするためにね。あとは、自然が美しい表情を浮かべる一瞬を逃さないこと」
「そうすれば、こんな山が見えるようになるんですか?」
「もちろんです」
高原さんは力強く頷きながら、迷いなく答えた。私は、再び青い山の写真に目を落とす。私が知っているモノクロの山とはまるで違う、だけど同じ山の写真。
不意に、心の奥がちくりと痛んだ。むず痒いような嫌な疼きを抱いた苦い痛みが、あっという間に胸いっぱいに広がっていく。
――あの日、東京の真ん中で感じた痛みと同じだった。
お礼の言葉とともに高原さんにカメラを返した後も、胸の奥で息を吹き返した痛みは消えることなくうごめき続けていた。
それからというもの、全身にこびりついた雪を落としながら『今日の収穫』を語るのが高原さんの日課になり、その話を聞くのが私の仕事に加わった。
金曜日、轍の刻まれた雪の道やうず高く雪を積んだ屋根、除雪車といった風景を一通り撮り終えたらしい高原さんは、いつもと違う写真を携えて帰ってきた。
「瓢湖に行ってきました。白鳥が飛来する場所だと聞いて、ここは必ず行こうと心に決めていたんです。鴨に鵜、雁――いろんな鳥がひしめき合っていました。彼らは賢いですね。お互いを邪魔することがないように、それでいて嫌味のない動きで、それぞれの居場所をしっかりと確保しているんです」
嬉しそうに話す高原さんの声は、いつもより少し弾んでいるような気がした。水面を走る白鳥やふわふわの羽毛に顔を埋めている小鳥の写真を眺める表情も、いつも以上にやわらかくなっている。
高原さんは、私が週に一度の休日をフル活用して惰眠をむさぼっていた土曜日も、その翌日も瓢湖に足を運んでいた。そして、旅館に帰ってくるといつものように写真を見せてくれる。瓢湖で出会った白鳥たちの写真だ。
写真を眺めているうちに、白鳥が持つ魅力がじわりと心の中に染み込んでくるのがわかった。あまり意識したことがなかったが、白鳥が見られる場所は限られている。冬になれば飛んでくる鳥だと思っていたが、どこでも見られる鳥というわけではない。
そういえば、白鳥について考えたことなんて一度もなかった。なめらかな翼を広げて力強く空を飛ぶ白鳥の姿を、じっくりと見たのも初めてだ。高原さんの写真技術が優れているから、見慣れた白鳥が美しく見えるのだろうか。山も、白鳥も、高原さんが撮る写真だから美しく見えるに違いない。
その瞬間、耳の奥に高原さんの言葉が蘇ってきた。
――大きく深呼吸をするんです。
反射的に、私は短く息を吸った。深呼吸とは呼べない一瞬の呼吸だったけれど、ふっと気持ちが軽くなるような不思議な感覚に襲われた。薄く口を開いたからか、私と一緒にカメラの画面を眺めていた高原さんがそっと顔を上げて私の口元に目を移したのがわかった。
「白鳥の鳴き声――あの喇叭みたいな澄んだ声が空から降ってくると、冬が来たなって思うんです。たいした話じゃ、ないんですけど」
「いやいや、たいした話ですよ」
高原さんが目を丸くして大げさに感動して見せるから、私は思わず吹き出してしまった。
ややあってから、高原さんは静かに口を開いた。
「冬を告げる喇叭が、白鳥の声ですか。――僕はね、白鳥を見ると懐かしくなるんですよ」
シベリアの、刺すような寒さを思い出してね。そう言いながら、高原さんは遠くを見るような目をして窓の外を眺めた。
「大学最後の年にシベリアへ行ったんです。どうしてシベリアだったのか、その理由までは覚えていませんが、気付いたら搭乗券を握りしめて出国ゲートを見つめていました。飛行機を降りてから、初めて吸った外国の空気の香りは今でもはっきりと覚えています。今までに出会ったことのない、鋭く冷たい香りでした。その香りを嗅いだ途端、ああ、ここは日本ではないのだと、唐突にそう思ったんです。それから、少しだけ怖くなりました」
「それまでは、怖くなかったんですか」
「実際に外国の空気を吸うまでは、わくわくする気持ちのほうが遥かに強かったですからね。さほど怖くありませんでした」
不安な気持ちに気付いていなかったんですよ。ぽつりと呟く高原さんの声を聞きながら、私はじっと白鳥の写真を見つめる。両翼をふわりと広げた白鳥は、黄色い嘴をうっすらと開いているせいで微笑みを浮かべているように見えた。
「当然、言葉はうまく通じない。頼れる人もいない。不安は、だんだん強くなっていきました。冷たい鈍色の世界をたった一人でさまよっているような気がして――僕は、この国に歓迎されてないんだと思ったこともありました」
「早く日本に帰りたい、と思いませんでしたか」
「思いましたよ。思いつきで旅をするもんじゃない、きちんと覚悟を決めてから外国へ行くべきだったと思いました」
でも、高原さんはすぐに日本へ帰ることができなかった。出発前の高原さんはシベリアに一週間滞在すると決めて帰りの航空券を予約していたからだ。もちろん、搭乗日時を変えてもらうこともできただろうけど、空港はとても遠かったし、なにより高原さんは慣れない環境にすっかり疲れ果てていた。
だから、高原さんはホテルの部屋に閉じこもることにした。
だが、当然ながらお腹は空く。喉だって乾いてくる。我慢に我慢を重ねたけれど、三日目の朝、ついに我慢の限界に達した。仕方なく、高原さんは重い足を引きずってホテルの外に出ることにした。
「そこで、見たんですよ」
鈍色の空をゆったりと飛ぶ、大きな白い鳥の姿を。目を輝かせて、高原さんは言う。白鳥ですか。私が尋ねると、高原さんはゆっくりと頷いた。
「僕は空を飛ぶ白鳥を見たことがなかったから、空を飛んでいる鳥が白鳥だと気付くのに少し時間がかかりました。じっと空を見上げていたら、近くを通りかかったおじさんに声をかけられましてね。――やばい、と思いました」
気さくで人懐っこい印象の高原さんらしからぬ言葉だった。本当ですよ、と高原さん。
「正直言って怖かったです。僕は耳が聞こえないんだ、と身振り手振りで伝える間も、せっかく声をかけてやったのにと思われたらどうしよう、と気が気じゃなかったです」
だが、おじさんは高原さんの予想をものの見事に裏切った。何度も頷きながらメモを取り出したおじさんは「英語は分かるかい?どこから来たの?」という意味の英文を見せながら、高原さんにメモとペンを差し出したのだ。
「日本から、と答えたら、おじさんはとても感動しましてね。朝ごはんを御馳走してもらいながら、いろいろな話をしました。そこで、白鳥の話を聞いたんです。あの白鳥は、これから日本に行くんだ、という話をね」
「それじゃ 瓢湖の白鳥の中に、高原さんがシベリアで見た白鳥もいるかもしれないですね」
「ええ。だから、白鳥を見ると古い友人に会ったような気分になるんです。だけど、もし白鳥の姿を見ていなかったら、あのおじさんに会わなかったら、今頃僕はどんな世界を見ていただろう――と思うと、少し怖くなりますね」
高原さんと白鳥は、目に見えない一本の糸で繋がっている。かつて、偶然その糸を見つけてシベリアに向かった高原さんは、同じ糸をたどって日本にやって来た白鳥たちと、瓢湖で出会った。もしかしたら、高原さんは写真の中で微笑む白鳥とシベリアですれ違っていたのかもしれない。空高く飛ぶ白鳥は、眼下をゆく高原さんに何か囁きかけていたかもしれない。
だけど、その白鳥の声は高原さんの耳には届かない。美しく澄んだ喇叭の音色を思わせるあの鳴き声を、高原さんは知らないのだ。
その瞬間、私は背筋がひやりと冷たくなった。
――ごめんなさい。
口から零れ落ちそうになった言葉を飲み込みながら、私はぎこちない笑顔を浮かべて高原さんにカメラを返す。いつものように笑顔をくれる高原さんから逃げるように、私はそっと目を伏せた。ほんの一瞬でも、高原さんのことをかわいそうだと思ってしまった後悔を噛み締めながら。
翌週は、新潟の冬にしては珍しく穏やかな晴天に恵まれた。控えめな青空の下で、太陽に暖められた雪が溶けるしっとりとした音があちこちから響いてくる。
月曜日。ほぼ一日中部屋に篭っていた高原さんが、刑事ドラマに出てくる刑事のようにペンとノートを携えてフロントにやってきたのは夕食後のことだった。
「中村さんの、おすすめの場所を教えてください」
「おすすめの場所、ですか」
はい、と頷きながら、高原さんは両目をきらきらと輝かせながら私の言葉を待っている。
おすすめの場所。唐突な質問に、私は思わずうめき声を漏らした。なにせ、高原さんはプロの旅行記者だ。写真を見る限りでは宿の周辺はとうの昔に歩き尽くされていたし、瓢湖にも足を運んでいる。五頭山の名が脳裏をよぎったが、耳の不自由な高原さんがたった一人で登るとなると少し不安だ。
「あ」
あった。高原さんのカメラにまだ収められていない場所が、一つだけ。
「阿賀野川」
ぽつりと呟いた私の前で、高原さんがほんの少し目を見開いた。あがのがわ、と一言ずつ区切って繰り返し、高原さんがメモし終えたのを確認してから、私はぽつぽつと言葉を継ぐ。
「川です。阿賀野を流れる川だから、阿賀野川。信濃川に比べたら派手さはないですけど ああそうだ、屋形船に乗って川下りもできるんですよ。今の時期だと、水墨画みたいな風景が見られます」
阿賀野川ライン下りのパンフレットを手渡すと、高原さんは隅々まで丁寧に目を通してから、ほっと吐息をついた。
「いい川だ。中村さんに聞いて、良かったです」
「いい川、ですか」
私は、静かに眉を潜めた。いい川だなんて、高原さんは本心からそう言っているんだろうか。おすすめした直後になんだが、川なんてあちこちに流れている。阿賀野川じゃなくても川下りはできるし、冬になればたいていの川は水墨画みたいな風景になる。
「都会だったら、川以外にもおすすめできる場所があったかもしれないですけど 」
都会――例えば、そう、東京みたいな。原宿、浅草、上野に銀座。歴史的な建物だってたくさんあるし、美術館や博物館も山ほどある。イルミネーションに彩られた街路樹や、夜景を一望できるおしゃれなレストランも。東京に住んでいない私でもこのくらいのものをぱっと思いつくのだ、本当はもっといろんなものがあるに違いない。
都会、と私の言葉を繰り返したきり、高原さんはそっと口を閉ざした。ほんの一瞬だけ、辺りがしんと静まり返る。沈黙が肌をちくりと刺した瞬間、「中村さんは」高原さんが、今までにないくらい慎重に私の名を呼んだ。すっ、と背筋が伸びるような、凛とした声だった。
「中村さんは、阿賀野の街が嫌いですか」
「嫌い、じゃないですけど 」
「好きでもない?」
逃げ道を削ぎ落とさんばかりの鋭い質問に、私はすぐ答えることができなかった。「ええ」と「まあ」が溶け合ったような曖昧な返事をしながら、私は高原さんから逃げるようにして目をそらしてしまった。
「ただ、田舎より都会のほうがいいなと思っているだけです。都会にはいろんなものがあるし、便利だし、なにより賑やかですから。でも、田舎にはそういうものがない」
「そう、ですか 」
否定とも肯定とも取れない口調でそう言った高原さんは、少しだけ悲しげな表情を浮かべていた。
「ここにはないから、いいものなんですか」
一瞬、高原さんが何を言おうとしているのか理解できなかった。どう答えていいものか戸惑いながら、私は再び曖昧な返事をしてうつむいた。
――ここにはないから、いいものなんだろうか。
そう思った瞬間、
「中村さんは 日が暮れてゆく音を、知っていますか」
高原さんから突きつけられたのは、唐突で不可解な質問だった。ぱっと顔を上げた私に構うことなく、高原さんは淡々と先を続ける。
「昼の世界を引き連れて、地平線の向こう側へ、あるいは水平線の下の世界へ向かう夕陽の足音を聴いたことがありますか」
「――そんな音、聞こえるはずないじゃありませんか」
すると、高原さんは口元にほのかな笑みを浮かべた。いつものあたたかい笑顔とは少し違う、哀れみに似た色を含んだ微笑みだった。
「地球は、時速千七百キロメートルという速さで自転していると聞きました。もちろん、地球が回っている音を僕たちが直接『聞く』ことはありません。一方で、『聴く』というのは地球の自転のように目には見えないものを感じるという意味です」
高原さんは、手元のノートに『聴く』という文字を書き記した。
「耳に加えて、目と心を使うのが『聴く』という作業です。聞こえないから目で見る。目で見えないから耳で聞く。あるいは、どちらもできないから心を研ぎすませて感じ取る。それが『聴く』という言葉の意味だと、僕は解釈しています」
それから、急に真剣な顔をして高原さんは口を閉ざした。じっと私を見つめていた高原さんの瞳に遠慮するような影が走った瞬間、
「僕のこと、かわいそうだと思ったことはありませんか?」
耳を貫いた高原さんの言葉が、私の心に深く突き刺さった。凍りついた私に構うことなく、高原さんは続ける。
「確かに、僕は川の音や風の音を聞くことはできません。でも、鼓膜を震わせる空気の波だけが音だと言うのなら、世界はとても単調でつまらないものになるでしょう。僕の周りは、余白ばかりが目立つ何もない場所になってしまう。でも、僕の目の前から川や風が消えてなくなることはない。聞こえなければ、見えなければ、何もないということにはならないんですよ」
大事なのは、そこにあるものをなかったことにしないことです。高原さんは、小さな声で付け加えた。
「耳が聞こえなくても、音を聴くことはできます。僕の周りに僕の耳には届かない音があるように、中村さんの周りには中村さんに見えていないものがあるはずですよ」
「でも 」
見えないものなんて、どうやって見るんですか。低い声で尋ねた私をなだめるようにゆっくりと頷きながら、高原さんはメモ帳に書かれた文字を指してみせた。
「中村さん、聴くんですよ」
「どういうことですか」
「さあ そればかりは、自分で考えるしかありません」
考えてください。高原さんは、実に軽やかな口調でそう言った。
それから数日間、私は高原さんと会わなかった。顔を合わせる機会がなかったわけではない。私がその機会をことごとく避け続けていたから、高原さんと会わなかったのだ。
あの日以来、私と高原さんの間にはぎこちない空気がたちこめていた。高原さんも同じように気まずさを感じているのか、私がフロントに立っているときには決して姿を見せなかった。
互いの気配を探りながら同じ空間で生活する、というのは想像以上に精神力を使う作業だった。数日続けただけで頭の芯が重苦しくなるのだから、忍者はさぞ疲れたことだろう――などと考えているうちに、ようやく土曜日、つまり週に一度の休日がやって来た。
休日。一日中、部屋で過ごしてもいい日。心の中でガッツポーズを決めながら眠りについたはずなのに、今日に限ってどういうわけか早起きだった。いつもなら休みの日は昼まで寝ているのに、時計は午前七時を指していた。示し合わせたようなタイミングで、旅館の入り口の戸をカラカラと開く音が響いてくる。そのかすかな音を聞いた途端、背筋がすうっと冷たくなった。反射的に掛け布団を頭の上まで引き寄せる。気付いたときには、少しだけ空いた隙間から慎重に外の気配を探っていた。
雪を踏みしめる音が、徐々に遠くなってゆく。同時に、大きなリュックを背負った高原さんの背中が瞼の裏に浮かび上がった。高原さんの歩みは、随分ゆったりとしている。雪の下に大地があることを確かめながら、高原さんは少しずつ前へ進んでゆく。
今頃、高原さんは何を考えているのだろう。雪国の朝はやっぱり寒いとため息をついているだろうか。それとも、これから行こうとしている場所に思いを馳せているのだろうか。
高原さん。口の中でそっと名前を呼び、布団から抜け出して窓辺に足を運ぶ。うっすらと曇った窓の向こうに、細く続く足跡があった。雪の上にくっきりと刻まれたその足跡が続く先にどれだけ目を凝らしても、高原さんの姿を見つけることはできなかった。
朝食を済ませてから、手持ち無沙汰を紛らわせるために部屋の掃除をすることにした。とはいえ、私の部屋はベッドと机、それから小さな本棚が二つしかない。ほぼ寝るためだけの部屋と言っても過言ではない状態だから、さほど汚れてはいない。それでも、窓の桟を拭いてみたり、本棚からすべての本を取り出して一冊ずつ戻してみたりしている間に、時間はあっという間に過ぎていった。
本棚の奥に見慣れないケースが転がっていることに気が付いたのは、掃除も終盤に差し掛かった頃のことだ。随分前の卒業旅行のとき、飛行機に乗るからと言って買ったきり使っていない耳栓だった。
その瞬間、ある考えが脳裏をよぎった。
今日一日、耳栓をして過ごしてみるのはどうだろう。高原さんに対する罪滅ぼしというわけでは、決してない。後ろめたさに起因する思いつきではないけれど、もしかしたら、高原さんの気持ちをほんの少し理解することができるかもしれないと思ったのだ。
――中村さん、聴くんですよ。
高原さんはそう言っていたけれど、そんなこと言われても、と私は思う。『聞く』も、『聴く』も、どちらも同じ『きく』ではないか。高原さんの言う『聞く』と『聴く』の微妙な違いを、私は未だに理解できていない。だが、高原さんによれば、聞くことができなくても聴くことはできるという。
――本当、だろうか。
おずおずと、私は耳栓をはめてみた。しばらくの間は耳が異物感に押しつぶされそうになったけれど、全く音が聞こえなくなるわけではなかった。世界が薄い膜に包まれたようになって、あらゆる音が私からほんの少しだけ遠ざかっただけ。
――なんだ。たいしたこと、ないじゃん。
そう思った瞬間、不意に肩から力が抜けた。耳栓をつけるだけなのに酷く緊張していた自分に気付いて、私は思わず笑ってしまった。笑ったら、不思議と少しだけ気分が軽くなった。忘れかけていたが、今日は休日だ。天気もいい。せっかくだから、外を歩こう。
服を着替え、コートをはおって旅館を出る。高原さんの足跡を辿りつつ最寄りのバス停まで歩く。バスに乗ってからも耳栓をつけているせいで苦労するような場面はほとんどなかったし、水原駅前のバス停に降りる頃には耳の違和感にもすっかり慣れてしまっていた。
いつもと違う感覚に慣れたまでは良かったのだが、程なくして何とも言えない孤独感が腹の底からふつふつと湧き上がってきた。レジで会計をするだけなのに、相手の言葉が聞き取れなくてうまく会話ができていなかったらどうしようとひやひやする。その怖さから逃げるようにして新潟市へ向かうバスに乗り込んだものの、アナウンスがぼんやりとして落ち着かない。とにかく、言葉に触れなければならない場面に直面するとどんよりと重苦しい気持ちになって、わけもなく不安でたまらなくなってくる。
結局、その不安に耐えかねて私は途中でバスを降りてしまった。下黒瀬。あのバスで新潟市に向かうときの、阿賀野市最後のバス停で。阿賀野川沿いにそびえる堤防を横目に、私はそっとため息をついた。
ばかみたいだ。せっかくの休日だというのに、私は何をしているんだろう。高原さんに会わないように気を配っていたはずなのに、これじゃまるで、高原さんの後を追っているみたいだ。堤防道路で、ばったりと顔を合わせるようなことになったら――。
そこまで考えて、私は大きく息を吸った。
別に、あの人の後を追っているわけではない。それに、高原さんに阿賀野川を紹介したのは五日前だ。五日も続けて阿賀野川に来るはずはないだろう。それに、高原さんなら瓢湖を選ぶはずだ。だから、堤防道路で高原さんと出会う確率はほぼゼロに等しい。
あれこれと思考を巡らせることに必死になるあまり、私は耳栓をつけたまま歩いていることをすっかり忘れていた。堤防道路に出て、視界に飛び込んできた阿賀野川を見たときに何か足りないと思ったはずみに耳栓のことを思い出したのだ。
「――あ」
白い息とともに吐き出された私の声は、いつもよりずっと大きく聞こえた。目の前の阿賀野川には、何かが足りない。音だけではない。私の心を強く揺さぶる『何か』が、阿賀野川には足りないのだ。
その『何か』が意味するものが、今なら分かる気がした。両手の人差し指と中指を、そっと両耳に添える。耳を塞ぐ小さな栓を取り払った途端、周囲の音が怒涛のごとく私の中に流れ込んできた。
ぴんと張り詰めた冬特有の気配に、遠くの道をゆっくりと進む除雪車の音。水が滴るかすかな音。堤防道路を歩く人たちの穏やかな声。傾きかけた冬の日に照らされた、穏やかな空気。それから、大空をゆったりと飛ぶ白鳥たちの鳴き声。あらゆるもの抱いて、阿賀野川は流れてゆく。その瞬間、目の前を悠然と流れる阿賀野川がにわかに輝きを増したように見えた。
――聴くというのは、地球の自転のように目には見えないものを感じるという意味です。
不意に、高原さんの声が耳の奥に蘇った。
あの日、高原さんは私に二つ質問をした。どちらの質問にも、私は答えることができなかった。私は、なにも分かっていなかったから。聴くという言葉の意味も、私が住んでいる阿賀野のことも。だから私は、ここにはないものでしか、ここを語ることができなかった。東京に行ったときも、そうだった。
そうですか、と呟いたとき高原さんは悲しそうな表情を浮かべていたけれど、たぶん、あのとき高原さんは本当に私を哀れんでいたのだろう。もったいないなあ。あるいはもっと端的に、ばかだなあと思ったかもしれない。
阿賀野川を流れる水の音を、高原さんは知らない。白鳥の声も、分厚い雪を踏むときの骨が軋むような音も、彼の耳には届かないかもしれない。
だけど、高原さんはこの街が奏でる音を聴いていたのだ。私が見ようともしなかった世界を見て、そこにあるものと呼応しながら。
高原さん。呟いてみるけれど、高原さんはここにはいない。聴くって、こういうことだったんですね。尋ねてみるけれど、その答えを知っている人はどこにもいない。
白鳥が数羽、こぉ、こぉと鳴き交わしながら飛んでいる。川面の輝き、白鳥の羽ばたき、この街に生きるすべてのものの息遣いが溶け合ってできた大きな渦が、私の声をさらってゆく。目には見えない大きな渦を引き連れて、阿賀野川はとうとうと流れ続けている。
帰りのバスで、高原さんとばったり出会った。瓢湖前のバス停からバスに乗り込んできた高原さんと目が合った瞬間、私は思わず手を振った。それに笑顔で答えながら、高原さんはゆったりとした動きで私の隣に腰を降ろした。
「あの」
高原さん。そこまで言ってから、私はふと口をつぐんだ。ごめんなさい、と言おうとしたはずなのに言葉が喉に詰まって出てこない。
「瓢湖に、いらしたんですね」
ぎこちない沈黙のあとに口を突いて出た言葉は、本当に伝えたかったこととは大きくかけ離れた姿になっていた。ええ、と高原さんが小さく頷く。
「中村さんも、お出かけでしたか」
「はい。私は、耳をふさいで阿賀野川まで行ってきました」
「え? どうしてそんなことを?」
高原さんは日本語を話す宇宙人をみたような表情を浮かべてまじまじと私の顔を見つめた。事の始終を話すと、高原さんは呆れたような笑みを浮かべた。
「耳が聞こえないというのは――僕の場合、耳栓ではなくイヤフォンをして音楽を聞いている感覚のほうが近いと思います」
「イヤフォン、ですか」
「そう。僕だけが聴こえる音を聴きながら、街の中を歩いているような感覚です。 でも、そうですね」
人との会話は、多少、ひやひやするものです。そう言って微笑んだ高原さんは、少しだけ嬉しそうに見えた。
「そう感じるのは僕だけじゃないと思うと、なんだかほっとしました。――それで、どうでしたか。聴けましたか」
今回の質問の意味は、すぐに分かった。はい、と迷いなく答えてから、急に不安になった。あれは、本当に正しい聴き方だったのだろうか。阿賀野川でどんな音を聴いたのか、ちゃんと説明してみろと言われたら、私はやはり答えに困ってしまうだろう。
「たぶん、ですけど」
控えめに付け加えながら、私はコートの襟に顔を埋めた。たぶん、ちゃんと聴けていますよ。高原さんが、微笑みを浮かべて呟いた。独り言のように、静かで淡い口調だった。
高原さんの朝は、早い。いつも七時には旅館を出て行く高原さんだったが、最後の朝はとりわけ早かった。午前六時三十分。いつもより三十分も早かった。残念なことに、私はいつもより三十分遅く起床した。あろうことか、寝坊したのだ。
「高原さんなら、少し前に出発なさったわ。これから飛行機に乗って北に向かうんですって」
慌ててフロントに出た直後、母から告げられた言葉に本日二度目の衝撃を受ける。
「なんで!?」
「お仕事だそうよ」
今ならまだ間に合うかもしれないわね、という母の声を背中で受け止めつつ、私は玄関から飛び出した。一直線に続く足跡を辿って、雪を舞い上げながら朝靄の中をひた走る。バス停までは、歩いて三分。走ればもっと早く着くが、バスの到着時刻までもう余裕はほとんどない。行く手に、バス停が見えてきた。そこに佇む大きなリュックを背負った後ろ姿が見えた瞬間、私は大声で彼の名を呼んでいた。届くはずのない声が、朝の空気を切り裂き雪に吸い込まれて消えてゆく。
やっぱり、あのときに伝えるべきだったのだ。もう一生会えないかもしれないのに。そう思った瞬間、何一つ伝えられなかった自分が情けなくてたまらなくなった。時間を巻き戻すことなどできないと分かっていても、昨日に戻れたらと思わずにはいられなかった。
苦しくて泣きそうになったまさにその時、高原さんが動いた。ゆっくりと、見えない気配をたぐり寄せるようにして私のほうを振り向いて、それからぎょっとしたような顔をした。雪を蹴散らし、必死の形相で走ってくる女性がいたら、誰でもそういう顔をするだろうけど。
「寝ていると伺ったので――お見送りは結構ですとお伝えしたのに」
半ば転がり落ちるような格好になりながらもなんとか止まることができた私を前に、高原さんは申し訳無さそうな顔をした。弾みに弾んだ息を押さえつけながら、私は首を大きく左右に振った。
「お見送りも、ですけど、他に――言わなければ、いけないことが」
「えっ」
「阿賀野川の、お話をしたあの日に、私は――音が、きこえないなんて、かわいそうだと」
思ってしまったんです、という言葉を言うための空気が足りなくてまともな声が出なかったが、高原さんには通じたらしい。抜け落ちた言葉も拾い上げてくれたのか、彼はほんの少しだけ驚いたような顔をしてから、笑顔を浮かべて首を振った。
「実は僕も、同じ理由であなたのことをかわいそうだと思ってしまいました。だから、おあいこです。――それより、今日に限って寝坊だなんて珍しいですね」
いつもは僕より早いのに。いたずらっ子のような笑顔を浮かべた高原さんの声は、迫り来るバスのエンジン音にかき消されてしまうくらい小さかった。
――さよなら。
そう言いかけた瞬間、とん、と頭に何かが触れた。あまりに突然の出来事だったから、それが高原さんの手のひらだと気付くまでに時間がかかった。
「僕が次に泊まりにきたときは、寝坊しないでくださいね」
高原さんは、ときどき手紙を送ってくれた。消印はいつもばらばらで、外国から送られてくることもあった。旅先で撮った写真を入れてくれることもあった。私も、ときどき高原さんに手紙を送った。どんなことを書いたのか、はっきり覚えていないけれど。
高原さんが再び泊まりに来ることを知ったのは、つい数日前のことだった。次にきたときは、と言っていたけれど、その『次』がこんなに早くやってくるなんて思ってもみなかった。
「今度は、仕事じゃないからゆっくりできるんだと」
そう言ってにやりと笑った父から、私は慌てて目をそらした。動揺する心を落ち着かせるように、大きく息を吸い、それから時間をかけてゆっくりと吐く。
――あの日、私は言わなければならないことを一つも伝えられなかった。
だから、今年こそはちゃんとあの人に伝えるのだ。一年前に言い損ねた言葉と、今の私が伝えたいと思う言葉を。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
