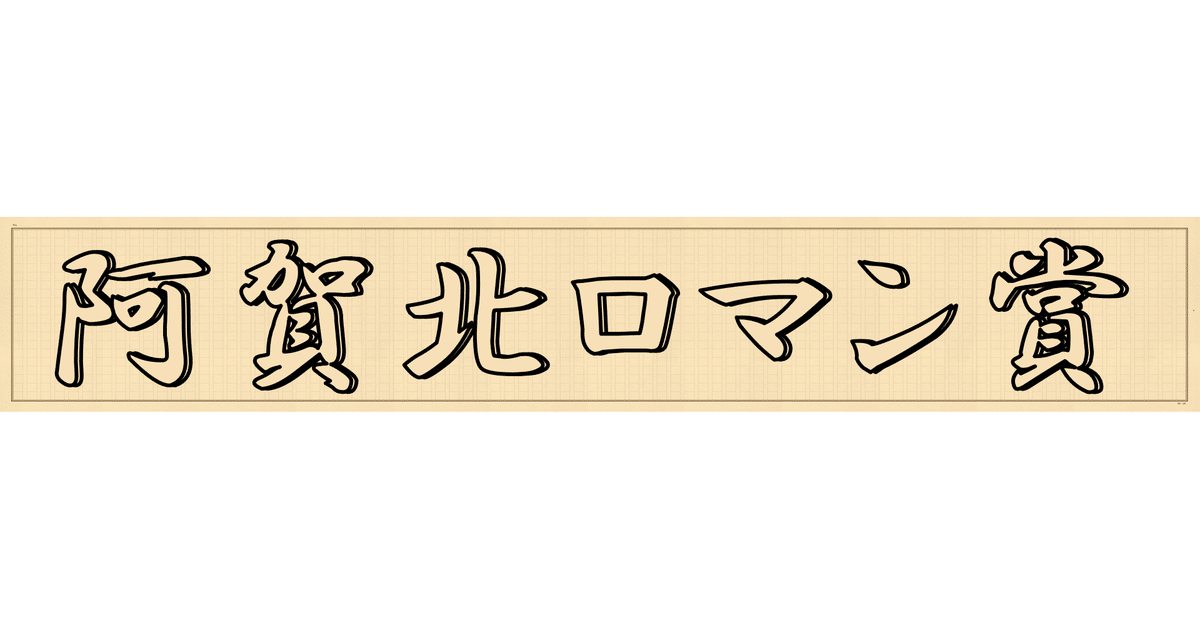
第十回阿賀北ロマン賞受賞作①小説部門 大賞『あぜ道の向こう』葉山エミ
この記事は新潟県の阿賀北エリアの魅力を小説で伝えてきた阿賀北ロマン賞の受賞作を紹介するものです。以下は葉山エミさんが執筆された第10回阿賀北ロマン賞小説部門受賞作です。2020年より阿賀北ロマン賞は阿賀北ノベルジャムにフォーマットを新たにし、再スタートしています。<詳しくはこちら>公式サイト
小説創作ハッカソン「NovelJam(ノベルジャム)」初の地方開催を企画・運営しています。「阿賀北の小説 チームで創作 敬和学園大が初開催 筆者と編集者、デザイナー募集へ」 (新潟日報)→ https://niigata-nippo.co.jp/news/local/20200708554292.html
『あぜ道の向こう』葉山エミ
数か月ぶりに会う弟の顔は思いのほかさわやかで、癪にさわった。
「ったく。出発まで三十分もあるじゃない。こういうときは十分前でいいよ」
菜美子がかみつくように言うと、はへへっと笑った。
「いいじゃん。久しぶりに話がしたかったんだ。明日は特別な日だろ。母さんの誕生日。生きていれば六十歳だもんな」
暁人の言葉に一瞬、菜美子はひるんだ。
そりゃあ、そうだけど――。
と足元に視線を落とす。買ったばかりのピンクベージュのパンプスが、ぴかっとなめらかに光っている。
キャリーバッグを引きながら、慣れた足取りでスーツ姿の女性が二人をよけていく。ホームには、新幹線がすべり込んできた。
久しぶりの東京駅は、いつも足を運んでいる新宿駅とは違って、どこか上品な時間が流れている。活気があるけれど、騒々しくはない。行き交う人々も、日本のあちこちから様々な香りを運んでくる。
「はい、お土産。伯父さんたちに渡してね」
「サンキュー」
嬉しそうに眺めながら、暁人は紙袋を受け取った。
亡くなった母の誕生日に母の故郷である新潟へ行こうと言い出したのは、暁人だった。一か月ほど前の電話で、やけに明るい声で暁人は言った。
命日には、二人で八王子にある母のお墓参りに行っている。だけど誕生日は母が生まれた場所へ行くべきだと、なんの気まぐれか言い出したのだ。
生きていれば還暦だから、何かしなければという衝動にかられたのかもしれない。弟には、ロマンチックな一面がある。
それに比べて現実的な菜美子はとうとう首をたてにふらず、それなら見送りだけでもと暁人にせがまれて、仕方なく出勤前の忙しい時間に東京駅に足を運んだのだった。
ふつふつと不満を煮えたぎらせながら、それでも来てしまったのは、やはり明日が母の誕生日で、暁人の向かう先が母の故郷で、そして東京に残る自分に対して後ろめたさがあるからだった。
見送りくらい、してあげよう。たった二人だけの姉弟なんだもの。
父親のいない姉弟にとって、母を亡くすということは、この東京のど真ん中に二人きりということだ。
しかし、暁人に指定された時間に来てみると出発まで三十分もあり、菜美子は憤慨したのだった。いったい、三十分も何を話せというのか。弟と。
「よかったね、休暇が取れて、天気もよさそうじゃない? 東京より涼しくていいよね」
「昨日までは雨が降っていたらしいから、少し蒸してるかもな」
「向こうも梅雨明けはまだなんだっけ。帰りは日曜の午後?」
「そっ、二泊三日」
「ふうん」
他愛ない会話で時間を埋めていると、出発の時間が近づいてきた。駅のホームがそわそわとし始める。
「姉ちゃんも一緒に来ればいいのに。きっと楽しいって。おれと姉ちゃんが新潟に行ったらさ、母さんも喜ぶと思うんだ」
菜美子が黙っていると、暁人は一人でしゃべりつづけた。
「なんか、わくわくするなぁ。向こう着いたらブログをアップするからチェックしてよね」
「ブログ? あんた、そんなのやってんの?」
「おぉ、コメント残してくれよな」
「ばか。それより、そろそろ行きなって」
暁人が乗るのは六号車の指定席だ。背中を押して新幹線に押し込む。くるりとふり向いたとき、暁人が真面目な顔をしていたので菜美子は身構えた。
「向こうで、瑠美子ちゃんに会えるかな」
発車ベルが鳴り響いて、暁人の言葉に蓋をする。菜美子は聞こえなかったふりをしてそっと視線を外した。
「いってらっしゃい」
菜美子が言うと同時に、ドアが閉まった。暁人が親指を立てて、にっと笑って応える。手をふる気にはなれず、菜美子はうなずいて、暁人が乗った新幹線を見送った。
白と緑の細い車体が、ゆっくりと加速して暁人を連れていく。
新潟駅に着いたよ! 安心してねー !(^^)!
九時に出社して企画会議を終えると、ラインが届いていた。暁人からだった。
心配なんかしていないのに。
菜美子はため息をついて携帯を置いた。
出版社で児童文学の編集者として働く菜美子は、今年で二十九歳になる。暁人は三つ下の二十六歳だが、年のわりに幼くて、いつまでもやんちゃな弟といった感じだ。
ラインを受信した時間を見ると、出発から二時間もたっていなかった。
新潟って、遠いようでけっこう近い。たったこれだけの時間で着いてしまうんだ。ほんのついさっき、暁人を見送ったばかりなのに。
菜美子はホワイトボードの自分の名前の欄に『外出』の札を貼ると外へ出た。これから昼食をとりつつ、吉祥寺まで原稿を取りに行く。
七月の空は青く澄みきっているものの、街の空気はむせかえるほど暑く、すぐにじっとりと汗ばんでくる。脇腹につぅーと汗が這う。
家を訪ねると、児童文学作家の神田夕子が菜美子の前で両手を合わせてきた。
「じつは、最後のシーンを直してるの。ちょっと待っててもらえる?」
菜美子は笑いながら、
「いいですよ。原稿を受け取るまで、絶対に帰りませんから」
夕子は四十代のベテラン作家で、菜美子ともそれなりに長い付き合いだ。持参したペットボトルのお茶を飲みながら、書斎にこもった夕子をリビングで待つ。いつもなら仕事の企画書などに目を通すところだが、この日はふと、壁に貼ってある日本地図に目を惹かれた。
壁の前に立つと、ちょうど目の高さのところに東京がある。
人差し指を、東京駅にそっと置いてみる。そこから新幹線のルートをたどって、群馬から新潟へ。さらに指を上へとすべらせて、たどり着くのは終点の新潟駅。
「ねぇ、トンネルばっかでつまんないよ。全然、外の景色が見えないや」
ふいに、声変わりをする前のなつかしい声が聞こえてきた。
と、次の瞬間カチャリとドアが開いて、菜美子は一瞬の白昼夢から目を覚ました。夕子が顔を出している。
「あら、何やってるの?」
菜美子は指を引っ込めた。変なところを見られてしまって、あわててしまう。
「すいません。ちょっと、見てました」
しどろもどろに答えると、夕子はいたずらっ子のような笑みを浮かべて、菜美子のとなりに立った。菜美子は観念して言った。
「弟が新潟へ行っているので、ちょっと気になってしまって。亡くなった母の故郷なんです」
「へぇ、新潟のどこ?」
「新発田っていうところです」
「うーん、知らないな」
「ですよね」
夕子が首をかしげて地図を見る。
「じつは私もよく知らなくて。いつも新潟駅から車で行っていたので、自分が新潟のどの辺にいたのかもよくわかっていないんですよね」
新潟駅をおりて、車に乗って、一時間くらい車に揺られていたのだろうか。
後部座席に菜美子と暁人、それぞれ横を向いて、窓の外の風景に釘付けになっていた。
菜美子は地図に目を凝らし、見慣れない地名を指で追っていく。
「あっ、あった。ありました。ここです、ここ。新発田市」
隠れていた宝物を見つけたような気持ちで、菜美子は言った。
「私、ここに行っていたんですねぇ」
どこかとんちんかんな言葉に、夕子が目じりを下げて笑った。
中央線に乗って新宿に戻る。午後の車内は座席はすべて埋まっているものの、立っている人の数はまばらだ。ドアにもたれて、東京という箱に詰め込まれた住宅や低層のビル群をぼんやり眺めていると、バッグの中で携帯が振動した。暁人からのラインだった。
新発田に無事到着したよ ( ^)o(^ )
もう一つメッセージが入っていた。ウェブのリンクが貼り付いている。嫌な予感を感じつつリンクを開いてみると、ブログに飛んだ。
やっぱり……。
暁人のブログだった。最新の記事は、『十年ぶりの新潟』というタイトルだ。
母の故郷、新潟の新発田へ無事到着。僕が十六歳のときに祖母が亡くなって以来、ずっと訪れていなかったので、昨日は興奮で眠れませんでした。新幹線は相変わらずトンネルばっかで景色はあまり見えないし、耳がキーンとなってしまいましたが……(;´д`)
それはさておき、十年ぶりの新潟は、暑いけど空気がうまい! そして、なつかしい母の実家で過ごすのを楽しみに、いざ到着と思いきや、な、な、なんと―――。家は七年前にとり壊して新築になっていましたーーΣ(゚Д゚) 知らなかった! ショックのあまり口がパクパクになったけど、とりあえず記念の一枚をパシャリ。
家は変わっていたけれど、僕を迎えてくれた伯父夫婦は変わらずあったかい。変わってしまった家、変わっていない人たち、フクザツで嬉しい再会でした。
写真を見て、菜美子は「マジ?」と小声でつぶやいてしまった。
白い外壁に、ダークブラウンの枠組みがおしゃれな家だった。たしかに、暁人がショックを受けるのもわかる。菜美子だって、昔の記憶にあるのは木造の平屋の家だ。
しかし、最後に新発田を訪れてから十年もたつ。あの木造の家だって相当古かっただろう。変わらないと思っていた方が、おかしいのかもしれない。
電車が新宿駅にすべり込む。いつのまにか車内には人が増えていて、ホームでも人々が整然と並んで待ち構えている。
地下鉄に乗り換えて印刷所に向かい、無事に原稿を入稿した。帰りは端の席がちょうど空いていたので、菜美子は腰かけてほっと一息ついた。全身から力が抜けていく。それでも、今日はなんだか落ち着かない。
暁人が新発田へ行ったりするからだ。ブログの写真なんか見なければよかった。
どんなにふり払っても、ちらちらと新発田の記憶が頭をよぎり、胸をざわつかせる。
轟音がうなる車内で、菜美子はそっと目を閉じた。
新発田へは毎年帰っていたわけではない。
菜美子の記憶が一番鮮明なのは小学校六年生の夏休み。その年は祖父の七回忌があって、親戚中が集まる予定だった。
菜美子と暁人は東京に母を残して、ひと足先に新発田へ向かうことになった。菜美子たちにとって、それは三年ぶりの新潟であり、数年に一度しか帰らない二人にとっては、初めて訪れるような感覚だった。
本家の岡田家には、菜美子の祖母と伯父夫婦、そしてその子供たちが住んでいた。
当時、祖母は八十代、伯父夫婦は五十代。そして、菜美子の従兄妹にあたる兄妹は二十代で、菜美子たちの遊び相手としては歳が離れすぎていた。というのも、母は六人兄妹の末っ子で、本家を継いだ一番上の兄とは十八歳も年が離れていたのだ。
「私の時代にはよくあることなのよ。田舎ならなおさら」
事あるごとに、母はそう言っていた。
新幹線での二人旅は浮かれっぱなしだったが、新潟駅に着いたとたん、二人は緊張に包まれた。迎えに来てくれた伯父夫婦の浩介とタキ子は、知らない大人も同然だ。いつもは落ち着きのない暁人も、借りてきた猫のようにおとなしく姉の影に隠れている。
浩介とタキ子は、不思議な匂いのする人たちだった。東京では、こんな匂いの人はいない。二人の衣服がこすれるたび、動くたびにぷうんと香ってくる。
なんだろう、この匂い。
菜美子は、タキ子の衣服にぴったりと鼻をくっつけて、思いきり香りを吸い込んでみたかった。
本家に到着すると、菜美子は母の言いつけ通り持っていた紙袋をうやうやしく差し出した。東京駅で買ったお土産だった。抹茶クリームと生クリームが入ったクッキーで、菜美子と暁人の二人で選んだものだ。
「まぁまぁ、ご丁寧に。重たかったでしょう、ありーがとうねぇ。それじゃあ、お供えにいきましょうか。仏様にちゃあんと顔を見せてあげなきゃね」
タキ子に案内された奥座敷には大きな仏壇がでんと置いてあった。タキ子は仏壇に話しかけながらろうそくに火を灯し、菜美子が持ってきたお土産を仏壇の前にそっと置いた。
部屋の中に足を踏み入れて、菜美子はあっと気がついた。仏様の部屋から香るこの匂い。それは伯父夫婦と同じ匂いだった。線香と畳と、そこで暮らす人たちの生活の匂い。菜美子はそれを胸いっぱいに吸い込んだ。
「どうぞ、お線香をあげてね」
タキ子に促されるも、菜美子と暁人はぼんやりと立っていた。暁人が不安げに菜美子を見上げるので、姉の役目として菜美子は遠慮がちに口を開いた。
「お線香って、どうやってあげればいいですか?」
東京のアパートで暮らす菜美子たちは、仏壇のある生活をしたことがなかった。タキ子は「あらあら、そうよねぇ」と朗らかに笑いながら、お線香のあげ方を教えてくれた。
菜美子と暁人が立てた線香が、煙をくゆらせながら立ちのぼる。菜美子はもう一度、二本の線香で香りの濃くなった仏間の空気を吸い込んだ。
その後は祖母の部屋に案内された。仏間を出るとき、菜美子はお土産の箱にちらりと視線を送った。あそこに置きっぱなしで、いつ食べられるのだろう。着いたらすぐに食べられると思っていたのに。
祖母のミヨは、お風呂と食事とトイレと、縁側での日向ぼっこ以外はほとんどベッドで過ごす生活だった。頭はしっかりしているものの、とにかく耳が遠い。ぐっと耳に顔を近づけて、お腹に力をいれて話さなければならなかった。
入り口に立つ小学生二人を見て、ミヨはきょとんとした顔をした。ミヨには、孫が十五人、ひ孫も三人いる。どの子供の子供だろうか、それとも近所の子供だろうかと必死に頭を巡らしているようだった。
「おばあちゃん。東京の、瑠美子ちゃんの、子供たちが、来ましたよ。おばあちゃんの、一番若い、孫ですよ」
タキ子がゆっくりと言葉を区切りながらミヨに伝えると、ミヨは考え込むような顔をした。
瑠美子ちゃん――。
一瞬、誰のことかわからなかった。それが母の名前だと菜美子が気がつくのと、ミヨが菜美子たちを孫だと認識したのは、ほぼ同時だっただろう。
「あぁ、瑠美子の」
ミヨはそう言って、顔をほころばせた。
母親の名前を他の人から聞くのは、なんだか変な気分だった。
ミヨに手招きされて、二人はそばへ寄った。ミヨが二人の頭を嬉しそうに交互に撫でてくれる間、二人は石のようになって、ただ立ちつくしていた。
その日の夜、伯父夫婦の子供たちが帰宅してから夕飯となった。長男の昌也と長女の美華は共に公務員だ。
「うちでは瑠美子だけだ。東京行って戻ってこなかったのはな。他はみんな戻ってくるんだ。菜美子、暁人、どうだ、ここはいいとこだろう? 住んでみるか? 星もよく見えるぞ」
浩介は二人のことを呼び捨てにする。菜美子にはそれが嬉しかった。
「東京がいいに決まってるよ。なぁ?」
昌也に言われて、菜美子は曖昧にうなずいた。
ずらりと並んだおかずの多さに、菜美子も暁人も圧倒されていた。タキ子と美華はしきりに菜美子たちの世話を焼いてくれて、
「ほらこれも」
「はいどうぞ、どんどん食べてね」
と、次々に食べ物を置いてくれるので、菜美子もそれに応えるために一生懸命に箸を動かした。
おおらかで、世話好きな家族のおかげで、夕飯が終わるころには菜美子も暁人もすっかりくつろいでいた。
食後、菜美子は縁側で足をぶらぶらさせながら庭を眺めて過ごした。腿の裏のひんやりとした木の感触が心地いい。後ろでは、お酒の入った浩介が野球観戦にいそしみ、暁人は昌也とのプロレスごっこに夢中になっていた。
気持ちいい。
時おり吹く夜風を頬に感じながら、菜美子はうっとりとした気分だった。
東京のアパートでは、いつも窓もカーテンも閉め切っている。窓を開けてもすぐとなりもまた建物なので、ろくに風も入ってこないのだ。解放された空間に身を置くことがこんなに気持ちいいなんて、菜美子は初めて実感したのだった。
翌日、菜美子と暁人は縁側で寝転がるほどくつろいでいた。こうなるともう行儀のいい小学生には戻れない。二人は畳をごろごろ転がったり、広い家でかくれんぼをしたりと大忙しだった。ドスンと着地しても、下には誰も住んでいない。苦情がくる心配もない。このチャンスを逃してはならないとばかりにはしゃいだ。
祖母のミヨの部屋は特に気に入りの遊び場になった。何といってもミヨは耳が遠いのだ。ちょっとくらい大声を出したって聞こえやしない。
ミヨもまた、滅多に会えない東京の孫の姿を嬉しそうに目に焼き付けていた。
タキ子は時間の合間をぬっては二人を畑に連れて行ってくれた。スーパーでかしこまって並んでいるトマトやキュウリではなく、まだ大地と繋がっている命ある野菜を、菜美子はこの手でもいで、かじりついた。
曲がっていたり、ぼこぼこしていたり、個性的な形に菜美子は見とれた。
時おり知っている人に会うと、知らない子供たちをタキ子が連れているものだから、皆が興味津々で菜美子たちを見た。その度にタキ子は、
「東京の瑠美子ちゃんの子供たちだ」
初日にミヨに言ったように説明した。すると相手は決まって、
「あぁ、瑠美子ちゃんの」
と納得した声を出す。
「すごい、お母さんて有名人なんだね」
暁人が感心して言った。菜美子も同感だった。
みんな瑠美子ちゃんのことを知っているんだ!
二人にとって、新発田での滞在は「瑠美子ちゃん」との出会いの旅にもなった。
「瑠美子ちゃんはね、学校が終わるとうちの子をよく駄菓子屋に連れてってくれたんだよ。うちの子も瑠美子ちゃんが来るのを楽しみに待ってたからね」
「中学生の時に瑠美子ちゃんがうちの田んぼに自転車ごと落ちてしまって、うちの人が車で送ってやったんだ」
「留美子ちゃんは勉強は、あんまできなかったでしょ。ミヨさんがよく愚痴をこぼしてたもの」
道端で、玄関先で、またはよそのお宅の縁側で、そんな会話がくり返された。
菜美子たちも母のことを「瑠美子ちゃん」とこっそり呼ぶようになった。菜美子たちにとってお母さんはお母さんだけど、ここ新発田では「東京の瑠美子ちゃん」だったり、「ミヨさんとこの瑠美子ちゃん」だったり、「うちの子の同級生の瑠美子ちゃん」なのだった。それはとても不思議な感覚で、初めて出会うお母さんだった。
ある日、本家に腰の曲がったおばあさんと、四十代くらいの女の人が訪ねてきた。玄関先で迎えたタキ子は床に正座をすると、おでこが床にくっつくくらいに頭を下げた。何度も何度も、タキ子のおくれ毛が床を掃く。お客様の二人も、それに応えて頭を下げて上げてをくり返す。
このお客様は、いったいいつになったら家の中に入れてもらえるのだろう。
その様子を見ながら、菜美子はそんなことを考えていた。やがて長い挨拶が終わると、お客様は仏間に案内され、お供え物をタキ子に渡し、お線香をあげて帰っていった。もちろん「あぁ、瑠美子ちゃんの」と言い残して。
仏間には菜美子が東京から持ってきたクッキーもまだそこにある。法事が終わるまで食べることはできないのだと、菜美子は薄々わかってきて、なんだか瑠美子ちゃんに騙されたような気分だった。
お盆休みになり、東京から瑠美子がやって来た。玄関先で日焼けした子供たちを見て、瑠美子は満足気に微笑んだ。
瑠美子はそのまま仏間へ行くと、慣れた手つきで線香をあげ、静かに手を合わせた。
菜美子と暁人は顔を見合わせた。
なぁんだ、つまんないの。瑠美子ちゃん、お線香のあげ方ちゃんと知っているんだ。
その姿は、東京で見る母とは違う、新発田の瑠美子ちゃんの姿だった。
菜美子はゆっくりと目を開けた。もうすぐ新宿に着く。
「向こうで、瑠美子ちゃんに会えるかな」
今朝の、暁人の言葉が蘇る。菜美子にはわかっている。暁人は瑠美子ちゃんに会いたくて新発田へ行ったのだ。そして、自分の足が新発田へ向かないのは、瑠美子ちゃんに会うのがつらいからなのだ。新発田には、瑠美子ちゃんの思い出があちこちに息づいている。行けば、きっとそれを肌で感じるだろう。
二年前に母が亡くなったとき、浩介とタキ子は老体に鞭を打って東京に来てくれた。二人とも八十近い。昌也と美華が始終二人に付き添い、親戚中から預かってきたというお香典を手渡してくれた。昌也も美華も、菜美子たちに気を使って「瑠美子ちゃん」の思い出話をしてくれたが、それはよりつらくなるだけだった。
「菜美子さん、携帯が……」
新宿のカフェで、新人作家の井澤恵理とプロットの打ち合わせ中、何度も携帯が震えた。
「なんか、今日は忙しそうですね」
菜美子と同世代の恵理は、耳によく通る明るい声で言う。
「仕事じゃなくて、弟からなの」
恵理がきょとんとする。
「仲いいんですねぇ」
「そういうわけじゃ……。今、母の故郷に行っているから、その報告だと思う」
「やっぱり仲いいじゃないですか。見なくていいんですか? 携帯」
菜美子は仕方なく携帯に手を伸ばした。ラインのメッセージが二件、着信も一件入っている。
「まったく、一日に何回ブログをアップする気なの」
「へぇ、ブログ。私も見ていいですかぁ? よかったら私のタブレット使ってくださいよ」
二人でブログを開いてのぞき込む。『伯父夫婦』というタイトルの記事を開くと、浩介とタキ子がテーブルに並んで座っていた。なつかしい二人の笑顔に、菜美子は胸をこつん、と叩かれたような気がした。
テーブルの上にはお菓子やお饅頭、フルーツや飲み物が所狭しと並んでいる。昼食後のお茶のひとときだろう。菜美子はふっと笑みをこぼした。
昼下がりからこれだもの、夕飯になったらどうなることか。
夜には昌也も職場から帰宅し、高校生の子供たちも一緒に夕飯を食べるだろう。もしかしたら、新潟市に嫁いだ美華も来るのかもしれない。テーブルを占拠するたくさんの料理と、それを囲むにぎやかな家族。「あれも食べろ、これも食べろ」と、そんな声が聞こえてくるような気がした。
もう一つ写真があった。台所に立つ女性の写真。昌也のお嫁さんで、今の本家の肝っ玉お母さんでもあり、台所を支えている人だ。お客様である暁人のために、今夜は台所を忙しく動き回るに違いない。ひと昔前のタキ子がそうしていたように。
「新潟美人ですね」
恵理が言う。菜美子もうなずいた。
もう一つ、記事がアップされていた。タイトルは『変わらない風景』だ。
散歩がてら、近所をぶらぶらしました。家は立派な新築になっていたけれど、周りの風景は変わっていません! 嬉しい (#^.^#)
写真がある。
四角いフレームの真ん中できっかり線を引いて、上半分はまっさらな青い空。下半分は濃い黄緑の風景だ。どこまでもつづく田んぼの写真だった。空と田んぼの境界線には、うっすらと青い影が連なって見える。遠くにそれほど高くない山があるのだろう。
「うわぁ、何もない所ですねぇ」
恵理が感嘆の声をあげた。
「なんか、新潟ってスキーができる雪山とか日本海のイメージが強かったんですけど、この写真だとほんとに何もないですね」
「うん、新発田は平野部だから」
菜美子は画面を閉じると、恵理に「ありがとう」と言ってタブレットを手渡した。
何もないところ、か……。
出版社へ戻る車内で、菜美子は新宿のビル風景を乗客の肩越しに眺めていた。
「どう、何もないところでしょ」
脳裏に瑠美子の声がやわらかく響く。菜美子は吊革につかまったまま目を閉じた。
法事が終わった翌日。瑠美子は子供たちを散歩に連れ出した。朝日がうっすらと空を染め始めたばかりの早朝だった。
前日の夕方に雨が降ったので、辺りにはしっとりとした空気が立ちこめ、時おり吹く風が、湿った空気を流してくれていた。
遠くに見える道路には車一台も通っていない。一日が動き出す前のしんとした朝だ。
菜美子と暁人は、肩を並べて瑠美子の背中を追いながら歩いていた。田んぼと田んぼの間のあぜ道をぐんぐん突き進み、ふとふり返ると、自分たちが歩いてきた道がどこまでも細く伸びていた。黒くぽつんと見えているのが本家だ。
「どう、何もないところでしょ」
立ち止まると、瑠美子は両手を広げて大きく深呼吸をした。
瑠美子の「何もない」という言い方に嘲笑するような響きはなかった。むしろそれを慈しんでいる。幼い菜美子たちにもそれがわかっていた。二人で元気よくうなずいて、瑠美子のマネをして大きく深呼吸をすると口々に言った。
「なんにもなーい」
「ない、なーい」
瑠美子も「そうでしょ、そうでしょ」と嬉しそうに何度も言った。
三人は鮮やかな黄緑色の田んぼに囲まれていた。視界を遮るものはない。行き止まりのない風景だ。朝もやのせいか、遠くにあるはずの山の影も見えなかった。
真っすぐ突き出た黄緑色の稲の中に、少し色が薄くて細い、やわらかそうな草が遠慮がちに伸びていた。
「出穂の時期なのねぇ」
瑠美子がしみじみと言った。
この穂がお米の元になるのだと、瑠美子は教えてくれた。
「この稲穂がどんどん黄色くなって、粒粒がぷくっと膨らんでくるとね、重くなって、お辞儀をするみたいに垂れてくるの」
瑠美子は自分の手を使って、稲穂が垂れる様子を表現して見せた。
「それって、タキ子伯母さんのことじゃない?」
ぴょんと跳びはねながら暁人が言った。
「だって、タキ子伯母さんいっぱいお辞儀をしてたよ」
瑠美子は微笑んだ。
「おばあちゃんは?」
菜美子も負けじと言った。
「おばあちゃんの腰も丸くていつもお辞儀をしてるみたいだよ」
「そうねぇ」
瑠美子は目を細めて笑い、朝日に目をしばたたかせた。
たっぷり雨水をたたえた稲の原に、朝日がゆっくり染み込んでいく。
しばらくの間、菜美子は名残惜しそうに田んぼの風景を眺めていたが、やがて覚悟を決めたかのように口を開いた。
「さぁて、帰ろっか」
子供たちは「えぇー、もう?」とがっかりした声を出した。
「だって、朝ごはんのお手伝いをしなくっちゃ。よし、走ろう」
子供たちが反応するよりも早く、瑠美子は走り出した。
地面を思いきり蹴り上げながら、その背中がどんどん小さくなっていく。
「お母さん、ずるい」
菜美子と暁人もあわてて後を追って走り出した。心臓がばくばくして、はち切れそうだった。それでも走るのをやめなかったのは、暁人に負けたくなかったのと、こうして三人で走ることが、特別な思い出になるとわかっていたから。
視界をかすめていった緑の影や、足の裏で受け止める土の感触。
そして、あぜ道の向こうで手をふって待っている瑠美子の姿は、今でも瞼の裏に焼きついている。
瑠美子は、二人がまだ幼い子供のうちに、新発田を思いきり体験させてやりたかったのだと思う。
十二歳の夏が終わり、次に新発田を訪れたとき、菜美子は田舎ではしゃぐ年齢はとうに過ぎていて、東京に残って原宿にくり出すことのほうが大事になっていた。
その後祖母が亡くなり、社会人になった菜美子が新発田へ行くことはなくなった。
新発田の人たちのことが頭をよぎらないわけではない。行けば、喜んで迎えてくれるだろう。
鞄の中で、携帯が震える気配がする。菜美子はそれを無視して電車をおりると、改札を出て出版社へ向かって歩き出した。
菜美子はこれからすることを頭の中で反復していった。
デスクに戻って、メールをチェックして、契約書を作成して、今日打ち合わせした内容をまとめておけば、月曜日が楽だ。今日は金曜日だから、みんな帰りは早いだろう。誰か誘って食事でも行こうか。何人かの同僚の顔が浮かんだ。
鞄の中で、再び携帯が振動する。
また?
菜美子は立ちどまって、仕方なく携帯を取り出した。ラインが二件。
おーい。ブログ見てくれたかな (・・?
もしもーし。
またブログアップしたよー
丁寧にブログのリンクをまた貼り付けている。
このとき初めて、菜美子は暁人に一度も返信をしていないことに気がついた。さすがに、それはひどいことをしたかな、と少しは反省する。
菜美子は指をすべらせてブログを開いた。すると、最新の記事のタイトルが目に飛び込んできて、菜美子は思わず「はぁ?」と声を上げた。
タイトルは『姉貴へ』だった。
人の邪魔にならないように道の脇へよけると、困惑したまま記事を開いた。
最初に、写真がアップされていた。
田んぼの写真だった。細い道が真ん中に一本、どこまでも真っすぐつづいている。その両脇には、緑の濃くなった稲が空に向かって伸びていた。
おそるおそる、本文に目を通す。
この写真は僕の思い出のあぜ道。九歳の時、母さんがここに連れてきてくれて、僕と母さんと姉ちゃんと三人でかけっこをした場所。
今回の帰郷で、どうしてもここに来たくて、あの時の記憶をたどってこのあぜ道を再び見つけた。といっても、家の周りはほとんど変わっていなかったから、楽勝だったけどね。
姉ちゃん、明日は母さんの誕生日だね。生きていれば還暦だ。まさか、こんなに早く母さんを見送ることになるなんて思ってもみなかったよね。
母さんが亡くなって、僕も姉ちゃんも、あまり会うこともなくなって(元々、そんなに頻繁に会ってもいなかったけどさ)母さんの話もしなくなっちゃったね。
僕が新発田へ行こうって言ったときも、姉ちゃんは絶対に「うん」て言わなかった。でも、今朝は久しぶりに顔が見られて嬉しかった! 見送りに来てくれてありがとう。
僕たちはもう社会人だし、いつかは結婚したりして、互いに疎遠になっていくかもしれない。だけど、ぼくはずっと姉ちゃんの弟だし、これからも一緒に母さんの話をしたいと思ってる。新発田にだって、姉ちゃんと来たいんだ。だって、ここは瑠美子ちゃんと過ごした思い出の場所だろ。
明日の瑠美子ちゃんの誕生日に、僕はこのあぜ道を思いきり走りたいんだ。心臓をばくばくさせてさ。だけど、とりあえず今夜は飲むぞ! 飲み過ぎないように気をつけるから、心配はしなくていいよ!
菜美子は携帯をしまうと再び歩き出した。
震える胸の鼓動を無視して、小気味よくヒールをアスファルトに打ちつけて歩いて行く。
えっと、デスクに戻ったら何をするんだっけ?
メールをチェックして、契約書を作成して、それから――。
それから――。
菜美子は急に勢いを失くして立ち止まった。細く伸びた影にぽつりと視線を落とす。
二年前、瑠美子は膵臓がんであっけなく逝ってしまった。病気が見つかったときは、若いのだから十分に闘えると思っていた。だけどそれは間違いで、若いからこそ癌も早かったのだ。
暁人がずっとさみしい思いをしていることはわかっている。一緒に悲しみを癒したいと願い、菜美子に手を伸ばしつづけていることも。
そんな暁人の気持ちに気がつきながら、菜美子はずっと背中を向けつづけた。
だって、つらすぎるんだもの。
暁人に会えば、嫌でも母のことを思い出す。新発田へ行けば、母の思い出が泉のように湧き出るだろう。
悲しみとの向き合い方は、人それぞれだ。
「今戻りました」
菜美子はいつもより声を張りあげて、オフィスに入っていった。
さてと。
鞄を置いて、ふうーと息をつく。
デスクの上に白い封筒が置いてあった。後ろを通りかかった同僚が声をかけていく。
「昼過ぎに届いてたよ」
「そう、ありがとう」
ひっくり返して裏を見る。送り主の名前を見て目を見張った。
暁人からだった。
もたつきながら封を切り、封筒を逆さまにしてひとふりすると、中身がデスクの上にするりと落ちた。
うかつにも、じわりと涙が浮かんだ。
まばたきをして、なんとか涙を引っ込める。
新潟行きの特急券だった。付箋が貼ってある。暁人の字で、一言だけ。
待ってる。
ばか。安月給のくせに……。
「菜美子さーん。今日、どうですか? このあと。ちょっと飲みにでも」
うきうきした声で後輩が話しかけてくる。たしかに、お酒は飲みたい気分だ。
口元に笑みを浮かべて、菜美子はふり向いた。
「ごめん、今日はパス。ちょっと行くとこがあって」
「へぇ、どこですか?」
大きく息をついて、こみあげてくる感情を押し込める。
心の奥に、緑の海原が広がっていく。
「新潟の新発田。知ってる?」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
