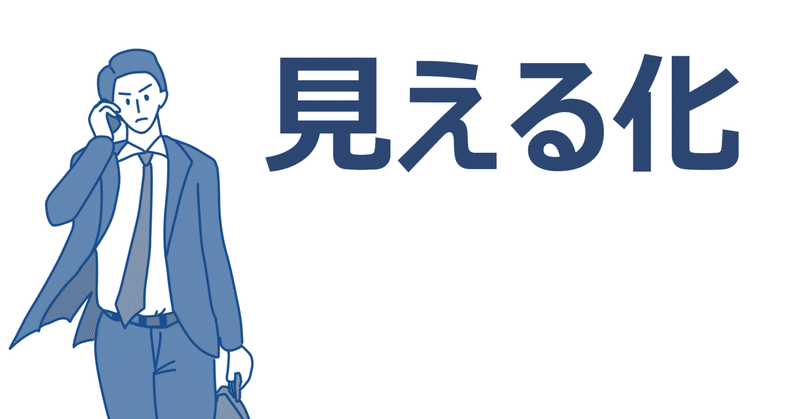
【学会誌】ライフサイクルアセスメントで見える化
こんにちは。
『表面技術』2023年8月号を読んでいます。
読んだ記事について、気になったポイントをメモしておきたいと思います。
今回読んだ記事のタイトルは「めっき向上の環境負荷要因の工程改善による排水由来の環境負荷の低減」で著者は東京都産業技術研究センターの田熊さん他数名の方々です。
内容
ライフサイクルアセスメントと呼ばれる手法でめっき工場の環境負荷を算定し、高環境負荷の工程特定と要因究明の事例に関して説明されています。
ライフサイクルアセスメントは「どの工程で環境負荷が大きく、どんな改善をすべきか」という指標を与えてくれるので、ウェット系の工場で環境対策をしよとするときに取り組みの根拠を示す際に説得力のある理屈になりそうです。
記事の中では改善方法に関しても解説されていますが、フィーリングで思いつく改善方法と大差ないのですが、しっかり理屈があるので場当たり的ではない印象を与えてくれます。
また、新人や現場に詳しくない担当者が工程を理解するためにも使える手法だと思います。
ライフサイクルアセスメントの方法
この記事を読んだ限り、ライフサイクルアセスメントは以下の手順で進められます。
インプットする化学物質・電力・水使用量の書き出し
アウトプットとなる廃棄物・排水中に含まれる化学物質量の収集(データベースや実測値)
各アウトプットの数値データを工程毎に整理して一覧表を作製
影響評価
特性化:影響領域(地球温暖化、資源消費、等)毎にどの工程の寄与が大きいかを見える化
統合化:影響領域全体の結果を統合して環境負荷の大きい工程を見える化
環境負荷が大きい原因を考察
考察結果を元に改善策を推進
記事の中ではデータベースはIDEAを、特性化と統合化はLIME2で行っています。
担当者だけでは難しい(感想)
記事は書いてませんが、ライフサイクルアセスメントを実施するのはかなり大変な印象です。担当者だけでは到底できない。
これ専門の部署があってもいい気がしますが、現場をわかっていないと的外れな分析になってしまうと思うので、組織としてリソースを割いて取り組む必要がありそうです。
ある程度経験が必要そう何ので、手伝ってくれる機関やコンサルがいれば、進めやすいかもしれません。
今日は以上です。
参考
ネットで調べた以下サイトを見ると記事から読み取った手順では若干足りない部分がありますが、大きな流れとしてはこんな感じのようです。
あと、LCAフォーラムというものがあって、情報発信されているようです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
