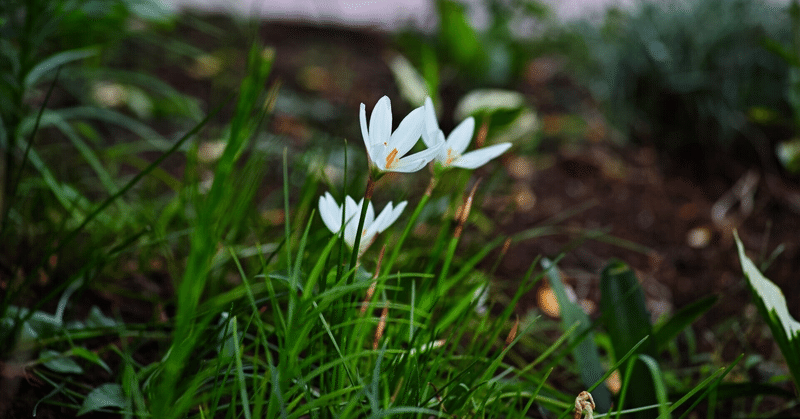
不調と付き合う、ということ
いくつも持病がありまして。
まぁ、持病というより体質だと今では受け止めています。
一つずつは大したことがないものの、併せ技で不調がやってくることもあり、
今回は何がいけなかったか?とアセスメントしながらなんとか乗り越えて生きています(笑)
ただ、ここに至るまでが大冒険でした。
不調とうまく付き合えなかったり、頑張りすぎたりして、これまでに何度もしくじっています。
①小学生の時:食べられなくなって成長が停止
②中学生の時:体調を崩したことをきっかけにバーンアウト、1ヶ月不登校→半年ほど別室登校→教室復帰&部活復帰
③高校生の時:体調を崩したことをきっかけに電車移動が苦手になり、休学→留年→退学
この「不調」はすべて、いわゆる自律神経失調症的なもので、③がこれまでの人生で一番しんどかったです。
ここまで不調に見舞われる人生で、ちゃんと働く大人になれるのだろうか?と思っていました。
高校退学後は通信制高校に編入し、2年遅れで卒業。
当時はまだ長距離移動が困難だったため、自宅近くの看護学校に進みました。
なお、看護学校卒業後は大学に編入しており、社会人デビューは合計3年遅れです。
看護学校に進む前に「不調との付き合い方」を見つめることになったのですが、
これがターニングポイントになりました。
この道のりの途中で、すべてを「気持ちの問題」と片付けられたりして、医療に対する不信感を覚えたこともありました。
(自分でもメンタルの問題だと思っていましたが、根本的には身体の問題でした。ただし、メンタル面ももちろん関係はしています)
不調に飲み込まれたばかりの時には、何がいけないのか、どうしたら元気になれるのか、すごく慌てて不安になりました。
大学受験のために頑張らなきゃいけない時期なのに(高校在学中は医学部志望だった)、なぜ自分ばかりこんな目に遭うんだろうと思い、それこそネットで色々調べ、泥沼にはまっていきました。
「元気ってどんな状態だったっけ?」と、「調子がいい」という感覚が全くわからなくなりました。
人のツテで少し遠くの医療機関にかかって精査を受ける機会を得て、不調の原因を理解でき、納得できました。
ここがある意味、「付き合っていく」ベースに繋がったように思います。
そして、不調との付き合い方を探っていくことを学びました。
いつどんな状況で症状が出るのか、どんな対処方法だとやりすごせるのか。
(例:数を数えながら深呼吸を繰り返す、この薬をこのタイミングで飲む)
症状日記をつけながら、自分に適した対処方法を試して見出していく作業をしていき、良くなったり悪くなったりすることもありながら、「まぁなんとかやれるよね」という状態を探っていくと、だんだんと不調を感じることが減っていきました。
それから、「必ず良くなる」と医師に保証してもらえたことも心強かったです。
(心療内科専門医の先生に感謝です)
もちろん、体調によっては踏ん張りすぎずに休むことも必要です。
ただ、長い目で見たときには「休む」という手段を入れつつ、低空飛行ながらに過ごすというスキルも大切なのでは、と思うのです。
疲れたり、何かのきっかけで弱ることもあります。
看護学校進学後も不調がやってくることはあって、「あなたが看護師をやっていくのは無理じゃない?」と言われたことも一度や二度ではありません…😅
(今、看護の教員をやれていることは奇跡だと思っています…)
それでも、良い時や悪い時もありながら、自分のペースでゆっくりやっていこうと思えることが、結構大事なんじゃないかな、と思います。
ちなみに、このしんどい過程で色々と諦めたこともありましたが、
「強みも弱みも受け止めて、どうしたらいいかを一緒に考え、医学的知識を持ち科学的根拠のもとに生活のなかで対処していく」という看護師の役割を患者として実感し、看護職を目指すことにしました。
(お世話になった病院で働くことが私の目標になり、数年後本当に就職しました)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
