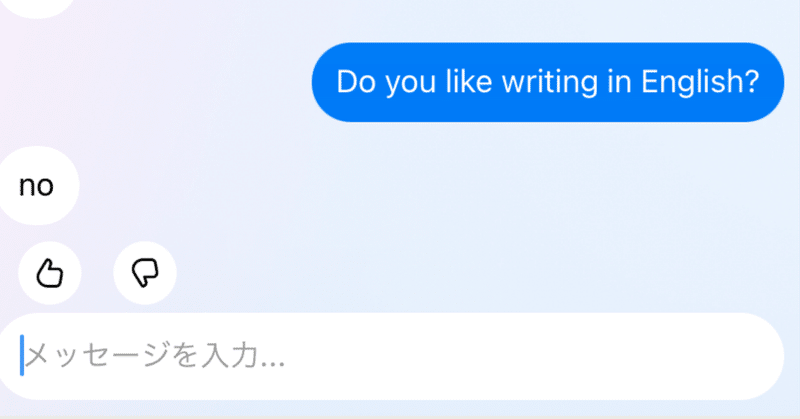
ライティング:種類別ライティング雑談
こんにちは~
以前の記事で書くと言っていた、ライティングについてだらだらしゃべろうと思います。
結構先延ばしにしていたかと思うんですが、如何せん私はライティングがダントツで苦手かつ嫌いです。
どれだけ頑張っても正解がないし、一番時間がかかるから。
しかも、書く文章とか受ける試験の種類によって書き方を変えないといけないという、、、。
1.英検の場合
英検にはほとんどの級でライティングが課されているはず。(四・五級は知らん)
個人的には二級・準一級が一番簡単だと思っています。
あんまり詳しくは覚えていないけど、二級は80ワード前後、準一級は120ワードぐらいだった気がする。
短くもなく長くもなく、自分の意見を一番シンプルにまとめられる長さですね。それにこのぐらいのレベルになってくると、ある程度のレベルの大学受験では困らないぐらいの英語力が付いているかと思うので、そこまでむずくない。
ほんまに難しいのは準二級・一級ですよ。(三級は、教える側だと難しかった印象)
準二級は40から50ワードぐらい、一級はマックス240ワードですね。
・準二級
三級の次に設置されている級で、目安は高校在学レベル。
私は中三の初めに取りましたが、何が難しいって、高校レベルの英単語が出てくることなんですよね。
だからみんな必死に覚えようとしますね。
しっかり覚えられていたら、(例えば動詞やったら、自動詞か他動詞か、何の前置詞が付くのか、どんなニュアンスなのか、を理解できていたら)ライティングで勿論使えます。
でも、落ちる人の半分はそうじゃないな。うろ覚えで頑張って使おうとするから文法がぐちゃぐちゃになって、他に気を付けるべきところ(スペリング、時制など)が疎かになってる気がする。
ほんで残りの半分は、多分語彙が稚拙過ぎる。ミスるのにびびって相応しくない言葉遣いをしてたりしますね。(主観が入りすぎてるとか、なんか子どもっぽい単語とか)
難しいですね。難しい言葉遣いだとミスが増えるし、簡単すぎると減点の可能性がある。
・一級
言わずもがな、学生の大半が受ける”英検”の最高峰ですね。
お題、単語、構成どれをとっても高難易度、さらに採点基準が超厳しいイメージ。
どの級でも基本的には、
intro( I think/contemplate/suggest/claim…)
body×2~3(Firstly/To begin with… Secondly/ In addition/Moreover/Furthermore…)
concl( Therefore/In conclusion…)
の三段構成ですね。(厳密に言うと、一級はbody×2+counter argument×1だと得点が高かったです)
一級の難しい所は、トピックセンテンスを書いて、ちょっと付け足したら終わり!では、済まない所です。
英語で論文などを書いたことがある方からすれば、200ワードってめっちゃ少ないと思います。ただ、残り時間を考慮に入れると、めっちゃくちゃにしんどい🤦♀️
この短い制限時間の中で、良く構成された文章を書くのはなかなか練習が必要ですね。
・日本の大学でのessay
私が一回生の時は、二週間に一回ぐらいのペースでessay書きまくってました。
英語系の学部なので(外大じゃないです)、勿論ライティングの授業もあった訳で、最長で2000ワードを書きました。
ただ、毎週そんなに多い訳ではなく、字数はだいたい300~500ワードでしたね。
今となってはぬるま湯ですが、入学したてはまあキツかった😭
別に字数はそこまで気にならないんですけど、文章を作る才能が絶望的に無かった。(今もです)
私は元々、introは短めでbodyに書きたいことを盛り込むタイプだったんですが、
英検一級ぐらいの長さだと太刀打ちできたものが、300~500ワードになると難しくなりました。
何故なら書きたいことだけじゃ長さに合わなくなってきて、結果ダラダラ文章を続けてしまっていたから、、、。
結局それは改善されることなく、学年末の2000ワードを迎えた訳ですよ。
グラフとか無理やりねじ込んで事なきを得ましたが、まあ酷かったなあ。
正直あんまり得るものもなく、無駄な練習を繰り返しただけ、な気もします。
・argument essay
で、今現在留学をしているわけですが、
こっちに来てから書いたessayは800ワード×2、1500ワード×1、2000ワード×1です。
こなす数こそ減りましたが、毎度毎度字数がえげつない。
しかもこっちで書く大半はargument essayと言って、種類が違います。
簡単に言うと、「私」や「あなた」という主語を入れてはいけないものです。
主観の入る単語(例えばenormous/wonderfulみたいな。それぞれsignificant/goodの方がいいねという感じ)は使えないし、論文や参考文献を読み漁る必要があるんですね。
素直にめんどくさいんですが、学ぶことはたくさんありました。
bodyとconclに関しても学ぶことはありましたが、比較的数が少ないので今回は省略します。
収穫があったのはintroですね。
<Athletes should be allowed to take performance enhancing drugs.
Do you agree or disagree?>
According to Savulescu, Foddy & Clayton (2004, p.1), the use of drugs to improve players’ physical conditions and skills has been one of the most serious problems of sports since the third Olympiad. This denotes that using drugs for a better score and medal has been common among sports players for a long period of time. Some think that it is comprehensible to utilize drugs for the better competition and the more intense excitement. Certainly, one of the purposes of playing sports is to make audiences excited. However, the use of drugs can result in such a terrible situation that people cannot handle easily. This essay will argue that despite its benefit, using drugs for physical enhancement can easily lead players to the undesirable results in terms of health problems and its aftermath.
これは実際に、私が留学に来てから一番最初に書いたものです。
お題はアスリートのドーピングについてですね。
で、私の意見はドーピングはしたらダメ🙅♀️です。
1.According to Savulescu, Foddy & Clayton (2004, p.1), the use of drugs to improve players’ physical conditions and skills has been one of the most serious problems of sports since the third Olympiad. This denotes that using drugs for a better score and medal has been common among sports players for a long period of time.
一番最初の二文を使って、アスリートの薬物使用の現状について触れています。
導入の導入という感じですが、勿論「私は~」という書き方はNGで、参考文献の著者を使って誘導します。
2.Some think that it is comprehensible to utilize drugs for the better competition and the more intense excitement. Certainly, one of the purposes of playing sports is to make audiences excited.
これは譲歩ですね。「確かにドーピング賛成派もいるよね~」と一歩引く。
3.However, the use of drugs can result in such a terrible situation that people cannot handle easily. This essay will argue that despite its benefit, using drugs for physical enhancement can easily lead players to the undesirable results in terms of health problems and its aftermath.
ここで、反撃します。「確かにそうだけど、でも、、、」みたいな論調ですね。
ほんで最後にこのessayのお品書きみたいな感じで、何を言うのかを説明しておく、といった具合。
勿論改善点は有ります。
例えば、譲歩の仕方とか。あまりに思いつかなさ過ぎて、あんまり良い形とは言えないですね。
ただまあ、しっかり導入することによってbodyもかなり良く構成できますし、introに関しては良いことを学びました。
以上!
ライティングも他の技能と同じく、正しく練習あるのみです。
次回は一級と準一級の長文問題をいくつか見ていく予定です。
ジャネ
The gist that nothing will not go well without the well-structured beginning can be applied to anything.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
