
イギリスへの謎の憧れ
イギリスの魅力は何かといえば、俗物のたくましさと美しさである。
イギリスはいい意味で俗物根性がたくましい。理想よりも現実を見て、生き残るために泥臭く手を尽くしてきたのだ。
「俗物」というと聞こえは悪いかもしれない。しかし俗物でないものなんて、大体はソクラテスやキリストみたいに「美しく死ぬ」羽目になるのである。
だったら、俗物でも生き残った方が偉いじゃないか。絶えず困難が押し寄せる中で、美しく死ぬなんてことも許されず、地べた這いずって泥すすってでも生き延びなきゃいけない、そんなクソッタレな現実を笑おう。
なにかに殉じて綺麗に死ぬようなヤツなんて、美しかろうが所詮、現実を変えられないのだから。
歴史とは「生き残った者」という名の勝者の物語だ。然らば、たとえ矮小なものとしてでも、生き残ることこそが正しいのだ。
こういうわけなのだろうか、王位継承に絡んだ流血沙汰を前にして、イギリスは女系/女子相続を認めることを選んだのである。
そこには「滅びるくらいなら変わった方がマシだ」という割り切りがある。
イギリスが女系/女子相続を認めたきっかけ?は、確かノルマン朝末期のスティーブンとマティルダの争いにあったはずだ。初っ端から波乱万丈である。
これは一見、伝統や既存の慣習をかなぐり捨てているようにも見える──が、実のところ、イギリスの「伝統」のしぶとさの秘訣はここにあるのだろう。
「保守思想の父」ことエドマンド・バークが、いみじくも『フランス革命の省察』に書いた通りである。
フランスは今大騒ぎらしいが──「理想」だの「革命」だの、いったい何をいっているんだか。「全部ぶっ壊してまた一から」だなんて、そんなこと上手くいくわけがないじゃないか。
俗物上等、政治なんてものは所詮弥縫、悪と悪の妥協にすぎない。革命によって一足とびに「理想の世界」に飛び立とうったって、そうはいかない。失敗するに決まっている。良いところは残して、腐ったところは地道に取り繕って、なんとかやっていくしかないのだ。
それは時代にそぐわなくなった古いものを、むやみやたらに残す「守旧」とは違う。手入れや修繕は必要だ。しかしだからといって、これまで積み上げてきた伝統をよい部分ごとぶち壊してしまうわけにはいかないのだ。
イギリスの支配階級にはこういった泥臭さがある。これはこれでかっこいい。
彼らはフランスのように──例えば平凡な王家の女マリー・アントワネットが、ダヴィッドの悪意ある筆致を通してさえ「王族の最期の矜持」を見せていたように──「理想の見せかけ」を最期まで演出して死んでゆくようなことはしない。
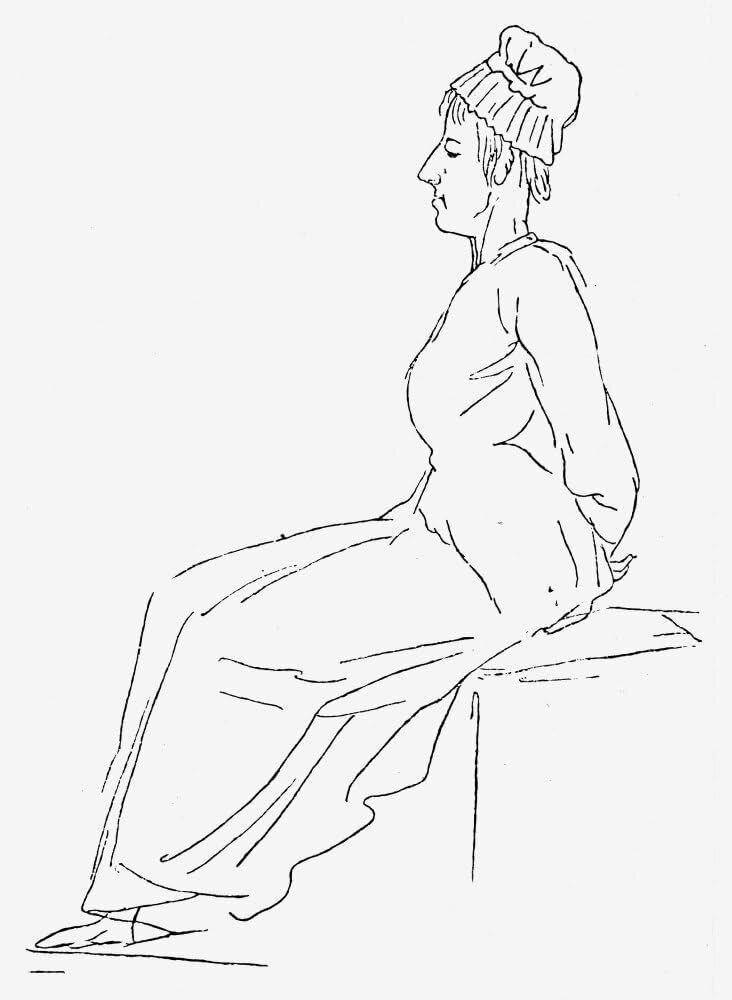
イギリスの支配階級というものは、実に柔軟に新興勢力を取り入れる。そうでなければ立ち行かないからだ。
王がそこのところの機微を読めずに特異な経過をたどったのが、17世紀のピューリタン革命から名誉革命に至る一連の流れ──三王国戦争の時代だろう。
いやごめん、私17世紀のイギリスに詳しくないから断言はできないんだけど。
例えば、ヘンリー8世の宗教改革によって解散させられた大小修道院の土地を獲得し、ジェントリが力を増したら、そいつらが徐々に支配階級に組み込まれていくのだ。
エリザベス1世の時代に財政問題が噴出したら、解決のためにシティの商人たちのグローバルなマネーを取り込む。王室が市民にすり寄ったわけだね。
それから少し経って、イギリス帝国を拡大させたジェントルマン資本主義だって、伝統的な支配階級とシティの金融との融合から生じてきたのである。
だからといって、イギリスの支配階級に理念がないのかといえばそんなことはない。彼らは新興勢力を巧みに取り入れながらも、自分たちの伝統的な価値観を「理想」として軸に据えることに成功しているのだ。
ゆえに、イギリス帝国時代におけるシティの資本家のような新興勢力は、旧来の支配者層と同じ価値観や生活スタイルを真似ることで、支配者層に仲間入りしていったわけである。イギリス旧来の支配階級の伝統が、新興勢力の価値観によって全く塗り替えられてしまうようなことはなかったのだ。
これは隣国フランスが革命前後に、贅沢から啓蒙へのドラスティックな転換を経たのとは対照的である。イギリスとフランスは同じく「世襲王政をしいた西欧の強国」でありながら、理想と現実に対する向き合い方が対照的な感じがして面白いね。
まあ、フランスは割とずっと大国感ある(カール大帝とか、ハプスブルク家との対立とか)けど、イギリスが大国になったのっていうて18世紀とかだしな。長らく「ヨーロッパの辺境にある二流の島国」というポジションで大陸ヨーロッパと渡り合わなければならなかった分、イギリスの方がこの辺老獪になったのかもしれない。
このたくましい俗物根性のゆえだろうか、イギリスには大陸ヨーロッパとは異なる独特の精神性が備わっているのである。
例えば、経験や観察からの帰納を重んじる、明るい学者精神。大陸ヨーロッパの合理論に対してイギリスが唱えたのは、経験論であった。
他にも、シェイクスピアやらベケットやらの文学に、ホッブズやロックの政治学、ニュートンの物理学と、有名どころだけ挙げてもイギリスは色んな学問をやっているわけだ。
イギリス帝国時代には船に乗って新大陸やら極地やらの探検もしているし、ご存知の通り、大英博物館とかいう巨大な略奪品展示場だってある。
イギリスにはそういう、どこにだって行くし、何だって集めてくるし、何だって見て知ろうとする無邪気な好奇心があるように思うのだ。
博物学的というか、驚異の部屋的というか。イギリスは多分、部屋に閉じこもって「完成された静謐さ」に身を委ねようとはしないだろう。面白いことは外にしかないのである。
それでいて、外から持ち帰ったものを机に並べながら、観察してあれやこれやと分類するのも好きそうなのだ。面白いね。
興味深いのは、イギリスはおそらく和辻哲郎のいう北ヨーロッパ(=音楽など、聴覚の文化圏)側に属しているにもかかわらず、「見る」ことを大いに愛していそうなところである。
それでいて、フランスのように明るい光を見つめすぎて目をくらませるようなこともない。真昼の屋外ではなく、ランプの灯った夜の居室。快晴ではなく曇天。そこでイギリスは見る。眩しすぎる光に目を焼かれることもなく、じっと見つめるのだ。
けれど、イギリスはやっぱり北ヨーロッパ側の血も引いているのだろうな。だから南の地中海世界とも違い、絵画や彫刻というよりは言葉に長けているのだろう。言葉は文字として読ませることも、声として聞かせることもできるからね。
……いやごめん、筆者が和辻哲郎『風土』エアプだから、今の話はやっぱり忘れてくれ。この文章は思いつきで書かれている。
あと面白いのは、どこまで「高尚に」学問を研ぎ澄まそうとしているのかが分からないところかな。
文学の金字塔・シェイクスピア作品が「演劇」であったように、イギリスの文化の精髄には、社会と交わったり大衆を楽しませたりするような、社交的で慇懃で陽気な軽やかさがあるように感じるのだ。
実用や熱意や真剣さの中に混じる、かすかなアマチュアリズムがイギリスの面白いところだと思う。しらんけど。私、ウォードの箱とか好きだよ。
民衆レベルでいえば、ユーモアや皮肉もイギリスらしさだろう。
困難な状況で笑い合い、冗談を飛ばし合うことを心得ている。それは前線で戦う者の勇敢さであり、防衛機制でもある。
イギリスには「前線」──外部との境界線が多いように思う。
そもそもUKという国の中で、イングランドとスコットランドとウェールズと北アイルランドがいがみ合いつつ(今のところ)同居している。
隣国フランスをはじめとする大陸ヨーロッパとも、何百年も対峙してきた。
近現代に至ると、アメリカや英連邦諸国との関係も浮上してくる。
大体、イギリスの十八番こと学問=科学の営み自体が、今引かれている境界線の先にジリジリと進むようなものだ。まあ実際に「進歩する」かは措くにせよ、進歩するのだと信じて、決して完成しない実証性を懲りずに追い求めるのである。
個人的に、こういう血塗られた泥だらけの道を鼻歌交じりにゆく強かさ、あるいは傲慢さが、イギリスの持つ最大の魅力だと思っている。
雨の中で笑おう。陽気に悲観しよう。武器を抜いて微笑もう。博愛の帝国であろう。変わらないために変わり続けよう。
海千山千の老獪さと、無邪気に好奇心を満たそうとする子どもっぽさ。思想の早熟さと国力の晩熟さとが手を取り合いもつれ合って、一つの不格好で美しい歴史を編んでいる。
ああイギリス、やっぱり貴方は最高だ。
とはいえ私は、貴方のことを何も知らないんだけどね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
