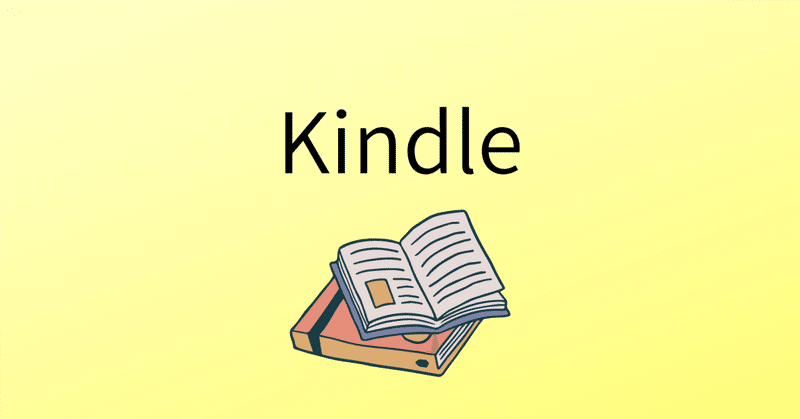
11日目。電子書籍のなかった時代を空想する
便利なものに囲まれて生活していると、それがなかった時代のことを忘れてしまう。
私自身、最新の機器や道具を使い倒すのが仕事でも趣味でもあるので、未来の方向に意識が向かいがちだが、今日の出来事を振り返りつつ、そのモノがなかった時代を空想しよう。
100日続けてみようと思います。11日目。
東海道53次をシェアサイクルで制覇してみようと計画中。ネットで検索するが、もう少し詳しい情報が知りたくなり、まとまった書籍を探してしまう。今までならば、電子書籍なので、欲しいと思った瞬間に情報が入手できるのが素晴らしい。それも書籍だと正確だ。出版業にいるからわかるけれど、複数人で内容をチェックして読みやすいように構成するから、ネット情報より格段に精度が上がる。
おかげで、どんどん買い足しています。買っても重さは0g。場所も取らない。すでに30冊近く買っている。まだ、スタートもしていないのに・・・(苦笑)
電子書籍はタブレットの登場とシンクロする。書籍データは印刷機械にかけるから、紙の本でもすでに電子化されていたわけだが、2007年にアマゾンKindleが登場して、2010年に初代iPadが登場して、どんどんインフラとして台数が増えるに従い、電子書籍市場も活性化していった。今だと、紙版も電子版も両方で発売される本がほとんどになったが、私が著者になった当時は、どうしますか?とか毎回聞かれたものだった。出版契約書にも電子の取り扱いの記述は、最初は入っていなかった気がする。
電子書籍がなかった時代というと、紙の本だけということになり、欲しい本があれば、本屋さんに行くか、そのあと登場したアマゾンなどのネット書店でポチって、数日待つ必要があった。本屋さんが近所にあれば、当日手に入るし、ネット書店であれば、数日後だった。
電子書籍ができる前は、待っていたんだ。本は待って入手するものだった。「待つ」がなくなったんだ。
本の手触りとか・・タブレットの電子書籍とは、物体としての違いもあるけれど、それよりか・・「待つ」だな。これが圧倒的に変わったんだ。
供給する側から言えば、中間コストがなくなる。物流コストや取次にかかる費用なども・・・。印刷物でなくなるから、紙や製本コストも当然なくなる。利益率がよくなるわけだ。同時にビジネスモデルも変革されているわけだけど。
ビジネス書作家 美崎栄一郎
https://note272.net/
トップ画像はshigekumasakuさんからお借りました。ありがとうございます。
普段はお金をもらって書いているのですが、noteは、基本的に無料で記事を書いております。サポートしていただけると、励みになります。
