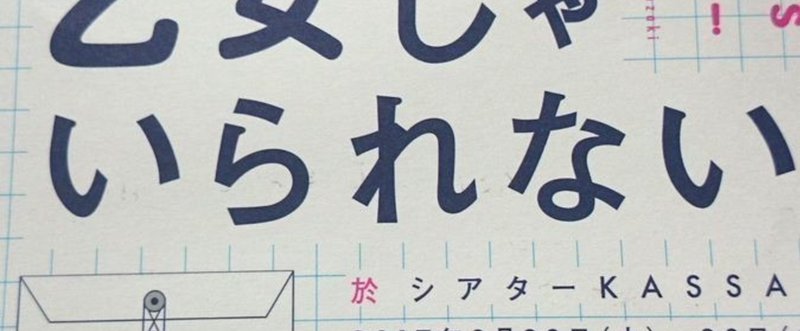
観劇日記:夢見る乙女じゃいられない(たすいち様)
2017年3月27日、たすいち様の「夢見る乙女じゃいられない」を観劇してきました。
上演時間は約2時間。高校演劇時代に慣れ親しんだ尺の二倍ですが、そんなことを気にする暇もない引き込む力がありました。胸が躍ったり騒いだり、肝を冷やしたり抜かれたり、腹を抱えたり痛めたりする名作でした。
観客としても、創作の末席としても、一個人としても思うところが多かったので、感想とか、いろいろ書いてみようと思います。高校演劇レベルが基本だから、視点が甘いかもですけれど。
一応再演(再再演)やDVD購入者の将来を考慮して、直接的なネタバレなしでいきますよ。
あらすじ
工藤優女は少年漫画家である!
彼女は日夜、アシスタントと弟と共に漫画を描いていた…のだが、ついに三度目の打ち切り、目下崖っぷちだ……。
工藤優女は少年漫画家である!
彼女は日夜、アシスタントと弟、そして新たな仲間、原作担当と共に漫画を描いている!首を賭けた新作『ドリームイーター』、夢食いを題材にした作品は男女に広くヒットした!
そんなある日のこと。弟の友人にしてドリームイーターの読者に異変が……。
最後にもう一度言っておく。
工藤優女は夢を求める少年漫画家である!
だいたいこんな感じ。ジャンルで言うとコメディが主体なのかな…?コメディときどきシリアスみたいな感じ。
主題について
キーワードは「夢」。言い換えて「願望」。対義語は「現実」。
「ああなりたい」「あれをしたい」というぼんやりとした、悪く言えば子供じみた夢。それを見られなくなる時間、学生的モラトリアムの終わり。
モラトリアムを超えて、夢を叶えた人間(この場合は漫画家だ)にも手加減なく襲い掛かる現実(打ち切り)。
夢はなんだ。悪夢ってなんだ。二つは現実とどう違う?
夢と、現実と、どう向き合えばいいんだ?
感想(劇全体について)
脚本、演技、音響、装置、照明、衣装、全てが噛み合ってたいい劇だった。
特に褒めるとすれば「テンポ」と「丁寧さ」。
テンポ。開演からオープニングまでの怒涛の掴みの早さ。コメディパートでの軽妙な掛け合い。セリフのないパートでのハイテンポな動きの劇(こういう無言ハイライトは結構好き)。逆に、きつい部分での間はじりっと伸ばして、悩む人間は言葉を出しあぐねて、緩急もきちんとついていました。殺陣も冗長にならずいいアクセントだった。
丁寧さ。何故その人はそう動くのか?行動原理をきちんと突き詰めて、演技が出来上がっている。セリフの有るシーンは当然ですが、セリフがない瞬間。二人が喋っているのを、他の人はどうやって見守るのか?
画面カットやズーム、映像編集がない舞台演劇だからこそ見られる「キャラクターが常に生きていること」を楽しめる劇はいい劇だ。
漫画のキャラクターたちが語り掛けてくるところも、キャラを丁寧に作ったからこその響きだったなぁ。
もちろん舞台装置だって丁寧。衣装も脚本も。丁寧で緻密な劇だった。
脚本・演出について
大きく分けてパートは3つ。「漫画家」「サークル」「ドリームイーター(劇中劇)」の三状況が出たり入ったり。現実ふたつをドリームイーター(DE)が繋ぐ感じが多かったかも。
DEが現実から完全に切り離されないところが好きだったな。
漫画家が現実で話し合いながらDEのやつらが「出来上がって」いく。
DEの1話分が終わって部隊がサークルに切り替わったからって、DE役者は舞台からハケない。なぜなら、読者の心にDEは「残って」いるから。
夢と現実は分かたれない。それを暗に示しているかのような立ち回りの演出が好きだったな。
全てのパートでの問いと伏線がひとつに繋がり、物語が転がり始める瞬間は、やられた!と心底思った。
夢の現実に直面する漫画家たち、夢と現実の狭間にいる大学生たち。夢と現実の関係性を問う作品。これは、あらゆるモラトリアムと、あらゆる創作者に見てほしい。
中身の感想については最後に回しますわ。
役者さんについて
全員書いてたら長くなりそう。頑張るぞ。キャラクターの思想や身の上、信条はあんまり触れないですよ。下手に書いてうっかりネタバレしたくないもん。
漫画家
工藤優女(中村桃子さん):崖っぷち漫画家。くどう夢。スーパーポジティブで、とんでもないエネルギー。そういう極端なキャラクターは得てして一色になっちゃうんだけど、そうはならなかった。機微が確かに生きていた。いいキャラクター。
井関希(永渕沙弥さん):漫画原作。移籍希望?真逆のネガティブ。彼女は彼女で、少しずつネガティブ以外の色を獲得していく。弱く、一方で強い。ラストシーンへの起伏を考えると、実際のところ一色じゃないのかもしれないね。そんな深みのある味でした。
雨津創(瀧啓佑さん):編集者。厳しくも優しい。出番はあんまり多くないけれど、フラットでいい話題回しをしてくれる。毎週のアオリが熱く、カッコいいぞ。
越夏音(能澤佑佳さん):作画アシスタント。ただの穏やかな人かと思いきや、時々我が強い。その我の強さと穏やかさの共存、夢と現実の噛み合い・噛み合わなさが、何気なく作品の全体像として象徴の一つだと思う。
工藤海(小太刀賢さん):弟兼アシスタント兼大学三年生。三場面を繋ぐ、ある種核のような存在。いい意味で癖と味が薄く、自然に馴染むキャラクター。周りが異常に濃い中でのこのキャラクターは度胸が要っただろうなぁ。自分ならなんか無理にキャラ付けるもの…すごいや。
大学生
貝瀬るりか(木野崎菖さん):就活もするし漫画も描ける三年生。
久遠さりな(梁稀純さん):就活もしないし漫画も描かない三年生。
モラトリアムを脱却しようとする微妙な立場と、脱却できないで道化になる微妙さ。るりさりの真逆なようで、似ているぎこちなさ、諦め、諦めきれなさ。これは本当にもう…胃にキました…名演なんだけどさぁ……るりさり希は胃と心に…くる…死ぬ……死んだ。
森村とあ(二宮咲さん):就活もしないし漫画も描かないが、モラトリアムが赦される一年生。無邪気、無慈悲。いつも明るい彼女が一度だけ、「一人」になるところが、酷く印象的でした。周りが巧いのもありますが、本人が「幼さ」をそこまででちゃんと演じているからこその恐怖でした。
春日野里太(伊藤貴史さん):就職を決めたけど漫画は描かない四年生。大学生の中では夢と現実に一番折り合いがついてる、かも。雨津さんと似たようなポジションと効果…なのか。直接的なセリフは少ないけど、ぶれないリアリティがあるから、鋭いことを言っても振り回して遊んでも映える。これはね、ご両人すごいことだと思いますよ……。
漫画の世界
獏(中田暁良さん):獏(夢食い妖怪)。三世界併せて一番の曲者。癖が強く、自分の美学を持ってるキャラを演じ切るのって本当に大変なんですよ!!本当に!やったことあるからわかる!
「どんな時でも生きている」と序盤に書きましたけれど、獏に一番それを感じました。自分以外のキャラクターを見てる時のあの…腕組みでの…傍観具合!絶妙…!
セリフをしゃべり始めれば勿論のこと、味が濃い。誘ってみたり、とぼけてみたり。動きひとつひとつもカッコいいし美しいんだよなぁ…くっそ…中田暁良とデートブロマイド買うべきだったか……!?
伊豆あきら(石井啓太さん):夢見る気弱な主人公。諦めまい。気弱だけど強い願望を持つ当たり、希と似てる部分がある。よわさ、優しさ、ノーマルさからの離脱。ギャップ、カタルシスの演出が丁寧。「漫画の主観」として、時にわざとらしい説明台詞を言わされることもあるけど、それでもくどくなりすぎないのは演技の濃さの調整が巧かった。
禍久しえら(竹内なつきさん):枕返し。反転の妖怪。自由、優しい、だけど弱い。和服も枷にならずよく動いた!爛漫!ただの爛漫に終わらず、どこかで何か底を見せない感じもあって…。
道好りいや(星澤美緒さん):あきらの友人。かわいい。少年漫画(それも女性読者に寄せ気味の作風)のヒロイン、というのは結構難しい役どころだっただろうに…。でも普通に可愛いって、実際難しいと思うんですよ。そういう意味では海に近い感想を持ちました。余計な記号を付けずにきゃぴきゃぴする。だから後半が活きる。
戸井いずみ(林弦太さん):あきらの熱血ライバル。実は今回観劇したのは、彼が目当てだったりする。優女のところにも書いたけれど、強すぎて、かつ汎用的なキャラクターは一色に染まってしまう可能性がある。それに呑まれず、熱血だけで終わらず、過剰な熱さとシリアスさの高低差、熱さや単純さが設定やポーズで終わらない行動の説得力。よくぞ演じられた!
石渡いるま(白井肉丸さん):退魔師参る。獏と並んで衣装の色が強い。キャラクターの主義主張としては、もっと強い。言葉も動きも圧力があって、軸と勢いがあって、ある意味では一番癖がなかった。誤魔化しがきかない役。そういう意味ではいずみに近い部分があり、いずみが他の要素を活かして「熱血」を表現したのに対し、いるまは「退魔」一本で演じ上げた。これは「キャラクターの掘り下げ」が、それこそ「漫画の中で」行われてないからだったかな?
一色、一本軸っていうのも相当難しいことなのだ。すごい。うむうむ。
アフターでカメラ向けたときに目線&ポーズご馳走様でした。
殺陣について
殺陣!見どころの一つです。少年漫画だもの。
とはいっても、矢鱈めったら斬った張ったってわけじゃない。必要なポイントで、メリハリをつけてアクション。いいものでした。
最前列で見てたら刀と傘の風圧が来たぞ!おすすめ!!
裏方について
美術:すごく凝ってる。所謂抽象劇系の、椅子が「椅子」じゃなくて「円柱」だったりするタイプの大道具。場面転換が多い劇に適してるんですよこういうの。
で、書割(背後とか壁のやつね)が漫画のページっぽくなってるのがよかった。しかも小口(本を開いたときの外端)までちゃんと再現されてるのがよかったねぇ…。
ペンとか定規とか主張強すぎでは?と開演前は思ったけど、そんなことが気にならなくなる・マッチする演者の力だったのでこれでトントンなのかもしれない。
ただ、せっかくなら「コマから出てくるのは漫画の住人だけ」とかしてくれるとよかったかなぁ…。
衣装:シンプルイズベスト。上の写真で、誰が何役でどんな奴かわかるでしょう?衣装なんてそれでいいんです。でも、それが案外難しかったりするんですよ…。
音響・照明:ほどよい。自分が高校演劇をやっていたころ、師匠に「演者の邪魔をするな」と教えられた。音を入れようと思えばいくらでも入れられる、光を変えようと思えばいくらでも変えられる……が!主役はあくまで役者なのだと。
そういう意味で見て聞いて、音響も照明も必要なポイント(漫画的な演出シーンとか、物語の転機)にはちゃんと入れて、そうでないところはちゃんと引いた。だからこそ印象的な(印象的にしたい)シーンが際立っている。
いや、高校演劇の地方大会レベルで測ってるからこんなことしか言えなくて…申し訳ねぇ…。
オープニングについて
すげぇ。入り、演出、ムービー、その全てがバッタバッタと主張してきて一瞬で心を掴まれる。いいものだ。
……そんなお祭り感であっても、意味と暗示を隠しているのだから恐ろしい。
感想(主題について)
夢にも現実にも半端者の自分は、笑わせてくれるコメディパートでも心躍るアクションパートでも補いきれないほどのグロテスクさを感じました。
夢を追うとどうなる?夢の果てはどうなる?どこかで折れたらどうなる?全て理想通りに、今すぐ夢が叶ったら?そんな妄想、仮定で現実逃避してないで、現実を見ないといけないんじゃない?
真正面から今の悩みと弱みの核を突き刺されているようで、とても、とても苦しかった。
夢をいくら見ても、現実が変わるわけじゃない。
願望をかなえることが出来ても、それは夢じゃなくて現実で、文字通りにリアリティを持つ。
ならば、我々にできることは――現実を見ることしかないのだろう。現実で踏み出すしかないのだろう。
結局は。
我が身を省みれば、小説を書いてみたり作品考察をしてみたり、現実を見ないで暮らしている。小説は一次選考にも落ち、作品研究はあまりのニッチさに広く膾炙されるはずもなかった。現実を放り出して没頭するほどの夢だったのだろうか?
いや、娯楽としてはそれで(それが)正しいのかもしれないが。
作品を生み出すとは?夢を叶える・諦めるとは?現実を見るって、夢を見ることと相反することなのか?
作品と自分の関係性もまた、考えさせられるものがありました。キャラクターたちと自分(作者)の対話、あれは我が身にも覚えがあるもので――奇しくも、全く同じ反応をしてしまっていたこともあり――胸を打たれました。
夢を諦めるって、現実を見るって、言葉では簡単だけど、簡単にできるわけがないじゃない。
「そこ」に彼らはいて、彼らの言葉は自分の言葉でもあって、それを信じたくもなる。
けれど、彼らは夢で、現実の自分は…熱血とか、夢追いとかの純度百パーセントの設定を持ったキャラクターじゃなくて…。
難しいや。
とにもかくにも、現実で歩いていくしかない。夢と共に。
そういうことで、まとめってことにさせてください。いやほんと、この問題はまだまだ纏まる気がしない…。
だから、再演とかDVDゲットチャンスがあったら大学生と創作者は見ろ!!
貴方はきっと、夢見るお客じゃいられない。
おしまい。
おまけ
舞台演劇ってこれからどうなるんだろうなーということを管を巻いたものがこちらになります。よかったら読んでください。
劇場に足を運んでもらうって、大変だよなー。これもまた夢と現実の競合なのかな。
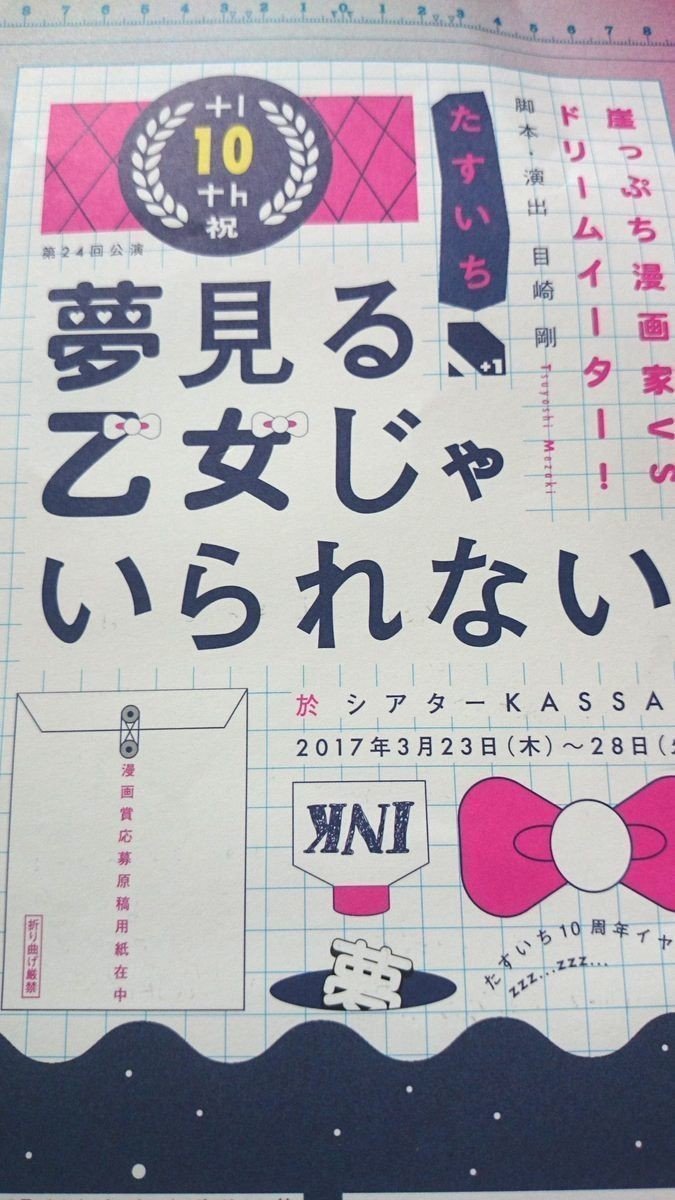
Twitterとかマシュマロ(https://marshmallow-qa.com/A01takanash1)とかで感想頂けるだけでも嬉しいです。 サポートいただけるともっと・とってもうれしいです。
