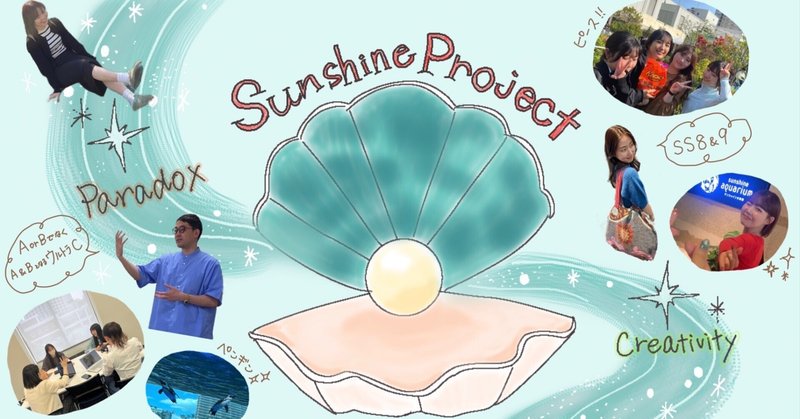
偽物感情パラドックスに悩む!実践を通して学んだ”真のニーズ”発見の難しさ〜サンシャイン水族館✖️舘野ゼミコラボ〜
皆様こんにちは、3期生の高田遥と申します。
初めての公的な執筆ですので、拙い文章ではありますが、暖かい目で見ていただけると幸いです。
今回は、3期生梅内さなみの素敵なグラフィックと共に楽しめる内容となっておりますので、是非最後までご覧ください。

1.初めに
今回は、サンシャイン水族館とのゼミコラボ企画を終えて経験したことについてお話ししていこうと思います。先週に続いて、私もこのような執筆は初めてなので、拙い文章になってしまうかもしれませんが、最後までお楽しみいただけると幸いです。
舘野ゼミは、サンシャイン水族館とコラボし、感情パラドックスに着目して「新たな水族館の使い方」の考案に取り組んできました。そして先日6月16日、最終プレゼンテーションを行い、無事にプロジェクトが終了いたしました。
前回同じく舘野ゼミ3期生のまりなとたまきが書いてくれた記事で、どのようなことに取り組んでいたのかがより詳しく分かるので、まだお読みになっていない方は是非読んでみてください。
2.感情パラドックス難関ポイント
感情パラドックスを基にプロジェクトを進めていくにあたり、私達はいくつかの感情パラドックス難関ポイントにぶつかりました。2章ではその難解ポイントについて説明していきたいと思います。
(感情パラドックスについてもっと知りたい!という方はこちらのnoteをご覧ください。)
2.1. 偽物感情パラドックス
まず、一つ目の感情パラドックス難関ポイント偽物感情パラドックスについて説明していきたいと思います。
感情パラドックスとは、簡単に言うと矛盾する二つの欲望です。例えば、「痩せたいけど食べたい」「安定した恋愛をしたいけど刺激のある恋愛もしたい」などが挙げられます。この「欲望」が「矛盾」することによって生まれるのが「感情パラドックス」であります。
しかしながら、私達は「矛盾」の要素だけに囚われてしまい「欲望」という要素を忘れてしまっていました。この「矛盾」だけに囚われたパラドックスとは、例えば以下のようなものが挙げられます。
癒されたけど、途中で見る体力がなくなってしまった
魚の生き方は楽そうだけど、ちょっとのんびりすぎそう
魚の中には見た目が変わっていて怖いものもいるけど、それでも見たくなる
これらは一見、感情パラドックスに見えますが、実は「矛盾」の要素だけに囚われた偽物感情パラドックスなのです。
「魚の生き方は、楽そうだけど、ちょっとのんびり過ぎそう」を例に取って解説すると、「楽そう」と「ちょっとのんびり過ぎそう」の二つが対立しており、一見感情パラドックスの様に見えますが、この文章の主体は「魚」であり「自分がどうしたいか」という欲望に関する情報がありません。
他の例も同様に「矛盾」の要素だけに囚われた偽物感情パラドックスになってしまっています。
一方で、初めに紹介した「安定した恋愛をしたいけど刺激のある恋愛もしたい」では「安定した恋愛」と「刺激のある恋愛」で対立関係ができており、「矛盾要素」を備えています。また「自分がどうしたいか」という「欲望要素」も備えています。これが本物の感情パラドックスなのです。
上記の偽物感情パラドックス3つの例は、実際に私たちが「水族館に行って感じた感情パラドックス」として初期段階にメモしていたものです。大詰め段階になって初めて自分達が偽物感情パラドックスについて取り扱っていると気が付き、見返してみると、初期段階でメモしていたものの多くがこの偽物感情パラドックスでした。私たちはこの偽物感情パラドックスを一生懸命深掘りしたが故に、なかなか前に進むことができませんでした。
これを通して学んだことは、感情パラドックスは「矛盾と欲望」の二つの要素によってできているものであり、矛盾している感情全てが感情パラドックスに当てはまるわけではないということです。

2.2. 愛のある感情パラドックス
続いて二つ目の感情パラドックス難関ポイント「愛のある感情パラドックス」について説明していきます。
今回、私達が見つけた感情パラドックスの中には、水族館に対しての愛があるものと愛がないものが存在しました。何かを企画する際やコラボする先方のいるプロジェクトにおいて感情パラドックスを使用する際には、この「愛のある感情パラドックス」が必要不可欠となるわけですが、その理由をそれぞれ例を挙げて説明していきます。
まず、水族館への愛のない感情パラドックスの一例としては「もっと満喫したいけどこのくらいでいい気もする」というものが挙げられます。この感情パラドックスは「もっとそこそこ型」に当てはまる、れっきとした感情パラドックスな訳ですが、これを深ぼってみると「そこまで魚に詳しい訳では無いため魚を見る集中力が長く続かないが、お金を払ってせっかく来た場所なのでもっと楽しまないと勿体無い」と言う本音が出てきました。これもたしかに感情パラドックスなのですが、水族館や魚に対する愛が見受けられません。
一方で、水族館への愛のある感情パラドックスの一例としては「ずっと魚を見ていたいけど他の人の邪魔にはなりたくない」というものが挙げられます。この感情パラドックスも「他人本意自分本位型」に当てはまる、れっきとした感情パラドックスです。これを深ぼると「気の済むまでお気に入りの魚をずっと観察していたいが、同じ場所を占拠してしまうとその人の見る機会を奪ってしまう、そんな傲慢なことはしたくない、申し訳ない」という詳しい感情を導き出すことができます。この感情パラドックスには、魚愛、水族館愛を見受けることができます。
もちろん、人にはそれぞれに異なる、興味・関心があるわけで、愛のある感情パラドックスが良く、愛のない感情パラドックスが悪い、と一概に言うことはできません。
では、なぜ、何かを企画する際やコラボする先方のいるプロジェクトにおいて、愛のある感情パラドックスが必要なのでしょうか。
このような愛のある感情パラドックスに苦戦している際に先生がくださったアドバイスは「今回のプロジェクトの目標は「サンシャイン水族館の新しい使い方を考えよう」というものであり、サンシャイン水族館の課題を解決しようとする企画ではありません。また、課題を解決する企画であったとしても、サンシャイン水族館や魚に対して愛のない感情パラドックスをもとに作った企画は、なかなかうまく行かないかもしれません」と言ってくださいました。つまり、-1を0にするわけではなく、0を1にするわけでもなく、1を2にするわけでもない、サンシャイン水族館や魚が持つ魅力を最大限に活かすことが最大に鍵になる、ということに気がつくことができました。
よって、今回のプロジェクト「サンシャイン水族館の新しい使い方を考えよう」で必要であったのは、「愛のある感情パラドックスを基に、サンシャイン水族館が持つ魅力を最大限に活かすこと」である、と気がつくことができました。また「愛のある感情パラドックス」は今回のプロジェクトのみに関わらず、何かを企画する際やコラボする先方のいるプロジェクトにおいて感情パラドックスを使用する際には、必要不可欠な要素であると学ぶことができました。

3. 論理思考脳とクリエイティブ脳
次に、プレゼンテーション大詰め段階で学んだことの3つ目、論理思考脳とクリエイティブ脳に関して説明していきたいと思います。
この章では先生や生徒など、外部から学んだことというよりは、私自身がプロジェクトを通して、実際に感じた・考えたことをベースにお話を進めていきたいと思います。
3.1. これから必要となるのか?!二刀流脳
私が高校生だった頃、自分でクリエイティブ面の思考が強いと感じており、文化祭の企画案出しなど、新しい何かを考える場では、人よりも多い数の案を提案していました。何の制限もかかっていない頭にあるものを柔軟に組み合わせた案を、思い立ったその場で口に出し、思いつきで前に進めていくという手法でクリエイティブな案を創出していました。
その後、立教大学経営学部に所属し、大学に入るまでは全く持ち合わせていなかった論理思考を、経営の側面、コミュ二ケーションの側面、文学の側面などから、長時間学習しました。その結果以前よりも、論理的に物事を考え、伝えることのできる人に成長している、と感じるようになりました。
しかし、今回のプロジェクトを通して、私の脳中で、論理思考がクリエイティブ思考よりも発達し、高校生以前に持ち合わせていたクリエイティブ思考が廃れてしまっているのではないかと感じてしまいました。そう気づかせてくれたのは、舘野ゼミ生でした。舘野ゼミではグループワーク中、ゼミ生から枠を超えたクリエイティブな案が多く出てくる光景を多く目にすることができます。それを客観的に見て、私は、論理思考を継続的かつ集中的に学んだことによって、論理的でないもの、もしくは現実的でないものは初めから排除するという無意識的な癖がついてしまったのではないかと気付かされました。
高校生の時は山ほど出ていた奇想天外なアイデアが、今はそれほど出なくなってしまった、そう感じてしまいました。
私は、今後世の中をより良い場所にしていくために、クリエイティブな思考は非常に大切であると考えます。また、多様な考え方が広まってきているこの世の中で生き抜くためには、クリエイティブ思考は必要不可欠な要素です。もちろん、論理思考も重要です。しかし、思考が非常に柔軟である高校生以下が世の中を作っていくのではなく、大人が中心となって世の中を作っていきます。よって、大人になろうとしている私が、論理思考に偏り、クリエイティブ思考を失っていくことはとても不本意なのです。かと言って、クリエイティブ思考だけに偏ってしまっても、せっかくの斬新なアイデアを思うように世間に伝えることはできないかもしれません。
ここで、私は「クリエイティブ思考と論理思考をバランスよく持ち合わせること」が必要であるとを、身をもって再認識することができました。また、私に今必要なことは、論理思考を継続的に高めながら、失いかけているクリエイティブ思考を取り戻し、両者をバランスよく向上させていくことであると気がつくことができました。
3.1. バランスを取るためには
では「クリエイティブ思考と論理思考をバランスよく持ち合わせること」は何をすれば叶うのでしょうか。
私は、主に二つの方法があると考えます。
一つ目は、芸術など右脳を刺激する物事に触れることです。舘野ゼミ内でも読んだ山口周先生の著書『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか?』にもあったように、右脳を刺激する物事に触れることでクリエイティブ思考を伸ばすことができると考えます。具体的には、美術館に行く、映画を見る、本を読む、自然を体験するなどが挙げられます。
二つ目は、意識してバランスを取ることです。自分の頭に無数の案が浮かんだときに、論理思考によって現実可能性を考え、それをすぐに排除してしまうのではなく、バランスをとりながら多彩なアイデアを自分自身で積極的に採用していく、ということです。これをするだけで両者のバランスは大きく変わるのではないでしょうか。
以上が、私なりに考えた、クリエイティブ思考と論理思考をバランスよく持ち合わせる方法です。もちろん他にもたくさんの方法があると思うので、この二点以外にも、バランスを取ることができる方法を常に探し求めつつ、舘野ゼミ生の仲間達に負けないバランスの取れた人材になれるよう、頑張りたいと思っています。

4. 最後に
今回は、サンシャインコラボのプラン作成大詰め段階にて、学んだことを中心に執筆させていただきました。
初めての公的な執筆で、至らないところも多くあったと思いますが、少しでも楽しんで読んでいただけていたら幸いです。
最後までご覧いただきましたこと、心から感謝申し上げます。
次回の投稿もぜひ、お楽しみに。
文: 立教大学経営学部国際経営学科3年 髙田遥
絵: 立教大学経営学部経営学科3年 梅内さなみ
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
