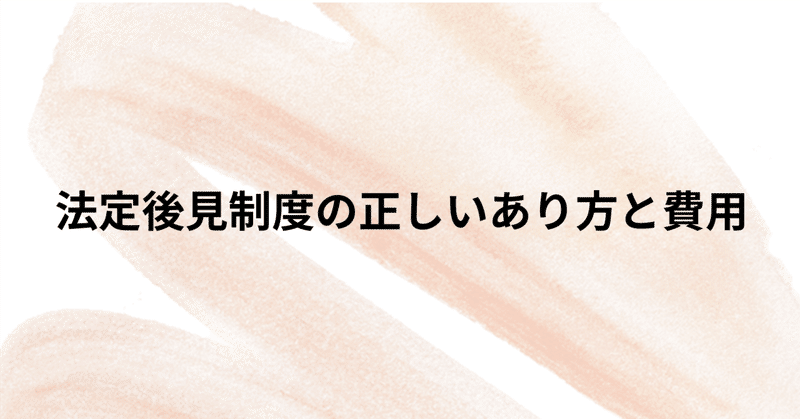
法定後見人の正しいあり方と費用
法定後見人の本来の仕事
法定後見制度の現状の問題点について過去に書きましたが、本来の法定後見制度は、定められている義務が正しく運用されていれば、それほど悪い制度ではないこともお伝えしておきます。
法定後見人の義務として課されている仕事は、財産管理と身上監護です。
「身上監護」の「身上」は分かるとして、「監護」は「看護」の間違いではないの? と思う方も居られるかもしれませんが、「看護」や「介護」などの日常の身体・生活の支援に関しては全く行いません。身上看護って何?
身上監護とは、平たく言うと身上に関する契約(法律行為)をする役目と言うことです。
身上監護の主なものとしては、①医療、②施設、③介護、④住居などに関する契約があります。
①医療に関する契約は、例えば、病気で入院・手術が必要になった時に、家族などの同意を得て医療を受けさせたり、医療費の支払いをするなどです。
また、②施設などへの入居に関する契約には、施設に入居する場合に施設と契約したり、入居費用を払ったり、提供されるサービスの内容を施設と確認したり交渉したり、面会事項について確認したり、と言ったことが考えられます。
③介護保険の認定申請や介護サービス契約には、認定に応じて必要な介護サービスを締結したり、費用を支払うなどがこれに当たります。
④自宅や賃貸など住居に関する契約としては、持ち家の場合は、固定資産税や都市計画税の支払い、屋根の吹き替えやバリアフリーなどの改築・修繕の契約や支払い。賃貸の場合は、家賃・更新料の支払いなどがこれに当たります。身上監護を正しく実現するために必要なこと
こうして見ていくと、特に、契約となると、家族にもよく分からない面もあったりするので、正しく運用されていれば、あながち悪い制度ではないと思われるのではないでしょうか。
ただ、ここまで書いて既にお気づきの方もおられると思いますが、もし、この通りに正しく運用されるためには、法定後見人が、被後見人(本人)と定期的に面会し、本人の病状や様々な症状を見て、前回の面会時との変化を正しく把握していくことが必要になります。しかし、法定後見人の実態はさまざま
もともと、善良な法定後見人であっても、月に1回、ごく短時間、面会に来てくれれば良い方です。
しかし、法定後見人の中には、一人で50人くらい受け持っている人もいて、自宅も入居施設もあちこちバラバラと言う場合、酷い場合ですと、電話だけで、本人確認も適当に、状態を確認する人もいます。
対面で会って目を見て表情の動きなども確認して話しても、差し障りのない話題だと、認知症がひどくなっていることに気づかない場合もあるのに、電話で、本人の変化など正確に分かるはずがありません。
本人は、認知症なので、法定後見人が杜撰でおかしいと仮に思ったとしても、言葉にして正確にそれを指摘することもできません。また、言えたとしても、周囲がそれをどこまで本気で受け止めるかもわかりません。
こう言うことが、法定後見人や、法定後見制度に対する不信につながっているのです。
ましてや、本人の認知症に乗じて、財産の横領など、あってはならないことです。この原因はどこにあるか
この様に、法律で定めたことがきちんとできない運用になっている原因は、法定後見人の人数が足らないことも一因です。
また、家庭裁判所が法定後見人の選任をする際に、人間性や過去の経歴や仕事ぶりなどを把握していないし調べようともしない、悪く言うと金目当ての人でも職業名だけで選んでいると言うことにも原因があると思います。
そして、例えば、家族などから「あの法定後見人は信用できない」などの苦情があったとしても、家庭裁判所はその法定後見人を後見人リストから外す事もない(横領罪で捕まれば別ですが)ので、善良な法定後見人は疲弊し、悪徳な法定後見人は楽して儲けると言う悪循環も生じている様です。
家族が法定後見人になることを申し出る制度もあるのですが、各地の家庭裁判所によって事情は異なると思いますが、現実にはほとんど認定されません。
成年後見促進法の改正によって、税理士、行政書士なども法定後見人になれる様になったのですが、横浜など一部地域を除いてまだまだ弁護士・司法書士が主体です。法定後見制度が「有料」であることは余り知られていない
法定後見制度は国の制度だから「無料」で利用できるから、有料の任意後見よりは良い、と思われる方も多いと思いますが、誤解です。
法定後見人 に対して、毎月いくら支払うかは、財産額を考慮して、家庭裁判所が決定します。定期的に支払う金額は、毎月3万円〜毎月10万円程度が多いと言われています。
意外に少ないと思われるかもしれませんが、仮に、5万円だと1年で60万円、これを生きている間、毎年支払い続けることになるので、決して安くはありません。
にも関わらず、月1回、短時間ちょっと顔を出すだけとか、電話で済ますとか、確かに報告書は作成しますが、ほぼ定型ですし、時給換算したら、どうなのかと言う気持ちにもなります。
さらに、後見監督人をつけた場合は、法定後見人とは別に、その人にも費用を支払う必要があります。
このように、「任意後見人は民間対民間の契約だから有料だけど、法定後見人は国の制度だから無料」と言うのは、大きな間違いです。法定後見制度は一度は始めたらやめられない
また、法定後見制度は、一度始めたら、いくら法定後見人が信用できなかったり、ウマが合わなくてもやめる事はできません。
ただし、例外的に、医師の診察で、認知症が改善されている(ちなみに、認知症は改善します。認知症改善プログラムについても、後日書いていきます)と言う診断書がおりたら別です。
ですので、制度を利用する際は、よく考えてからにしましょう。
法定後見人が言うことを守ってくれないとか、施設のことなどで話し合いたいのに全く来ないとか、これが欲しいと言うものと全然違うものを送ってくるなどで不信感を抱いた際は、法定後見人が弁護士であれば所属の弁護士会に、法定後見人が社会福祉士であれば地域包括センターや社会福祉協議会や市町村とご相談ください。
有料なのに、やるべきことをしないのなら、つけている意味がありません。
認知症の方の財産を守る方法は、他にもあります。
©️2023 ようてんとなーたん
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
