
note(LaTeX)でいろいろな数式やコードを書く方法
noteでは数式を記事に挿入することができます。今回はその方法を解説します。
数式記述の方法
noteには数式入力の方法が2つあります。インライン形式とディスプレイ形式です。まずはインライン形式から紹介していきます。
インライン形式
インライン形式は$${y=x^2}$$のように、文章中に数式を挿入できます。しかし、長い数式の記述や方程式を解くときの手順を表したりするにはあまり向いていません。
入力方法は、$${$${入力する数式}$$}$$とするだけです。例えば、$${$${5x+6}$$}$$と入力すると$${5x+6}$$と出力されます。
ディスプレイ形式
ディスプレイ形式の出力は下のようになります。
$$
y=x^2
$$
これは改行などもできるので、長い数式などの記述に便利です。
入力方法は次のような感じです。
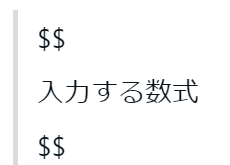
ディスプレイ形式の改行は、行の最後に$${\verb|\\|}$$と入力することでできます。
また、基本的に中身の記述方法はインライン形式もディスプレイ形式も同じです。ここからはその中身の記述方法を解説していきます。
*数字や文字の入力は基本的に小数でもそのまま入力です。分数や行列などは後述します。
四則演算・分数・指数・根号
まずは四則演算の入力です。$${+,-,=}$$はそのまま+,-,=を半角入力すればOKなので、$${\times,\div}$$の入力方法を紹介します。
$${\times}$$→$${\verb|\times|}$$
$${\div}$$→$${\verb|\div|}$$
バックスラッシュと円マークは同じ文字扱いなので、フォントの関係でバックスラッシュが出ない場合は円マークにしてください。
次に指数と根号を入力してみましょう。
$${y^n}$$→$${\verb|y^{n}|}$$
$${\sqrt{n}}$$→$${\verb|\sqrt{n}|}$$
$${\sqrt[y]{n}}$$→$${\verb|\sqrt[y]{n}|}$$
y^{n}は、指数に入るものが1文字の場合は{}を外しy^nなどとしても正常に出力されます。
最後に分数です。インライン形式だと小さく表示されてしまいますが、ディスプレイ形式なら通常の大きさになります。(ここではインライン形式で書いているので小さく表示されています。)
$${\frac{b}{a}}$$→$${\verb|\frac{b}{a}|}$$
帯分数は、$${\verb|1\frac{1}{2}|}$$などのようにすると、$${1\frac{1}{2}}$$のような感じにしっかり出力されます。
他の演算子
その他の演算子も見ておきましょう。
$${<,>}$$は直接半角入力でOKです。
$${\infty}$$→$${\verb|\infty|}$$
$${\pm}$$→$${\verb|\pm|}$$
$${\mp}$$→$${\verb|\mp|}$$
$${\geq}$$→$${\verb|\geq|}$$
$${\leq}$$→$${\verb|\leq|}$$
$${\geqq}$$→$${\verb|\geqq|}$$
$${\leqq}$$→$${\verb|\leqq|}$$
ここまでのことを総合すると、2次方程式の解の公式が書けますね。$${x=\frac{-b\pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}}$$は、$${\verb|x=\frac{-b\pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}|}$$と入力すれば出てきます。
微積分・極限
まずはlimを入力してみましょう。limは、インライン形式とディスプレイ形式で表示が異なりますが、入力方法は同じです。インライン形式では$${\lim_{h \to 0}}$$と表示され、ディスプレイ形式では
$$
\lim_{h \to 0}
$$
と表示されます。入力方法は次のようになります。
$$
\lim_{h \to 0}{f(x)}→\verb|\lim_{h \to 0}{f(x)}|
$$
右矢印は、上を見れば分かりますが$${\verb|\to|}$$で出せます。
次に微分ですが、これは簡単です。$${f'(x)}$$と入力するには普通に$${\verb|f'(x)|}$$と打てばいいからです。また、導関数は上のlimを使えばできますし、$${(関数)'}$$も普通に打つだけでOKです。
次に積分です。
$${\int{f(x)}dx}$$→$${\verb|\int{f(x)}dx|}$$
$${\int_{a}^{b}{f(x)}dx}$$→$${\verb|\int_{a}^{b}{f(x)}dx|}$$
$${[f(x)]_{a}^{b}}$$→$${\verb|[f(x)]_{a}^{b}|}$$
定積分の{a}と{b}についている波カッコは指数と同じように中身が1文字ならつけなくてもかまいません。
三角関数・角度
次に三角関数です。
$${\sin \theta}$$→$${\verb|\sin \theta|}$$
$${\cos \pi}$$→$${\verb|\cos \pi|}$$
$${\tan 30^{\circ}}$$→$${\verb|\tan 30^{\circ}|}$$
$${\arcsin \frac{1}{2}}$$→$${\verb|\arcsin \frac{1}{2}|}$$
$${\arccos \frac{\sqrt{3}}{2}}$$→$${\verb|\arccos \frac{\sqrt{3}}{2}|}$$
$${\arctan 1}$$→$${\verb|\arctan 1|}$$
これは$${\verb|\cos ^{-1} \pi|}$$などと入力すれば$${\cos ^{-1} \pi}$$と出力させることもできます。
次に角度に関する記号です。
$${30^{\circ}}$$→$${\verb|30^{\circ}|}$$
$${\angle A}$$→$${\verb|\angle A|}$$
ギリシャ文字
三角関数のところで$${\theta}$$や$${\pi}$$などが出てきましたが、ここでギリシャ文字をすべて紹介しておきます。
$${\alpha}$$→$${\verb|\alpha|}$$
$${\beta}$$→$${\verb|\beta|}$$
$${\gamma}$$→$${\verb|\gamma|}$$
$${\delta}$$→$${\verb|\delta|}$$
$${\epsilon}$$→$${\verb|\epsilon|}$$
$${\zeta}$$→$${\verb|\zeta|}$$
$${\eta}$$→$${\verb|\eta|}$$
$${\theta}$$→$${\verb|\theta|}$$
$${\iota}$$→$${\verb|\iota|}$$
$${\kappa}$$→$${\verb|\kappa|}$$
$${\lambda}$$→$${\verb|\lambda|}$$
$${\mu}$$→$${\verb|\mu|}$$
$${\nu}$$→$${\verb|\nu|}$$
$${\xi}$$→$${\verb|\xi|}$$
$${\omicron}$$→$${\verb|\omicron|}$$ または$${\verb|o|}$$
$${\pi}$$→$${\verb|\pi|}$$
$${\rho}$$→$${\verb|\rho|}$$
$${\sigma}$$→$${\verb|\sigma|}$$
$${\tau}$$→$${\verb|\tau|}$$
$${\upsilon}$$→$${\verb|\upsilon|}$$
$${\phi}$$→$${\verb|\phi|}$$
$${\chi}$$→$${\verb|\chi|}$$
$${\psi}$$→$${\verb|\psi|}$$
$${\omega}$$→$${\verb|\omega|}$$
大文字にしたいときは、\Piなどのように最初を大文字にします。
数列
次は数列です。
$${a_{n}}$$→$${\verb|a_{n}|}$$
これは単純ですが、問題は$${\Sigma}$$です。これもlimと同じようにインライン形式とディスプレイ形式で表示が異なります。インライン形式では$${\sum_{k=1}^\infty}$$のように表示され、ディスプレイ形式では
$$
\sum_{k=1}^\infty
$$
のように表示されます。入力方法は次のような感じです。
$${\sum_{k=1}^{100}}$$→$${\verb|\sum_{k=1}^{100}|}$$
$${\sum}$$単体は$${\verb|\sum|}$$と入力すればできます。
連立方程式
連立方程式は次のように入力します。ただし、これはディスプレイ形式でしか正常に出力されません。
$$
\begin{cases} x+y=4 \\ 2x+3y=11 \end{cases} \\
→\verb|\begin{cases} x+y=4 \\ 2x+3y=11 \end{cases}|
$$
つまり、\begin{cases} (式1) \\ (式2) \end{cases} という構文です。
行列
行列は種類がいろいろありますが入力方法は基本的に同じです。また、行列もディスプレイ形式のみの対応です。
$$
\begin{matrix} a & b \\ c & d \end{matrix}\\
\verb|\begin{matrix} a & b \\ c & d \end{matrix}|\\
\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\\
\verb|\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}|\\
\begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{bmatrix}\\
\verb|\begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{bmatrix}|\\
\begin{vmatrix} {12} & {50} \\ {90} & {11} \end{vmatrix}\\
\verb|\begin{vmatrix} {12} & {50} \\ {90} & {11} \end{vmatrix}|\\
\begin{Vmatrix} a & b \\ c & d \\ e & f \end{Vmatrix}\\
\verb|\begin{Vmatrix} a & b \\ c & d \\ e & f \end{Vmatrix}|\\
$$
コード入力
さて、これは数式ではありませんがフォントを変えて挿入したいときなどに便利な方法があります。
$${\verb|abcde|}$$→\verb|abcde|
\verbの次についている"|"はバーティカルバーまたはバーティカルラインといい、Shift+¥で入力することができるはずです。
さて、多分これ以上やると数式挿入が多すぎてNoteが限界を迎える(もうすでにちょっと重い)のでここで終わります。ほかの記号もまだまだたくさんありますが、そういうのは基本調べれば出てきます。最後まで見ていただきありがとうございました!
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
