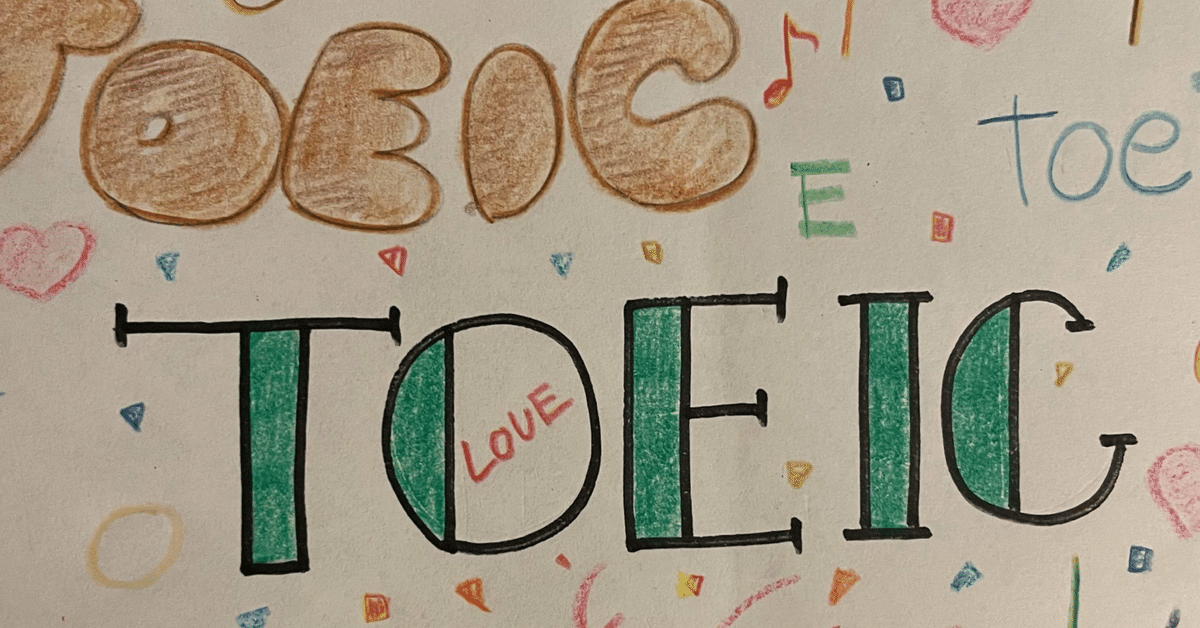
英語が苦手だった私がTOEIC L&Rで800点超えられた勉強法
学生の頃から英語を苦手としていた私がようやく目標としていた800点を超えられました。
ここでは、実際にTOEIC L&Rで点数をUpさせるポイントをシェアします。
5年前の状況
まず、TOEICを頻繁に受け始めた5年前の状況をおさらいします。
5年前は500点前後。10年前に受けたときは350点。
事前の勉強も特にせず、なんとなく受けていた。
特に目標も無かった。
まあそれでは向上しませんよね。
その後の得点の推移

Listningが徐々に向上し、ようやく400点超えとなりました。ゆっくりと増加しています。
それに対しReadlingは浮き沈みが激しく、上がったときは急にあがりました。
なお有識者ならピンとくるでしょうが、私は公開テストではなくTOEIC Program IPテストを受けています。公開テストはコロナ禍で中止や抽選になっており、かつ2時間かかってしまうので、ちょっと受けづらいですよね。
TOEIC Program IPテストは団体が申し込むと受けられるもので、コロナ前から実施されていました。コロナ禍ではオンラインで自宅から、かつCAT(適応型プログラム)で1時間程度の試験時間で受けられるため非常に便利です。
TOEIC Program IPテストは個人では申し込めないため、これを提供してくれている会社には非常に感謝しています。
TOEICの傾向と対策
TOEIC L & RはPart1~Part4のListning SectionとPart5~part7のReading Sectionに分かれています。
Listeningは名前の通り、聞き取りをチェックするテストです。英会話の単語や表現を聞き取れるか、話の筋を把握できるかが重要となります。高度な語彙は必要ありません。必要ないのですが、それでもReading350点程度の語彙や文法は必要となります。(個人の印象です)
Readingは文法、語彙、長文読解能力をチェックするテストです。文法は穴埋めで出題されるため、文の時制、単語の品詞、意味などの知識が問われます。文法の中で、仮定法過去が出たのを見たことは無いですが、現在完了進行形、未来進行形は出てきます。また、接続詞や前置詞を多く問われるので語彙は必要です。
長文を読んで回答するには読解スピードも重要となります。急いで読んで、かつ読み返さなくとも意味を把握できるレベルまで練習する必要があります。
一般に、Listeningは満点を取りやすいがReadingで満点を取るのは難しいとされています。理由は明らかで、Listeningに必要なレベルはReading350点なのに対し、Readingで必要な語彙は無限と言って良いためです。日本語でも知らない単語が多々あるように、出てくる可能性がある単語を全て知っておくのは不可能に近いです。
つまり順番としては、
文法、語彙を磨いてReadingを350点レベルまで引き上げる。
Listeningを日々鍛錬して聞き取り力をUp。
Readingの語彙を増やし続ける。
となります。
勉強法
私が体験したお勧めの勉強法をお知らせします。
DMM英会話
Listening対策です。
DMM英会話は言わずと知れたオンライン英会話システムで、特長は教材の豊富さです。
私は「発音」で英語の発音を総点検しました。発音記号の発音の仕方がわからなければ単語の聞いた音のマッチングが出来ませんし、正しい発音もできません。新しい単語を覚える際に正しい発音を把握することすらできません。発音記号と正しい発音の音をマッチさせることは非常に重要です。
その後は「語彙」や「デイリーニュース」を読んで、語彙と英文の読解速度を向上させました。
オンライン英会話では先生と挨拶や自己紹介する機会が毎回あるので、英会話に慣れるという意味でも非常に効果があります。
最初は質問も回答もおぼつかないのですが、慣れてくると先生の発言の中でわからなかった単語を聞き直したり出来るようになります。DMM英会話ではコースによってネイティブスピーカーを選べたりしますが、初心者のうちはESL(第二言語)が英語の先生で十分です。
TOEIC TEST 英単語 出るとこだけ!
Readingの語彙対策です。
タイトルのとおり、ちゃんと頻出単語がPick upされています。また、例文が他の単語を盛り込んだ形になっているので、何度も頻出語句に触れられ覚えやすくなっています。
CD付きなので音声を聞きながら単語をチェックし繰り返し読んでいました。音声の構成が英単語、和訳、英単語、英例文、和訳という順番なのも覚えるのに非常に良いです。
TOEIC L&Rテスト 直前の技術-受験票が届いてからでも間に合う11日間の即効対策プログラム
Listening、Reading共通の対策ですが、特にReadingの得点Upに寄与したイメージです。
TOEICの問題の傾向、解き方を教えてくれます。特に役に立った点は後述します。
公式TOEIC Listening & Reading 問題集 8
Listening、Reading共通の対策ですが、特にListeningのトレーニングに有効です。
TOEICの本番のナレーターが起用されているため、これを聞き取れなければ本番でも聞き取れません。各Part、特にPart2を繰り返し聞いて、何を言っているのか判別できるように特訓しました。
Listeningの語彙、文法理解が足りているかのチェックにも使えます。過去問でわからない表現や単語があるということは、まだReadingの能力が足りていないということです。
また、ReadingについてはTOEICで使われやすい語彙の習得に繋がります。plumber, lamber, dye, fabricなど日常生活やニュースでは触れない単語が出てきたりします。"RSVP"なんて急に出てきてもわかりません。
以前の問題集もチェックすると良いです。
英語でアニメを観る
Listening対策です。
子供向けのアニメで、ゆっくりはっきり発音されている英語を聞き取れるようにします。なお、実写Dramaはしゃべりが速く単語や表現も難解なので、TOEICの勉強とは少々釣り合いません。
字幕付きであれば字幕を見ながら発音を聞いて頭に定着させて良いことにしています。聞いてわからないものは理解しようがないので。
私に合っていたムービーを挙げておきます。
「Peppa Pig」
イギリス英語、程よい難易度、程よい速さ、短いセンテンスなので非常に聞き取りやすいです。固有名詞があまり出てこないのも良いです。まずこれをちゃんと聞き取れるようになることを目指しました。面白いので何回も観れます。
Youtube Kids, Netflixなどで英語版を視聴できます。
「Sofia the First」
Disneyの子供向けアニメで、ミュージカル風です。「Peppa Pig」より語彙も速さもちょっとレベルが高く、固有名詞も出てきます。王宮、学校、魔法など色々なシチュエーションが出てくるので飽きがきにくく語彙も増えます。他のDisney作品もそうなのですが、Disney作品は言葉の選び方に気を付けられているので、凝った高度な表現はあまり出てこないのも良いところです。Disney+では字幕が出なかったのですが、一番聞き取りづらいミュージカル部分はネットで文字起こしされているので聞き取れなかった部分はそちらをチェックしました。
Disney+で英語版を視聴できます。
「Frozen」
劇場版のディズニーアニメです。速さは「Sofia the First」と同じぐらいで聞き取りやすいです。歌はちょっと難しいのでこちらも字幕で確認しながら歌います。(ドワーフの歌は置いといて)
なおPixer作品は(声優でなく)俳優が演技しているせいかしゃべりが速く表現も難しいのでお勧めしません。
直前の準備
今までは試験までの長い勉強期間のお話ですが、試験直前にしておくこともいくつかあります。
BBCニュースを1.5倍速で聞く
耳をネイティブの速いしゃべりに慣れさせるために、TOEICと関係ないニュースを聞きます。TOEICの過去問を聞いていると内容を把握しようとしてしまい、少々疲れてしまいます。聞き流すぐらいがちょうどよいです。
レッドブルを飲む
連日の勉強で疲れているため、薬で覚醒させ集中力を高めます。
ただ尿意も高まるため、2時間試験の場合は量を少な目にしておくと良いでしょう。1時間であれば問題なかったです。
Part別の注意点
最後に、経験則からの各PartのTIPSを共有します。
Part1
写真を説明する文を選ぶ問題です。
頻出する単語が他のPartとは異なるため、Part1向けに単語をチェックしたほうが良いです。
名詞:awning, wheelbarrow, drawer, cabinet, shelf, railing, faucet, stool, ...
動詞:lying down, kneeling, leaning against, reaching (into), loading, ...
cabinetとshelfの違い、わかりますか?
Part2
音声のみで、質問に対し選択肢から適切な返答を選ぶ問題です。
質問が一度しか読まれない上、英語は出だしを聞き落とすと何を問われているのかわからない言語なので、出だしを1度で確実に聞き分けられるスキルが必須となります。過去問のPart2を聞きまくって、出だしを聞き分けられるように訓練しました。
まずはWhere、When、Why、それ以外を聞き分けられるように。
さらにDid you, Would you, Why don't, Haveも聞き分けられるように。
さらに時制がわかるようになればOKです。
一方、回答選択肢のパターンは、
Yes/No系(Yes, It is.)
何時、何処、何故への直接的な回答 (6 o'clock.)
それ以外 (Chris is in charge of it.)
に分けられます。ここでTIPSが2点あります。
Yes/No系の回答は、Where, When、Whyへの質問に対する回答になりません。日本語でも「何時?」と聞いて、「いいえ」とは答えませんよね。つまり、Where, When、Why系の質問であれば、Yes/Noで始まる選択肢は間違いと言い切れます。
Becauseで始まる回答は、Whyで始まる質問への回答にしかなりません。つまり、質問がWhyでなかった場合、Becauseで始まる選択肢は間違いと言い切れます。
その他は文脈で判断するしかないのですが、過去問を見て、そういうパターンもあるのか…と覚えていくことになります。たとえば
Why don't we plan a vacation tonight? (今夜休暇の予定を立てませんか?)
という質問に対し、
I have a deadline tomorrow. (明日締め切りがあるんです)
という回答が来たりします。
Part3
複数人の会話を聞いて、テキストの選択肢から回答を選ぶ問題です。
問題のパターンはなんとなくあるので、聞きながらどの展開になるか予測する力と、純粋なListening能力を高めることになります。
よくあるのはカスタマーサービスを依頼するタイプで、
店舗側がまず社名を言う
お客側が問題を伝える
店側が対策や指示を伝える
お客側が次に何をするか言う
という構成です。
質問も
店舗の業務内容
どういった問題か
次に何をするか
といった質問が多いので、会話が始まる前に問題文をちらっと見ておき、何を問われるか意識しながら聞くと良いです。
なお、会話の出だしは社名などの固有名詞が来がちなのでそれを聞き流しつつ、業務内容を聞き取ることになります。
Part4
基本的にはPart3と同じ問題ですが、こちらは単一話者のバージョンです。対策もPart3と同じです。
よくあるのはラジオでのイベントの紹介、従業員への業務連絡です。
業務連絡では
イントロダクションで従業員へこれから伝えることを言う。
問題などを伝える。
従業員への指示を伝える。
といった流れが多いです。
問題もPart3と同様に
店舗の業務内容
どういった問題か
次に何をするか
といったものが多いです。会話が始まる前に問題文をちらっと見ておき、何を問われるか意識しながら聞くと良いです。
なお、表や図がある問題では、問題文に"Look at the graphic," などと絵を参照する指示があるので、絵を観るのは対応する問題文を読んだ後にしましょう。
Part5
ここからReadingです。Part5は文法穴埋め問題です。
問題文を読む前に選択肢を見て、どの問題のタイプかを見極めます。
Part5では単語の活用系の問題、接続詞や前置詞などの接続の問題、語彙の問題に分かれます。
「活用系の問題」では空欄の前後を見て回答を選択します。形容詞や副詞に関しては純粋に前後を見るしかなく、名詞句を形容するなら形容詞、動詞句を形容するなら副詞を選ぶことになります。submission formのように名詞の前に名詞が来ることもあるので注意が必要です。動詞の活用系については時制が関連するため、全文を読んで内容を把握する必要がありますが、canの後ろなら原形、to不定詞なら原形、すぐわかることもあります。
「接続の問題」では空欄の後に文が来るか名詞句が来るかがまず大事です。Regardless of ~ など、ofの後は名詞句が来ます。Despiteもそうですね。接続詞であれば順接や逆接などを文脈から判断する必要があるため、問題文を全部読むことになります。
「語彙の問題」は知っていれば答えられる、というだけなのですが、一応接頭辞や接尾辞を除けば意味が分かることも無くはないので5秒程度は考えてみても良いかもしれません。
Part6
短文の穴埋め問題です。基本的にPart5と同じです。
一点違うところとして、ある文章が入る位置を[1]~[4]から選べというものがあります。文脈を考慮しなければ回答できないため高難度です。事前に挿入文を読んでも本文を読まなければ挿入箇所はわかりませんし、候補[1]に到達したときに判断するのも少々難しいです。そのため、いったん候補[1]には入らないものと考えて進行し、候補[2]まで読み進んだら選択肢を考えてみるのが良いです。候補[4]はまとめの段落にあることが多く、挿入文の内容から候補[4]であろうと考えられることもままあります。そのうえで、候補[1]~候補[2]に入らないなら候補[3]に入るのでしょう。
なお、挿入文側にit や theが入っている場合、それらが指し示すものがその文の直前に大抵あるので、挿入箇所を決めるヒントになります。
Part7
1~3つのパッセージを読み、質問に答える問題です。
読み進める前または前半に、問題の1つめ、2つめををちらっと見ておくと良いです。
問題はヒントとなるパッセージの順番と同じ順番で出てくるので、1つ目の問題は1つ目のパッセージに関するものとなっています。「この記事の目的は何か」といった問題では、聞かれていることを把握した状態で読み進めると良いです。一方、「選択肢の中で何が述べられているか」といった問題はパッセージ全体を読んだ上でそれぞれの選択肢について判断しなければいけないため、パッセージを読み終えてから選択肢をチェックすることになります。
時間が限られているため、読み進めるスピードが大事です。効率的に読んでいき、迷ったらとりあえず回答して次に行くぐらいの気持ちが大事です。
おわりに
Readingは勉強すれば向上するかもしれませんが、Listeningは頭と耳のトレーニングが必要になるため日々の継続が必要となります。
Listeningの点数が低い方は長期的な学習をお勧めします!
(この後は投げ銭形式の感謝文のみです。)
ここから先は
¥ 200
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
