
act2 : Mon. Dec. 18th
◀第1話 act1 : Sun. Dec. 17thから読む
翌朝、俺はマンションの裏手にあるゴミ集積エリアへと向かっていた。
月曜日──燃えるゴミの日。
ここ二週間ほどゴミを出しそびれていたために、
膨れ上がったポリ袋を両手に提げる羽目になってしまった。
朝方の空気は冷やかで、ぴんと張り詰めている。
息を吐くと、白いもやが大きく広がった。
手早く済ませて、暖房をきかせた部屋に戻ってしまいたかった。
「よっ、と」
二つの袋を、集積エリアに放り込む。
すぐ傍では、主婦と思しきオバさまが二人、井戸端会議に興じていた。
寒い中、わざわざご苦労なことだ。
「昨晩、発砲事件が近くであったんですって。ご存知でした?」
「……ええ。怖いですね、こんなに身近なところで発砲だなんて。
物騒なこともあるもんですね」
耳に流れ込んできた、ひそやかな会話。
いつもであれば聞き流していたであろう、些細なお喋り。
そこに紛れ込んだ異質な一言に、胸がざわついて仕方がない。
「発砲事件」と。彼女たちは、確かにそう言っていた。
部屋に戻ると、ジャージ姿の「凛」──いや、「リン」が起きていた。
ジャージは、俺が昨晩に見繕ったものだった。
結局、手持ちの服で適当なものが見つからなかったのだ。
改めて見るとジャージの袖は余っているし、
裾の部分も随分と上にまくりあげられている。
男女の体格差もあって、やはりリンには少し大きかったらしい。
リンは、テレビを点けてニュース番組に見入っていた。
画面には「会社社長宅襲撃事件から1年」というテロップが躍っている。
「──エンジェルドール製造大手『堂崎カンパニー』の
社長宅が襲撃された事件から、今日で丸一年を迎えます。
捜査は依然として進まず、解決の兆しは見えていません」
画面が切り替わり、事件の犠牲者の顔写真が表示される。
死者は六名。堂崎カンパニー社長である堂崎氏とその妻、
そして邸宅に勤めていた警備員や家事手伝い。
彼らの顔は、よく知っている。忘れるはずもない。
なぜなら俺は、ほんの一年前まで堂崎家の人間だったのだから。
──二年前、俺は交通事故で家族を亡くした。高校生の時だった。
身寄りを失って独り身となった俺を、
迎え入れてくれたのが堂崎家だったのだ。
もともと、我が家と堂崎家は親交があり、
俺は幼い頃から堂崎家に出入りしていた。
だから、堂崎家の一員として生きていくことにさほど抵抗は感じなかった。
凛は、堂崎家の一人娘で、俺の幼馴染だった。
同じ「家族」となったことで、戸惑いはあったけれど、
それよりも一緒に暮らせる喜びの方が大きかった。
堂崎邸が何者かに襲撃されたのは、それからわずか一年後のことだ。
新しい環境にもようやく慣れ始め、
上手くやっていけると思っていた矢先の出来事だった。
事件の一週間前、俺は堂崎氏から命じられてこの高級マンションに入居した。
大学入学を機に一人暮らしを体験しておくべきだ、
というのが彼の言い分だった。
突然のことだったが、特に断る理由もなく、彼の言葉に従ったのだ。
凛も、俺と同じく堂崎氏からこのマンションに引っ越すように言われていた。
しかし、家財道具をまとめるのに時間がかかるという理由で、
彼女は家に留まっていたのだった。
──そして、事件に巻きこまれてしまった。
事件の後になって、ようやく思い至ったことがある。
堂崎氏は、自身に迫る危機を察知していたのではないだろうか。
だから、俺たち二人を自宅から遠ざけようとしたのではないか、と。
もし、凛がもっと早くマンションに移っていたならば。
そんな「もしも」の世界を、どれだけ描いたことか。
「──堂崎さんの長女、凛さんは現在も行方不明のままで……」
静かな部屋に、ニュースキャスターの声が反響する。
リンは、テレビをじっと注視していた。
……本来ならば、警察に伝えるべきなのだろう。堂崎凛が生きていた、と。
しかしそれは、目の前にいる少女が「本物」の凛であればの話だ。
これは、凛ではなくて──彼女の形をした人形なのだ。
「……手当、してくれたんだね」
袖口から覗いた包帯をさすりつつ、リンがぽつりと言った。
「ああ」平静を装い、淡々と答える。
リンは逡巡していたようだった。
しばらく顔を伏せた後、緊張を含んだ声音で尋ねてきた。
「傷……見たんだよね?」
「……見た。結構ひどいケガだったな。特に、右脚のやつなんかは」
リンの肩が、怯えたようにびくりと跳ねる。
そこへ追い討ちをかけるように、俺は言葉を継いだ。
「足裏のエンブレムも、見たよ」
沈黙が、降ってきた。
リンは身体を小刻みに震わせ、床に視線を落としている。
「ひとつ、聞きたいことがあるんだ」
物言わぬ人形をよそに、俺はなおも話を続けた。
「──昨晩、近くで発砲事件があったらしくてさ。
その傷は、事件と何か関係があるのか?」
「…………」
「答えない場合も肯定と捉えるからな。
もう一度聞くよ。関係あるのか?」
応答は、なかった。
リンはうなだれたままの体勢で、微動だにしない。
「関係、あるんだな?」
……リンが発砲事件に関わっている?
脳裏に、昨日の出来事がまざまざと蘇る。
部屋の前に倒れていたエンジェルドール。
身体に刻まれた、多数の傷。
右脚の傷が銃痕だとすれば、傷の大きさにも納得がいく。
加えて、病院・警察への通報を拒否したこと。
諸々をひっくるめたうえで考えられる可能性としては──
リンは、何者かから追われ、逃げているというところか?
なぜ、俺のところへ来た?
そもそも、人間の凛は……「本物」は、今もどこかで生きているのか?
次々と浮かび上がる疑問。
思考はまるで追い付かず、その一方で想像は悪い方向に膨らむばかりだった。
「……ごめんね。今は、質問には答えられない」
リンが、おずおずと口を開いた。
たどたどしい口調で、絞り出すように話す。
「疑問もたくさんあるだろうし、自分が怪しまれているのも分かってる。
でも──」
いったん言葉を切って、伏せていた顔を上げると……
リンは、意を決したように俺に向き直った。
「お願い。一週間だけ、ここにいさせて欲しいの」
すがりつくような、哀切に満ちた瞳だった。
リンの願い。
言い換えれば、それはつまり「匿ってほしい」ということなのだろう。
頭の片隅で、警鐘が鳴り響いている。
もう一人の自分が「止めておけ」と声の限りに叫んでいる。
凛に似ているだけの、素性の知れないエンジェルドールを
匿う義理がどこにあるというのか。
こいつは、人形なんだ。
……凛に、似ているだけの……。
「──条件がある」
深く息を吐いて、リンを真っ向から見据えた。
彼女の面持ちに、緊張の色がさっと広がる。
その瞳を覗き込むかのようにして、俺は問いかけた。
「さっき、俺の質問に『今は答えられない』って言ったよな?
だったら……去り際でいい。
その時に全部、包み隠さず教えてくれよ」
ためらいを見せるかと思われたが、予想に反してリンの返答は早かった。
「……うん。約束する」
そう言って小さくうなずき、リンは俺を見つめ返した。
そのまま、俺たちは押し黙る。
何をどう話したものか、どのように接するべきか。
相手の出方を互いに窺う、ぎこちない空気が部屋には満ちていた。
とはいえ、場の主導権はこちらにある。
匿う者と、匿われる者。立場の力量差は歴然としていた。
俺には、この関係を意のままに規定する権利があるのだろう。
それは同時に義務でもある。
この部屋の主として、訪問者の立場を定めなければならない。
逡巡する思考を放り出して、硬くなっていた身体の力を抜く。
それから、緩やかな声音を意識して、言った。
「……家にいる間、包帯は自分で取り替えてくれるかな。
『血がけっこう出てたから』昨日は夜通しで手当てしてたんだ。
……本当に大変だった。もう『出血』はないみたいだけど」
──嘘を、ついた。
リンの眼が、大きく見開かれる。
そこには、戸惑いの色が濃く表れていた。
次いで、何か言いかけようとする素振りを見せたものの、
俺はそれを手で制し、言葉を続けた。
「お前は人間だ、そうだろう?」
彼女の瞳をまっすぐに見つめ、同意を求める。
俺は知っている。
彼女が凛ではないこと。
そして、人間でもないこと。
……血の通わない人形であること。
けれど、俺には耐えられなかった。現実を認めたくなかった。
凛が俺のもとに帰ってきたのだと……そう信じたかった。
だから、俺は嘘をついた。
自分自身を、騙したのだ。
「──おまえは『堂崎 凛』なんだ」

それは、意思の表明だった。
リンに対して……そして、己に対しての。
──俺は、お前を「凛」として扱う。
人形じゃない、ひとりの人間として。
「……うん。ありがとう……」
リンは、こくりと頷いて視線を落とす。
そして、俺を見上げると、ゆっくりと微笑んだ。
「包帯、今日から自分で取り替えるね。
痛みはもうないけれど……何かの拍子に『出血』するかもしれないから」
そうだ、それでいい。
リンは、俺の意図を理解したようだった。
「よろしくね、テツくん」
リンは口元をほころばせ、懐かしい口調で俺を呼ぶのだった。
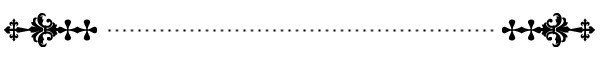
俺は、あてもなく街をぶらついていた。
「大学に行く」とリンに言い残して家を出たものの、
とてもじゃないが登校する気分にはなれなかった。
大学では今日から試験が始まるにも関わらず、だ。
一応、これまで単位に関しては順当に取得してきていた。
ここで単位の一つや二つを落としたところで、特に問題はないはずで。
……それに、いま考えるべきはリンのことだ。
そう自分に言い聞かせ、さ迷うようにして歩き続けた。
足取りはやけに軽く、ふわふわとした浮遊感さえ覚える。
それは決して、喜びや期待といった正の感情からではない。
単に、地に足が付いていないというだけの話だ。
リンのことについて思考を巡らせてみても、
ぐるぐると空転するばかりだった。
ため息を肺の奥から絞り出し、天を仰ぐ。
空は蒼く、雲ひとつない快晴だった。
ちっぽけな自分を嘲笑うかのように、
澄んだ世界はどこまでも続いていた。
どれくらい、歩いただろう。
気付けば、空は黄金色に染まっていた。
人もまばらだった街は、いつの間にやら人波であふれ、喧騒に包まれている。
雑踏のただ中をくぐり抜けるようにして、歩を進める。
会社帰りと思しきサラリーマン、制服に身を包んだ学生たちの群れ。
凛が行方不明となってからは、
街を歩く同年代の女性を目にするたびに凛の面影を探していた。
通学途中の電車の中で、立ち寄った飲食店で、
無意識に視線を巡らせるのが常だった。
不意に、リンのことを想った。
もう、外で幻を求める必要もないのだ。
家に帰れば、彼女がいるのだから。
「……晩飯、買って帰らなきゃな」
足は、自然とコンビニに向いていた。
店に入り、買い物かごを手に取った拍子に、目に留まったものがあった。
雑誌コーナーに陳列された週刊誌の束。
普段なら見向きもしない区画だった。
なのに、今日に限って惹かれたのは……その表紙に、
「ドールメーカー社長宅襲撃事件」の文字が大きく躍っていたからだ。
見れば、その他の週刊誌も、襲撃事件に関する記事を見出しに掲げていた。
吸い寄せられるようにして、俺はそのうちの一つを手にとっていた。
──俺はゴシップ誌というものが嫌いだった。
それは、養父の興した事業……エンジェルドールが
非難の対象として取り上げられることが多かったからだ。
堂崎カンパニーは、もともと義肢メーカーとして名を馳せていたと聞いている。しかし、精密機械メーカーの合併吸収を機に、
ヒューマノイド製造へと舵を切った。
結果、多用途型ヒューマノイド「エンジェルドール」が開発された。
それが一〇年前のことだ。
発売されるやいなや、エンジェルドールは世間の注目の的となった。
「より人間に近いエンジェルドールを」というのが、
堂崎氏の口癖であり、カンパニーの理念だった。
それまでにもヒューマノイドは各社から発売されていたが、
いかにも旧時代のロボットを彷彿とさせるような
デザインのものばかりだった。
そこにきて、人間と同様の外見を持つ
エンジェルドールの登場は衝撃的だったのだ。
加えて、「カスタマイズ」という概念を取り入れたことや、
人間の心理プログラムを搭載することで、
多様な感情表現が可能になったこと。
その特徴のどれもが革新的で、
前時代のヒューマノイドとは一線を画していた。
かくしてエンジェルドールは爆発的に普及し、
ヒューマノイド製品の頂点に君臨することとなったのだ。
当初は主に、介護への転用や独居老人のサポート、
ハウスキーパーとして用いられていたという。
そして次第に、ドールを「家族」や「恋人」として
傍に置くユーザーも増えるようになった。
この風潮に乗じて盛んになったのは、性産業だった。
繁華街に行けば、ドールを売りにした風俗店を
腐るほど目にすることができる。
そんな風潮から、識者はこぞってドールを
「新時代のダッチワイフ」と揶揄したものだった。
そういった背景もあって、ドールを
「卑しいもの」であるとして、快く思わない層も多い。
そのためか、堂崎カンパニーは人間工学の最先端企業と賞賛される一方で、
後ろ暗い噂も絶えなかった。
週刊誌では、「大企業の闇」と称して
悪しざまに書き立てられることも珍しくなかった。
案の定、開いたページには
「地下組織との繋がり エンジェルドールの暗部」
と題された特集が組まれていた。
「……結局、ありきたりのネタかよ」
似たような話題は、幾度となく目にした事がある。
週刊誌を棚に戻そうとページを閉じかけたところで、俺は手を止めていた。
『闇に秘匿された 禁断の人形』
表題の後に続くフレーズに、俺の視線は釘付けになっていた。
我に返り、舐めるように文章を追っていく。
『堂崎氏みずから指揮を執り、極秘に開発されていたドールが存在する……』
その記事でも、裏社会との繋がりが指摘されていた。
組織の名は『傀儡』。
その名称には聞き覚えがあった。
ドールを用いたテロ活動を専門に行う犯罪者集団だ。
『堂崎カンパニーは、違法なドールの製造を秘密裏に請け負っている』
『傀儡と癒着し、ドール撤廃論を唱える権力者を排除している』
『現行のヒューマノイド法で禁じられている軍事転用の禁さえも犯している』
以前ならば鼻で笑っていただろうゴシップも、
今となっては真実味を帯びて脳裏に響く。
混線していた思考が、ひとつの形に収束していく。
堂崎氏が開発を進めていたドール、それがリンなのだとしたら。
あのエンジェルドールが凛に似せて作られていること。
俺のもとへ訪れたこと。
俺の名前を知っていたこと。
──リンの来訪からずっと、頭の隅に引っかかっていたことだった。
彼女が、堂崎氏が制作した「禁断の人形」だったとしたら。
彼が、愛娘をモデルとして作ったと考えればどうだ。
すべてに、辻褄が合うんじゃないか?
そして、それゆえに「傀儡」から追われていた……とすれば?
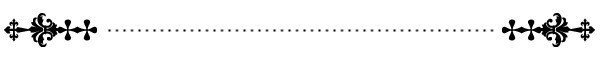
パンやおにぎり、飲み物などを二人分買いそろえ、
俺はマンションに向かった。
すでに日は傾き、そこかしこに長い影が伸びていた。
部屋に戻ると、リンはベッドの上で何かを読んでいた。
「ただいま、リン」
声をかけ、今しがたコンビニで買ってきた商品をテーブルに広げる。
「夕飯、買ってきたんだ。
食欲がないようなら食べなくてもいいけど……どうする?」
「……食べたい」
凛は、読んでいたものをベッドに置くと、
おぼつかない足取りで卓についた。
実際のところ、エンジェルドールは食事をとる必要はない。
主要なエネルギー源は電気なのだ。
彼らの体内にはバッテリーが内蔵されていて、
専用の充電器でエネルギーを補給する。
カスタマイズで食事機能を追加することもできるが、
ユーザーからの人気は芳しくないと聞いていた。
それはそうだ。
ドール自体がただでさえ高価なところに、
わざわざ食費を上乗せすることになるのだから。
リンに食事機能が搭載されているところをみると、
かなりの金額をかけてカスタマイズされたのだろう。
おそらくは、他の機能においても、
人間に限りなく近づけられているものと推測できた。
リンは、ナイロン袋の中から「青汁パン」と「ドリアンミルク」を
迷いなく手に取った。
手なれた動作で袋を開き、黙々と食べ始める。
「やっぱり」
予想通りの選択に、独りうなずいてみせる。
「……なにが?」
リンが食事の手を休め、怪訝そうな面持ちで首をかしげた。
「『青汁パン』と『ドリアンミルク』。凛の好物だったよな?
真っ先に確保するだろうな、とは思ってたけど」
……「青汁パン」と「ドリアンミルク」。
この街のコンビニにしか売っていない、
ローカル名物とでもいうべきB級グルメ。
「青汁パン」は、その名前の通り、とんでもなく青臭い。
「食べる青汁」と銘打たれたこの商品は、どぎつい緑色をしていて、
その外見と味は食欲を一気に萎えさせる魔力を持っていた。
「ドリアンミルク」も同様だ。
果物の王様として有名なドリアンの風味を再現した乳飲料。
えもいわれぬ激臭と非常に微妙な味わいが特徴的なシロモノだ。
どちらの商品も、罰ゲーム商品として人気が高い。
つまるところ、肝心の味の部分に関しては、
まったく評価されていないのだった。
しかし、この凶悪なご当地名物が、凛にとっての大好物だった。
普段は自分の好みを主張しない凛だったが、
この二つの商品に対しては格別な愛着を抱いていた。
「……憶えてて、くれたんだね」
嬉しそうに弾んだ声。もふもふと美味しそうにパンを頬張るリン。
その仕草が懐かしくて、恋しくて。
急に恥ずかしさがこみ上げてきて、とっさに目を逸らした。
「ところで、さっきは何を読んでたの?」
「アルバムをね。ごめんなさい、勝手に本棚さわって」
「別にいいけどさ」
俺は夕食を軽く済ませ、ベッドに腰掛けるとアルバムを手に取った。
独りになって以来、幾度も読み返した記憶の欠片。
俺が堂崎家に迎えられてからの、一年間の記録だった。
適当にページをめくっていると、ほどなくして横にリンが座ってきた。
顔を寄せ、横からアルバムを覗き込んでくる。
俺はいったんアルバムをたたみ、改めて最初のページを開いた。
そこには、堂崎家の庭で撮った家族写真が載っていた。
誰もがみな、一様に笑顔を浮かべている。
俺が堂崎家にやって来て初めて撮った写真だった。
「……懐かしいね」
俺は頷いて、ページを一つずつ丁寧に手繰っていった。
「あの頃」の風景が、そこには散りばめられていた。
堂崎家は、何かと賑やかな家庭だった。
花見に海水浴、月見にスキー。
春夏秋冬、季節ごとのイベントに連れ出してくれたものだった。
それはおそらく、俺を案じてのことだったのだろう。
少しでも新しい家族に慣れるように、
色々と行事を計画しては、家族とふれあう機会を設けてくれていた。
それらの思い出はすべて、大事なものとして今も俺の内にある。
「花見の時、鈴木が弁当ひっくり返したよな」
そうだ、この時は鈴木のやつもいたんだった。
小さい頃から仲が良いおかげで、
鈴木はたびたび堂崎家のイベントに参加していた。
「上から毛虫が落ちてきて、大慌てしたよね」
「海に行ってボートを借りた時、
調子に乗って沖合まで出てことがあっただろ?
潮に流されて危うく遭難しかけたもんな」
「近くの小島に流れ着いて、どうにか助かったもんね。
後ですごく怒られたけど」
リンにインプットされている記憶は、「凛」と同じもののようだった。
それぞれの写真にまつわるエピソードを事細かに覚えている。
それが嬉しくて、同時に複雑な気持ちにもなった。
「これ、秋に別荘に行った時に撮ったんだよね」
リンが指差した写真には、俺と鈴木が二人、森林を背景に写っていた。
バーベキューをしている場面なのだろう。
どでかい肉の塊に鈴木が喰いついている。
その横で、俺はピースサインを掲げて写っていた。
「……鈴木くん、用意されてた肉を
自分ひとりでほとんど食べちゃったんだよね」
「あの時はさすがに怒ったな。
肉を焼いたそばから、あいつが横からかっさらっていくんだ。
おかげで野菜ばっか掴まされる羽目になってさ」
「私は小食だから、むしろ助かったけど」
「凛は基本的にあまり食べないし、動かないもんな。
堂崎さんがどこかに連れて行っても、本を読んでるか、
そばで俺たちが騒いでるのをじっと見ててさ」
「……楽しそうな二人を見てるだけで、満足だったから」
凛は大人しくて、もの静かな女の子だった。
鈴木はいつも「深窓の令嬢ですな」なんて軽口を言っては笑っていたんだっけ。
……過去の思い出に浸りながら、俺は自然と頬を緩めていた。
リンと上手くコミュニケーションがとれるか、人間として扱えるか、
最初は自信がなかったが、まったくの杞憂だったようだ。
それどころか、俺はすでに彼女を「凛」として認識し始めている。
違和感を覚えなかったのは、
凛がもともと人形のような雰囲気を纏っていたからかも知れない。
──凛ちゃんは、お人形さんのように可愛いね。
俺たちがまだ幼かった頃、大人たちは凛を口々に誉めそやしたものだった。
もっとも、エンジェルドールの普及に従って
「人形のようだ」という形容は、
次第に好ましいものとして認識されなくなっていったのだが。
アルバムに見入る凛のほうへ、何気なく視線を移す。
白く透き通るような白い肌、華奢な手つき、
桜色のつややかな唇、落ち着いた声。
ひとつとして、違わない。
知らず知らずのうちに、記憶との齟齬を探している自分がいた。
粗を見つけようと躍起になっていた。
身体に点在する傷に加え、足裏のエンブレム。
それらは「違い」の最たるものだったが──
逆に言えば、それ以外はまったく同じだった。
やっぱり、こいつは「凛」なんだ……と、確信は深まるばかりだった。
そんなことを隣の人間が思っているなんて、
人形であるリンは気づきもしないだろうけれど。
彼女は、はにかんだような笑みを浮かべ、次のページをめくった。
「……あっ」
リンの視線は、そのページの最後──右下にある写真に注がれていた。
ダブルベッドに寄り添って腰掛けている、俺と凛。
その表情は、緊張のせいかがちがちに強張っている。
凛はカメラから目を逸らしているし、
一方の俺はといえば、引きつったような痛々しい笑みを浮かべている。
それは、別荘の寝室での写真だった。
あの日、俺と凛にあてがわれたのは同じ寝室。
そのうえ、ダブルベッドというセッティングだった。
最初に目にした時、えもいわれぬ気分になったのは言うまでもない。
「いいね、まるで新婚夫婦のようじゃないか」
あの時、堂崎氏はカメラを構えながらそう言ったのだった。
「何を固くなっているんだい、親である私としては喜ばしい風景だがね?」
そんなふうにからかわれた憶えもある。
親公認の仲とは言うものの、あまりにも開けっぴろげな計らいだった。
写真を撮り終えた後、堂崎氏が俺に耳打ちした言葉は、
さらに露骨なものだった。
「哲くん、今夜はよろしく頼むよ」……と。
リンの横顔を、ちらりと盗み見る。
先ほどとは一転して、そわそわしたような雰囲気が感じ取れる。
リンには、この時の記憶もあるのだろうか。
この写真を撮り終えた、その後の顛末を憶えているのだろうか。
あの時。結果から言えば、俺と彼女は何もしなかった。
──いや、できなかったのだ。
俺のほうは年相応に健全な男子だったし、
加えて堂崎氏からの後押しもあったわけで。
完全に「その気」になっていたのだ。
凛だって、少なからず期待しているものだと思い込んでいた。
でも、凛の肩に触れた瞬間、分かってしまったのだ。
……彼女の身体が、震えていることに。
その身にまとっていたのは緊張や期待ではなく、明らかな恐怖だった。
一度は、気づかないふりをした。
そのまま、おぼつかない手つきで抱き寄せて、唇を重ねて。
身体を重ねようとしたところで。
凛の動揺は、ピークに達していた。
迫ろうとした俺の胸板を手で押しとどめ、首を横に振る彼女。
顔は青白く、頑なに閉じた目にはうっすらと涙が滲んでいた。
「……こわい。ごめんなさい、怖い……!」
怯えに染まった、明確な拒絶の言葉。
それが、すべてだった。
リンは何も言わず、ぎこちない手つきでアルバムをめくる。
その沈黙と仕草が、答えを示していた。
──リンは、おそらく憶えているのだ。
次に開かれたページに、写真はなかった。
真っ白なスペースが、虚しく配置されているだけだ。
一年前の秋。別荘での二人の写真が、堂崎家での最後の記録なのだった。
「テツくん、私がいなくなってから……」
空白のページに目を落としたまま、リンが重たげに言葉を紡いだ。
「……私がいなくなってから、好きな人、できた?」
その言葉を耳にした瞬間、手が独りでに動いていた。
リンの襟首をつかみ、そのままベッドに押し倒していた。
「どうして……お前が、そんなことを訊くんだ」
あいつの顔で、あいつの声で、尋ねられたくなかった。
目の前にいるのは、写し身のエンジェルドール。
「凛」として扱おうと心に決めていたものの、
頭の片隅では「人形」だと認識してしまっている。
その人形に、試されるような物言いをされたことが許せなかった。
「あれから恋人ができたかって? ──できるわけ、ないだろう?」
勢いのままに、俺は口走っていた。
「……凛のこと、忘れられなかったんだよ。
忘れられるわけ、ないだろう!?」
偽りのない、本心だった。
一年の間に膨れ上がった想いは、
抑えようとしても、もはや止められなかった。
「ずっとずっと、心配してたんだ。
生きてて欲しいって思ってたんだ。
また、一緒に思い出を作れるように……
願って……」
こみ上げる激情の塊が、胸を焼いていく。
押しとどめていた言葉が、行き場を失っていた寂しさが、
喉から溢れだしていく。
その奔流をせき止めることなんて、できやしなかった。
誰かに聞いて欲しくて、でも言えなくて。
諸々の言葉を届けたかった相手が──その分身が、目の前にいた。
「……ありがとう」
澄んだ瞳が、俺を見上げていた。
その眼差しに、恐れは微塵も感じられなかった。
整った形の鼻。薄く艶やかな唇。シーツに広がった黒い髪。
──無防備なリンを見降ろしながら、荒い息を吐く自分。
襟首に回した手を、思い出したように離す。
昂っていた感情は、嘘のように消えていた。
後に残ったのは、どうしようもない罪悪感と自己嫌悪だった。
リンの手がすっと伸び、俺の目尻を優しくぬぐった。
わずかに濡れた指先を見て、初めて自分が泣いていたと知る。
なめらかな、細い指が頬にかかる。
「ねぇ、テツくん」
肌の感触を確かめるように、彼女はゆっくりと撫でさすっていた。
「私、あの時できなかったこと、したい」
落ち着いた声音に、俺は躊躇する。
一年前の苦々しい記憶が脳裏をよぎる。
どうしたって、鮮明に思い出されてしまう。
こちらのためらいを察したのか、リンは淡く微笑んだ。
「……今なら、いいよ。もう、いいの」
リンの両手が、俺の背中にまわされる。
二つの手のひらに、迷いが溶かされていくのを感じながら。
──俺は、リンにそっと口づけをした。

いいなと思ったら応援しよう!

