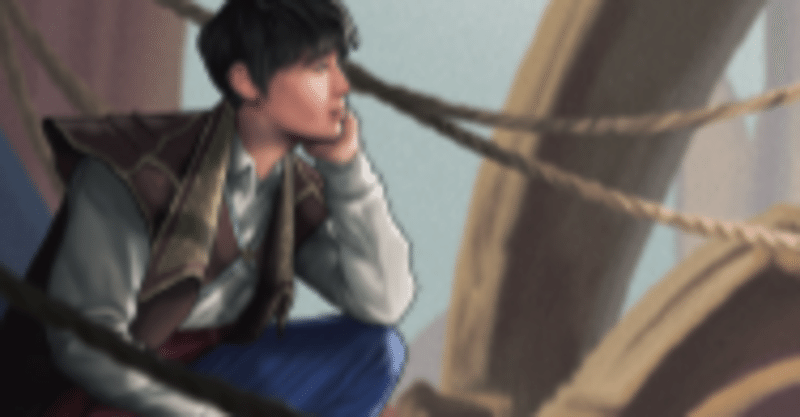
【MTG】初動から値下がりするカードの見分け方マニュアル
皆さんこんにちは。
最近はMTG熱が落ちたり上がったりしている84gです。
小説書きたいし、野球楽しいし。
てなわけで、今回は戦術記事ではなく、筆者の中にある『初動から値崩れするカードの見分け方』の出力になります。
筆者、こんな記事を書いてました。
各カードショップさんはネットなんかで発売前に予約販売を開始します。
そのときに付く金額から下がるのが多いんですが、それの予想となります。
筆者としては値崩れしてでも確実に初日から遊びたいカードを買うシステムだと思ってるので、そもそも値崩れしようが値上がりしようが関係ないと思える好きなカードでやるべきとは思いますが。
とにもかくにも、初動より値崩れするカードはどれかっていう予想記事を書いていて、今のところ『カルロフ邸』の方は3枚予想で全部値崩れして的中。
『サンダージャンクション』は次の弾の発売までを期日にしているので答えは出ていませんが、軒並み落ち気味と的中傾向です。
筆者の中ではこの値段ではありえないとう論理があり、そこに従ってありえない金額のカードを挙げています。
が、どうにも読者さんからの反響が多い。
零細アカウントであるうちとしては毎回アクセス数とイイネが多い。
「もしかして皆さん、値崩れするカードの指針がないのでは」ってことで、僕の中にあるマニュアルを共有する記事です。
その壱 『通常レアの温故知新』

令和MTGの赤を代表するカードと言っても過言ではない。
昨今、MTGをやっている方でコレを知らない人はほとんどいないでしょう。
登場当初は数百円でしたが、発売後に強さが知れ渡り、スタン・パイオニア・モダンにおいてトップメタに採用され、4500円クラスとなりました。
今はスタンダードで禁止され、2000円クラスに落ち着いています。
つまり、Mレアではない通常レアは『《鏡割りの寓話》クラスでもなければ5000円にはならない』、
そして『モダンやパイオニアなどふたつのフォーマットで使われる程度なら時間経過と共に2000円程度になる』ということ。
続きまして。

ストーリーのめちゃくちゃ重要なシーンが強いと良いよね。
これを書いている段階では最新段は『サンダージャンクション』なので、ひとつ前の段、『カルロフ邸』のレアである《世界魂の憤怒》。
スタンダードでは世界魂ランプのキーカードであり、モダンでもアミュレットタイタンで試されており、土地を戻すという挙動から無限コンボルートのある強力なカードです。
こちらですが、現在価格は300円ほど。
「1つのフォーマットのトップメタの1つで使われる程度なら爆騰しない」ということですね。
つまるところ、1000円を超える通常レアとは幅広いフォーマットで使われるカードのことです。
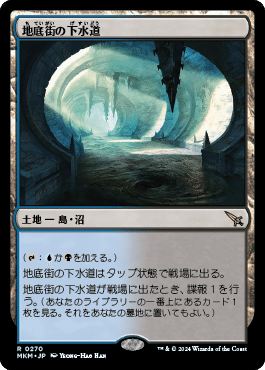

カード名的にマスターズ系かイクサラン次元でしか再録もしにくいのもネック。
なので、予約販売価格が1000円を超えているカードの場合、それが複数フォーマットにおいてトップティアになるという自信がなければ、値崩れする確率が高いということですね。
もうひとつのポイントは『それが4枚入るカードであるか』です。

今は落ち着きましたが、スタンダードでしかほぼ見ないカードである《負け犬》は一時期1000円級カードでした。
これは低マナ域として4投するデッキが強かったためですね。
黒いデッキであれば欠点らしい欠点もなく、雑に採用できる点も評価されていたように思います。

近い時期に出た同じく黒の通常レアであり、スタンダードで禁止指定もされた1枚。
こちらはパイオニアでも利用実績がありましたが、最大でも500円級。
4投のリストも多くあったと記憶していますが、『使うとしても2~3枚』という構築も多かった。
供給量に対して4投されないなら、そこまで高騰しない、当たり前ですね。
MTGは例外も多数ありますが、基本的に低いマナ域のカードの方が4投されやすいです。
なので『低マナ域のカードの方が爆騰しやすい』という傾向は感じます。
また、当たり前ですが『多色のカードはそれだけで固有色の関係で統率者では使われにくい』というのもチェックですね。
そもそも統率者戦では1デッキに1枚しか入らないため、統率者戦でいかに強くても多色・高マナ域のカードはすぐに値段が落ち着く印象が有ります。
というか、大半の通常レアカードは半数以上が発売後一ヶ月で最安値100円級になりますしね。

下落も高騰もしていない稀有なカード。
こういうカードもあるから難しい。
上記の情報を総合すると《潜入者、悟》や《犯行現場の再現》が1000円を超えているのはありえないという理論展開になるのもおわかりかと思いますし、
上記の僕の記事の内容と読み合わせていただけると楽しんでいただけるかと思います。
その弐 『神話レアの温故知新』
問題は神話レア、Mレアですね。
基本原則として、ドラフトブースター(プレイブースター)の通常レア枠が約8分の1くらいの確率で置き換わったものがMレアです。
通常レアはひとつのパックに大体70種くらいで、Mレアは20種程度。
特定の神話レア1枚を出すには、8×20で160パックを剥けば(概期待値として)1枚出現。
特定の通常レア1枚を出すには、8パック中7枚が通常レアってことは80パック剥けば70枚の通常レアがでることになるので、概算期待値としては80パックに1枚です。
ちなみにこれ、めちゃくちゃザックリです。
そもそもフォイルとか特殊枠とかあるし、各数字が弾ごとにズレが有るので。
まあ、つまるところ、イメージとして「市場には、Mレアは通常レアの半分しか存在してない」ってこと。
160パック剥けば1枚出るMレアと、80パックで1枚出る通常レアだから。
この辺り、ブースタードラフトとかをやってると自然とプール内のボムレアの枚数とかの勘定する関係でイメージできるようになる話なんだけど、やらないと意外と考えない話。
なので需要が集中した場合、Mレアの供給が足りなくなるのは必然であるってこと。

ドミナリアを代表するキャラクターのひとり。
こちら、スタン当時7000円くらいしてました。
筆者は当時は初心者だったことで把握していませんが、モダンでまで幅を利かせていたとはいえ、2フォーマットだとその金額です。
現在はスタン落ち、モダンでは5マナというマナ域が疑問視され、パイオニアのアゾリウスコントロール系統のデッキのフィニッシャー。
とはいえ、アゾリウスコントロールの立ち位置がやや難しくなっており、2000円前後まで落ち着いてきました。

別にドミナリアを代表するキャラクターではない。
パイオニアでは主に採用していたラクドスミッドレンジが《血王ソリン》採用のラクドスヴァンパイアにチェンジしたことで採用数が激減。
スタンダードでも絶対君主というわけではなくなったが、それでも未だに1万円カードです。
これでも値段落ち着いてるんですが、統率者やレガシーでも需要があるのはやはり強い。

当たり前だけど、ドミナリアを代表するキャラクターであるわけがない。
現在4500円カード。
さっきチラっと名前が出ましたが、《血管切り裂き魔》の登場で一気にトップメタへと躍り出たシンデレラ吸血鬼。
なんだよシンデレラ吸血鬼って。
ほぼパイオニアでしか使われていないカードですが、シークレットレイアーぐらいでしか再録されておらず、流通量に対して需要が多く高騰しています。
調べたらモダンでも使用実績がありましたが、パイオニアでの支配的な流通に比べると少ない、と言わざるを得ないでしょう。
つまるところ『パイオニアひとつでトップメタだが他フォーマットではそこそこ』クラスのカードでも5000円近くまで爆騰する、それがMレアです。
で。ここで暴落カードを挙げますが、《世慣れた見張り、デルニー》は予約価格が4000円でしたが、どう考えてもトップメタの一角という1枚ではない。
『1つのフォーマットで4投トップメタを取れる』と判断される金額、それが4000円ということですね。
その参 『そもそも強いカードって何よ』
ここまでで、『より多くのフォーマットで4枚使われるカードが爆騰し、働く場がないカードは下落する』ということをお伝えしましたが、じゃあそもそも強いカードって何よって話ですね。
まず、そのカードの『強さ』を考察します。
それが単独で強いカードなら、既存カードと単純比較します。
正直、そういうタイプのカードはそこまで評価がズレません。強いもんは強い。
それがシナジーで強いカードなら、そのカードの要求値と期待値を考察します。
例えば、それが『特定のカードと揃って手札に来た場合、超強力な威力を発揮する』という場合。
仮に、考察するカードをA、シナジーするパートナーをBとし、Aが墓地のカードを必要とするカードで、Bが墓地から戻すと強いカードだった場合。
その場合、このままだとAとBが4枚ずつしかなく、コンボが決まるのが不安定です。
その際、AやBに類似するカード、A´やB´が存在する場合、2種8枚となりデッキの安定性は大幅に上がるわけです。
具体例をここでひとつ。


この2枚は、墓地に《パルヘリオン》がある状態で《脂牙》が出れば3ターン目にゲームを決定付ける強力コンボです。
上の例でいうところの、Aが《脂牙》、Bが《パルヘリオン》に該当し、B´が《エシカの戦車》や《スカイソブリン》ですね。
ちなみにこのコンボ、モダンやレガシーではほぼ使われておらず、パイオニアでもトップメタから転落しつつあります。
なので、『下環境で天下を取れる!』デッキというのは必然的に『パルヘリオンシュートを何らかの形で上回っていること』ってことですね。
新規のシナジー系カードを見たとき、近い特性を持つトップメタのデッキを思い浮かべてみてください。
その際、トップメタよりどんな面が勝っていますか?
A´やB´が多くてコンボの再現性の高さからくる要求値の低さ?
カード単独の性能が比較的高く、コンボ不発でも戦える汎用性?
コンボパーツの色やマナカーブが揃っているマナ基盤的な強さ?
トップメタ相手に致命的に効く挙動を有する環境的立ち位置?
次に、『そのカードを相手にしたときに対処できるか』を考えてみてください。

《デルニー》なんかは典型例で、3ターン目に出しても仕事をしないことが多い。
更に本体のスタッツが低いので、対処手段は『そのまま殴れば良いだろ』です。
『他のクリーチャーを必要とする』っていうのも要求値の高さですね。
弱いカードではありませんが、上振れに対して弱いときに何もしなさすぎる。
同じ3マナで、『墓地から《パルヘリオン》を呼び出してゲームエンドを狙う《脂牙》』がトップメタから落ちようとしている中、
『他に生き残っている特定のクリーチャーの誘発を倍にする《デルニー》』がどうして4000円で構築で受け入れられるのって話。
けちょんけちょんに言ってますが、弱いカードとは思ってないです。
統率者需要はもちろんありますし適材適所。ただ価格の推移の考察として見た場合、っていう意味ですね。
とにかく、そのカードをマナカーブに沿って動かしてみてください。
その間にトップメタの仮想敵たちはどんな強力な動きをしていますか?
先手ならギリギリ間に合う? なら後手なら?
トップメタ相手にでもボコボコにできるなら、それは土地を含めて何枚のカードを必要とするでしょうか?
MTGでは土地が有るので、『初手に有る土地以外のカードは3~4枚』だと思って下さい。
その想定の中、その新規カードとパートナーのカードは都合よく手札に来てくれましたが、では片側だけ来た場合はどうでしょうか?
上振れでコンボが揃った場合、下振れでカードが揃わなかった場合はどうでしょう。
高額化するカード、勝率の高いカードとは『下振れに対して上振れが明らかに強いカード』のことを指します。
その四 『例外』
「肆」って絶対差別されてるよね。
「一二三」は他記号と見分けしにくいから「壱弐参」が使われるけど、四は視認性に問題ないから「肆」って使わねーもん。
というわけで、カードの評価の際はそのカードがメタ上でどの程度の立ち位置を取れるかどうかの分析が必要という記事でした。
もちろん、想定外の状態とかも多く、筆者も値崩れしない安牌だと思って暴落カードを買ったことも多いです。
最近だと、ニューカペナの3マナオブニクシリスを初動で引いてたので、5000円から値崩れする前に売れば良かったなぁ、などと思ってみたり。今500~1000円だよアレ……。
たた、繰り返してく内に、「どうしてそのカードは環境にフィットしなかったのか」というか、自分の思惑とどう違っていたのかを見極めできてきました。
言語化と分析と学習。これもMTGの楽しみのひとつだと最近では思っています。
更に統率者デッキやらユニバースビヨンドとかとか、変な商品の変なバージョンもあるので難しい。
当記事はファンコンテンツ・ポリシーに沿った非公式のファンコンテンツです。
画像はMTG日本公式より引用しています。
ウィザーズ社の認可/許諾は得ていません。
題材の一部に、ウィザーズ・オブ・ザ・コースト社の財産を含んでいます。
©Wizards of the Coast LLC."
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
