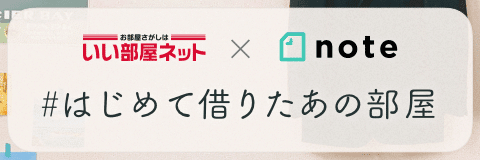あたしの、ひとりきりの部屋から
あたしは二度と戻りたいとは思わない。
あの、はじめて暮らした、夜の星も見えない、ひとりきりの部屋には。
***
2005年4月、東京。
夕方になると、あたしはぐったりと三鷹駅に降り立つ。大学の課題がたんまり入った手提げが重い。陸橋から、ビルに挟まれまっすぐに伸びる大通りを眺めた。
あたしを知っている人は、誰も、この街にはいない。
夕焼けに染まるはずの空は、灰色の建物に遮られ切り取られている。どこにもつながらない身体を、重い足取りで動かした。
夕飯を買って帰らなきゃいけない。財布の中身は千円札が数枚。大学の教科書があんなに高いものとは知らなかった。10万円の奨学金とわずかな仕送りでは、きれいにパックされた豚肉も魚も、青々とした野菜も、なにもかも手がでない。
不自由なミニキッチンで料理するぐらいなら、総菜コーナーからオムライスでも買ったほうがましだ。でも、その数百円すら。あたしは次の仕送りまでの日数をカウントし、カップラーメンと菓子パンをつかむ。
レジに並ぶ前の親子のカゴには、ひき肉や玉ねぎが入っていた。ハンバーグでも作るのだろうか。10歳ぐらいの女の子が、お母さんの隣で袋詰めを手伝っている。
きょう母は、あたしのいない実家の台所で、父と妹に何をつくったのだろう。ぐう、と空っぽの胃袋がなった。

大学から5駅も離れた三鷹に住んだのは、あたしの妥協で、希望だった。
「女の子の一人暮らしは危ない」と、呪詛のように唱える母親が唯一首を縦に振ったのが、守衛つき・門限あり、23時にシャッターが降りる、10階建ての要塞みたいな学生会館。
三鷹の北口から目抜き通りを歩いて5分。ピカピカのスーパーと、昭和を閉じ込めたみたいな肉屋を横目に見ながら、「人通りも多いし、安心よね」と、引越しの付き添いで来た母は満足気にうなずいた。
母は、偉大で、一番で、正しい人だった。高校生は、遊ぶ友達の名前から連絡先まで親に報告するのが「普通」。バレンタインのチョコは「禁止」。男女交際に「不純」の頭文字をつける母を持ったあたしは、彼氏の存在を気軽に親に話せる友人が、信じられなくて、うらやましかった。
思いきって色つきのリップを買った日。鏡に向かって薄い桜色をつけるあたしに「色気づいちゃって」と笑う母。ああ、この家にいる限り、あたしは一生、母の娘なのだと、背筋に流れたのは冷たい予感だ。
『夜遊びなんて、簡単にさせないわ』
守衛さんに挨拶をし、窮屈なワンルームを見回す母のにこやかな目が、そう言っている気がした。
細長い部屋には備え付けのベッド、勉強机、本棚。玄関脇に、キッチンとは言い難いサイズの流しとコンロ。8階だというのに向かいのマンションに遮られ眺望はゼロに等しい。
はじめて住む部屋は、「快適」の2文字とは程遠いと思った。それでも、あたしはやっとひとりになれる。
荷ほどきが終わらず泊まりそうな勢いの母を、新幹線の時間があるでしょと追い払うように階下まで見送る。目についた弁当屋でのり弁を買って、ペットボトルのお茶と一緒に床に座って食べた。
時計の秒針の音すら響かない部屋は静かだ。窓の外に顔を出すと春の夜の浮かれた気配を感じた。ビルの看板がちらちらと光っている。あたしは手すりに身を乗り出して、天を仰いだ。
ここから見える夜空は、なんて、せまいの。
実家の屋根先に輝いていた春のスピカを探す気にもなれず、窓を閉め、急いでコロッケと漬物を口にかきこんだ。ざわざわしたこの胸の高鳴りを、心細いと呼ぶのだと気づいたのは、ずっと後になってからだ。
***
最初の失敗は、新歓だった。オールで飲むぞとはしゃぐクラスメイトに「門限がある」と告げたあたしは、イケてなかった。郊外に位置するキャンパスだから、一人暮らし組は自然と徒歩圏内に住む。たった2週間で、あの子とあたしの間に壁ができたのが、手に取るようにわかった。
つまずきは重なる。講義が難しい。机にかじりついて入った国立大学。帰国子女や留学帰りがわんさかいる英語専攻で、泣きそうになりながら辞書をめくる。
母からの電話は週に最低2回。部屋の固定電話が音を出すのは決まって夜10時頃。まるで、遠くからあたしを監視しているみたい。
頭の痛い春が過ぎ去り、曇り空がしくしくと泣き出す梅雨になっても、あたしの交友関係は品行方正な学生そのままで、母が心配することなど何もなかった。
学生会館には、地方出身の女子学生が多い。在籍する大学はバラバラ。交流が盛んとはいえない。かろうじて、隣の部屋の住人と数回会釈をした程度。教室でも、ひとり。部屋でも、ひとり。
母が選んだ赤いチェックの布団にくすんだ萌黄色のカーテン。姿見の周りに散らばる化粧品。安っぽいデザインのやかん。この部屋は、なにもかもがちぐはぐだった。まるで、あたしみたいに。
一言も発しなかった夜は物言わない天井を眺めて、この身を抱くように布団にくるまって寝た。

その日は、6月の日曜日の夕方だった。小ぶりの雨が降っていた。肌寒い日で、あたしは長袖を羽織った。午後4時を過ぎるとスーパーの総菜に半額のシールが貼られる。空っぽの冷蔵庫を少しでもマシにしなければいけない。
ビニール傘を差して、とぼとぼと通りを歩く。香ばしい焼き鳥の匂いが流れてくる。休日の食材を買い込んだ家族とすれ違う。だれもが、それぞれの家に帰ろうとしていた。
横断歩道で停止した先、透明な傘の向こうに見覚えのある影があった。同じクラスの女子たちだ。あの子とあの子は一人暮らしで、あの子は実家組のはず。なんで三鷹に。飲み会かな。休日に約束して遊ぶほど、仲が良いのが普通、なんだ。
歩道の白線との距離が永遠のように遠ざかり、鋭いものを突き付けられたみたいに、心臓がぎゅうとなった。
あたしに、気づくな。どうか、気づかないで。
傘を握る手に力を込めて、ぎゅっとつま先を来た道に向けた。息を止めて。女の子特有の高い笑い声から小走りで遠ざかる。
学生会館の重たいドアを開け、古びたエレベーターに飛び込んだ。8の数字を叩くように押す。あたしだけの部屋に逃げ込むと、床に散らばったプリントと本とくたびれた衣服がむかえてくれた。
壁の輪郭がゆがむ。胃の奥から、どうしようもない孤独がせり上がってきて声にならない叫びになった。あたしは、なにも持っていない。恋も勉強も整った生活も、友達さえも。なにも。
あたし以外の動くものがない部屋に、絞り出した「さみしい」が反響する。一人でも、涙はちゃんと馬鹿みたいにあふれた。
***
目をひらくと、薄暗い闇だった。枕に顔を突っ伏して、あのまま眠っていたらしい。
ドアをたたく音がする。入り口が厳重な学生会館の住人は、めったに鍵をかけない。そのまま入ってくればいいのにと、あたしは鉛みたいな体を持ち上げて、のろのろとドアノブを回した。
廊下の明かりが、暗い玄関に筋になって差し込む。まぶしさに目を細めた光の中に立っていたのは、背の高い、ショートヘアのひょろっとした女の子。季節外れの小麦色の肌。見覚えがある。隣の部屋の住人だ。
「あのさ、」
想像よりも高い声があたしの顔に降ってくる。
「料理の本とか、もってない?」
そんなんないよと喉から出かかった瞬間、視界の隅に電子レンジに積み上げた本が映る。母が置いていった料理本。2冊手にとって渡すと、彼女は軽快に笑って「ありがとう!」と言い残し隣のドアに消えた。
扉が閉まる。暗い部屋のスイッチを探る。蛍光灯に照らされた室内は雑然として汚かった。
彼女の名前は、なんだっけ。散らばった衣服を拾い集める。そもそも知らない。カーペットにコロコロをかける。クラスのあの子たちに、あたしは何回ちゃんと名前を呼んだのかな。小さなシンクにたまった食器を洗う。せめて、自分の生活だけでもマシになりたい。まともに使ってなかった排水口に、濁った食器洗剤の泡がさらさらと流れて消えた。
次に目を覚ますと、時計の針が22時を指していた。つけっぱなしにした電気がまぶしい。水を飲もうとキッチンに目をやると、玄関脇の棚の上に見慣れないタッパーが2つ、置いてあった。横には貸したはずの料理本。
フタをあけると黄色のチーズが目に入った。続いて、ふわんと鼻をくすぐるひき肉の香り。その下には白いご飯が敷き詰められている。もう一つには刻んだトマトとレタス。彼女のお裾分けに違いなかった。
お腹がぐう、となった。こんな夜中みたいな時間だけれど。文句を言う人は誰もいないからいいよねと、100均で買ったお皿を取り出す。ご飯と具材をお皿にうつし、電子レンジにかける。チーズが、とろりと溶けた。スプーンとお水を入れたコップを、窮屈なローテーブルにセットする。レタスとトマトもこんもりのせて。あたしは「いただきます」と手を合わせた。
ふわんと白い湯気が上るひと口は、3分待つカップラーメンよりも、レトルトのミートソースをかけたパスタよりも、ずっとずっと温かかった。
外の雨は、止んでいた。通りを歩く人の声は響いてこない。秒針の音だけが、部屋の時間を進めていく。あたしは変わらず一人で。きょうは、あたし以外の誰かが、この部屋に来た最初の日。
ごくんと飲み込むと、泣きたい気持ちが胸の奥からあふれそうになった。
もどってきた料理本に付箋が貼られている。滲んで凝らした視界に『ありがとう!』の走り書きと彼女の名前が映った。
タッパーを返すとき聞いてみよう。この料理なに?って。確か沖縄のやつでしょ、って。
日焼けした肌のナオが、得意気に「タコライス」と答え、あたしが貸した料理本にそのレシピなんて載ってないと知るのは、もう少しあとのこと。

「ちゃんと暮らしてるよ」と言えるようになるまで、さらに2つの季節を越えないといけなかった。それでも、夏休みの前に英語リサーチのアルバイトが決まり、食材は人並みに買えるようになった。
隣のナオとは、自炊仲間になった。夏の空気に酔っぱらってジュースでゲラゲラと笑い、試験前は憔悴した肩を叩き励まし合った。冬の寒い日に、彼女の終わった恋の話をじっと聞いた。
ひとりきりの部屋の壁が、少しずつ、なくなっていく。
情に熱くて、ふさぎ込んでいた隣人の私の嗚咽に、思わずドアをノックしてしまった行動派の彼女は、大学2年のときに長期留学で隣の部屋を出て行った。その頃には、大学と構外のサークルに、あたしは小さな居場所を見つけていた。
友人から勧められたうつくしい詩集を本棚に飾った。好きな人が好きといった曲を集めた。たまに、ナオから知らない国のポストカードが届いた。
赤いチェックの布団と、くすんだ萌黄色のカーテンの部屋は、ちぐはぐなままだったけれど。この手で選んだものを増やし、少しずつ不器用に、あたしは母から離れていった。
あの、ひとりきりの部屋で。
あたしは狭苦しいキッチンで料理をして、たまに成功し、数えきれないほど失敗した。窮屈なユニットバスで、さめざめ泣く夜もあった。課題のために徹夜をし、ふと顔をあげると、窓に切り取られた夜に三日月が浮かんでいた。
ひとりだった。よわかった。強がっていた。空っぽの夜を何回も越えた。
あの部屋に戻りたいとは思わない。でも、誰かといるために、ひとりになる必要を教えてくれたのがあの部屋だった。そして手を伸ばせば、その先につながる手が、きっとあるという希望も。
脆くて儚い日々を閉じ込めた学生会館は、10年経って真新しいマンションに変わっていた。
もう、ない。でも。
少しだけやさしくなって、もっと強くなりたいと願った18歳のあたしは。泣いて笑って生きていくと歩きはじめた。あの、ひとりきりの部屋から。
この記事が受賞したコンテスト
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?