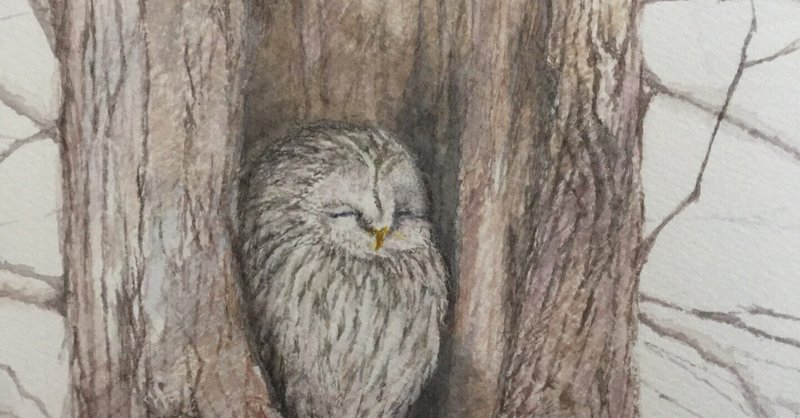
幸田露伴の随筆「折々草38~45」
三十八 雪中庵蓼太
蓼太は、「五月雨やある夜ひそかに松の月」という句で世に知られるが、その日常は奢侈を極め、食事をする時は高貴の人がするように必ず懸盤(かけばん)を用いたと云う。なので田舎の人などは、その形態の物々しさに驚き気を奪われて、包んで来た謝礼の金を増し改める者が多かったと云う。苦々しい俳人と云うべきである。ただしこの話は本当であろうか。
注解、
・雪中庵蓼太:大島蓼太、江戸時代の俳人、与謝蕪村・加舎白雄などと共に中興五傑の一人。。
・懸盤:懸盤膳、ひな人形などで見られる脚付きの膳。
三十九 神功皇后
神功皇后の征韓の御功績を仰ぎ畏(かしこ)みて称(たた)えまつらない者はいない。しかしその事の原因と結末をよく知る人は少ないようである。皇后に神が乗り移って、「西方に此の国よりも優れた国がある。美人の眉のようになだらかな向いの国である。金銀をはじめ目の輝くような種々の珍しい宝がその国には多い。新羅と云う国である。」と皇后に云われて、新羅を攻めることを天皇に勧めたのは人の知るところだが、皇后の母君が葛城の高額比賠命(たかつかひめのみこと)と云われて、新羅の国から移って来た天日槍(あまのひほこ)六代の孫にあたる人であることに、気付かない人が多いと見えて、人々の話題にもならないで来たようである。気を付けて新羅征討の由来を考えてみるとよい。
注解、
・神功皇后:第十四代天皇の仲哀天皇の皇后、仲哀天皇崩御から応神天皇即位まで摂政として約七十年間君臨。仲哀天皇の没後新羅に出兵し朝鮮半島の広い地域を服属下においたとされている(三韓征伐)。『古事記』『日本書紀』
四十 平賀源内
平賀鳩渓が功利を信条とした人なのは云うまでもない。最近秩父に旅行して、「源内が秩父で鉱山採掘をしたことを聞いたが、そのような云い伝えは有るか」と訊ねたところ、「あります、あります。秩父の極めて山奥に中津川と云う所があります、人跡も殆んど無いような所ですが、そこに源内が採掘したと云う鉱山があります。」と土地の老人が答えた。このことは嘘ではないようである。文化文政の頃の幕府の資料にも、「明和の年に平賀源内は中津川の北西に在る字(あざ)榧久保(くかやぼ)などの鉱山を採掘したと記されている。猶よく考えてみるとよい。
注解、
・平賀源内:江戸時代中頃の人。本草学者、地質学者、蘭学者、医者、殖産事業家、戯作者、浄瑠璃作者、俳人、蘭画家、発明家。
四十一 林和靖
林和靖(りんなせい)を人は皆、高潔の隠士で敬い慕うべき高徳の人のように思う。しかし西湖の図を持って来た客人がいて、その図に「孤山の下の樹木幽遠な処に題して林処士庵」とあったので、和靖は欣然として頷いたと云う。その猶も世を忘れなかったことを知るが善い。
注解、
・林和靖:中国・宋の詩人。西湖の孤山に廬を結んで閑居して詩を作る。
四十二 陳眉公の奇言
堯が天下を許由に譲ったが許由が之を受けなかったので、後世の人は皆これを高潔だと云って異論はない。しかしながら陳眉公が云うには、「堯の時の大地は悉くが洪水のために獣の跡や鳥の跡があるだけで、その後ようやく平らな土地が出来、民に作物の植え付けなど教えたりしたが、しかし荒れ果てた天地からは少しばかりの作物が得られるだけであった。どうして受容することができよう。天子の尊さを以てしても茅や茨は切れない、獣の角は切れない。神に具える食を以て些か飢えに当て、鹿皮の衣で些か寒さを防いで、天下の楽しみは受けられず、天下の苦しみは集まるばかり、堯が色黒で舜が色の黒いのも無論その為である。許由がどうしてこれを受けられようか」と云う。皮肉な論である。面白いことは面白いが軽薄なことは軽薄である。このような論は、ただ茶飲み話として聞くだけか。
注解、
・陳眉公:陳継儒、中国・明末期の書家・画家。
・堯:中国神話・三皇五帝時代の五帝の一人。
・許由:中国古代の三皇五帝時代の伝説の隠者。伝説によれば、許由は陽城槐里の人でその人格の廉潔さは世に名高く、当時の堯帝がその噂を聞き彼に帝位を譲ろうと申し出るが、それを聞いた許由は潁水のほとりにおもむき「汚らわしいことを聞いた」と、その流れで自分の耳をすすぎ、箕山に隠れてしまったという。
・舜:中国神話・三皇五帝時代の五帝の一人。堯から禅譲されて帝となる。
四十三 甲州流軍学
甲州流と世に云われる兵法がある。その甲州流が武田氏の兵法であるかどうかは知らないが、思うに信玄の遺法と甲州諸士の伝える話を集めて才識のある者がまとめたものでは無いだろうか。説くところは実際の経験によって出たものと思われて、能く情理に合致するものが無くは無い。人相を相(み)ることを説いて、「人を相(さげす)まんと思わば、先ず我が心身を能く沙汰(さた)して正路に気を持って、毛頭私無く思案工夫の分別仕(つかまつ)るべきなり。(人を判断するには、マズ自分の心身を調えて正道を心掛け、少しの私心も持たずに能く考えて判断すべきである。)」と云うなどは、言葉は俗に近いが実に正大である。「マズ他(ひと)を判断しないで自分を反省する心掛けが真(まこと)に適切である。自分の心が静かであるか速いか、重いか軽いか、根気はあるか淡泊か、この六ツの心の上にまた、自分は奢って無礼であるか、謙(へりくだ)って慇懃であるか、邪欲の心があるか、短気の意地があるか、堪忍できるか、物が能く出来るといえども、根気があるか、弁才は明瞭か、心は明らかであっても身なりが至らぬ者の眼には鈍くみえるか、心は剛であるか、心は強であるか、合計十七の品々の何れが我が身に備わっているかと能く考え判断して、自分自身が分からなければ他(ひと)の鑑定は出来ることではない。身分の高い者は云う迄も無いが身分の低い者であっても、善い被官(ひかん・勤務先)を見つけて、親兄弟のように大切に思い、馳走(ちそう・駆け回り様々の人と交際する)して意見を聞いて自分の悪い意地を治して、その後に人を鑑定するならば、大方十人中九人は善悪の判断に間違い無いと心得よ」、と云うなど実に至論である。また論じて云う、「人の様子でその技能(わざ)を見定める儀は、喩えば小刀のかさねの薄く造ったものは、楊枝などを削って見ると深入りする、かねあじの堅い小刀では竹は削ってものらないものである。竹にはかねの甘いものが至当である(人の様子でその人の技能を鑑定する件では、たとえば小刀の厚みを薄く造ったものは、楊枝などを削ると深く入る。刃金の堅い小刀では竹を削っても入らないものである。竹には刃金の軟らかい薄いものが最適である。)」と。これもまた、人才それぞれその適所にあるべきことを云って、この譬喩はなはだ巧妙である。
注解、
・甲州流軍学:小幡景憲が開いた軍学の流派。武田信玄の戦術を理想化している。武田流、信玄流とも呼ばれる。小幡家は武田信縄の代から武田氏に仕え、小幡景憲の父・昌盛は高坂昌信の寄騎であったという。武田氏滅亡後、小幡家は他の武田遺臣とともに徳川氏に仕えた。小幡景憲は徳川秀忠に仕え、武田氏の遺臣を訪ねてまわって軍法を学んだ。主なところは、山本勘助より軍法を伝授されたという広瀬景房、馬場信房より城取りの伝を伝授されたという早川幸豊、上泉流軍配を伝える岡本宣就らに学んだという。 そして時期は不明だが『甲陽軍鑑』を入手し、これに武田遺臣たちより学んだ内容を加えた軍学を教授した。
四十四 徂徠
徂徠は儒者中の高祖や項羽のような人である。その人を一言で云えば唯この言葉あるのみである。そしてその徂徠の言葉の気象広大で作用活発なことは、人に達人でなければ決して言えない言葉であると思わせる。その言葉はどのようなものか。云う、「人才は疵物(きずもの)に有り(優れた才能を持った人は、欠点を持った人の方に多く見出すことができる)」。
注解、
・徂徠:荻生徂徠、江戸時代中期の儒学者・思想家。
・高祖:中国・漢の高祖劉邦、漢王朝の創始者。
・項羽:中国の英雄、秦末期の楚の武将。西楚の覇王と称し天下を劉邦と争った。
四十五 気質
万人に共通するのは道理である。一人が持つのは気質である。気質の偏りを正す工夫を知らない人を生まれたままの人という。悪いことは無いが、サテそれでは世の困り者と云える。また自分の気質を正そうともしない者を横着者と云う。本物の剛勇でないことは勿論だが、横着な無精者に限って自分の気質のままに行動することを剛勇としている。天心爛漫などと云う言葉は、常にこのような輩(やから)の巣の上に懸けられた看板の文字である。気質のままにするのは可(よ)いけれども、やがてそれ等の輩は欲の赴くままにすることを可(よし)とする傾向があるのは、常々世の中で見かけることである。そのような輩は修業や工夫などと云うものを無益と看做(みな)す習慣にあるが、余りにも人らしくなく、口惜しいことである。と私が師事した菊池松軒先生が幾度となく云われたことを、この頃大層身に沁みて思う時が多い。
注解、
・菊池松軒先生:幕末の漢学者。幸田露伴は十五才の頃その漢学の塾である迎曦塾に通った。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
