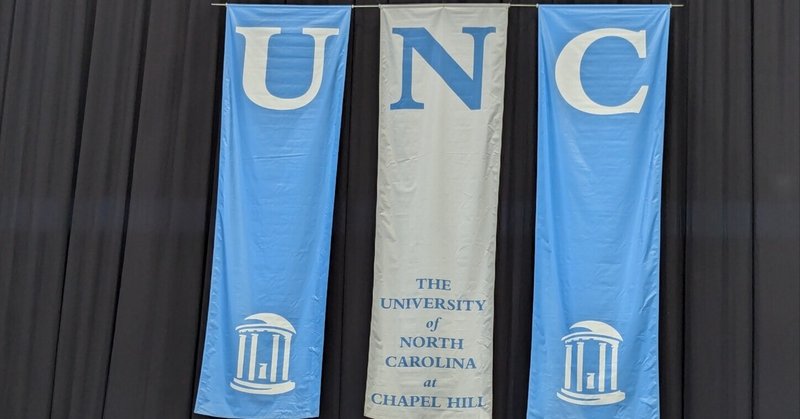
米国MBAを修了して
Google日本オフィスから米国本社に異動して現在6年目になりました。先日、働きながら米国の大学でMBAを無事修了したので、学校選びや仕事との両立、プログラムの感想などを書き残したいと思います。MBAを検討中の方などのご参考になれば幸いです。
TL;DR(要約)
Googleの広告部門でGlobal Product Leadとしての勤務3年目に米国のパートタイムMBAに入学、フルタイムでの勤務と並行し、2年3ヶ月かけてUNC Kenan-Flagler Business Schoolを成績優秀者として卒業しました。プログラム在学中に結婚、妊娠出産、さらに目標だったProduct Managerへの異動が実現しました。かかった時間や努力、また学費は相当なものになりましたが、総じて素晴らしい経験でした。
以下、非常に長くなりますので、ご興味がおありの方のみどうぞ。目次から「最後に」に飛んでいただければ全部読んだかのような気持ちになれるのでお時間のない方はそちらでどうぞ!
なぜMBAを取得しようと考えたか
MBA(経営学修士)はもはや良い話よりも「誰でもとれる」「役に立たない」「時間と金の無駄」「会社/プロダクトをつまらなくするのはMBAの奴ら」と揶揄されることが多い昨今なので、なぜ今さらMBAというのは当然誰もが考えることだと思います。
若かりし頃私はあまり何も考えていない若者で、大学院やMBAなどというものが私の人生の選択肢にあるとは思いもよりませんでした。慶應大学を卒業し、リクルートエージェントという会社で営業としてそれなりに長く働いてきましたが、その後縁あってGoogle Japanに営業として転職したところ、部署にはアメリカやヨーロッパでMBAを修了している方がたくさんいることを知りました。そのほかにも様々な分野で修士、博士の方が当たり前のように存在していて、面白いことに「うらやましいな」と思ったことを覚えています。それは、自分の知らない選択肢を彼らは人生の早い段階から認識して決断してその道に進んでいることに対しての感情だったと思います。念の為記しておきますが、社内ではもちろん学位の有無でつけるポジションや昇進が変わることは一切ないですし、学部卒で極めて優秀な方も非常に多いです。
しかし実際にMBAプログラムを受験しようと考えることはありませんでした。なぜなら、せっかくGoogleに入社できたのでMBAのために仕事をやめて1〜2年海外へというのは全く良い選択とは思えなかったこと、仕事もついていくのに精一杯な自分がGoogleを辞めてまで行く価値のある良い学校に受かるとも思えなかったことが理由でした。加えて、Googleでの日々の仕事、例えばミーティングや社内でのブレストでも今まで経験したことのない知的な刺激に溢れており、当時ほとんど話せなかった英語も日々の業務の中で上達するチャンスがあるし、仕事を中断してMBAに高いお金を払って行くより、ここでいろいろ勉強した方が良いのではと考えました。
そんなこんなで6年ほど日本で営業と製品スペシャリストとして働いていたのですが、米国本社のGlobal Product Leadのポジションの面接に合格し渡米する機会に恵まれました。その辺りのことは以前のnoteに書きましたので、ご興味がありましたらどうぞ。
渡米して最初の1年は英語でのコミュニケーションがあまりにも下手くそなうえ、新しい仕事でどう自分の経験を生かせばいいかいまいちわからず、かなり苦労しました。2年目も半ばになるとようやく自分の仕事が高い評価をもらえるようになり、余裕が出てきました。常に何か向上していないと気が済まないタイプなので仕事の余裕を何に使おうかと考えたところ、まだまだ下手くそな英語をなんとかしたい、より良い仕事をして上を目指したい、というのが優先順位の上位にありました。しかし、英語自体の勉強をするより英語で勉強をしたほうが効率が良いというか効果がありそうだし、まず何かオンラインコースでもとろうか、ということになりました。PythonでAtCoderを始めたのもたしかこの時期だったと思います(MBA準備のため辞めてしまいましたが、またやりたいです)。オンラインで無料で提供されているコースの中から仕事に役立ちそうなもの、趣味に関連するものをいくつかやってみた結果、もっとディスカッションや課題でコミットメントが求められるものをやってみても良いなと思うようになりました。そこで、MBAは実務に即しているしコミットメントが必要そうだし、考えてみるかとなったわけです。
ちなみに、MBA以外のMasterプログラムも少し検討しましたが、2年間を使うほど興味を持てる専門分野がその時点では考えつかなかったのでMBAにすることに決めました。その過程でなにか深めたいものが見つかったら卒業後に別の修士課程を検討しても良いだろうし、とも考えました。
プログラム選びについて
『MBAに行くなら絶対トップスクールのフルタイムでの濃密な学校生活だ。対面でのディスカッション、教授や学生、卒業生とのネットワーキングこそがMBAの価値だからだ。それ以外は高い金を払う意味がない。』という意見は、実は私も賛成です。私があと10〜15歳若かったら、かつ、自分が憧れる会社で働いていなかったら、卒業後のキャリアチェンジやステップアップを志して、受験勉強に時間をかけてトップスクールにチャレンジすることは当然の選択に思えます。
ただ私の場合は、前述の通りすでに自分が憧れる会社で働いていること、社会人としてのキャリアも中盤であること、すでに米国に住んでいることなどから、仕事を辞めてのMBAのメリットを得られないと考えました。そうすると、働きながら無理なく通えるプログラムということで、近所の夜間・土日のプログラムか、オンラインということになります。しかしいくら近所でも通学となると仕事への通勤に加えてどうしても往復1時間〜はかかってしまうので、オンラインの方が効率が良いと判断しました。
次に受験ですが、レジュメやエッセーに加え、通常はGMATまたはそれに類するテストスコアが要求されることが多いようです。米国で教育を受けていない人は英語力の証明としてTOEFLかIELTSも要求されます。日本人で受験された方のブログなどを拝見するに、多くの方がこれらの準備に2年くらいかけているようでした。予備校に通われる方までいるようで、しかも目標の点数が取れるまで数万円の費用をかけて何度も受験するなど、かなり大変そうな印象を受けました。今思えば、まず一度受けてとりあえずどのくらいの点数になるのかを知るなどしてみても良かったのですが、私はこれらのテスト対策に時間とお金をかけるのは前述のMBA取得の目的からすると無意味に思えたので、免除があるプログラムのみを検討しました。また、開始時期が年に1回のプログラムは合格から入学まで半年以上待たなければいけないことになり、その待ちの時間も無駄に思えてしまい、すぐ始められるところの優先順位が上がりました。このあたりのPros/ConsはSpreadsheetに整理して意思決定の参考にしました。
GMATは職歴によって免除されることが多いので、まずAdmissions officeに問い合わせをして可否を教えてもらいます。英語力スコアの免除については明記されていませんでしたが、GoogleのUS officeで3年働いているので免除してほしいとメールしたところ、いずれの学校からも問題ない旨の返信がありました。面接もあるのでそこで見極めれば良いということだったのだと思います。
受験料はたしか高くても$100くらいで、受かる可能性も何もわからなかったので、とりあえず良さそうなところをいくつか併願することにしました。受験にはレジュメのほか、各校2〜3本程度のエッセー、2〜3通の推薦状が要求されます。これらの選考が通ると次はオンライン面接となります。レジュメとエッセーはオンライン添削サービスを利用し、その後はテーマが変わってもエピソードは流用できるので、自分で仕上げました。推薦状についても、こういうエピソードを入れてほしい、ここを強調してほしい、というたたき台を作り、それを現職のディレクター、日本時代のマネージャーなどにお願いして推薦状にしてもらいました。出願プログラム全てのエッセーを快く引き受けてくれたディレクター、マネージャーには本当に感謝しています。(余談ですが、このディレクターが私のキャリアに非常に協力的で、Product Managerへの挑戦もこのディレクターが話を持ってきてサポートしてくれました。)
面接は、Admissions officeの担当の方と1対1もあれば面接官が2名のこともあり、また、面接専門の外部のスペシャリストに依頼しているところもありました。質問はたしかエッセーと似たような内容で、志望動機やキャリアゴールなど一般的なものだったように記憶しています。英語が下手くそだとはいえ、現職では日々英語で仕事をしており、また自分のチームの採用面接も担当しているので、さすがに一般的な質問内容の面接で英語力的に困ることはなかったです。英語が苦手な方はまず色々なテーマに応用できる定番エピソードを5つ程度作文して、ひたすら練習されることをお勧めします。それで大体なんとかなります。渡米以前の英語学習についてはこちらのnoteに書きました。
結果としては、GMAT免除を事前に断られた1校は除き、受験料を払って出願した学校は全て合格しました。そのなかで最終的に候補にしたのはこれらの学校です。
Indiana University-Bloomington (Kelley)
University of North Carolina-Chapel Hill (Kenan-Flagler)
University of Southern California (Marshall)
合格後、卒業生の方などにお願いしてお話を聞かせていただき、自分なりの基準でUNC Kenan-Flagler Business School(以下KFBS)に決めました。決めたポイントとしては、
1)オンライン、オフライン共に大学・MBAランキングで上位である
2)事務局の方、卒業生の方が親切で信頼できる方々だった
3)STEM分野も強いMBA(Pythonでデータサイエンスを学ぶ授業もとることができました)
4)西海岸在住でテック企業勤務の自分が、普段あまり接点のない人が多くいそうな東海岸の学校
5)オフラインプログラムもオプショナルで参加可能
6)オンラインMBAプログラムを開始してから10年と比較的長い実績がある
7)UCSDでPhDを修了している夫が「周りに聞く限りその3校のなかで一番名の知れている、良さそうな学校」と言っていた
8)実際、アメリカ最古の公立大学という長い歴史と伝統がある
となります。学校選びは本人が何を基準にしたいかになるので、よほどの上位校でなければ色々な決定理由があると思います。
実際の生活
プログラムは、前半のCore(必修)科目とElective(選択)科目にわかれており、CoreではいわゆるMBAっぽい科目(マーケティング、会計、経済、データ分析、コミュニケーションなど)を、1科目10週にわたって学びます。1学期に2〜4つ程度の授業を並行して受講します。オンラインのリアルタイム授業は1科目週1回90分、17人1クラスで、全員がカメラon、発言やディスカッション内容も評価されます。授業の前には毎週3時間程度かかるビデオ教材と、課題、そして授業後には課題と中間・期末テストなどが科目により課されます。チームワークを重んじる学校ならではか、毎週授業時間外にグループワークがある授業も多かったです。とても良い経験になりましたが、皆忙しい社会人なので本当に大変でした。授業も課題もとにかく準備に時間がかかりますし、試験勉強などは何日もかかるので、土日に会社の会議室で勉強したりもしました。
後半のElectiveでは自分で好きな授業をとれるようになり、また、1科目5週間と比較的ライトになり、プログラムや勉強への慣れとともに英文を読むのも速くなり、ずいぶん楽に感じるようになりました。後半で印象的だった授業は、Story Telling、Innovation Technology、Leading in the Middleなど、いわゆる会社を経営する立場でなくとも日々実践できる内容だったり、今ホットな分野の話だったりするものでした。昨今のMBA不要論、MBA無駄論を受けてなのか、一般社員にもすぐに役立ちそうな内容が随所に盛り込まれていたように思います。
オンライン授業に加え、Core授業を取り終わったらオプショナルでSummitという3日間のin-personのイベントにも参加できます。私はカナダのバンクーバーでのサミットに参加することができました。ほかにもUNCのキャンパスや、Portland、South Africaなどでの開催もあったのですが、出産と育児のタイミングで参加できず、そこは少し残念でした。3日間のサミットは、その土地の研究者やビジネスリーダーを招いてのまる1日の授業、社会科見学、ディナーなど充実した内容でした。良い友人もできました。余談ですが、そのサミット中私は妊娠初期で1秒でも横になっていたいという体調、かつ、PMになるための社内面接の準備と本番がまるかぶりし、授業の事前課題と事後課題も同時に終わらせなければいけないという、人生で一番ハードな1週間だったように思います。しかもバンクーバーからカリフォルニアのサニーベールまでは夫とロードトリップで帰りました。結果的には面接も受かりましたし全部しっかりやり遂げたので、思い出深いイベントになりました。こうしてみるとやはり自分は体力と気力に恵まれているなと感じます。二度目はちょっといいかなという感じですが。
成果
昨今「意味ない」と言われがちなMBAですが、自分にとってはどうだったかという点を振り返ってみたいと思います。
よかったこと
大きな自信になった
ノンネイティブがクラスに多くて2〜3人という環境にもかかわらず、卒業時の成績優秀者のみが招待されるBeta Gamma Sigmaというhonor societyへ入会、つまり成績優秀者として卒業することができました。まぁ上位20%が条件ということなので結構な人数いるわけですが。卒業式でも入会者は特別に紹介され、自分の英語力不足をハンデとしない成績を残せたことをとても誇らしく思いました。いくつか点数が公開される授業ではクラスでトップのものもあり、また、エッセー課題で4週連続クラスの最高点だったときには自分の視点やライティング力が優れていることを認識できてとても嬉しく感じました。
クラスには有名企業で活躍している人たちや、米軍の幹部候補の人たちもたくさんいましたが、その人たちとグループワークを一緒にしてみると自分の仕事の仕方、考え方、人との接し方、理解の速さなどはアメリカ社会でも通用するんだと感じることもできました。今まで日本で長く働いてきてアメリカでの経験はGoogleの広告プロダクト部門という自分が製品も人もよく知っているところのみだったので、そういった基礎知識や繋がりのないところでも普通に仕事ができそうだと思えたことは、とても良かったです。
いっぽうで、やはり自分に足りないことを認識する場面も多々あり、悔しい思いもたくさんしました。馴染みのない話題でも自分の言葉で意見を構造化して述べること、人を説得すること、専門分野ではないところで自分を認めてもらうこと、などは本当に難しかったです。これからはより高度なコミュニケーションをとれるようにまた日々頑張っていこうと思います。
英語でのインプットのスピードが上がった
毎日仕事でもたくさんの英文ドキュメントを読んで、当然英語でミーティングに出て、という生活をしていたものの、いままでは仕事しかしていなかったので時間をかけて準備やフォローをすればいいと思ってしまっていました。しかしMBAを並行することにより、仕事に加えて課題の締め切りがあるのでどうしても読む速度や書く速度を上げなければならず、それが良いプレッシャーになり、プログラム終了後に英語の本を読んでみてかなり読む速度が上がっていることを実感しました。
ただ、語彙はやはり努力しないと増えないということも実感しました。何度も同じ言葉を調べてしまったり、曖昧な意味で記憶してしまっていたりというのは特に気になりました。書いて覚える、使って覚える、というのがやはり必要ですね。
英語でのアウトプットがそれほど苦にならなくなった
これは仕事との相乗効果ですが、原稿を丸暗記しなくてもプレゼンができるようになりました。伝えたいことさえ整理しておけば、それほど緊張せずにその場で考えながら話すことができるようになったのは、本当に大きな進歩です。しかしディスカッションの発言は前述の通りまだ不十分だと感じることが多いです。発言をする度胸だけはさらに強化されたのですが、伝わっているか、相手を説得できるか、という点においては自分の目指すところには全く至っていません。
Product Managerになれた
自分の目指すポジションに、プログラムを1年残して就くことができました。MBAを取りに行った目的のひとつ、自身の向上とそれに伴うキャリアアップが在学中に達成できたことになります。上記の自信や、多少は鍛えられたアウトプットがとても役に立ちました。PMの仕事で生かせそうなことを日々学べたのもよかった点です。PMを目指した経緯、社内転職のプロセスはこちらのnoteをご参照ください。
自分の狭い業界の外の人たちに出会えた
先ほども触れたのですが、私のアメリカでの経験はGoogleの広告部門のみなので、全く異なる分野、金融、コンサル、医療、メーカー、小売、サービス、政府、公共、軍、ファミリービジネスなど、さまざまな組織の、しかもメンバーからVPまで、本当に幅広い人と知り合うことができたのは有意義でした。KFBSは特に現役・退役軍人が多いプログラムのようで、全く知らない世界の話を聞くのはとても勉強になりました。当たり前ですがいろいろな人がいて、いろいろな考え方があって、なにか簡単なトピック一つに対しても正反対の意見が出たり、当たり前だと思われるようなことにも別なやり方が提案されたりと、驚くことも多かったです。
また、どんなことでも堂々と発言したり、質問や確認をするのは勉強になりました。どんな意見もブレストやディスカッションの場面では価値がありますし、いろいろな視点や考え方に気付かせてもらえました。いっぽう、聞いていなかっただけの人が挙手してついさっき説明されたことをそのまま質問することもあり、しかし皆特段気にしてもおらず、日本人的な日本人である私だけが「いや話ちゃんと聞いてなよ」と内心思っている、というようなこともよくありました。そういった心労の無駄遣いはしないのが良いんだろうなぁいうのも勉強になりました。
とても良いプログラムだった
教授陣、授業の内容、事務局のサポートなど、全体を通してとても質が高かったと思います。当然他とは比べることはできないのですが、素晴らしい教授にも出会え、オンラインでの体験がよくなるような工夫もたくさんあり、厳しくも楽しいプログラムでした。伝統あるUNC卒業生の一員として思い出に残るような、誇りを持てるような経験をさせていただきました。
自分にとっては良い時期に学べたし、仕事でのフィードバックループがあった
時期に関しては、一般的には遅いですが私の今の人生ではこのときしかなかったし、ベストだと言い切れます。日米での仕事のあらゆる経験があるからこそ、ああなるほど!と思えるトピックが非常に多く自分の実体験ともあわせて深く学ぶことができましたし、ディスカッションにも貢献できました。また、パートタイムMBAだからこその良さとして、昨日授業で学んだことを今日実践できるということもあります。授業に関するトピックで上司や同僚に話を聞かせてもらったり、自分の学びをチームにシェアしたりという機会もありました。2年間の休職期間を取らずとも少し仕事から距離をとって会社・仕事・自分を理解しなおすことができ、かつそれをすぐに仕事に生かすことができたというのはとてもありがたかったです。MBAをとるには遅すぎるのでは、パートタイムは価値がないのでは、と思っている方には、私にとってはそんなことはなかったとお伝えしたいです。
ただやはり、もっと早く学んでいればと思う科目はたくさんありました。科目に限らず、もっと世界が狭かった時期にこうして視野を広げていたらどうだっただろうとも思います。もし1社目で働いていた時にMBAで留学するという選択肢が自分の中にあって、かつ決断していたらどんな未来になっていたのだろう。こればかりはわかりません。今これを若い人が読まれていたら、ぜひいろいろと視野を広げて可能性を検討してみてください。
もっとこうすればよかったこと
総じて大満足のMBAでしたが、何事も振り返りが大事なので「また同じことをやるとしたらどこを改善するか」という定番の振り返りをしてみたいと思います。
テスト。最初から時間とお金の無駄と決めず、GMATかGREを受けても良かったかもしれないと思いました。(ないと思いますが)最初から良いスコアを取れて勉強せず出願できる可能性もあったわけで。テストスコアがあると、CMU Tepper、Michigan Ross、Berkeley Haasのオンラインプログラムも受験できます。
教授のオフィスアワー。質問は授業内と授業後の居残り質問で十分できたので、個別に教授にアポをとって質問や相談をしたことはなかったのですが、個人的な繋がりを作るためにもやってみるべきでした。
交流。後半ではPMへの転向もあり本業が忙しくなってしまったことで、単位を取るのに精一杯になってしまい、授業以外での交流をほとんど図ってきませんでした。いろいろと話せる友人が数人できましたが、もっとネットワーキングに力を入れても良かったと思います。
費用について
KFBSの学費は他のプログラムと比べても群を抜いて高かったです。とあるアメリカの財団からの奨学金少しと、会社からの補助(業務に関係する講座とかに補助が出ます)を引いて、オリエンテーション、サミットなどイベントの参加費用と交通費などを足して、全部合わせておよそ$90,000ちょっとくらいでした。改めて見るとかなりの金額になりますね。アメリカに住んで働いているのでまだ良いのですが、これが日本から仕事を辞めての私費留学となると為替やインフレもあるのでかなり大変になりそうですね。
最後に
終わってみればなんとかなりましたが、やはり働きながら学位をとるというのはそれなりにたいへんなものです。時間の制約、締切を複数抱えるプレッシャー、加えて私の英語力不足から来る思い通りに発言できない悔しさ、学ぶのに人の倍以上時間がかかることへの苛立ちと焦り、などなど、普通に暮らしていたら味わわなくて済む類の感情がたくさんあります。しかしネイティブのクラスメイトたちですら大変だと言っていたので、まぁ多分英語ができても大変なんだと思います。それでも前述の通り、私にとってはやってよかった、やるべきだったことの一つです。
2年3ヶ月のMBAプログラム期間の間に、アリゾナからカリフォルニアへの引越し、Covid-19で在宅勤務から出勤の日々への変化、結婚、妊娠、Product Managerへの転向、出産などもあり、本当に忙しい日々でした。国内外たくさん旅行もしましたが、旅行先から授業に参加できたのはオンラインプログラムの利点でした。(しかし産後2週間で授業に出たのはさすがに辛かったなと今思い出しました。90分座っているのもつらいですが、脳がついていかなかったです。)
これが可能だったのは、なんでも相談に乗ってサポートしてくれ、産後は家事も育児も全てやってくれた夫、そして運よく無事に生まれた我が子のおかげです。プログラムを決める際に相談に乗ってくださったりアドバイスをくださったTwitterのみなさまも、ありがとうございました!
MBAを修了してみて、人生に遅すぎるということはないとあらためて実感することができました。当然早い方が良いこともあるでしょうけれど、やらなかったことを後悔し続けるよりやってみて後悔するほうがいいですし、やってみて仮に後悔したら、それは後悔というより学びになるはずです。
仕事では相変わらずIC(Individual Contributor)なので経営とは遠いですが、Product ManagerはプロダクトのCEOのようなものだと言われることもあるくらいなので、プログラムで学んだことが生かされる場面が多そうです。すでにこれまでの仕事とは大きく違う裁量、意思決定の頻度と重み、部署を超えての協働の楽しさと難しさをひしひしと感じています。これからも次の目標に向かって、がんばります。
それではまた。

ビール1杯くらい奢ってやるかと思ったらサポートお願いします🍺
