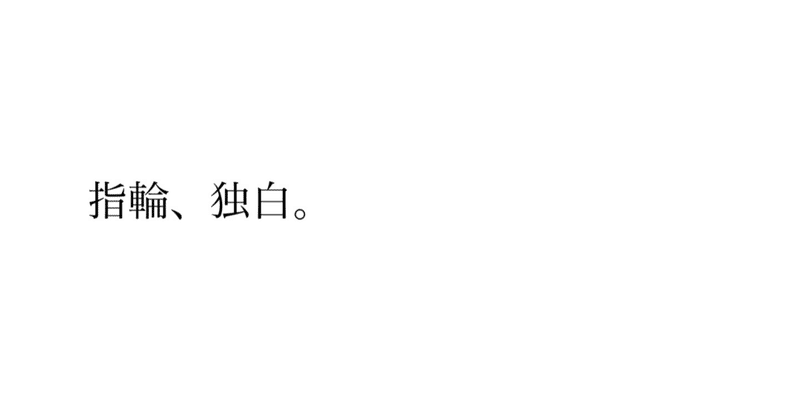
指輪、独白。
いつまでたっても君の薬指は空白のままで、いつまでたっても僕はそのことに気が付かないふりをして。いつかの帰り道、どこかの家から漂うカレーの匂いに涙した君の姿を美しいと感じてしまったから。こんなに壊れてしまった僕だから。
デートはいつもチェーンの居酒屋で、隣席の学生のはしゃぐ声で君との会話もおぼつかない。水みたいに薄められたお酒を飲みながら「おいしい」と笑う君の顔は泣いているみたいだった。会計の時、君はいつも前もって多めに僕に渡してくれて、この矮小なプライドを傷つけまいとしてくれた。そのやさしさに痛みを感じなくなったのはいつからだろう。
まじめに働こうとしたときもあった。みんなと同じように就活もした。大企業に入社するのだと疑わず、小さな会社を志望する友人のことを心の中で馬鹿にしていたのを覚えている。そんな友人は先月子どもを授かったらしい。SNS上で子どもを抱いて笑う友人の顔は、いつか夢想した大人の男性そのものだった。一方で鏡に映る自分の姿はというと、どこにも入社することができず、たいそうな夢もなく、ただ日々を派遣労働で摩耗している、それでいていつかドラマチックな変化が起きて事態が好転すると信じ切っている、気色の悪い幼さがにじみ出た風貌をしていた。あの日からSNSはすべて消してしまった。
君にプレゼントをしたときもあった。日払いの給料をその指輪につぎ込んだせいで、その日の君の誕生日は家でコンビニの惣菜になってしまったけど。「新しいネイルに合うね」指輪をはめた君のその言葉で、はじめてネイルが変わっていることに気が付いたっけ。そんな指輪もいつからか君ははめなくなっていた。僕がそのことを問いただすと「太っちゃって」と笑っていた。太るほど食費に使えるお金なんて僕らにはないのに。
休みの日は嫌いだった。特に君が仕事の時は。朝、君を見送ってから僕は世界で一人になる。一人になると考えたくもないことを考えてしまう。気を紛らわそうとテレビをつけると、みんな幸せそうに笑っていて、吐きそうになってくる。何回も読んで台詞まで覚えてしまった漫画に手を伸ばしてみるけど、内容が頭に入ってこなくてすぐにやめてしまう。そうこうしているうちに眠ってしまって、君の帰宅する音で目が覚める。よく夜になると死にたくなるなんて言う人がいるが、僕は違う。夜は君がいてくれるから、君が僕の生を肯定してくれるから。
君の生の肯定はなんだったのだろう。あの日、頭の中がぐちゃぐちゃになった僕は家を飛び出して、ひとりで浴びるほどお酒を飲んでいた。その帰り道、トラックの眩い光に体が包まれて。そこからの記憶はない。
君が最後に会いに来てくれたのは、もう10年も前だったかな。ずいぶんと皺が増えていた。本当はそのことを笑い合いたかった。お互いに歳をとったねなんて言いあいたかった。左手の薬指の埋まった君が呟いた「さよなら」は、今までで一番優しい響きがした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
