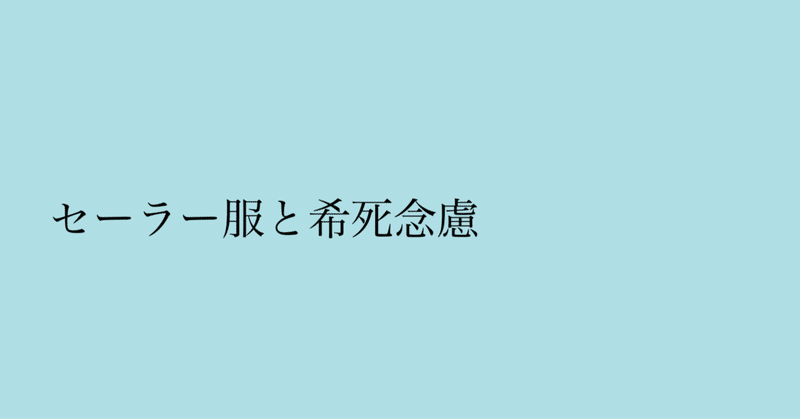
セーラー服と希死念慮
死ぬ機会を探している。なんでかなんて自分でもわからない。どちらかといえば恵まれた生活を送ってきたような気さえする。両親はぼくのことを愛してくれたし、友人も、恋人だっていた。もしぼくの人生に、映画の世界みたいにドラマチックな絶望があれば、ぼくは死にたい自分を肯定できたのかもしれない。でもそれは叶わなかった。絶望すらも、ぼくは持ち得ていなかった。ただ死にたい心だけを抱えていた。
最初は電車に飛び込もうとした。大勢の人の前で死ぬことは、ある種ドラマチックな気がした。電車がホームに侵入する音が聞こえた。足が震える。近づく電車の音より自分の心臓の音の方が大きいような気がした。もう少し、もう少し電車が近づいたら飛び込もう。
その時だった。ぼくの横を石鹸のような香りが駆け抜けていった。その香りの主がひとりの女子高生だったということに気が付いたときには、彼女は線路への最後の一歩を踏み出していた。瞬間、電車がぼくの前をけたたましい音を上げながら通過した。
そこからは早かった。電車は変にずれた位置で停車し、駅員さんたちが真っ青な顔で走り回っていた。どこかで嘔吐する音も聞こえる。ぼくはといえば、深く息を吐き、その場に座り込んでしまった。
美しかった。あの少女がなぜ死のうと思ったのかはわからないけれど、ぼくの横を駆け抜けた瞬間、あの瞬間彼女の命は光り輝いていた。そしてその光は一瞬にして消えてしまった。そのすべてがぼくの目にはこの上なく美しく思えた。
それ以降電車で死ぬのはやめた。彼女と同じ死に方をしても、ぼくにはあの輝きを出すことはできない気がした。自分なりの、美しい死を望むようになった。
とはいうものの、美しい死というものはなかなか思い浮かばなかった。首を括るのは死後の筋弛緩により糞尿にまみれると聞くし、オーバードーズは失敗のリスクが怖かった。それ以上に、一瞬の輝きを放つ死が欲しかった。
その輝きを手にするにはぼくには足りないものがたくさんあった。知識、経験、そして希望。あの女子高生の死があそこまで光り輝いていたのは、彼女がその未来を燃焼させたからだった。ぼくにはその燃焼させるに足るものがなかったのだ。
その日からのぼくはまるで人が変わったかのようだった。仕事に精を出し、家族との時間をなによりも大切にした。休みの日にはよく外出をするようになった。様々な場所に行き知識を蓄え、美しい景色を見つけることに注力した。この世界を愛おしいと思えるようなことならなんでもした。友人や恋人が悲しんでいたら、なんとかして励ました。世界には希望が満ちているのだと。
そんな生活を続けるうちにぼくの死への渇望は薄まっていった。あの少女の美しかったはずの瞬間に思いをはせる時間も日に日に減っていった。夜眠りにつくときも、明日への希望に胸を膨らませていた。
そんな日々が続いた時だった。いつものように通勤電車を待っていた時のことだ。電車の到着のアナウンスがホームに流れた瞬間、ぼくの横を一人の少女が駆け抜けていった。あっ、と思った瞬間には少女は線路に姿を消していた。電車はまだ遠くにいた。
急いで線路を見下ろすと、少女は気を失っているようだった。飛び降りた拍子に頭でも打ったのだろう。躊躇はなかった。
ぼくは線路へ飛び降り、少女を抱え上げた。この子には未来があるのだ。命に見切りをつけるには早すぎる。周囲の人間がホームの上から少女を抱え上げてくれた。ほら、君のためにこんなにも大勢の人が動いてくれるじゃないか。
ホームの上の人々が何か大声でぼくに訴えかけてきたが、既に間近に迫った轟音で何を言っているのか聞こえなかった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
