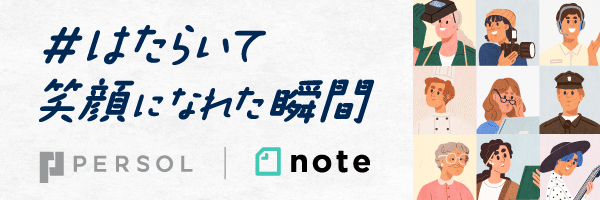はたらくことの喜びについては、だいたい恋ヶ窪の焼き鳥屋で学んだ
大学入学のために上京して、はじめて住んだのは国分寺市の恋ヶ窪というところだった。
とてもこじんまりとはしているものの、なんだかほんわかしたいい街だった。
何より恋ヶ窪という地名に惹かれた。
恋ヶ窪というそれだけでときめくような地名があるなんて、さすが東京だと18歳の私はとても感心したことをよく覚えている。
はじめて一人暮らしをした街なので、思い出はいくらでも汲み出てくる。
生まれてはじめて感じるような心躍ること、今でも辛いくらい嫌な気持ちになったこと、ここでは到底書けないことなど、こうして文章書いている今も鮮明に蘇ってくる。
その中で私がはたらく喜びとはどのようなことか、恋ヶ窪で学んだ出来事を書いてみたいと思う。
恋ヶ窪で生活していて起こったことの中で、もっとも素敵な思い出のうちの一つである。
それは今でも心の中の片隅で輝き続けている。
それは恋ヶ窪駅の近所の焼き鳥屋さんでアルバイトをした時に起こった。
私が「はたらく」という行為をしたはじめての場所である。
大学生になり、自由になるお金が欲しいとアルバイトを探していた。当時は超引っ込み思案でシャイだったので、なかなかアルバイト応募の電話をかけられなかった。
周りの人たちは、ファミレスやファストフード店などでアルバイトをするのが一般的であったが、私は同年代の人たちがたくさんいることに気遅れして、応募するのを躊躇していた。
きらきらしている同年代の人と接するのが当時は苦手であった。だからファミレスやファストフードには二の足を踏んでしまう。
しかし他にどんなところでアルバイトすればいいか分からない、という状況に陥っていた。
そんな時に恋ヶ窪駅から家へ帰るために歩いていると、小さな焼き鳥屋さんの扉にアルバイト募集のポスターが貼ってあるのを見つけた。
毎日通っていたのだが、その日は偶然、そのポスターが目に止まった。
そして「ここなら働けそう」というイメージが降りてきた。
きっとこの雰囲気の焼き鳥屋さんなら同年代はいないし、年配の人となら接することができるのかもと心のどこかで思ったのだろう。
お店の電話番号をメモして家に帰ってすぐにかけてみると、次の日に面接をすることになり、その場で採用された。
初出勤の日は朝から緊張の極みだった。大学入試だってこんなに緊張しなかった。
「はたらく」という当時の私にとって未知のことが、果たしてできるのだろうか。
不安でいっぱいだった。
アルバイト初日、お店のエプロンを締めると、いやがおうにもやるしかないという気持ちになった。注文の取り方や洗い物の仕方や掃除のやり方やレジの打ち方を必死で覚えた。
その店はまかないがあり、大将がお弁当を作って帰りに持たせてくれた。
初日は大好物のカツ丼弁当だったことをよく覚えている。
翌日はニラ玉弁当、その次は野菜炒め弁当とスケール感がだいぶ下がっていったので、初日はご祝儀的な意味もあったと思うが、大将の料理は美味しく、一人暮らしの私にはありがたかった。
慣れるまでは焼き鳥屋さんのアルバイトは大変で、苦労したことが多い。
私の主な仕事は客席で注文を取り、厨房で大将が作った料理を客席に運ぶことである。
「カシラタレで一本、塩で一本。レバータレで二本。ハツ塩で一本」などというオーダーがなかなか覚えられずに何度も聞き返してお客さんに嫌な顔をされた。
会計を打ち間違えて、10の位が一桁くらい違う金額を請求してお客さんからめちゃくちゃ怒られたこともあった。
飲み物を違う席に持っていってしまうことも最初の頃はよくあり、大将から指摘されるとともにたしなめられて落ち込んだこともあった。
しかし人は環境に慣れていくもので、しばらくすると通常業務は普通に行うことができるようになった。
特にミスがなく一日が過ごせる日が増えて、淡々と働くことができるようになった。
早くアルバイトが終わる23時にならないかなとちらちら時計を見つつ、お客さんの座るカウンターやテーブルと厨房を行き来していた。
アルバイトは週に4日くらい入っていたが、「今日もバイトめんどくさいな」と思いつつ、そこそこ仕事がこなせるようになり一定の満足感はあった。
仕事をそこそここなしている自分はまあまあできる人なのではないか、という思いですらいた。
働くってこんなもんかとある意味で達観したような不遜な気持ちでいたのかもしれない。
そんな気持ちを見透かすようにある時、とある常連のお客さんから言われた言葉を今でも忘れない。
「にいちゃん、ちょっと仕事できるようになってきてると思ってるけどつまんないでしょ。自分からいけばもっと面白くなるよ」
聞いた瞬間は酔っ払いが何を偉そうなこと言ってるんだと思い腹がたった。
アルバイトなんだから十分責任を果たしてるでしょ?と嫌な気持ちになった。
アルバイトなのに「自分からいく」必要があるのか、その言葉を聞いたすぐには疑問に思った。
しかし冷静に考えてみると確かに今の自分は最低限のことをやっているだけである。注文を取り、料理を運び、お皿やグラスを下げて洗い物をする。
受け身の仕事である。
常連のお客さんに言われたことに対して、そう言うならやってやろうという反骨心もなぜか芽生えてきて「自分からいく」とはどういうことをすればいいか考えてみた。
そこで一つ思い当たることがあった。大将は常連のお客さんでいつも一杯目に同じ飲み物を頼む人に対して、暖簾をくぐって入店してきた瞬間に作り始める。まだ注文は取っていないが、きっといつもと同じ飲み物を頼むので、先回りして作るのだ。
常連のお客さんが席についてすぐに飲み物を出せるので、客にとって嬉しいサービスである。
私はこれに乗っかってみることにした。
私はそれまでは、そんなお客さんにでもいつもマニュアル的に「飲み物はどうされますか?」と聞いていた。
大将がもう作っているし、お客さんも「ウーハイで」と答えるのは決まっているし分かりきっているのだが、私はとりあえず他のお客さんと同じような接客をしていたのである。
でも思い切ってそれをやめて、ある日そのお客さんが席に座ると同時に「いつも通りウーハイをもう大将が作っちゃってますけどそれでいいですか?」と言ってみた。
ちょっと馴れ馴れし過ぎで怒られるかと思いつつ言ったのだが、常連のお客さんは「大将が作っちゃったなら飲むしかねぇよ、にいちゃんも分かってきたね」と嬉しそうに返してくれたのだ。
大将も私のそんな接客に嫌な顔はしていない。
それがきっかけとなり私はお客さんに「自分からいく」ことができるようになった。
必ずチューハイの濃いめを頼むお客さんには、「チューハイ」と言われただけで「大将に内緒でかなり濃いめに作ってきますね」と言ってみたり、常連のお客さんの焼き鳥の好みを覚えて「今日も皮は塩が多めの良く焼きでいきますね」と言葉を先に添えることをした。
そうするとお客さんはみんな嬉しそうにしてくれるのである。お節介かなと思うこともあるのだが、個人経営の焼き鳥屋さんに来る常連さんは、自分のことを覚えて欲しい人が多いことに気が付いた。
できるだけ構われたくない人はチェーン店に行くだろう。
しかし私がアルバイトしていた個人経営のこじんまりとした焼き鳥屋さんに来るお客さんは、自分のことを認知してもらってこの空間で一緒に楽しみたいのだということがなんとなく分かってきた。
大将は積極的にお客さんに話すタイプではないが、包容力がありお客さんは大将に話を聞いてもらいたがっていた。
私はそれもよく聞くようにもなった。
大将に「そろそろ孫が産まれそうなんだ」という話をしていたお客さんがしばらくして来た時には「お孫さん産まれましたか?」と問いかけてみた。
そのお客さんは「なんでにいちゃん知ってるの?大将のやつなんでも言いやがるな」と言いつつかわいい赤ちゃんの写真を見せてくれた。
新生児微笑をしている赤ちゃんを見て、お客さんは満面の笑みである。私もそんなお客さんを見て嬉しくなって、思わず微笑んでしまった。
私はこの時に働く喜びが分かった。
アルバイトとお客さんという関係であっても、心を通わせることができる。
仕事を介さなければこのお客さんと出会うことはなかったし、赤ちゃんの写真を見て微笑み合うことなんて絶対にない。
歳も生まれた場所も何もかも違う人とでも、働くということを通して知り合い、喜びを共有することができる。
そしてこの喜びが得られるのは受動的ではなく、能動的に仕事をしようとしたからだ。
どんな仕事でも自分の態度次第で退屈になり得るしエキサイティングにもなる。
「自分からいく」という態度によってお客さんが嬉しい気持ちになり、自分も笑顔で働くことができる。
そんなことを分からせてくれた恋ヶ窪の焼き鳥屋さんには本当に感謝している。
卒業してアルバイトを辞めてからも、何度かは行ったが、とある日に訪ねてみると小綺麗なアパートが建っていてお店はもうなかった。
しかし、お店がなくなっても私の心の中にはその焼き鳥屋さんで学んだ、働く喜びとはどのようにしたら得られるかということがずっと残り続けるだろう。
この記事が受賞したコンテスト
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?