
時計街の錬金術士
『これをあなたが見ているって事は、きっと私はもう居ないんだろうね』
『――なんでかな。よく解らないけど、これを見つけるのは他でもないあなたのような気がする。それで、あなたの事だからきっと、他の誰にも見せようとしないだろうしね』
『色々伝えたいことがあったと思うんだけど、余裕がないとトンじゃうね。何言ったらいいかわかんないや』
『……だから、一番伝えたい事だけ伝えます』
『愛しています。あなたと同じ時間を過ごし始めた時から、ずっと』
† † †
壁に投射されていた映像は唐突に途切れ、音声はぶつ切りにされたように止まる。
暗寂のなか、座卓の上と床を手で探る。一通り探り終えた後、そういえばと思い至って胸ポケットに目当ての物を探り当てる。
「……ふー」
紙箱の中から一本の紙巻きを取り出し、先程まで手の内で弄んでいたオイルライターで火を付けた。肺を満たした紫煙を、密室という環境に感(かま)けずに吐き出す。
左手首を傾け、淡く光る蓄光塗料で針の位置を確認する。
――もうすぐ六時になるらしい。経過した時間を正しく認識すると、不思議と急に睡魔に襲われる。
ぼんやりとした頭にニコチンが効いてきた為か、そろそろ起きてくる同居人の存在に思い至った。
座卓の上に放り出していた、ネックレス型のアミュレットを回収し首にかける。今の今まで映像記録を出力していた宝飾品は、微かに熱を帯びていた。
「……」
この不思議なアクセサリーの中に記録を残した人間が、幻影となって俺に語りかけてくるような気がした。再び煙草を口に含み、思考を煙に巻く。
「おはよう、ございます。ジュンペイ。今日は、早いのですね」
背後から、幼さを残した女の声が俺に降りかかる。文節ごとに何と発言しようかと思案しているかのような、ところどころぶつ切りにされた喋り方だった。
「おはようニア。悪いがさっき起きた訳じゃない、いつも通りだ」
「そうですか。では、これから、就寝ですね。喫煙した、後なのですから、歯磨きを、してから、床に就いてください」
「……へーい」
内心舌打ちしながら立ち上がる。カーテンを開く音に振り向くと、俺より背丈も年齢も二回りほど小さい少女が、朝日を浴びて微笑んでいた。
その少女の美貌は、おおよそヒトのものとは思えない。少女らしいあどけなさや可愛らしさを併せ持つその『造形美』は、簡潔に表現するのであれば「神が造った」とするのが模範解答だろう。
白と黒を基調とした派手すぎないドレスは、過去の文献にあった使用人の出で立ちを連想させる。実際、主婦業に用いるには機能的であるとは彼女の談だ。
――この少女と二人きりの共同生活ももう十の年を数えそうであるが、ふとした瞬間彼女の出で立ちにはっとさせられることさえある。
「歯磨きが、面倒ですか?」
少女――ニアを見つめてなかなか動こうとしない俺に、彼女は首を傾げて問いかける。
「いや……まぁ、少しだけ」
「歯ブラシは、ここに用意、してあります。よろしければ、磨いて差し上げますよ?」
「要らん。自分でやる。くれ」
半ばひったくるように、小さな手から差し出された歯ブラシを受け取る。
口に含むと微かな辛みとミントの匂いが広がった。……いつの間に用意してたんだ?
「……そろそろ、ジュンペイは、生活習慣を、改めるべきかと、思います」
「ふぇいふぁふひゅーふぁんへぇ(生活習慣ねぇ)。ひふぁひ(しかし)、ひごふぉふぁひごふぉらひらぁ(仕事が仕事だしなぁ)」
俺がそう言う(?)と、ニアは少し寂しそうな顔をしてから、俺の腕に彼女の細い腕を絡めて引っ張った。
「歯、全部ちゃんと、磨けましたか?」
「ん」
「裏側まで、ちゃんと、磨きましたか?」
「――んや」
「磨いてください」
「……ん」
歯の裏を磨くことに意識を傾けながらニアに引っ張られていく。照明を付けていない薄暗闇の中でも、彼女は的確に俺を洗面所へ誘導した。
「ちゃんと、磨きましたか?」
「ん。ん」
世話焼きすぎる少女に少し呆れながらも、小刻みに首を縦に振る。
「はい。では、ペッして、うがいしてください」
「ッペ……あのさ、俺ァ要介護人じゃねーんだけど」
「うがい」
「…………はいはい」
硝子のコップに水を注ぎ、その何分の一かを口に含む。
――別に、毎日がこんな至れり尽くせり(悪く言えば軟禁監視)の状態である訳ではない。何というか、今日のニアはハッキリ言って過剰だ。機嫌が悪くてダル絡みされているようにさえ感じる。
「がんうぇばぼーばぁ(何でだろーなぁ)」
「……何が、『なんでだろう』、なのですか?」
「ペッ……いや、何でもねぇ」
――コイツの言語識別能力には時折恐怖さえ覚える。おちおち独り言もできねぇ。
「まぁいいや。俺は寝る」
「はい。おやすみなさい」
俺は自分の寝床へ向けて歩き出す。ニアも俺と一緒に歩き出す。
「いやいや……」
「どうしました?」
「何で付いて来てんの?」
問うても不思議そうに首を傾げるだけのニア。俺の名誉の為にもう一度言わせてもらうが、普段はこんなことは一切無い。幼女属性とかは専門外だ。
ニアは、黙して答えない。普段は俺の質問に対して愚直なほどに素直なのだが……。
その表情からは何も伺い知ることができない。元々感情表現が薄いタイプだ(先ほどの微笑は彼女にとって満面の笑みだったりする)が、やっぱり機嫌が悪いのだろうか。
「なんか俺、お前を怒らせるような事したか?」
「いいえ」
突き放すような物言いではない。あくまで純粋な否定だ。
「……何かあったら言えよ。家族なんだし」
「――はい、そうします。私と、ジュンペイ。二人の、家族です」
独り言のようにそう呟くニアは、少し照れているようだった。これくらいはもう慣れてもいいモンだと思うがなぁ。
「さて、俺は寝る。昼過ぎになったらテキトーに起こしてくれ」
……このままニアとぼちぼちはなすのも悪くないかと思ったが、このままではニアは家事に手が着かず、俺は次の仕事に支障がでる。
「わかりました。起きたら、ご飯を、食べますよね?」
「ん、頼むわ」
床一面に散らばったジャンクやら素材やらを踏まないように気を付けながら、俺は自室をゆっくりと前進していく。
その様子を、ニアは部屋の入り口でじっと見ていた。彼女には俺の部屋への立ち入りを禁じているため絶対に入ってこない。例外は、大晦日の掃除を行うときだけだ。
「なぁ、ニア。いつまでそこ立ってんだよ。俺もう寝るよ?」
物が散乱したベッドへようやっとたどり着いた俺はシーツの端を掴みつつ、未だに突っ立っているニアへ振り返る。
「――恐らく、ジュンペイが、そこで睡眠を、取ろうと、考えているなら、それは不可能だと、思います」
「は? 何でさ」
口では問いながらも、俺は掛け布団を捲り上げる。それがいけなかった。ちゃんとニアの話を最後まで聞けば良かった。
――俺の寝床に、素っ裸の女が入っていた。
† † †
「酷くないですか教官、据え膳を食わないどころか殴り倒すなんて」
「うっせ。マトモな服着ろや。あと教官はやめろ」
俺は煙草を銜えて火を付ける。一口紫煙を吸い込んだところでまた歯磨きをしなければならない事に気付き、煙を吐きつつ舌打ちした。
「えー? いーじゃないですかきょーかーん」
「……ハァ」
さっきまで俺のベッドに潜り込んでいた、このトチ狂った少女の名はサクラという。金髪碧眼の、明らかに和名に相応しくないルックスだ。
「サクラさん。昨晩は、ジュンペイに、話を通してあると、伺いましたが」
「お前……」
相も変わらず無表情なまま居間を片付けているニアの言葉を聞き、このガキは俺の不在中にニアに無理を言って押し入ったのだと理解した。
「あはは……それはまぁ、事後承諾して頂こうかと」
裸にワイシャツ一枚(俺の)を着込み(勝手に)、ニアが出した有り合わせの朝食をぱくつきながらサクラはニヘラと笑う。
「何が事後承諾だよ……どうせテメーのおめでたい頭で考えたプランじゃ、あそこで俺が襲ったら証拠を取って色々と要求する手筈だった、とかじゃねーの?」
「む、そこまでわたしはがめつくありませんよ。精々がこの書類に署名と判を」
「よくもまぁ婚姻届なんざ用意したなお前」
月並みだが、呆れを通り越して感心すら覚える。
「ジュンペイ。そろそろ、睡眠を取らないと、貴方の今後の、活動に、支障を来す、恐れがあります」
「……ん、もうそんな時間か。ロクでもねぇアホに意味なく説教して無為に時間を浪費しちまったな」
「そんなに無駄であることを強調しなくても良いじゃないですか酷いですー! 足痺れたー教官膝枕してくださいよー!」
「何でだよ一人で寝てろ。ていうかさっきまで寝てただろ」
正座させられながら飯を食っていたサクラは、そう喚くなり居住まいを崩して生足を床に投げ出す。……少し目で太腿を盗み見てしまうが俺は健全な男だから仕方ない。
「……せっかくですから、ジュンペイも、寝る前に軽く、朝食を、取りますか?」
ニアさん、アンタ目敏すぎだろ。間の取り方がマジでプロいよ怖ぇよ。
「いや、食うと寝付けなくなる。それより、少し早めだが『調律』を済ませる」
「わかりました」
言うが早いか、ニアはさっきまでゴミやら道具やらでごちゃごちゃだったフローリングの床をまさぐり始める。かちこち、とどこかで歯車がかみ合う音が、小さく部屋にこだまする。
「あの教官、調律ってなんですか?」
「……お前、一応錬金術士だよな……?」
思わず頭を抱える。ニアの方を見やると、流石に彼女は手際よく、作業を終えているようだった。
「……まぁいいや。一応、俺はお前の指導係だったしな。見せてやるから付いてこい」
床の一部がスライドして現れた竪穴を指差す。ニアはすでにはしごで地下に降り始めていた。
「一応を強調しつつ仕方ない感を出しながらもなんだかんだで面倒見が良い。そんな教官がわたし大好きです」
「はり倒すぞクソガキ」
「押し倒して乱暴しても良いですよ?」
ニコニコしながら顔を近付けてくる。本当にコイツは……。
「ジュンペイ。早く、してください」
ぬっと竪穴から頭を半分だけ突き出したニアが俺たちを睨んでいる。
コイツは意味も無く俺を急かすなんて事をしない。今日は本当にどうしてしまったのだろうか。
「行くぞサクラ。どうにも今日はニアの調子が良くない。もしかしたら『調律』に時間が掛かるかもしれない」
「よく分かんないですけど、了解です」
梯子を踏み外さないように注意を促してから、仄暗い竪穴をサクラに先行させて降りていく。――後でパンツ見られたとか難癖を付けられると面倒だからな。
「……もしかしてコレ、練金工房ってやつですか?」
「まぁな。大したモンじゃねーし、お下がりだがな」
そう、本当に大したモンじゃない。
あるのは合成炉に調律器。それから、数と種類だけは豊富な、用途がまちまちの練金具。
ここにある物全てが、近年の安価な量産型練金用品よりも劣ったパフォーマンスしか発揮しない。つまりはとびきりの旧式だ。
「ジュンペイ。こちらの用意は、出来ました。早く、始めましょう」
「そう急かすなって。ゆとり持って行こう」
俺は調律器のカバーを上げて布を取り、軽く鍵盤を弾いて調子を見る。白い鍵盤を押し叩くと、静謐な音を奏でた。
「教官、ピアノ弾けたんですか?」
サクラが俺の背中にくっ付いて、興味深そうに覗き込んでくる。やめろ鬱陶しい。
「たまたまだ。それにコレは練金具だ、楽器じゃない」
それぞれのキーを一つずつ、強弱をつけて弾いてゆく。音を聴き、調律器自体に狂いが無いことを確かめる。
「……問題なさそうだ。ニア、そっちは準備できてるか?」
「はい。万端、整っています」
何冊かファイルバインダーを抱えたニアが調律器の影から現れた。
「お、スコア取ってきてくれたのか。済まないな」
ニアから差し出された譜面の束を見ずに受け取る。バインダーの中からひとまずは毎回決まって演る譜面だけを取り出した。
「ひとまずはプレリュードで様子を見てからだが、今回はインターリュードを慎重に――」
「ちょ、ニアちゃん!? なんて格好してるんですか!」
思考を纏めるための独り言を遮られ、少し眉根に皺が寄ってしまう。
「おいサクラ、見学者が騒ぐんじゃ――」
「身に纏った、衣類を、全て脱いだ、だけです。別段、なんて事でもない、日常茶飯事です」
サクラへの説教を、今度はニアに遮られる。ちなみに彼女は、さっき書類を持ってきたときから全裸である。髪を束ねる留め具も外しているため、正に一糸纏わぬ姿と言えよう。
「おい、ニア……」
「そりゃわたしだって服くらい脱ぎますよ! でも教官という男性がいる前で何の脈絡もない脱衣は不健全なのでは!?」
お前が言うな。
「私は、必要性があって、ジュンペイに裸体を、魅せています。不純な動機で、脱衣する、貴女とは違うのです」
おーい、なんか「見せている」のアクセントおかしくなかったか?
「ぐぬぬ……ぺったんのくせに……!」
「所詮、バグだらけの、野生動物の分際で……」
顔と顔を突き合わせ、互いに闘志をぶつけ合う二人。サクラは低く唸り威嚇をする猛獣のように、ニアは一見冷静に見えて瞳の奥に闘志を燃やす蛇のように。
「おいお前ら、下らん事で喧嘩すんな。いい加減始めないと俺の睡眠時間がなくなる」
俺が困るという点を前面に押し出して仲裁を行うと、睨み凄んでいた二人はたちまちしゅんと小さくなる。
「ご、ごめんなさい教官」
「済みません、ジュンペイ。お手を、煩わせました」
二人揃って上目遣いで怯える様はまるで子犬の姉妹(きょうだい)を見ているようだった。
「別にそこまで怒っちゃいない。さっさと済ませたいだけだ。……ほれ、ニア」
「はい」
俺が両手を広げ、ニアがおずおずと抱きついてくる。首に腕が回されたのを確認してから、華奢な腰と脚を持ち上げる。完璧と表してもなお余りある肌の質感と肉の軟らかさが、ニアの芸術的価値の高さを改めて認識させる。
「あーっ! お姫様だっこ! ずるい!」
「ずるいじゃねぇよ」
これは『調律』を行う際には毎回行う慣習だ。ニアに毎回コレを要求されたお陰で、もう俺が自発的にやるようになってしまった。一体いつからだったか……。
地下の工房はそんなに広くない。ニアを抱き抱えて五歩も歩けば目的の装置に辿り着く。
「ありがとうございます。ジュンペイ」
「構わんが、お前ホントにコレ楽しいの?」
響束具という装置――魔術の書に記載があった、拷問具にも似た椅子にニアを降ろして座らせる。
「……『調律』中は、躰を、動かすことが、出来ません。視界も、無くなります」
「…………」
響束具からベルトを引き出し、ニアの剥き出しの胸部に巻き付けていた手が止まる。
「別に、ジュンペイを責めているのでは、ありません。ただ、不安なのです」
「……済まない、こんな半端物で」
本来なら、俺のような錬金術士のなり損ないがニアの『調律』を行うべきではないのだ。
やむを得ないから現状このような形に落ち着いているだけであって、俺以外に曲がりなりにも調律器を扱える錬金術士がいるならそいつに任せるべきだ。
この状況は、彼女の創造主への――何より、ニア本人への冒涜に他ならない。
「そうではありません、ジュンペイ。貴方の『調律』の腕は、最早、どの一流錬金術士にも、劣らぬものと、なっています」
俯く俺の顔に、血が通っていない事が信じられないくらい暖かい手のひらが触れる。
「じゃあ、なんで……」
「……貴方に触れられず、貴方の声が聞こえず、貴方の姿が見えない。それが、不安なのです」
ふと見上げると、ニアの瞳は優しい光で満ちていた。
なだらかな驚きを抱きながらも、俺は作業を再開した。四肢や首に悪趣味な桎梏めいた響束具を裸体のニアに幾重にも繋いでいく。
「お前も、結構子供っぽいトコあるよな」
「はい。まだ十五年しか、生きていませんから。てぃーんえいじゃー、です」
「はは、どこで覚えてきたんだそんな言葉。……目、瞑ってくれ」
「はい」
高純度の練金結晶すら霞ませる輝きを湛えた瞳が瞼に覆われる。眠り姫、という単語を想起させるニアの頭に腕を回し、煤のように黒い、アイマスクのようなヘッドギアを装着させる。
「……いつもと同じように行くからな。なるべく早く終わらせる」
「はい」
全身の可動部を一切の遊びを許さず締め付けられたニアは、声だけで返答する。心なしか、発声するのも辛そうだ。
細く溜め息を吐きながら調律器まで戻り、鍵盤の前に備え付けられた椅子に浅く腰掛ける。
「あ、あの!」
「あ?」
さっきから調律器の側でそわそわしているサクラが挙手していた。
「結局、『調律』って何なんでしょうか!?」
「…………」
自分の額に手を当てる。そう言えば溜め息って結構エネルギー消費するそうな。
「ニアは、見ての通り自動人形だ。だかr……」
「えぇっ!? そうなんですか!?」
「……まぁ、見た目だけなら判りにくいかもしれんが。当たり前だが、機械や人工物にはメンテが必要だろ?」
「あ、はい……? あいえ、そうですよね!」
俺の顔色窺って反応変えんな。ていうかマジでコイツ錬金術以前に一般常識大丈夫か。
「とにかく、だ。ニアには定期的にメンテナンスが必要なんだよ。アイツのカラダは人体に似せて造られているから、腹掻っ捌いて中身イジるわけにもいかねぇ」
「うぅっ、逆に他の自動人形はそうやってメンテするんですかね……?」
若干青ざめた顔でサクラが呻く。
「アホ。普通の自動人形はどっかしら継ぎ目なり開口部があるんだよ。ニアの場合、内部構造にそういう物理的なアクセスができねーから、この古くさい調律器を使って間接的にメンテを行うんだ」
一枚だけスコアを調律器の譜面台に立てる。形式としてはピアノのそれと変わらない、二段の五線譜に旋律が記されたものだ。題名は、『幕開け』。
「サクラ、終わるまで黙ってろよ。神経使う作業だ」
「はい!」
「いや、だから黙れよ」
「! ……!」
無言で力強く頷くサクラを流し目で見てから、俺は鍵盤に触れて一つ深呼吸をする。身が、引き締まる。
「……うし」
五線譜に散りばめられた音の地図に従い、演奏を開始する。ごく安易で単調、しかしこの曲は弾く度に表情をガラリと変える。音色がニアの体調に逐一反映されているためだ。工房に反響する音を拾う事に、一時の妥協も慢心も許されない。
元が譜面一枚の短い曲であることもあって、序律はすぐに弾き終える。演奏終了後の余韻も聴き取ったのち、覚えた違和感を元に主律に使う曲を脳内で選定する。
吟味のための黙考は十秒程度だったろうか、すぐさまファイルバインダーから複数の譜面を取り出す。それぞれが二~三枚の譜面で構成された曲だ。題名はそれぞれ、『流転』、『星』、そして『息吹』。中でも『息吹』は、ニアのお気に入りでもある。
俺は『流転』を譜面台に広げ、再び冷たく冴え渡った鍵盤に指を添えた。
† † †
「そうか、調律器の使い方までこの子にレクチャーしてくれたのか。ありがたいよ」
「あんなのは指導に入らねぇって。ただの実演だ」
ニアの調律終了より十二時間後の現在、俺は柄にもなくバーのカウンターでオールドグラスを傾けていた。実のところ、酒はそんなに好きではない。
「まぁまぁ、僕と君の間柄じゃないか。今日は日頃の分も兼ねて奢るから好きなだけ飲み食いしてくれよ」
俺の隣には、朗らかな顔でタンブラーを弄ぶ黒服の男が腰掛けていた。名を、アロウ・クロスェントと言う。
俺の元同僚で、サクラの上司だ。
「やったーアロウさん太っ腹! いっただきまーす!」
「食うとき喋んな。あとお前には奢るって言ってねぇぞコイツ」
「いやまぁ……奢るけどね? 君はお酒はダメだよ」
「ふぁーい!」
返事をするが早いか、サクラは目の前の皿に没頭する。
俺は煙草を銜え、火を点けた。奢りの申し出はありがたいが、外出前にニアの晩飯を食ってきたばかりだ。飯を食う気分じゃない。
「あれ、ご飯食べないんだ?」
「腹減ってねぇんだよ……。飯代がわりに今後サクラ(コイツ)がトチ狂った家凸してこないように首輪でも着けといてくれりゃそれで良い」
「むむっ! むごごもがっ!」
「喋んな」
米粒飛ばしてくれるなよクソガキ……。
「あはは、それは飲食代より高くつくよ?」
「フツーに仕事しろって言ってんだよ。しっかりしてくれ治安維持隊長殿」
――アロウは、この街に幅を利かせるマフィアもどきの幹部だ。彼らは『組織』を自称し、自警団なんかも編成してこの世界の警察を気取っていたりする。……まぁ、俺の古巣でもあるので若干の自嘲が入った表現ではある。
「ああそうだ、仕事で思い出した。今日は君に依頼があって来てもらったんだ」
にこにこと微笑みながら、アロウは鞄から数枚の資料を取り出した。写真も数枚添付されている。
「身から出た錆というか、身内の恥で申し訳ないんだけど、今回は組織の異端派閥の掃討を頼みたいんだ」
「穏やかじゃねぇな……仲良くしろよお前ら」
溜め息に紫煙を混ぜて吐き出す。両隣を非喫煙者に挟まれているので、上を向いて煙突のように煙を吐き出すほかなかった。
「ウチは元々、錬金術っていう強大な力を人々に平等に分配する管理組合として生まれたんだ。派閥争いだって当然起こる」
「錬金術自体は古代文明の遺物で、単なる道具だ。それに責任を求めんのもお門違いだろーが」
「お、さすがは現役の錬金術士。ありがたい言葉だよ」
「やめろ持ち上げんな気持ちワリィ」
――それに俺は、錬金術士としては半人前だ。ロクに使える錬金術など、両手の指で数えるほどしかない。
「まぁ、『組織』の人間全員が君ほど高潔な精神を持ち合わせてたら仲良くできるのかもしれないけどさ」
「持ち上げんなっつったろ」
「……いや、撤回するよ。君だって、組織から去っていったんだもんな」
アロウはどこかに遠い目を向けながら、タンブラーに入った酒をちびりと飲み込んだ。俺もそれに倣い、ロックグラスに口を付ける。
別に、『組織』の手足として動く生活に不満があるわけではなかった。ましてや、アロウがそこに負い目を感じる必要性なんて一切無い。
「俺は……その」
アロウの言動を否定するために彼女の名前を口にしようとした瞬間、心臓が鷲掴みにされる。その手の指は細長く、錆びた刃物のように俺の中心を鈍く侵食していく。
「アイツ、が……」
酒は十分に回っているが、なかなか言葉を切り出せない。――未だに、割り切れてすらいないのだ。もう九年は経ったというのに。
「……今日の僕は失言が多いらしい。ごめんね、ジュンペイ」
「…………別に」
苦し紛れに言葉を吐き、黒い情動を散らす為にフィルターを深く銜える。肺を満たしきるまで直に吸うと、煙はすっかり辛(から)くなってしまった。
「あれ? 確か教官いなくなる時は『嫌気が差した』とか『何となく』とか言ってませんでしたっけ?」
皿に盛られたチャーハンを片付けたサクラが首を傾げる。今は、この純真さ――いや、アホさがありがたい。
「建前真に受けてんじゃねーよ。……そういやあの時、お前はまだちんちくりんだったなぁ」
「ろりろりな十一歳でしたよ。……あの時は、わたしがダメすぎて教官に愛想尽かされたのかと思いました」
ニコニコしていたサクラの表情に、薄く影が差す。
――当時のサクラは、子供らしからぬ大人しいガキだった。今思えば、親類もなく『組織』でも浮いていたサクラが心から頼れる大人は俺だけだったのかもしれない。
「そいつは、済まなかったな。今更だが」
「ホントですよ。教官を慕うちっちゃい教え子をおいてけぼりにするとか。泣いちゃいましたよ」
彼女はこんな風に冗談めかして言うが、これでいて結構ナイーブな奴だ。
落ち着きがある奴だと思っていたが、それは悲しみから自衛するために感受性が死んでいただけだったのかもしれない。実際は小さい体と同じく精神も幼かっただろう。本気で泣かせてしまっていたのかもしれない。――そう思うと、さっきとはまた別種の痛みが胸に巣食った。
「……そんな顔しないでくださいよ。わたしバカですけど、今ので教官にも割り切れない、やむにやまれぬような事情があったのは、何となく解りましたから」
ほっぺたに米粒をつけたままで、サクラは儚く微笑んだ。イイ感じの雰囲気が絶妙にしまらない、そんなアホらしさも彼女らしくて笑えてくる。
「ククク……ああ、そうだな。お前は本当にバカだ」
「あーひどい! 人の気遣いに乗っかっちゃうとか! 建前真に受けないでくださいよー!」
お弁当の存在に気付かずぷんすかとむくれるサクラの頬を撫でて米粒を取ってやる。突然のボディタッチに唖然とするサクラの頭に、間髪入れずに手を置いて撫で回した。
「良い女に育ったな」
「な、なんですかいきなり……子供扱いしないでくださいよぉ……」
別に子供扱いなどしていない。歳は一回り離れているが、弟子が立派に育ち俺に近づいてきた気がして、嬉しかったのだ。
――いや、やっぱコレって子供扱いか?
「も、もう。撫でてれば機嫌直ると思ってるんですか? 教官のばーか。……ばーか」
「うっせ。大人しく撫でられてろバカ弟子。うりうり」
「あっ、それ……気持ちぃ…………」
「――――あの、僕お邪魔かな……」
すっかり蕩けた表情になってしまったサクラの頭をいじくっていると、隣から気まずそうにアロウに声を掛けられた。
「ああ済まんアロウ。別に存在忘れちゃいなかったぞ」
「むしろ第三者の目があることを意識しながらそんなギリギリの行為を敢行するとか正気を疑うよ……」
「多分、正気じゃないんだろ」
「うぅー、あーうー」
なでなでを続行しながらもくつくつと笑う。
――俺を狂わせた根元に触れられて、それによって生じた悲劇を知って。それでバカにバカみたいな慰められ方して。
全くもって冷静じゃいられない。きっと、心のバランスが壊れてしまったんだろう。酒も入っているしな。
「……ま、仕事の用件は最初に話し終えたしね。お代と一緒に資料は置いていくから、一通り目を通してくれると助かるな」
「了解、ゴチな」
「ぅあ、うーぁうー」
「……収拾着かなくなる前にやめてあげないと、面倒なことになると思うよ? それじゃ、おやすみ」
三人の飲食代には少々過剰な額の貨幣と溜め息をカウンターに残し、アロウは路地の闇へと溶けていった。
この瀟洒なバーは時間を感じさせることのない雰囲気作りを心掛けているらしい。――もしくは時計を買う金が無いのか。
手首を返して文字盤を見ると、もう少し暇を潰せば日が変わりそうな時間だった。
「たまにはその日のうちに帰ってやってもいいかな。……おい、サクラ。そろそろ出るぞ」
アロウが置いていった書類と金を手元に引き寄せる。……つもりだったが、その動作は側(わき)からしなだれかかってくる質量に妨害された。
「んむー、きょーかーん……」
俺の拘束(?)を抜け出したサクラが、俺に抱きついていた。彼女は俺の腕に両腕を――というか全身を絡ませるようにしてロックする。
「やめちゃ、やだー……」
じゃれる猫のように俺の肩に喉を擦り付けてくる。顔を真っ赤にしたサクラは、潤んだ瞳で物欲しげに俺の目をじっと見つめてくる。
「…………」
それに対して俺は、空いた手で無言のチョップを実行。
「――いったーい!今この瞬間にそれしますか普通!?」
「うっせ。場酔いしてんじゃねぇよクソガキ」
口の端を吊り上げながら、短くなった煙草を灰皿に押しつける。どうやら、いつもの調子が戻ってきたらしい。
「……その、ありがとな。サクラ」
「ほぇ……?」
何のことやらさっぱり、という顔をしている。本当にアホだコイツは。
だが、それで良い。
だからこそ、なのだから。
「むぅー……好き! 教官大好き!!」
「喚くな!」
「痛い!」
† † †
「ただいま」
サクラを『組織』の寮に送ってやってから帰ってきた。日が変わる前には帰るつもりであったが、そのせいで結局、腕時計の短針は文字盤の右半分へと傾いていた。
「おかえりなさい、ジュンペイ。今日は、早いのですね」
トテトテと廊下の奥からニアが駆けてくる。――帰宅直後に彼女の姿を見るのは、実に数年ぶりの出来事だ。
「今日は実働じゃなかったしな。たまには寄り道しないで帰るのも悪くないかと思って」
いや、正確には寄り道はしたのだが。深夜に女を送るくらいは、義務というか必要経費的労働みたいなもんだろう。
「休眠状態に、入る前に、貴方の顔を見るのは、久し振りな気がします。お腹は、減ってないですか?」
にこにこしながら俺の顔を見上げてくる。よほど嬉しいのだろうか、心なしかいつもより距離が近い。
背の低い彼女と目を合わせようとすると必然的に目線が下がるわけだが、今回は角度的に胸元の隙間から肌色が覗く形になる。
「……お前、下着とか着けないわけ?」
「下穿きであれば、調律や、躰の洗浄などの、脱衣が必要な、とき以外は、着用して、おりますが?」
「そうじゃなくて。上だよ上」
ニアには曖昧な物言いが通じない――知っていたことだったが、いい歳こいた野郎の口から発するのは何となく憚られる。
「……胸当ての、ことでしたら、私には不要と、判断しています」
……ああ、そう。
「済まん、戯れ言だ。少し酔ってのかもな。向こうで飯食わなかったから微妙に腹減った」
「わかりました。では、二日酔い防止も兼ねて、何か軽食を、作りますね」
頼む、と一言告げると、ニアは俺を迎えた時と同じく小走りでキッチンへ向かっていった。
少々嬉しそうな彼女の背中を見送り、俺は自室へ向かった。床に転がったジャンクを適当に蹴散らし、ベッドに腰掛けてアロウから受け取った資料を広げる。
粛清対象の大旨は、アロウから口頭で聞いた通りの過激派閥だった。何でも、人類全体を悪と見なし、この世界の崩壊を目論む輩だとか。
コイツらの狙いは、言葉で表せば単純明快。半径十キロ足らずのこのセカイの外壁を破壊する。旧文明が遺した不浄の遺物が街を侵し、生命は悉く死に絶える。
「百万殺せば英雄、ってか」
反吐が出る。胸ポケットから紙箱を取り出した。
「……やらかした」
どうやらバーで吸ったのが最後だったみたいだ。明朝まで待つ以外に選択肢は無い。
半ばヤケクソな気分になりながら紙箱を握り潰し、再び資料に目を落とす。
――頭の名は、アヴレイド。初老の男だ。活動履歴を参照するに、かなり血の気が多く衝動的な人物だと考えられる。
そんなオヤジの元に集う連中もなかなかに出来上がった奴らだ。テロリストと評しても行き過ぎではではない。容赦は、不要だ。
対象の拠点や構成員を頭に叩き込み、戦力を想定し作戦を組み立てる。『組織』に所属していた頃からの、間違いなく俺が一流と評価される仕事の一環だ。
「――殺しの腕だけ一流なんて、錬金術士の名が泣くな」
半人前の身で自嘲気味に嘯く。一種愉快な、ある意味嗜虐的とも取れる奇妙な高揚感を覚えながら紙束を捲っていく。
――すると、まるで見つかることを拒むかのように袋綴じにされたぺージを見つけた。ご丁寧に、そのページが一つの封筒のように拵えられている。
「なんだこりゃ……エロブロマイドでも入れてあんのかよ」
実直な性格に見合わず色を好むアロウのことだ。どうせ下らない遊び心でイタズラでも仕込んだのだろう。
様々なガラクタが転がっている床を二秒ほど見つめ、刃物を探すのを諦めた。少々乱暴だが、一応内容物を傷つけないように注意しながら紙袋の封を切る。
出てきた物は予想に反して、一枚の紙切れだった。手紙らしい。アロウの性格をよく反映した、無駄に几帳面な筆跡でただ一行のみの文章が書かれている。
事前調査にて粛清対象の拠点より押収したものだ。要確認。
A. Crossent
署名の下に、朱い輝き。ごく小粒な宝石がテープで貼付されていた。
見てくれはただの光る石であるにも関わらず、その用途はすぐに思い当たった。胸元に下げていたアミュレットを取り出すと、すぐにその宝石が嵌まりそうな窪みを発見する。
手紙が破れることも厭わずに、震える手で毟り取るようにテープをはがして宝石を摘む。
――呼吸が苦しい。鷲掴みにされた心臓が悲鳴を上げる。
二、三度失敗して宝石を取り落とす。気持ちを落ち着けようと煙草を探すも、胸ポケットは空だった。
「クソッ……」
小さな石を見失わないうちに拾い上げ、首に掛けたチェーンを外してアミュレットを座卓に置く。奥歯をかちかちいわせながら、果たして宝石はアミュレットの窪みにかちりと収まった。
心臓に、錆びた刃が突き立てられる。細く呼吸をしながらも、手だけは何とか止まらずに済んだ。
軋む胸を手で押さえつつ、遂に映像記録アミュレットの駆動スイッチをオンにした。
『これをあなたが見ているって事は、きっと私はもう居ないんだろうね――』
「は、はは……」
そうだ、何をビビってたんだ俺は。
いつもと変わらない、日常の一部と化した、習慣みたいなものじゃないか。
この虚像の中に、彼女は存在しない。あるのは、厳然たる事実のみ。俺が生きて、彼女は死んだ。
それだけだ。
『愛しています。あなたと同じ時間を過ごし始めた時から、ずっと』
壁に投射された映像の中の彼女が、瞳に涙を湛えながら微笑する。その幻影を見ていると、心臓を握る手の力が幾分和らいだ気がした。
「……そうだ。そろそろニアが、なんか作り終えたはずだ。早く、早く行ってやらなきゃ――」
映像が途切れるのも待たず、俺は立ち上がる。言い訳するようにぼやきながら。
『――――いやだよ、死にたくない!』
だがその言い訳は、赦されなかった。再び彼女の手が、俺の心臓を万力の如き膂力で締め上げ始める。
『やだ、死にたくない――死にたくないよ! やめてよ! 助けてよぉおっ!!』
「んだよ、コレ――」
本当は、何となくわかっていた。
小さな宝石は、記録映像出力装置(アミュレット)の追加メモリー。記録されている映像は、そのまま続きとなっていたのだ。
それはすなわち、彼女が嬲られ、殺害される様子。
『やめてっ、痛い! いたいよぉ! やだやだやだあああああっ!!』
『かっ……や、だ……じゅん、ぺい』
『助けて……淳平っ……だずげでよぉ…………』
† † †
ぱちん、と控えめな打撃音と共に、俺の頬に鈍痛が走った。
「……ジュンペイ、大丈夫ですか? 私が、解りますか?」
「――あ?」
どうやらニアに頬を張られたらしい。何げなしに腕時計を確認すると、帰宅してから二時間は経過していた。
「いや、そもそもお前さ、何で俺の部屋入って来てんだよ。立ち入るなって言ってただろうが」
こみ上げてくる虫酸を吐き出す代わりに、少々棘のある言葉を俺より一回り小さい少女にぶつけてしまう。
すると、ニアは怪訝そうに眉を顰(ひそ)めた。
「覚えて、いないのですか?」
「何がだよ……」
「ここは、工房ですよ」
「はぁ……?」
それじゃあ俺は、意識がトばして動いていたとでも言うのか。それじゃまるで夢遊病患者じゃないか。
辺りを見回すが、どうにも視界がボヤけて上手く周囲の状況が把握できない。今になって酒が効いてきたのか、悪酔いにも程がある。明日は二日酔い確定だな。
「ジュンペイ」
ニアが俺に憐れみの視線を向けてくる。彼女の顔はハッキリ見えている。そういえば、顔が結構近いな。
「――そんな目で見るなよ。やめてくれ」
俺の胴に回されたか細い腕の存在に気付き、振り解こうとする。が、少しでも外力を加えれば折れそうなその見た目に反し力は強く、なかなか俺を解放してはくれない。
「ニア、お前何がしたいんだよ。いい加減にしねぇと流石に……」
「ジュンペイ!!」
「っ!?」
ニアが声を荒げる。今まで一度たりとて起きなかった異常(イレギュラー)に、俺の思考は一瞬で消し飛んだ。
ニアが腕を解く。柔らかな熱が通(かよ)った小さな手が、俺の目元に添えられる。
「大丈夫、ですよ」
液体が拭われる感触。
――そうか涙が溜まって周りがよく見えなかったんだ。
事実に気付くと、急速に頭が冷えてくる。恐ろしいことに、俺の手には抜き身の刀が握られていた。
「……悪い。冷静じゃ、なかった」
刀を手から滑り落とし、穏やかに微笑むニアを抱き寄せる。ドレスの中の躰は、服の上からの見た目より更に細かった。
「何が、あったのですか?」
「……それは」
彼女の名を口にしようとすると、再び息が苦しくなる。どうやら俺の体内に巣喰った悔恨は相当に根が深いらしい。
全身から自重を支えるだけの体力が抜け落ちる。心臓が締め上げられて血が回っていないのかもしれない。俺は膝から崩れ落ち、小さな少女に、優しく抱き留められた。
「ゆっくりで、いいのです。無理をしないで、ジュンペイ」
「……」
頭を優しく包まれ、撫でられ、諭された。
ニアの暖かさと柔らかさに包まれているのが、心地良い。
バカみたいだと思った。
――俺も、ニアも。
俺は、十二年ぶりに人に縋って泣いた。
† † †
「――今回の仕事相手は、晴を殺した張本人だったんだ」
たったそれだけの事実。それを音にするのに、どれだけの時間を費やしたことか。未だ、俺は涙声だ。
「はい。九年前に、ハレは、私たちの前から、居なくなりました。他殺、だったのですね」
「ああ……。だから俺は、その犯人を炙り出して殺そうと思った」
当時の――今でも変わらず抱き続ける殺意を告白すると、俺の頭を抱く彼女の手に、少し力がこもった。
「……『組織』を、抜けたのは、アロウさんや、サクラさんに」
「そうだ。『組織』の連中を巻き込みたくなかった」
しかしそれ以上に、俺はニアを巻き込みたくなかった。
とは、言えなかった。
一緒に暮らしているのに。何にも代え難い、俺にとって一番大事な存在であるはずなのに。
彼女が俺に寄せる信頼を、俺は裏切り続けていた。毎日毎日、彼女が休眠状態に入ったのを見計らって晴の遺したメッセージを反芻(はんすう)し続けた。
それは、彼女に対する明確な背徳行為だ。
「ニア、ごめん。俺はお前を信じられなかった。晴のことを、お前に言いたくなかった」
「……ジュンペイ」
俺の頭から、ニアの腕が離れていく。抱擁を解(ほど)かれた俺は、自分でも驚くほどに狼狽した。
「に、ニア……」
ニアは、何も言わなかった。
代わりと言わんばかりに、額にやや熱っぽい感触が降ってくる。少々の湿り気を帯びたそれは、ニアの唇だった。
「家族でも、大事な人でも、隠し事をします。嘘を吐きます。当たり前です。人間ですから」
「……軽蔑するか? するよな」
一縷の安堵を覚えながらも、俺が彼女に縋ることがとてつもなく罪深いことに思えた。ついつい口から自身を卑下する言葉を吐き、免罪符まがいの自慰を行ってしまう。
「はい。正直に、申しますと、底無しのお馬鹿さんの、とーへんぼく、だと思ってしまいます」
「お前はホント、どこでそんな難しい言葉を覚えてくるんだ?」
俺が力ない笑い声を零すと、ニアが再び俺の頭を抱き締める。今度は抱擁と表現するより、ヘッドロックと称した方がニュアンスが近い。少々不躾に、薄くも確かな弾力を持った膨らみが顔に押しつけられる。
「――聞こえますか?」
「……ああ」
かちこちと、ガンギ車とアンクルが噛み合いを繰り返す音。それは、ニアの『鼓動』だった。
「私は、人間では、ありません。それでも、生きています。ジュンペイの、生きた、家族です」
まるで独白、もしくは宣誓であるかのように、ニアはどこまでも清らかに言葉を紡ぐ。
「私は、人間では、ありませんから、嘘を、吐きません。ジュンペイのように、気遣いや、大事な人を、傷つける、事を怖(おそ)れて、嘘を吐く、ということが、できません」
「……それでいいんだよ。俺は、手前(テメェ)の勝手な理由でお前を騙したんだ」
溜め息混じりに言い切ると、またしてもニアは無言で腕を解(と)き、今度は俺の瞼に唇を落とした。
「たった今、私は、自分勝手な理由で、貴方に接吻を、行いました。これで、おあいこですね」
一瞬惚けてから、後からこみ上げてくる苦い笑いを抑えることに苦心する。全く、いつからニアは俺を尻に敷くようになったんだ?
「それじゃあ、俺は俺の勝手な理由でこれからも嘘を吐くぞ。俺はお前を愛しているからな」
「はい。私は貴方を、裏切りませんから。安心して、私を騙してください。ジュンペイ」
みたび、ニアが幼さを残す顔を近付けてきて、夜空の星のような瞳を閉じる。
彼女の純真過ぎるキスが、俺の唇に注がれた。
† † †
目を覚ました頃には、腕時計の短針は九の目盛りを通過していた。一般的な水準としては寝坊も良いところだろうが、俺からすれば随分な早起きだ。
寝ぼけまなこをこすり、ベッドから這い出る。……朝に起きるってのも、たまには悪くない。
洗面所で顔を洗う。そう言えばタオルを持ってくるのを忘れていた。どうしたもんか。
「おはようございます、ジュンペイ」
「……おお、さんきゅ」
いつの間にか俺の脇に立っていたニアが俺にタオルを手渡す。……もしかして俺、ニアがいないともう日常生活すら送れないんじゃないか。
「昨日、作ったものでよければ、朝食が、あります。食べますか?」
「そうだな。結局寝る前に何も食ってないし、腹減った」
そう言ったところで、ちょうど腹の虫が鳴いた。昨夜は食事どころじゃなかったので、ニアが作った飯を食い損ねてしまったのだ。
「ふふ。用意しますので、食卓に着いて、待っていてくださいね」
流し目に微笑んでから、ニアは台所へと消えていく。その一連の動作が、何故だが妙に色っぽく見えた。
「……疲れてんのかね」
「もう少し、睡眠を、取りますか?」
ニアが台所からひょっこりと頭だけ出して覗いてくる。なんだそれ可愛いなオイ。
「気にすんな独り言だ。腹減った」
「はい、わかりました」
軽く頷いて引っ込んでいく。狂った調子を整えようと思い、胸ポケットに手を突っ込みかけた。コレで三度目だ。
「悪いニア、煙草買ってくる」
再びニアが頭を出す。今度は幾分機嫌が悪そうだ。
「40秒で支度しな、です」
「無茶苦茶言うなよ……」
「冗談です。数分したら、できあがるので、それくらいには、帰ってきてください」
「へいへい。三分間待ってくれ」
近所の雑貨屋に行くくらいならその程度の時間で事足りる。朝の外気を楽しみながら喫煙、というのは許してくれないらしい。
「……あと」
「あん?」
玄関で靴を突っかけていると、背後から控えめに声が掛かる。
「今回のご飯は、自信作です。できれば、一服前に、食べて欲しいのです」
「――あいよ、了解した」
ポケットに小銭があることを確認し、オイルライターを下駄箱の上に置いてから玄関を開けた。
「んで、何でお前居んの?」
「教官カレーですよカレー! カレーはよ! はよ!!」
俺が家を外した僅かな隙にサクラが上がり込んでいた。図々しいことに手にはナイフとフォークが握られている。……カレーなんだよな?
「おかえりなさい、ジュンペイ」
「いやまぁ、うん、ただいま。何でコイツ上げたんだよ?」
「サクラさんが、ジュンペイに、話を通している、と……」
「よくもまぁこの間と同じ言い訳が通ると思ったもんだ良かったなサクラ通っちまったよ畜生」
「えへへ」
「褒めてねぇ」
ニヘラと笑うサクラのこめかみに拳をあてがい、押しつけながらグリグリ回転させる。
「いだだだだいだいだだいだい!!」
「ニアもいい加減学習してくれ。じゃねぇとこのアホが更に救い様のないアホになっちまう」
「それは、非常に哀れです。ごめんなさいジュンペイ。猛省します」
「サラっとニアちゃんもひどい!? あ、でもわたしの事心配してくれてるみたいだし教官なりの気遣いだいいだだだだ反省します反省してます!」
涙目で喚くサクラに嘆息していると、漂ってきた芳(かぐわ)しいスパイスの匂いが鼻腔をくすぐった。
「なるほど、自信作ね」
「はい。一晩、寝かせたので、コクも増したと、思います」
その弁に基づくと、昨晩ニアは「何か軽食」と称してカレーを煮込んでいたことになる。確かに二日酔いには良いと聞くが……。
「すっごい美味しそうですよー教官! でもニアちゃんが、まずは教官に食べてもらいたいって。ていうか朝からカレーって珍しいですね」
サクラが目を輝かせながら早口を炸裂させる。お前どんだけカレー食いたいんだよ。
「いや、そもそもお前は何で食う前提なんだよ」
「いえいえむしろ食べる以外の選択肢がありません」
「太るぞ」
「たとえわたしがぽっちゃり体型になっても教官を悩殺してみせます!」
「ふざけろ」
最早コイツのアホ会話に付き合うのもアホらしくなった。双の拳から解放してやる。
「ハァ……つー事だニア。悪いけど、用意できるか?」
「はい。元々多めに、作っていますので、サクラさんも、お掛けください」
くすくすと笑いながら、ニアが皿にご飯を盛りつけ始める。その様子をサクラが爛々とした眼差しで見つめる。しっぽをぶんぶん振る犬のようだ。俺はそれをほっといて食卓の席に座る。
「お待たせしました、ジュンペイ」
静かに白磁のプレートが置かれる。盛りつけられたカレーライスは、食欲をそそる香りと湯気を立ち昇らせていた。少し大きめのスプーンを受け取り、手を合わせる。
「いただきます」
「はい、召し上がれ」
合掌もそこそこに、スプーンで白飯とルウを掬い、口に運んだ。
美味かった。元々家事の類は完璧のニアの渾身の作、美味くないわけがなかった。
「――どう、ですか?」
「美味いぞ。多分、俺が食ってきたカレーの中では一番」
誇張や世辞で言っているんじゃない。騙しているんでもない。本当に、美味かった。
「流石に、それは大袈裟だと、思いますよ」
ニアはかぶりを振るも、まんざらでもなさそうだ。
「ニアちゃん! 早くわたしの分も!」
「はい、どうぞ。三人で、一緒に食べましょう」
辛抱堪らないと言わんばかりの勢いでサクラが俺の向かいに就き、ニアが皿を並べる。そしてニア自身も自分の皿を持ってきて、俺の隣に座った。
「いただきまっす!」
「頂きます」
熱々のカレーライスにも関わらず、サクラは猛スピードでかっこんでいく。ニアはスプーンの上に乗せた分に息を吹きかけて冷ましつつ、ゆっくりと食していた。
「熱っ! うま、うまっ!」
「サクラさん。カレーは、逃げませんから、少しゆっくり食べましょう。……美味しく、できましたが、まだ更に、高みを目指せますね」
ニアさんよ、アンタはいつからそんな料理人気質な事を言うようになったんだ?
「ニアちゃん、これお店出せますよ! きっと『組織』も出資してくれると思うし! て言うかお金払ってでも毎日ニアちゃんの料理食べたい!!」
「ニアで自分の欲求満たそうとすんな」
サクラの提案を俺が即刻却下する。この街で新たに事業を始めるのなら『組織』に話を通さなければ始まらない。が、今更『組織』と新たなパイプ築いても、俺達にとってはメリットが殆ど無い。結果儲かるとしてもショバ代増えんの嫌だし。
それにニアの家事が疎かになったら困るし。
「私は、ジュンペイと一緒に、暮らして、喜んでもらえれば、それでいいのです。あまり、開業などには、興味を持てません」
取り留めなく思考していると、当の本人であるニアがサクラの願望をぶった切った。
「あーあ、フラれたちゃったぁー」
「残念だったな」
落ち込むサクラを余所に、カレーライスを口に運んでいく。しかし本当に美味いなぁ……。
「ぐぬ、他人事(ひとごと)だと思って……ハッ、教官と結婚すれば、毎日ニアちゃんの料理が食べられる……!?」
途端サクラの眼光が鋭くなる。完全に獲物を狙う猛禽類のそれだ。
「教官! お付き合いを前提に結婚してください!! そしてニアちゃんはわたしに毎朝ミソシルを作ってください!!」
言っている事自体が支離滅裂で、順序も立場も滅茶苦茶だ。
「お前は一体、どこへ向かっているんだ……」
「……てまえみそ、というものですが、カレー、美味しいですね」
心の底から吐いた俺の溜め息と、ニアの下手くそなお茶濁しが見事に重なった。
† † †
「ニア、昼過ぎくらいまで工房に篭もる。危ないから途中で入ってくんなよ」
洗い物をするニアに予め注意しておく。錬金術ってのは少しの失敗が大事故になりかねないので、特に俺のような半端者は神経を使う。工房が地下にあるのも、最悪錬金に失敗しても地上階を含めた周囲をまとめて吹っ飛ばさないようにするためだ。
「はい。その後は、どうしますか?」
「昼飯食ってから出掛ける。今日は長丁場になりそうだ」
「承知しました。ですが、昼食も、カレーです。ごめんなさい」
口では謝りながらも、ニアは上機嫌であまり悪びれてないみたいだ。俺も口の端を上げながら頷く。
「構わないさ。あと一週間くらいはそのカレーで行けそうだ」
「そうですか。でしたら、もう少し、多く作っておけば、しばらくは、横着できましたね。残念です」
ニアが悪戯っぽい笑みを微かに浮かべる。まだ固さはあるものの、最近の彼女はいつになく表情などの感情表現が豊かだ。
「あっ教官、わたしに教官の錬金術見せてくださいよー。『調律』以外も、教官の錬金術実際に見てみたいですー」
地下への梯子に足を掛けたところでサクラが寄ってくる。俺は『組織』に居た頃にサクラと師弟関係を結びつつも、実のところロクに錬金術を実演したことはなかった。
「……昔から言ってただろうが。俺の錬金術は半端なんだよ。お前が見ても得る物は無い」
昔から、サクラに教える時にはまず座学だった。実演の必要があれば『組織』の錬金術士に頼むか、俺が監督してサクラ本人にやらせるか。
『組織』内でのサクラの活躍は、アロウ経由で度々耳に入ってきていた。知識方面ではまだまだだが、練金の腕は既に俺を上回っている。
「でも、昨日の『調律』はスゴかったと思います!」
「九年もやってりゃあれくらいできて普通なんだよ」
むしろ合成や抽出など、基本的な錬金術が未だに大してできない時点で及第点以下と評価できる。
「……じゃあ、今度わたしに調律器の弾き方を教えてください」
むすー、とサクラは頬を膨らませる。……それ、お前の仕事に一切関係ないよな?
「まぁ、気が向いたらな」
「絶対ですよ?」
「気が向いたら、な」
「むー……」
むくれるサクラが何だか可笑しくて、俺と目線を合わせようと屈んでいる彼女の頭に手を置き、ぽんぽんと撫でてやる。
「また今度な、いい子だから」
「……そうやって、すぐ子供扱いする」
顔を赤くしてサクラが早足で居間から去っていく。手の掛かる元弟子だ、と少しの充足感を感じながら溜め息を吐いた。
「ニア。悪いけどサクラが退屈しないように相手してやってくれ。できれば追い出しといて」
「はい。多分、無理でしょうけど」
「だよなぁ」
絶対アイツは昼飯食っていくつもりだろうな。
「んじゃ、しばらくは任せたぞ」
そう言い残して地下へと潜り、地上への防護扉を堅く閉じた。
工房に降り照明を灯すと、床にブッ刺さったままの刀がお出迎えしてくれた。そういえば寝る前に放置してたんだった。
工房の床に穴を空けてしまったことにウンザリしつつも、柄を握って引っこ抜く。緩やかに湾曲し、黒く防酸化処理が施された刀身は、カミソリの様な鋭さと鎧の如き頑強さを両立させていた。
少々の時間なら眺めているだけで潰せるこの剣は、間違いなく俺の錬金術士生命での最高傑作だ。
「あーっと、鞘どこに行ったんだ?」
工房の一角に築かれたガラクタの山を漁る。刀とは別で放置していたが、幸いにも割と浅いところに埋まっていた。
そのシルエットはとても刀剣の入れ物とは思えない歪(いびつ)さだ。鞘そのものに小銃の撃発機構(レバーアクション)を組み込んでおり、自分で言うのもアレだが兵器としてはかなり無理のある設計である。割と最近に整備し、それからはまだ一発も撃っていないから大丈夫なはずだ。
一応、ループレバーを起こして排莢口(エジェクションポート)を開き、そこら辺に転がっていた真鍮の空砲(ブランク)を装填する。
排莢口を閉鎖し、トリガーを引く。
耳をつんざく炸裂音と金属同士の衝突音。無理矢理鞘に沿うようくっつけられた銃身から鯉口へ、太く短い射突杭が飛び出た。
「……フゥ」
飛び出した杭が銃身に引っ込むところを確認し、発砲済みの空砲を排出して動作確認を終了する。フルロードカートリッジの炸裂による衝撃で痺れた手首を軽くほぐし、硝煙を立ち昇らせる鯉口に刀を差す。
――これだ。この鞘走りの音。そして納刀しきった瞬間の鍔鳴り。これが堪らない。
「……いや、浸ってる場合じゃねぇって」
独り言で自制し、鞘に納めた刀を壁に立てかける。刀が倒れてこないのを確認して、乱雑に散らかった室内でも一際物が溢れた机の上を漁り始める。目当ての物は練金合成の法を記した調合書と、それらを実行するための素材。
「――さて、やりますか」
まずは一枚の紙切れと、弾頭や薬莢を握りしめて地下室のはす向かいに設置された合成炉に向かう。
一人でも扱えるよう小型化された炉に、材料や触媒、燃料を放り込む。ここら辺は結構アバウトだが、途中の計量や作業工程をミスると俺が消し炭になりかねない。集中力と気合いの勝負だ。
気を紛らわす為に煙草を吸いたくなる衝動をぐっとこらえ、俺はライターで炉内の燃料に火を付けた。
† † †
教官が地下室に潜ってから、わたしはマンガという絵本のような物を読んで時間を潰していた。家事の最中にちょっかいを掛けられるを嫌がったニアちゃんが貸してくれた、彼女の私物だ。
「…………飽きた」
絵は上手なのだがストーリーがなにぶん稚拙で、目新しさを感じた初めは良かったのだが、今では紙束をペラペラして遊んでいる始末だ。
「退屈でしょう、それ」
ちょうどそこに、洗濯物を干しにベランダに出ていたニアちゃんが戻ってきた。向こうから話しかけてきたってことは、今は手が空いているって事でいいのかな。
「ハイ、すごく。絵は良いのにもったいないですよ」
「私は、作者ではないので、そう言われても、なんとも」
僅かに苦笑しながらニアちゃんはソファに腰掛けた。一見ぼんやりと休憩しているように見えるが、その視線は絶えず地下工房の入り口に注がれている。
「……ニアちゃん、てさ」
「はい?」
数秒の沈黙にも耐えられず、見切り発進で喋り出してしまう。ニアちゃんがこちらに目を向けている。なにか、意味のあることを話さなければ。
「あーいや、答えにくいことだったら別に良いんですけど、教官とニアちゃんって、どうして二人っきりで暮らしているのかなー……なんて」
これじゃあまるで牽制しているみたいだ。いやそういう意図がまるでないと言えば嘘になるけど。
わたしの問いに対して、ニアちゃんは逡巡するような素振りを見せた後、薄く目を閉じて短く息を吐いた。そんな人間くさい所作をする彼女が、人工物であることが未だに信じられない。
「それについて、お話しするには、まず私の、生い立ちから話す、必要がありそうです」
「あ、それちょっと気になります。教官がニアちゃんを造ったって訳じゃなさそうですし」
教官は自分を半端物だと言っていた。ニアちゃんのような可愛くて性格の良い自動人形を造ったような人であれば、少なくとも錬金術士としての力量が足りないなんて事は言わないんじゃないだろうか。
「長い話に、なりそうです」
「だいじょーぶですよ。教官が戻ってくるまでまだ掛かりそうですし、退屈してるとお腹減りそうです」
「それは、いけません。サクラさんの、肥満化を、防ぐためにも、昔話を、披露しましょう」
「あーっ! そういうこと言う!?」
ニアちゃんがくすくすと笑い始める。わたしも最初はむくれていたものの、いつまでも笑い止まないニアちゃんを見てるとこっちまで吹き出してしまった。
――そう言えば、昔は、教官が私の大きなミスをしたら笑ってくれてたな。それでわたしも貰い笑いしてたら、ヘコんでいたのが嘘みたいに楽しくなっていたんだっけ。
『組織』を去ってからの教官はどこか疲れたように笑うようになった。今の彼もどこか哀愁が漂うダンディな感じで素敵だけど、わたしは前の飄々としている教官も好きだったな。
「ふふふ……。では、そろそろ、始めますよ」
「にひひ……あ、お願いします」
……もしかしたら、教官に影を落とした出来事が知れるかもしれない。そう思うと、期待のような、恐怖のような、不思議な感情で胸が詰まる気分だった。
‡ ‡ ‡
――私の躰は、エイク・メギストスという、錬金術師の、手によって、製造されました。
彼の、錬金術の手腕は、非常に高く、彼が創造した、この躰を、私は自分の、優れた点であると、誇りに思っております。
しかし、エイクは、私を、稼働させる事が、できませんでした。繊細な駆動部や、複雑な理論回路を、正常に、動かす為の、原動機関を、考案できなかったのです。
私が、稼働を開始したのは、十五年前の、出来事です。
彼の代わりに、私に命を、吹き込んだのは、ハレという錬金術士でした。彼女は、エイクが、弟子にするために、引き取った、元孤児の、少女です。
ハレは、絵を描いたり、お話を作るのが、好きな少女でした。よく、マンガを描いては、私に読ませ、感想を、求められたものです。
私が稼働を、開始してから、程なくして、もう一人の孤児が、エイクの元に、やってきました。それが、ジュンペイです。
我が家に、加わった直後の、ジュンペイは、口数が少なくて、私やエイク、ハレに鋭い目を、向けるばかりでした。
ジュンペイは、不真面目な人間では、決してなかったのですが、錬金術師であるエイクや、同い年にして、私の原動機関を創った、ハレに対し、劣等感が、強かったようです。
それでも徐々に、少しずつですが、私達の絆は、より親密に、より暖かなものへと、変化していきました。
老衰により、エイクが亡くなった際も、私達は互いに、団結して、生きていこうと、約束しました。ハレが私とジュンペイを、抱き寄せて、大声で泣き、ジュンペイも感極まり、涙を流していました。
まるで、つい、昨日の出来事のようです。もう、彼の死から十二年も、経ったのですね。
そして、ハレがこの家を、去ったのが、九年前です。
……はい。確かに、ジュンペイが『組織』から、抜けたのも、九年前ですね。
‡ ‡ ‡
「……で、なんでハレさんとやらがここから出て行ったんですか? ケンカしちゃったんですか?」
朝と変わらぬカレーを頬張りながら、サクラが純粋な興味本意からくるであろう好奇心を顔に丸出しにして訊いてくる。
「まぁ、そんなところだ。あと食う時は喋んな」
「ふぁーい」
サクラが食卓を囲む光景に慣れつつある自分に嘆息し、カレーを一口、また一口と掬って食す。やはり、ウマいな。
――サクラの相手をしてやる際に、俺達の過去を話したとニアから報告を受けたが、これならサクラを俺の事情に巻き込む事はなさそうだ。コイツの上司であるアロウだって、サクラを巻き込む事は本意でないはずだし。
「……ごちそうさま。ニア、これから仕事に行くが、その前に墓参りに行く。一緒に来るか?」
手早く昼食を済ませ、皿洗いに取りかかっているニアに食器を持って行く。彼女は手元から目を逸らさずに頷いた。
「はい、ご一緒します。少し、用意に、時間を頂たいです」
「構わないぞ。俺も用意があるし、着替えたい」
流石に煤だらけの作業着では、慰霊の相手に申し訳が立たないってもんだ。
「あっ、教官。わたしも一緒にお墓参りしていーですか? わたしも少ししたら仕事行かなきゃですし」
空の皿を運ぶサクラに尋ねられ、どうしたものかと一瞬迷う。まぁ、墓参りくらいなら別に良いか。
「別に構わんが、お前ソレ仕事間に合うのかよ。アロウにどやされんのは御免だぞ」
「だいじょーぶですよ。次の仕事は、ガルミス・アヴレイド一派の包囲兼突入部隊のサポートですから」
つまり、俺の仕事の補佐ということか。いやまぁ、確かにアロウがこの仕事を回してきた時点で、ヤツや部下のサクラが噛んでくる可能性は十分あったか。
「んじゃ、墓参りも一緒に行くか」
「はい! お供します!」
「用意するから待ってろ」
「お供します!!」
「着替えるっつってんだよ察しろアホ」
「いえ察した上で付いて行こうと痛いっ!!」
サクラのデコに軽く拳骨を見舞ってから、開けっ放しにしておいた床の扉に降りていく。練金工房の合成炉の一角から、焦げ臭いが黒煙と一緒に漂ってくる。
「……まぁ、悪くはないよな」
正直な話、手足が飛んでいないだけまだ僥倖と言える。
オーバーヒートした炉から出る煙は止めようがないので放置。壁に立て掛けておいた刀を肩に担ぎ、ガラクタの山から革製のベルトを拾い上げる。なめし革のそれはガンベルトと称される代物だ。拳銃嚢(ホルスター)は空だが、弾留め(バレットホルダー)に先ほど合成した弾薬を一発ずつ収納していった。
それだけ済ませて、とっとと地上に上がる。必要以上に燻製される趣味はない。
「……こんな事なら、昼飯食いに出てくる時に上げておくんだったなぁ。ゲホッ」
片手が塞がった状態で梯子を登り切り、扉を閉める。工房を出る前に浄化装置を起動しておいたため、そのうち合成炉も鎮火して空気が綺麗になるはずだ。
刀とガンベルトを適当に放って、洗面台に向かう。さっきのでまた手に煤が付いちまった。
「ジュンペイ、どうぞ」
「おお、スマン」
手を拭いていた俺に、ニアが駆け寄ってきて服を渡してくれる。それは、俺が『組織』で働いていた頃の仕事着だった。
「……一応これも、礼服ですし、派手さもないので、良いかと、思ったのですが」
俺が少し躊躇ったのを感じたのか、ニアは目を伏せる。まぁ、これ以外にロクな服の持ち合わせもないし彼女の判断は至極妥当だ。
「別にこれ自体は指定された制服でも何でもないからな。ていうか、未だに残っていたのに驚いたよ」
早速受け取った服に着替えるため、汚れた作業着を脱いで洗濯篭に入れる。しかしこんな汚れを毎回綺麗に落とすのは大変だろうな。
「じゅ、ジュンペイ……」
「ん? なにさ?」
「少しは、その、配慮していただけると、その、はい……」
ニアが顔を背けて歯切れ悪くぶつぶつと呟き始めた。何だ、やっぱり汚れモンを押しつけられるのは不満なんだろうか?
「ああー、済まん。やっぱ俺も自分の洗濯物くらい自分でした方が良いか?」
「…………はい?」
「…………いや、何でもない。ごめんなさい」
「はい」
笑顔が怖かった。目が笑ってないとか、そういうレベルじゃない。世界が永久凍土になる勢いだった。
しかし、俺は何に配慮するべきだろうな? ――そんな事を考えながらも、シャツを着てスラックスに脚を通し、首にネクタイを締める。ニアは俺をチラチラ見たり目線を外したりと忙しそうだ。
ハーネスを背負ってからスーツベストを羽織って着替えは終了。黒と灰の無彩色、それが俺の仕事着だった。
「ジュンペイ。ネクタイが、曲がっていますよ」
ニアの細い指が、俺の胸元に触れる。少し背伸びをしているのが微笑ましい。
「あまり、だらしがないと、エイクに見せる、顔がありませんよ?」
「はは、今の姿を師匠が見たらなんて言うだろうな」
首回りに僅かな圧力を感じる。どうせ後でズレまくるというのに、ニアは真剣な瞳で一分の狂いもないようにタイの位置を正していく。
「……はい、おしまいです。今日もお仕事、頑張ってください」
「おう、任せろ」
軽くニアの頭を撫でてから、置いておいたガンベルトを腰に緩く巻き付けて刀を差す。刹那に、俺の精神が入れ替わり、頭の中で掃除の手順が組み上がっていく。――遂に、終わらせることができるんだ。
「ジュンペイ」
背後からの軽い衝突は、冷徹に支配された俺の脳を再びじんわりと溶かしてきた。腰に回された腕は、彼女らしからぬ自己中心的な独占欲を言外に叫んでいる。
「……ジュンペイ」
だが彼女は、ただ俺の名を呼ぶばかりだ。「行かないで」の一言が、彼女の口からは発せられない。
ニアは人間じゃないから。
愛しているから、俺を裏切れない。
「――何してんだよ。そろそろ行くぞ」
ならば、俺はニアを裏切ろう。
俺は人間で、ニアを愛しているのだから。
「ジュンペイ、ジュンペイ……っ」
それでも、固く結ばれた手はほどける気配を見せない。その手に俺の手を添え、包み込む。
「大丈夫だって。いつもとおんなじ。だろ?」
「……はい」
「心配すんな。まだ、カレー食べ足りないんだ」
「はい、はい……」
「冷静になれよ。このままじゃ金が底を突いちまうって」
「はい――」
「――遅くとも、日が変わるくらいには帰ってくる」
「はい」
緩んだ両手に、俺の手を絡めて握りしめる。小さな手のひらは、俺の存在を何度も確かめるように握り返してきた。
「きょーかーん! まーだ時間掛かりますかー?」
玄関の方からサクラの声が飛んでくる。すると、いままでがっちり俺をホールドしていた細腕が、ぱっと離れていった。
「悪い、今行くぞー」
ニアの急変に戸惑いつつも、玄関にギリギリ届く程度の声量で返事をする。振り向くとニアは、小さく縮こまりながらもこちらをじっと見つめていた。
「行きましょう、ジュンペイ。サクラさんを待たせては可哀想です」
「そうだなぁ、アロウは結構時間に厳しいし、遅れでもしたら確かに可哀想だ」
ニアはさっさと歩いていってしまう。お陰で俺の言葉の後半は、半ば独り言のようになってしまった。気恥ずかしさのようなやりづらさを感じながら、俺も頭を掻いて玄関へ向かう。
「さぁ、エイクさんのお墓参りして、それでさっさと仕事片付けて、カレー食べましょう!」
「お前は結局ソレか……」
仁王立ちで鼻息を荒くするサクラに呆れながらも、ローファーに足を通すニアに倣い屈んで靴を履く。
「ごめんなさい、ジュンペイ。お察しの通り、今晩もカレーです」
特に悪気はなさそうに、ただ柔和に微笑むニア。注視すれば、その目尻に若干の水分が溜まっているのが分かる。
「そろそろ何かしら、バリエーションっつーか工夫が欲しいよな」
「ふふ、そうですね。何か、考えておきます」
「おお! カツカレーですかオムカレーですか! 楽しみです!!」
† † †
道すがら、花屋で菊の花を買ってから共同墓所までやって来た。師匠ほどの人物であれば墓所も結構な待遇が望めたが、生前は特別扱いを嫌った彼に配慮して俺と晴はこの街の人々と同じ墓所に彼を弔ったのだ。
草原に並び立つ墓石を数えながら歩く。師匠に詣でるのは毎年の慣例であるため、特に迷うことはなかった。
――エイク・メギストス、刻暦一一五四年没。たったそれだけが彫られた、飾り気のない墓標だった。
ニアが花を供え、サクラも黙って手を合わせる。俺はしばらく黙祷してから、胸ポケットから紙箱を取り出して、一本だけ入っている銘柄違いの紙巻きを銜えて火を付ける。
「……フー。最近じゃどこも、線香なんて置いてなくってさ。アンタの好きだった煙草だ。これで勘弁してくれ」
墓標の前に、吸い口を立てて置く。この煙草も、そろそろ廃盤になるそうだ。
「……サクラ、先現場行っとけ。俺が突入する時に直前情報皆無だと死ねる」
珍しく押し黙りずっと手を合わせ黙祷するサクラの肩を軽く叩く。自分以外が既に祷りを終えていた事に気付くと、彼女は少々照れくさそうにはにかんだ。
「あっ、はい。そうですね、じゃーまた現地にてお会いしましょー」
サクラは一度頭を下げると、手を振りながら元気良く駆けていく。一応もうアイツも二十歳(はたち)手前だというのに、いつもあんな調子だから年齢以上に幼く見える。せめてもう少し静かにしてればガキ扱いしないで済むんだがなぁ……。
「ニア、お前もそろそろ戻って良いぞ。付き合ってくれてありがとな」
「礼には、及びませんよ。そろそろ、エイクの、十四回忌ですので、その時はまた、ご一緒させてください」
「おう、そうだな」
俺達は頷き合う。が、俺もニアも動かない。動きだそうとしない。
「……お前がここまで強情とは、少し意外だったな」
「――申し訳、ありません」
ニアが軽く目を伏せる。薄い唇は真一文字に結ばれていた。
「……ホラ、これ貸してやるから」
俺はスラックスのポケットから小さな機械を取り出した。手の平サイズのカプセルから導線が伸び、イヤホンが接着してある。
「これは?」
「原始的なラジオだよ。最近造れるようになった。精度も拾える周波数域も狭いが、まぁ、お守り程度に」
半導体を利用するラジオは、錬金術入門としてよく造られる器具であるが、俺の腕ではこんな玩具紛いが精一杯だ。
「そうですか。では、ありがたく頂いておきます」
「使い物にはならんけどな。どっかの誰かが流してる音楽くらいは聴けんじゃねーの?」
「では、音楽を、聴いて、待っていますね」
目を細めて口の端を僅かに上げる。それが、ニアの最大限の笑顔であることを俺は知っていた。
「んじゃまあ、多分、また明日」
「はい。また、明日」
丁寧に腰を折って、ゆっくりと頭を上げる。ニアの仕草は何時も何処をとっても控えめで上品だ。
再度俺に微笑みかけてから、ニアは師匠の墓に背を向け去っていく。俺はその決して振り向かない背中を、建造物に遮られるまでずっと眺めていた。
――師匠の下に捧げた煙草がすっかり短くなった頃、俺は左腰に提げた刀を抜いた。
「……悪い師匠、使わせてもらうぞ」
柄を逆手に握りしめ、剣先を墓石とネームプレートの隙間に刺し入れる。少し力を込めて抉ると、石板は拍子抜けするような軽い音を立てて外れた。
現れた墓標の窪みには、拳銃が収まっていた。シングルアクションの回転弾倉拳銃。今や『組織』が自動式を採用している事を鑑みると、コイツは反論の余地なく時代遅れの旧式銃である。
俺はその銃を手に取り、空撃ちしたり軽くクルクル回してみたりする。マットステンレスの銃本体に歪みや遊び、錆は一切確認されない。古めかしいオイルドフィニッシュのグリップは、細かい傷があるもののカビや汚れは見受けられない。
銃身にはただシンプルに、墓標と同じく"Eik Megistus"と彫られているのみだ。
ソリッドフレームの装填口(ローディングゲート)に、今朝から工房で造っていた弾薬を一発ずつ装填していく。輪胴弾倉(シリンダー)に六発全てを込め終え、装填口を閉じて右腰のホルスターに納めた。
これで、戦いの準備は全て完了した。
……後は、心を清算するだけだ。
俺は、首もとのアクセサリーを外し、燃えつきかけている煙草の側に鎖ごと静かに置いた。帰ってきて、取りに来たくなったらまた回収すればいい。
外したプレートを元に戻し、立ち上がって煙草を銜える。そろそろ仕事の時間だ。
歩きながら、ガンベルトによって吊られた二つの質量を確かめる。この二つの重みだけが、今の俺を支えてくれる。
墓所を出たと同時に、オイルライターの蓋を開け、ドラムを擦って火を点けた。
† † †
「あ、教官。おはようございますー」
指定された集合場所に着くと、先に現場入りしていたサクラが目敏く俺を見つけて駆け寄ってきた。後ろにはアロウや、『組織』の連中の顔も見られる。
「おう、おはよう。もう準備できてんの?」
「はい、もうばっちりお膳立てしてますよ」
「そうか、なら良い」
会話を適当に切り上げ、俺は再び煙草に火を点けた。サクラも仕事の重要性を理解しているのか、にこにこしながらもいつものような無駄な口を利かない。
「やぁ、ジュンペイ。状況については理解してきてくれたと思うけど、一応確認だけね」
人通りの一切無い裏路地の薄汚い地面に、アロウは躊躇わずに上質なスーツで膝を突いて大きめの紙を広げる。
「アヴレイド一派の拠点は、雑居ビルに偽装してあるが上下二階のワンフロア二つに分かれている。激しい戦闘が予想される、注意してくれ」
アロウの説明を受け、内心ウンザリしながら紫煙を吐き出す。彼の言葉と内部図を信用するなら、連中は建物内に戦車だって入れられる事になる。
「彼らの身内が『組織』にどこまで潜伏しているかは、申し訳ないけど掴みきれなかった。だから、今回は不確定要素を除くために、周囲に僕らが展開して監視と立ち入り制限、電波妨害を行う。できれば僕らの直接介入は避けたいけど、狙撃班はここと、ここね。ヤバくなったら敵を狙撃地点に誘導してね」
「ふー……了解した」
前日、脳内で組み立てた戦術に新たな情報を付け加えて補強していく。考え得る内での最大脅威を設定し、それをベースに戦闘を組み立てればそう難しい事じゃない。
まだ長い煙草を銜えたまま、路地裏から出て雑居ビルへゆったりと歩く。根城の周囲に罠などが無いのはアロウ達が確認済みだ。
「……んじゃ、いっちょ行きますか」
鞘の装填レバーに手を掛け、排莢口を開いて空砲を装填。指をレバーに添えたまま、ビルの分厚い戸を押す。当たり前だが、鍵が掛かっていた。
行儀良くピッキングなんて真似はしない。右腰から拳銃を抜き、錠前と蝶番に向けて発砲。後は力ずくで蹴破って突入する。
周囲確認の為に首を左右に巡らす――前に、足首に僅かな抵抗。
ワイヤーだ。
「あっ、やっべぇ」
ドア枠から外れかけている扉のノブを乱暴に引っ張って剥がし取り、即席の盾にして身を守る。前方から爆裂音と衝撃。指向性地雷か。
「発破用の爆薬なら間違いなく死んでたな……連中も建物ごと吹っ飛ばすほどアホじゃなかったか」
盾にした扉を捨てて、銜えた煙草を一服する。外からの見た目より案外広い室内に、埃やら破片やらが舞い上っていた。
視界は少々悪いが、目立った遮蔽物が無い分、これ以上罠の心配をする必要は無さそうだ。人の気配もない。
上階はどう攻略してやろうか――そんな風に作戦の軌道修正をしていると、何らかの重量物が床のタイルを踏みしめる音がした。キュラキュラという無限軌道の音……キャタピラだ。
「……前言撤回。アイツらアホだ」
猛烈に嫌な予感を感じ、なりふり構わず横っ飛びに身を投げ出す。すると、それだけで体が飛ばされそうな発射音と共に、俺がさっきまで立っていた位置に砲弾が飛んでいった。実際に視認できたのは、砂埃が衝撃波に切り裂かれてできた弾道と、壁に空いた人間の上半身大の大穴だけだ。
視界が開き姿を現したのは、原動機を唸らせるずんぐりとしたフォルムの戦車型ゴーレム。砲塔が旋回しない旧型だが、人間一人を挽き肉にするには未だオーバースペックな代物だ。
ゴーレムは弾の再装填に躍起になってるようで、砲口をこちらに向けつつも一向に動かない。この距離なら俺を轢き殺した方が早くて確実だろうに……論理回路を設定した錬金術士は三流だな。
確かこのタイプは、人員を搭載する戦車と同じように上部と後部の装甲が薄かったはず。俺は銜えた煙草を深く吸ってから、ゴーレムの頭上を越すように放り投げる。すると、ゴーレムはまるで俺が背後に回ったのを追いかけるかのように旋回を始める。
――ダストで視界が悪い中、俺に向けて的確な砲撃をしてきたことから熱源探知であることは解っていた。まんまとゴーレムが俺にケツを向けるのを見やりながら、鞘のレバーを起こしてまだ発射していない空砲を排莢する。
代わりに、黒くコーティングされた空砲を装填。素早くレバーを引き戻し、ゴーレムの背後にぴたりと陣取り、構える。
「メギストス流、奥義」
刀がすっぽ抜けないようにしっかり握りつつも、腕は極限まで脱力する。腕力を込めると振りの速度が落ちるし、下手をすると肩が脱臼する。
腰を落として反動に備えたのち、トリガーを引く。
「『一葬』……!!」
焼夷炸薬が射突杭を押し出し、鍔を打撃して刀を高速で鞘から弾き飛ばす。人間の筋力では到底叩き出せない運動力を利用し、俺は超高速の唐竹割りを繰り出す。
杭を押し出して噴出した高温の燃焼ガスを纏わり付かせた刀身は、戦車型の装甲をバターのように引き裂いた。
間髪入れずに、刀を手放してリボルバーを抜く。装甲を斬っただけでコイツは止まらない。銃身をねじ込んで弾倉に残った弾を全て発砲する。心臓部を破壊されたゴーレムは、さっきまで怒ったように唸っていたのが嘘のように急停止した。
「フゥ……あ、ネクタイ曲がってる」
クールダウンの意味も兼ねてネクタイを直す。刀を拾って鞘に戻し、リボルバーを再装填する。旧式のコイツは再装填に十秒以上掛かるのが難点だが、この階に他の敵は居ないので問題ない。
人間は全員、戦車型の戦闘に巻き込まれないように上階に待機しているのだろう。ゴーレムの邪魔にならないようにする意図があってか、隙を突けるような死角は存在しないし。
戦力の逐次投入が悪手であるとは有名な兵法だ。まず間違いなくアヴレイド派閥の構成員全てで、上階を固めて籠城してくるはずだ。
策も無しに階段から突っ込めば、俺は飽和攻撃を食らって死ぬ。
「さて、どうすっかねぇ……」
俺は、斬り口を燻らせながら鎮座する戦車型ゴーレムに背を預けつつ、思考を巡らせた。
† † †
「報告します、導師アヴレイド」
「うむ、何だ軍首長。言ってみろ」
大儀そうに椅子に腰掛けるガルミスに対し、私は内心呆れかえる。この緊急事態に即してもこの男は、大物である自分を演出すること以外頭に無いのだ。
しかしそんな、ある意味不測に動じない大物という態度も、私の報告を受ければ容易に剥がれてしまうだろう。本当に、威張るか怒鳴るしか能のない男だ。
「……ゴーレムが破壊されました。一時的な継戦不能ではなく、完全に沈黙したようです」
「何……!?」
ガルミスの顔が見る見る赤くなる。その光景は私に、熱湯で茹で上がる軟体動物を連想させた。
「落ち着いてください、導師。今は怒りを鎮め守りを固めるべきです。密偵の話では、『組織』は表立って我々を攻撃することはできません。今回の強襲は少人数の……」
「ならば何故その少数にゴーレムがやられた!? 密偵が偽の情報を流したからに決まっている! これだから金で靡く低俗な輩は信用ならんのだ!! 貴様の責任だぞ軍首長ッ!!」
だとしたら、何故わざわざ密偵は襲撃の日時を正確に報告したのか――そう反論するのも煩わしい。
元々この派閥は、ガルミスの狂った思想に共感する狂信者か、際限なく暴力を振るいたいならず者の二種しか居ない。彼がこうなると、この面倒な事態に仲間割れという更なる厄介を引き込むことになる。
「聴いているのか!? 軍首長! 貴様の責任だと言っているんだ!!」
「はい、申し訳ありません導師。全ては私の責任です。もしその慈悲深き御心により一時ばかりの命を頂けるなら、賊を討ち倒し、彼の者に究極の絶望を与えてご覧にいれましょう」
これで間違いなく、私の派閥内での立場は悪くなるだろうが、背に腹は代えられない。今は外敵を除く方が先決だ。
「……う、うむ。その幾許ばかりの命、我の為に捧げよ」
「ハッ」
時期尚早だが、この老害は戦闘に巻き込んで殺そう。このまま私が事態を解決しても、この男は自身のカリスマを疑う事を知らないので、このままだと私の建前を真に受け本当に処刑を行いかねない。
――しかし、啖呵は切ったもののこれ以上私が出来る事は無い。一階からの階段は入り口を多数の武装した兵達で固め、窓から突入される可能性も考慮しつつ狙撃を警戒した配置を行わせている。もっと人員がいれば他の手も取れただろうが……全く、何が『軍首長』だ。
「――敵だ!」
「何っ!? 撃て! 全員撃ちまくれぇ!!」
私が目の前の無能への苛つきに気を取られているうちに、敵を発見した兵にガルミスが勝手な指示を出す。私が指示を出す前提で役割分担を決めたというのに、お陰で統率が滅茶苦茶だ。
「おいっ! 勝手に撃つな! 導師も皆を止めてください!!」
「えぇい五月蝿い! 賊を殺せ!!」
兵達は自分の持ち場を離れ、各々が手にした拳銃や小銃を階段に向けて乱射する。統制が乱れるどころか、向こうは一発も撃ち返してきてないのに誤射でこちらに被害が出ている始末だ。
こうなっては是非も無い。速やかに無能を始末しようと決意し、懐の拳銃を抜いて密かにガルミスを照準する。
辺りを見回し、全員が階下の賊に夢中であることを確認する。が、階段下から何か赤子大の物体が投げ入れられた事に気付き、私は体裁無く叫んだ。
「――射撃止めろ! 撃つな――――ッ!!」
投げ入れられた物体は、砲弾。戦車型ゴーレムが積んでいた物だった。
砲弾に銃撃を当てたのが、果たして敵なのか味方なのかは解らなかった。
閃光と轟爆が、炸裂する。私の体は紙切れのように吹き飛ばされ、床に叩きつけられて血反吐を吐いた。
兵達の射撃も止んでいた。皮肉にも、敵の一手が兵とガルミスの暴走を止めたのだ。
二つ目の砲弾が、先程よりも私の近くに転がってくる。程なくして、炸裂。逃げるどころか起き上がる間もなく私は再び宙を舞った。
「ぐ……クソ、ゴハッ……!」
またしても地面に叩きつけられた私は、何とか一矢報いようと身を起こそうと試みる。が、体が言うことを聞かない。
「こ……これは、貴様の不敬の報いだぞ軍首長……!」
死体の山から血塗れのガルミスが起き上がり、私に捨て台詞を吐いて屋上へ続く階段へと遁走していく。どうやら彼は、他人を盾にして生き延びたらしい。
「この…………!」
ここまで来ればせめて道連れに。そう思い、銃を握った右腕を伸ばす。が――
「あぁ……あぁ、クソ! クソォ!!」
右腕が、無くなっていた。
「おい」
ゾッとする冷徹な声が掛かり、反射的にそちらへ振り向く。
目に映ったのは、血の滴る黒い刃が
† † †
「……居ねぇな、アヴレイド」
刀の血振りをして、ぽつりと呟く。顔の判別がつかない死体も結構あったが、服装から見て下っ端で違いないだろう。
階下には一人も逃がしていないし、そもそも息のあった奴も自力で逃げられる状態ではなかった。
となると――
「……上、か」
階段に引き摺ったような血痕を発見し、刀を抜き身のまま担いで注意深く階段を上がる。屋上への扉は、ご丁寧に開け放されていた。
「――よくぞこの我の前に堂々と現れよったな、汚らわしい『組織』の犬め!!」
アヴレイドは弾丸よりも先に騒音と唾を飛ばしたくなる人物らしい。お陰で俺は、何の苦労もなく屋上に出ることができた。
「よう。ガルミス・アヴレイド……だよな? 殺しにきたぞ」
「ほざけ! 錬金術師である我に楯突こうなど――!!」
アヴレイドが俺に自動拳銃を向ける――よりも早く、俺はリボルバーを抜き撃つ。鉛玉は肩に命中し、アヴレイドは拳銃を取り落とす。
「ぐぎゃぁああああっ!? ききっ貴様! 一体何をしているか分かって……ぐぅううっ!?」
くずおれたアヴレイドにつかつかと歩み寄り、肩の銃創に刀を刺し入れて引き上げる。
「ピーコラうるせぇぞ爺さん。俺の質問にだけ答えろ。いいな?」
「ぐ、うぅ……うく、うくくくくくく」
頭がイカレたのか、それとも余程のマゾなのか、アヴレイドの呻き声は途中から気味の悪い笑い声に変わった。俺は気分が悪くなり、アヴレイドを落下防止用の柵へ蹴り飛ばす。
「ぐくっ、ぐふふふふ……知っているぞ、ジュンペイ・ヒラガ。お前が私に問いたいのは、ハレ・タンダが、殺された理由だな……?」
「何がおかしい?」
ヘラヘラしているアヴレイドの腿を撃つ。が、やはり何かがブッ飛んでしまったのか、彼は薄ら笑いを続けている。
「クハハハハ……! 我の動機はただ一つ、錬金術師である我を差し置き、錬金術の『真理』に触れたからよ……!」
「真理……? いや待て、お前の!? お前の身内以外に、共犯が――――」
俺の言葉は、最後まで続かなかった。
不気味に笑うアヴレイドの頭が、文字通りに吹き飛んだから。
男の頭が水風船のように弾けた後、一拍遅れて銃声が聞こえてきた。長距離からの狙撃だ。
「クソ……」
まだ、終わらないのか。……いや、冷静になれ。結論を出すのはまだ早い。
とにかく今は、仕事を終わらせるのが優先だ。アロウ達の下へ戻ろう。そして、帰るんだ。
気怠さとやるせなさが苛む体を引き摺って、とろとろと階段を降りていく。戦闘中は興奮して気付かなかったが、二階は血と火薬の臭いが混ざり合ってなかなか精神衛生によろしくない。
「……そうだな、保険くらいは掛けとくか」
それは、保険と呼ぶのもおこがましい、分の悪い賭けだった。
俺は、そこら辺に転がっている死体を漁り始める。あまり時間は掛けられなかったが、何とか三体目で目当ての物を発見できた。
「――誰か、誰でもいい。聴いて欲しい事がある」
† † †
「――彼は『組織』の教義に背き、邪な企みを胸に抱えたものでありました。ですが、彼もまた人の子であり、彼の心の弱さを責め立てることは、何人たりとて許されざる邪悪であります」
若い神父の仰々しい台詞が、ドームのような地下空間に反響する。彼の他の人間は、俺とアロウのみ。俺たちは黙して男の言葉が終わるのを待つ。
ここは、セカイの中心地。巨大な歯車が奏でる重厚かつ荘厳な音は、人々を外界の穢れから護るための自浄システムのそれだ。
司祭の長ったらしい祝詞に眠気を感じ、欠伸を噛み殺す。日付はついさっき変わってしまった。
「――錬金術師、ガルミス・アヴレイド。練金の地に産み落とされし者、練金の深奥、時計街の中心にて安らかに眠れ」
やっと終わったか。俺は欠伸と溜め息が混ざった吐息を吐く。
「お疲れさま、ジュンペイ。これで今回の仕事は終わりだよ。報酬は日の出以降に送金役を手配するよ」
「何で暗殺対象の密葬に暗殺者本人が参列しなきゃなんねーんだよ」
自身の気分を偽らずに舌打ちする。アロウは、困ったような苦笑いを浮かべるだけだ。
「あはは、機嫌悪いね……」
「そらそうだろ。本当なら俺は今頃、帰ってカレー食ってたんだからよ」
足下に置かれたアヴレイドの棺桶を軽く蹴る。死者に鞭打つのは御法度だろうが、九年来の恨みだ。これくらい許して欲しい。
「邪魔して悪かったよ。今回、君のお陰で本当に助かった」
「……おう」
生返事をしてアロウに背を向け、煙草を銜えてライターを擦る。やはり、一仕事終えた後の一服は格別だ。
「フー……そうだアロウ。一つ、訊いておきたい事がある」
「ん? 何かな? 今ならお礼も兼ねて、答えられる事なら何でも訊いて良いよ」
人当たりが良さそうに、実に機嫌が良さそうに。
「そうか。…………いや、そうだな」
アロウ・クロスェントは、嘯いた。
「これで訊いた方が、手っ取り早い」
俺は反転するや否や、即座に拳銃をホルスターから抜き、撃鉄を起こして発砲。胸に弾丸を受けたアロウがうずくまる。
すると、どこからともなく現れた黒服集団が、拳銃や剣を構えて俺を取り囲む。さっきまで長ったらしく喋っていた司祭まで、迷いなく俺に銃口を向ける始末だ。
「撃つな!!」
苦しそうに喘ぎながら、アロウは胸を押さえて立ち上がる。その瞳は、黒い感情でどろりと濁っていた。
「……何で分かったんだ? ジュンペイ」
「いや、何でって言われてもなぁ。お前以外に思い浮かばなかっただけだ」
俺はリボルバーから空薬莢を排出しながら答えた。それを見て俺を囲む黒服達――さっきまで俺と同じ現場にいた『組織』の連中は殺気を強めるも、アロウがそれを手で制す。
「ちょっとは頭使えよアロウ。アヴレイド本人はあんな単細胞野郎で、派閥の規模は小さいし、内輪でも揉めてるみたいだった。あんなボロクソな馴れ合い共が十年近く俺に尻尾すら見せなかったんだぞ? どう考えてもおかしいだろ」
ガンベルトから抜き取った、赤い弾頭を備えたニッケルの薬莢を装弾口へ放り込む。
「……それだけかい?」
「一応他にも、『組織』関連の情報を篩(ふるい)にかけて俺に流せるのがお前だけとか、今日の狙撃のタイミングとか色々あるぞ。どれも確証には至らなかったがな」
吸い終えた煙草を踏んで消火すると、アロウは突如気が狂ったかのように大声で笑い出した。
「――くくかはははははカハハハハハハハ……! そんな穴だらけの推理で僕は殺されるのか! 君は随分とあのクソ女にご執心のようだね!!」
「あー……アロウ」
「何、気持ちは分からなくはないさ! 君は彼女を尊敬し、僕は嫉妬した! たったそれだけ、それだけの違いなんだ!!」
「いやあの、お前さ……」
「ここまで来たら、君も道連れだジュンペイ! 一緒にハレの下へ逝こうじゃないか!!」
俺はアロウにもう一発ブチ込んだ。溜め息を付くのも面倒臭い。
「またか!? また撃ったなジュンペイィイイッ!?」
いきり立って腰の剣を抜くアロウ。俺は激高する彼の姿にウンザリしながら、リボルバーの撃鉄を起こした。
「いやあのな? お前に撃ったの二発とも回復弾な。つまりハッタリ、鎌掛けだ。そんだけピンピンしてりゃ分かるよな?」
「…………」
アロウはポカンと口を開け、胸を押さえていた自分の手を呆然と眺める。当然、血なんか付いてない。
「――殺せ」
「そう来ると思ったよ」
俺はアロウが指示を出すよりも早く、自分のこめかみに銃口を当てて引き金を引く。発射された赤い弾頭は俺の頭に鈍い衝撃を与え、霧散する。
それと同時に、世界が、俺に付いて来れなくなる。通常の三分の一の時間が流れる空間で、俺は残りの弾丸四発をそれぞれ別の方向に発射。銃持ち達の急所に鉛を撃ち込み、即座に絶命させる。
ゆったりとした踏み込みで襲いかかる剣持ち複数人も、近寄ったところを刀で斬り捨てる。現実の時間にして、僅か二秒の競り合いだった。
弾の効果が切れたところで、俺は血振りをしてから納刀する。アロウは暢気に拍手をしていた。
「はっはっは、やっぱり強いね、ジュンペイ」
「そうだな」
手短に答え、鞘の鯉口をアロウに向けてから引き金を引く。射突杭に弾き出された刀はそのまま飛翔体となり、柄頭からアロウの顔面に突き刺さる。銃が弾切れで油断していたアロウにとっては、正に青天の霹靂たる一撃だろう。
「――ッだァ!」
大質量の銃撃を受けたアロウに素早く詰め寄り、奴の顔にめり込む刀をキャッチして、そのまま振り下ろす。アロウの左腕が身を離れる。切っ先が浅く彼の胸を抉った。
「ッがァアアアアアア!! クソが! なんてことしやがる!!」
切断面から大量の血を流し喚くアロウ。錯乱しているのか、手にした剣をがむしゃらに振り回している。
「終わりだ、アロウ・クロスェント」
「あはははははははァ! 終わり? 終わりだと!? まだだ、まだ終わりじゃないんだよォオオァ!!」
何を思ったか、アロウはアヴレイドの亡骸が収まった棺桶に深々と剣を突き刺した。
「お前らみたいな錬金術士をォ! 僕は絶対に許さないッ!! 僕を否定する錬金術を、僕は否定するぅうう!!」
喉を潰さんばかりの声で叫んだアロウの周囲に、突如として黒い烈風が吹き荒ぶ。
「オイオイ、まさか……!」
「そうだッ!! これが旧文明を滅ぼした決戦兵器、とくと味わえ!!」
――そう、旧文明が遺した穢れとは、錬金術による広域殲滅兵器だった。
必要な物は、ほんの少しの練金術の知識と人体――そして、術者の命。
「やめろ!! この街(せかい)の百万人、全員殺す気か!?」
「そうだァ! 錬金術によって生かされる命など滅んでしまえばいいんだッ!!」
人外の存在へと変貌し、『穢れ』の核になりつつあるアロウへ斬りかかる。が、奴を中心に逆巻く暴風に触れただけで、刀はみるも無惨に砕け散った。
「な……ゲホッ、ゴホッ!?」
「無駄だよ! 街ごとこの力に呑まれて死ねェ!! ジュンペイィッ!!」
穢れの暴風がさらに強くなる。刀を破壊したのと同じ様に、それは俺の体を蝕み壊していく。歯を食い縛っても、一瞬たりとて耐えられずに薙ぎ倒される。息が、苦しい。
――ああ、こりゃ無理だ。絶望とか諦観とか、そんな表現も生ぬるい。これには抗えない。それが、自然の摂理であると悟った。
† † †
「――――ペイ、ジュンペイ。ジュンペイ!」
肩を揺すられ、優しい微睡みから浮上する。
「……あ? 俺……てか、ニア? なんで?」
地面に倒された俺の側で、ニアが静かに泣いていた。目が届く範囲全てで、相変わらず穢れた嵐が猛威を振るっている。なのに何故か俺の周囲だけは、空気が非常に穏やかだ。
「ニア……これ、お前が……?」
「――はい。正確には、ハレが私に、吹き込んだ、『息吹』の、力です」
瞳から限りなく澄んだ涙を流しながら薄くはにかむニアの耳には、俺が渡した携帯ラジオのイヤホンが挿してあった。分の悪い賭け……アロウの悪事を止める為の、電波を妨害された中での広域無線は、ニアにちゃんと届いたのだ。
そして彼女は、ノイズだらけの俺の声を判別し、理解して駆けつけてくれたのだろう。
……しかし、これで事態が解決したわけじゃない。少なくとも俺はニアという安全圏に居られるが、『穢れ』をこのまま放っておけば、瞬く間にこの街の生物は死滅する。
「アロウを、止めねぇと」
だが、どうすればいい? 穢れの嵐は、生物無生物を問わず浸食していく。ニアがいれば核であるアロウに近付けるが、それでも奴への攻撃手段がない。
「――ジュンペイ」
俺が悩んでいると、ニアは首元のリボンを解き、ブラウスのボタンを数個外した。
「私の『命』を、使ってください」
「な……」
ニアの動力、つまり命の核である力を使え。彼女はそう言っているのだ。
それはつまり、彼女の躯から、命を奪い取ることを意味する。
「それは、無理だ……」
「いいえ、ジュンペイなら、できます」
力強く頷くニア。対して俺は、唇を噛んで首を振る。
「嫌だ……嫌なんだ……!」
ぼろぼろと涙を零す俺に、ニアは優しく口づけをした。儚く、短いキスだった。
「大丈夫ですよ、ジュンペイ。また、必ず、会えます」
俺は、何も言わずに師匠の銃から空薬莢を全て排出する。――口を開けば泣き言が出そうで、声を発さないように手を動かすくらいしかできなかった。
「いつまでも、待っています。貴方と、再び出会える、その時を」
ガンベルトに残った最後の一発を装填。――ありとあらゆる物理結合を分解し、理論構成式レベルまで分解する、俺の切り札。
それを込めた銃を、ニアのはだけた胸元に向ける。――俺が晴のように、穢れに対抗できるだけの錬金術士であれば……そんな悔恨の思考が、カチリと金属が噛み合う音に遮られる。
ニアが、俺の握る銃の撃鉄を起こしていた。
「――愛しています、ジュンペイ」
俺は、引き金に触れた。反動で暴れる銃をそのまま手放す。
ニアの胸にぽっかりと空いた光の渦に手を差し入れる。労せずに、ニアの核がにぎれてしまった。
「俺も、愛してる。ニア――」
小さな躰に湛えられた、大きな力を引き抜く。
「……あ、嬉し……で…………」
その瞬間、その瞳は綺麗なガラス球に。その肌は手触りの良い膜に変貌する。
それは、どうしようもなく、紛れもなく、人形だった。
「――待たせたな。終わりにしよう」
視界は悪かったが、穢れは核を中心に渦巻いていたのでアロウを見つけるのは容易かった。
「お前は錬金術が嫌いなんだよな? そりゃあこんなクソみてーな錬金術は嫌って当然だ」
既に現象の一部となり、物言わぬ物体に成り果てたアロウへ語りかける。
「じゃあさ……見せてやるよ、俺達の錬金術を」
師匠が鍛え、晴が芽吹かせたニアの命――――白銀の刃を、正眼に構える。
「――メギストス流、奥義」
黒の嵐の中、白刃がより一層輝きを増していく。それに『穢れ』は何か危険を感じ取ったのか、アロウだったモノから無数の棘がしなりながら俺に向けて飛び出してくる。
俺はそれを最低限の足運びと剣捌きでいなし、僅かに生じた一寸の隙に、迷わず突撃し、一閃。
「――――『無塵』」
† † †
俺は冷たい床に臥したまま、胸ポケットから取り出した紙箱を開き、煙草を一本取り出して銜えた。吸いすぎです、とそろそろ怒られそうだなとぼんやり考えながら、視線を鋼の天井から横にズラす。
隣には、ニアの脱け殻が転がっていた。
しばらくその芸術品を眺めてから、まだ火を点けていなかった事に思い至る。スラックスのポケットを手探るも、愛用のオイルライターが入っていない。どこかで落としたか?
すると、近くでドラムとフリントが擦れる音がした。そちらに顔を向けると、いい具合に煙草の先端が火に炙られる。
「……ありがとな、サクラ」
「いえ、おやすいご用ですよ」
深呼吸をするように煙を吸い込み、フィルターを銜えたまま肺から吐き出す。紫煙は重力に逆らって空気と混ざり、やがて広大な時計街心臓部の虚空へと霧散した。
「教官、地上が今大変なことになってます。街の浄化機構が停止まって、さっきここから生じた穢れがまだ残留しています。このままじゃ……」
サクラは頭上の巨大な歯車を不安げに見上げる。先刻とは明らかに異なる、異質な不協和音。内部から穢れに浸食されたセカイの自浄システムが悲鳴を上げているのだ。
「……んじゃ、直さないとな。このセカイを」
俺はなけなしの力を絞って、それでもふらつきながら立ち上がる。握っていた銀の刀を心配そうにこちらを見つめるサクラに手渡し、足下に転がっていたリボルバーを拾い上げる。
シャツの襟に指を突っ込み、そこに仕込まれた弾薬を取り出す。ニアに撃ち込んだのと同じ弾。正真正銘、これが最後の一発だ。
「教官……」
「サクラ、俺が留守の間、ニアを頼む」
銀色に輝く弾薬を弾倉に押し込み、シリンダーを回転。撃鉄を起こして、銃口を足下に向ける。
「そんな……無理ですよ。わたしが教官の代わりなんて」
刀の柄を抱き、目に涙を溜めるサクラ。俺は彼女の頭に手を置き、軽く撫でる。
「俺みたいな半端な錬金術士が出来たんだ。どれだけ時間を掛けても良い。お前なら、絶対に大丈夫だ」
「……本当に、どれだけ掛かっても知りませんよ?」
「問題ないさ、俺にもそれくらいの時間が必要そうだ」
サクラの頭が、俺の手から放れていく。俺は短くなった煙草の最後の一口を吸い、火種を踏んで消した。
「じゃあ、またな。サクラ――」
慣れない笑顔を作りながら、トリガーを最後まで引き絞る。着弾した床に小さな光の渦が生まれ、それはどんどん大きくなって俺を飲み込んでいく。
「――カレーっ、無くなってても知りませんからっ!!」
サクラは満面の笑みで――涙と鼻水を盛大に垂らしながら、豪語した。
‡ ‡ ‡
――『軌跡』から『太陽』へ。穏やかな音色は、その表情を四季の移ろいであるかの如く滑らかにその表情を変える。実に、惚れ惚れするほどに見事な繋ぎ、美しい『調律』だ。
「……参ったなぁ。ここじゃ商売上がったりだが、この街を離れたくなくなってきた」
だがこれは、この街に溢れる音がこんなにも素晴らしいのがいけないんだ。……そう自分に言い訳しながら、せめて私もこの音と調和したいと考え、鞄から横笛を取り出して吹き始める。
『太陽』は私にとっても馴染みのある曲だ。それを奏でるこの街自体の音色は未知のものであったが、デュエットにはそう苦労しなかった。
音楽と一体になっていると、ついつい時が経つ事すら忘れて夢中になってしまう。『太陽』が終わると、不意に背後から控えめな拍手が上がった。
振り向くと、そこには少々無表情な少女が佇んでいた。おおよそ自然発生的とは思えない完璧な美貌とあどけなさのバランスが素晴らしく、身にまとったどこか使用人を思わせるドレスも、彼女の可愛らしさを最大限に引き立てる。
「とても、お上手ですね。素敵な、演奏でしたよ」
「ははは、これはこれは。お褒めにあずかり光栄です」
私は横笛をしまい、大きく膨れ上がった鞄を再び背負う。綿の抜けた肩紐が食い込んで少し痛い。そろそろ買い換え時かなぁ。
「ご挨拶が、遅れましたね。初めまして、旅人さん。私はニア。この街の、統括管理者の任を、承っています」
折り目正しくこちらにお辞儀をするニアさん。丁寧ながらも動作はかなり自然で、彼女を造った錬金術士の腕前は推して知るべしといったところだ。
「どうも初めまして。ギネウ・マグヌスと申します。お察しの通り、旅する錬金術士であります」
私もニアさんに倣いお辞儀をする。とはいっても、鞄の重量のせいで殆ど亀のように首を下げるだけになってしまったが。そんな私の様子を見て、ニアさんは僅かに微笑み、くすくすと静かに笑うのだった。
気恥ずかしさに頭を掻くと、私の腹の虫が不機嫌そうに鳴いた。私の体はどこまで主に恥をかかせたいのか。
「ギネウさんが、よろしければ、私の家で、ご飯を食べて、いきませんか?」
「是非に」
その提案はこれ以上なく魅力的だった。二つ返事でお願いする。
ニアさんの家へと案内される道すがら、街がまた新たな曲を奏で始める。題名は『息吹』。調律譜の歴史の中では比較的、新しい曲だったはずだ。
「……この街は、気持ちが良いですね。沢山の緑があって、素敵な音が溢れている」
「はい。この街に住む、人々は、皆この自然と、街の音色を、愛していますよ」
ニアさんはどこか誇らしげにそう語る。事実、二十世紀以上続いてきた穢れの時代――刻暦に終止符が打たれたのもここ数年の出来事。これだけの緑を街の内外問わずに広げるこの時計街は、相当に優れた浄化機関を有しているのだろう。
「まぁそうなると、私は商売にならなくて少し困るんですけどねぇ。最近はこの浄化装置がどこでも売れないんですよ」
「きっと、少しずつ、世界が綺麗に、なっているんでしょうね。――永い時間が、掛かりましたが」
「……ええ、本当に」
ニアさんの言葉に哀愁の様なものを感じながら、しみじみと首肯する。……彼女は一体、どれだけの時間を生きてきたのだろうか。
「あっ、ニアー! ただいまー!」
自然と建築物が調和した街並みをゆったりと歩いていると、道の向かいから金髪の少女が手を振って駆けてきた。どうやらニアさんの知り合いのようだ。
その少女は、腰に銃と刀を合体させたような奇妙な武器を佩いていた。手首には、彼女の細腕には少々大きい、男物と思しきアンティークな腕時計を着けている。
「お帰りなさい、カエデ。本日も、ちゃんと、お仕事をしましたか?」
「うん、もちだよ! だから早く帰ってご飯! ご飯!!」
ニアさんにカエデと呼ばれた金髪少女は、元気の有り余った仔犬のようにニアさんの周りを跳ね回っている。
「初めましてカエデさん。私はギネウ。旅する錬金術士です」
「こんにちは! へぇー、お兄さんもわたしとおんなじ錬金術士なんだね!」
カエデさんはニアさんとは対照的に、大きく朗らかに笑う。まるでこの街そのもののような、とても元気のいい子だ。
「ていうかお腹減ったー! ニアお腹減ったぁー!」
「承知しています。お客人の、ギネウさんを、待たせるのも、いけませんね。早く家に帰りましょう」
「わーい!」
カエデさんがニアさんに抱きつく。彼女らの言動を整理するにどうやら二人で共同生活を送っているみたいだ。
「そんな女性の花園に、私がお邪魔しても良いんだろうか……おや」
ネガティブな独り言を吹き飛ばされる。再びこの街の音が色を変えたのだ。やはり繋ぎも演奏も、筆舌に尽くし難(がた)い。
「あ、この曲初めて聴いた! ニアー、これなんて曲?」
「……済みません、解りません。私も、これは初めて、耳にしました」
「おや? そうなんですか、珍しい。この曲はかなり古くからある、有名な調律譜ですよ」
「へー、ギネウさんすごいねー! ニアが知らないことも知ってるなんて」
「ギネウさん、この曲は、なんという、題名なのですか?」
「はい、この曲はですね――」
「――――『再会』と、いいます」
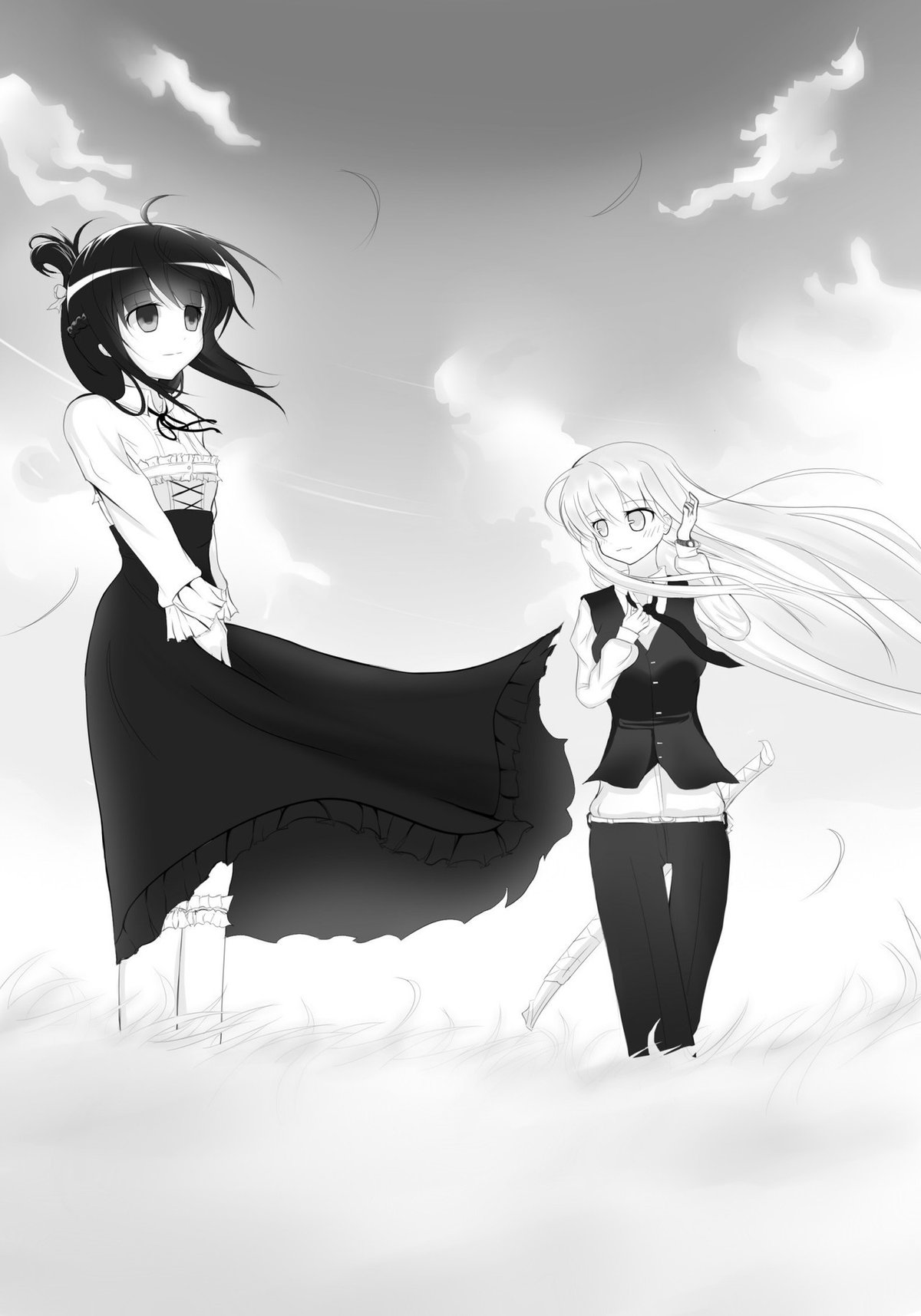
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
