
古典ミステリー初読再読終読 クロフツ『樽』 The Cask (1920)
クロフツの『樽』は、「アリバイ・ミステリー」なるサブジャンルを発明したとして、ミステリー史上名高い長篇だが、十代の終わりにいちおう買ってはみたものの、その後の数十年、まったく感応が起こらず、匂いもしなけれれば、予感も働かず、ついに未読のまま、五十代の終わり、死の予感を伴う引っ越しの折に他の一万冊ほどの蔵書とともに手離した。
◎プロジェクト・グーテンベルクとタブレットPCの「目の近い読書」
いまになって読む気を起こしたのは、このところの読書の流れ――Project Gutenbergなどで古いミステリーの原文が容易に入手できることがわかり、邦訳の解釈や日本語表現がひどくても、原文を見て補正できるようになったために、未読だったE・W・メイソン、イーデン・フィルポッツ、E・C・ベントリーなどを読んだ――による。

もうひとつ、タブレットを買ってデスクトップPCより格段に読書しやすい環境ができた、ということにも促された。とくに英文は90センチ向こうのスクリーンでは非常に読みづらいが、20センチの目睫にあるタブレットなら、楽に読める。
ここまで、矢の家、闇からの声、赤毛のレドメイン家、トレント最後の事件などを原文を参照しながら読んだ。それはいい。しかし、『樽』はやめたほうがいいんじゃないかと感じた。今回もまったくネガティヴな予感しか働かなかった。
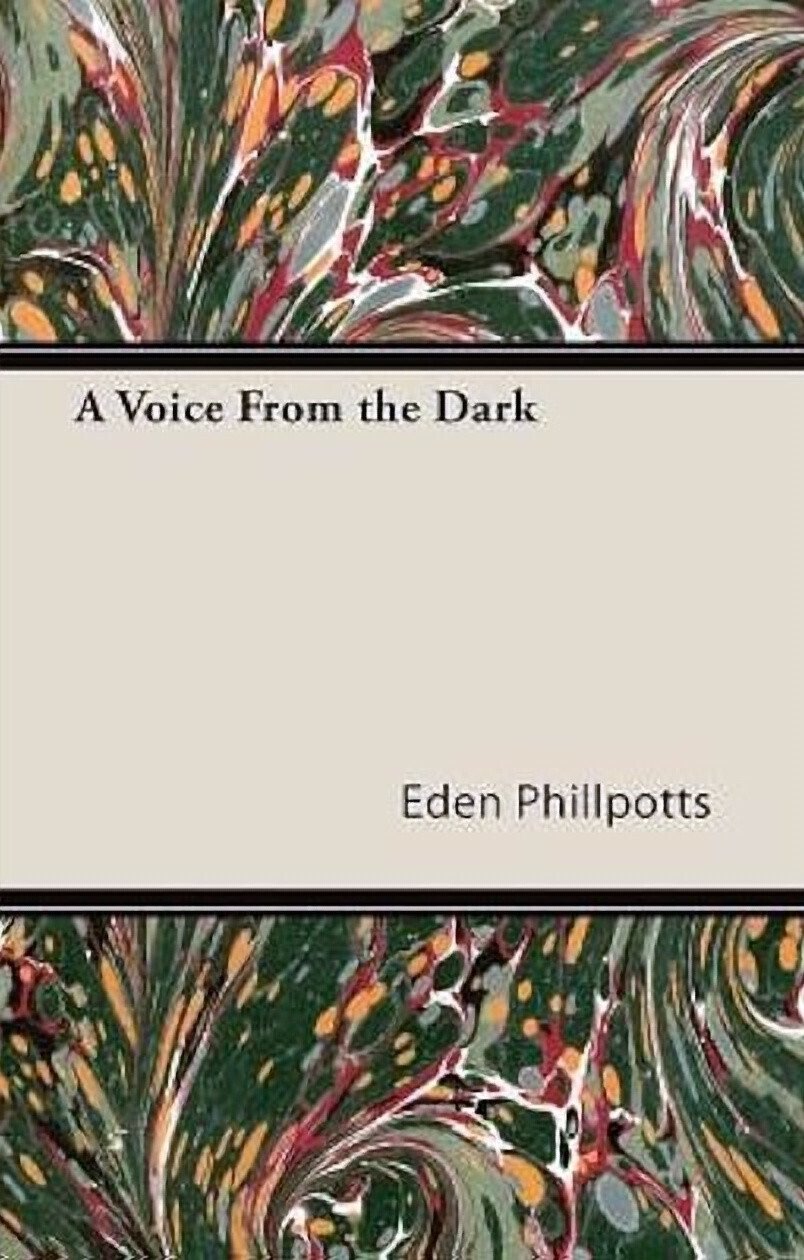
それはたぶん、『樽』にインスパイアされたという鮎川哲也『黒いトランク』は、真面目に書かれているけれど、退屈に感じたし、同じく横溝正史『蝶々殺人事件』は、物語としてはそれなりに楽しめるものの、謎解き部分はやはり退屈に感じた、そして、松本清張『ゼロの焦点』に至っては、「なあにがアリバイだ、こんなマッチ棒を一万本使って組み上げたような小細工、上手くいくはずがない、軽く息を吹きかけただけで崩れるじゃないか、バカもいい加減にしろ」とおおいに立腹した、という過去の経験もあずかってのことだった。アリバイづくりなど、現実にはほとんど意味がないままごと、児戯だ。
◎ロンパリ・アリバイ
港での樽の落下事故、壊れた樽からの意外なものの出現、謎の受取人の登場、わずかな隙を衝く樽の奪取、警察の手配、と意外にも展開は速く、冒頭は気持よく読める。
偶然も幸いして樽の行方を突き止め、探偵が中身を確認するあたりまでは快調で、樽が再び消え失せ、その捜査にかかるあたりから、足跡だの、柱の傷だのという、本格ミステリーのお約束、退屈な検証フェイズに入る。これは必要悪だからしばらく我慢していたら、パリに舞台が移り、開巻ほどではないにしても、再びテンポがよくなって、安心した。恐れていたほど退屈ではない。
パリでの英仏共同捜査で容疑者は二人に絞り込まれる。アリバイ物にありがちな、犯人の意外性はないパターンね、とここらで子供のころからのアリバイ崩しを好まない地金が出てきて、作者の書きっぷりの欠点に目が行くようになった。

どうでもいいことを思いだした。昔、斜視のことを、片目がロンドンを見て、片目がパリを見ている、という心で「ロンパリ」と云っていた。とくに若い女性が軽い斜視だったりすると、「あのこはロンパリで可愛らしい」などと評したものだ。
退屈しはじめたわたしは、この二人の警官、ロンドンの名警部とパリの名警部は、優秀な捜査官であるかのような作者の言いようとは裏腹に、思考の焦点がロンパリで、作者の都合でしばしば馬鹿になり、容疑者のアリバイ主張を深く検討せずに、正しいものと受け取り、通過するものだから、ちょっと待てよ、そんな裏付け捜査はないぞ、裏付けになっていないじゃないか、もっと追及しろよ、と思う。「本格ミステリー」ではよくみられる決定的な欠陥を抱えているぞ、とちょっと機嫌が悪くなってきた。
◎「イディオット・プロット」、読者よりはるかに馬鹿な登場人物という普遍的な陥穽
SF作家の誰かが名付け親だと思うが、idiot plotという言葉がある。ふつうの知性の持ち主なら明白なこととして理解するはずのことを、登場人物はなぜか理解できずに、とてつもなく愚かな行為をすることをエンジンにして話を展開するのを指す。
たとえば、松本清張のごく初期のアリバイ崩し小説に出てくるのだが、そんなこと、旅客機を使えば簡単にできるじゃないか、と読者は思うのに、刑事たちはまったく思い至らず、最後になって、ああ、旅客機があるのか! なんて大発見をしたかのように騒ぎ、解決へと雪崩れ込んでいく。冗談を云っては困る。定期航空路なんて昭和戦前からあるのに、そんなことにも気づかないなんて馬鹿な話があるものか、と憤慨した。
あるいは、マット・デイモン主演のSF映画で、地球に帰るための十分な燃料が宇宙船にない、という局面があり、多少ともSFを読んだ人間は、スリング・ショット(スウィング・バイ)を使えば燃料消費なしに加速できるじゃないか、と思うのだが、NASAのお歴々や地上スタッフも、宇宙船に搭乗した頭脳明晰な宇宙飛行士たちも、誰ひとりそのことに気づかず、JPL=ジェット推進研究所の若い宇宙航空力学研究者に教えられて、NASAの長官が「そんなことが可能なのか」と部下に質し、その方法を救出作戦に採用することになる。

わたしはどっと崩れ落ちた。宇宙旅行では、恒星や惑星など、大きな質量のある天体のまわりを半周することで、燃料消費なしに重力による加速をする、なんていうのは、極ごくごくごく初歩的な知識、イロハのイだ。SFが大好きな小学生でも知っているだろう。現に、ヴォイジャー探査機はこのスリング・ショットを繰り返して徐々に加速し、太陽系外へと飛び出した。NASAのスタッフがそれを知らないなんて馬鹿なことがあるものか!
(スリング・ショットの原理説明)

シナリオ・ライターは、人工衛星、ロケット、宇宙船を飛ばす専門家ばかりの登場人物たちを、そんな当たり前の力学知識も持ち合わせない愚か者に仕立てたわけで、こういうのを「イディオット・プロット」と呼ぶ。ありえないプロットなのだ。
◎頭がキレる優秀なマヌケ警部と激情的で沈着冷静な犯罪者
アリバイなんていうものは当てにならないものだ。そもそも、たいていの人間は、ある事件が起きた時のアリバイなど都合よく持ち合わせているものではない。そういうものを土台にして小説を構成したところで、不自然でぎこちないものしか生まれないのは目に見えている。
『樽』では、捜査にあたった警部はある容疑者のアリバイは完璧だと納得するが、読者は、月曜だか火曜だかはっきり覚えていない、という証言をその程度の裏付けで月曜と確定するとはどういうことだ、ぜんぜん証明されていないじゃないか、なぜ、その点をもっと考究して、容疑者の小細工がどのようなものか想像しようとしないのだ、登場人物にいきなり馬鹿のふりをさせるなよ、と腹を立てる。
お話の運びの都合上、いまその点を解明するわけにはいかないから(いまわかってしまっては、後段のアリバイ崩しが不要になってしまう!)、この頭脳明晰なはずの警部を一時的痴呆にしてしまう、という作者の手つきが丸見えで、まったく奇術になっていないのだ。
本格ミステリーと呼ばれる古典的な謎解き物語にしばしば見られる欠点は、犯罪計画を成立させるための、あるいはそもそも小説それ自体を成立させるための、ご都合主義から生まれるこのイディオット・プロットなのだ。

また、フェアな謎解きたらんと思えば、あらかじめ手掛かりを提出しなければいけないが、その提出の方法が稚拙だと、読者は、これが探偵の決定的な錯誤だな、とたちどころに気づいてしまう。この「月曜か火曜かわからない」というのがポイントだ、月曜という探偵の判断が間違いで、のちに火曜だったと判明するに違いない、と読者は受け取ってしまい、意外性はゼロ以下になってしまう。腕のいい作家は、手掛かりの提出に工夫を凝らし、読者にその重要性を気づかせないものだ。
(話はずれるが、ジョイス・ポーターのドーヴァー警部シリーズは、探偵が異常な人間で、何が手掛かりで、何がただのバカ騒ぎなのか、さっぱり見分けがつかず、読者は五里霧中、探偵も食べ過ぎで体調不良だとか何とかで、捜査らしい捜査もしないのに、事件のほうが勝手に解決してしまう、という不思議な手法によって、本格ミステリーが陥りがちなイディオット・プロットの罠の回避に成功するという画期的なものだった)。

『樽』の犯罪は激情殺人であり、殺しそのものは計画されたわけではなく、突発的に起きてしまう。しかし、犯行直後の二時間ほどで、犯人はあまりにも遠回りな、フランスとイギリスのあいだで大きな樽がぐるぐる動きまわる、異常に複雑な死体隠蔽と犯罪転嫁の弥縫策を思いつく――。
ひどい違和感がある。あとさき考えずに人殺しをした人間が、直後に我に返ったことはまあいいとしよう。しかし、その瞬間に、こんな冗談みたいに複雑で、警察を揶揄しているとしか思えないアリバイ工作を考えつくものか? こういう心理の動きはあり得ないと感じた。それほど異常な人物なら、その異常性をあらかじめきちんと描写しておかなくてはいけないが、犯人だから、いかにも犯罪を犯しそうな人物として描くわけにはいかないと来る!
このあまりにも矛盾した人物像を恥ずかしく感じなかったのは、これを書いたとき、クロフツはまだ素人だったからだろう。小説作法、人物の造形、リアリティーの醸成、ということを真剣に考えたことのあるプロの作家なら、こういう人物造形は不可と判断し、アイディアを捨てただろう。

人物像の矛盾を解消するには、激情殺人ではなく、計画殺人にするべきだが、しかし、そうなると、あまりにも無理が過ぎる樽の移動などという弥縫策は意味を失う。計画しておこなうなら、はるかにましな方法が山ほどある。死体を樽詰めにしてドーヴァー海峡を渡らせるなどという、呆れるほど迂遠な方法は、苦しまぎれの急場しのぎだからこそのものだ。完全に矛盾している。
◎無秩序乱雑な大量殺人と秩序ある叮嚀な人殺し
いかにも素人くさい小説で、あちこちに小説作法への無理解が見られるが、とにかく、誠実に書かれていて、じつはわたしの腹立ちもそれほどひどくはなかった。クロフツ先生、素人だから、人物造形が不得手で、小説作法の要諦をご存じなかったんですな、といったあたりの苦笑い程度のものだった。
鮎川哲也は、たぶん、アリバイ崩しという手法のみならず、クロフツのこの誠実さにも惹かれて、誠実が誠実の羽織を着て誠実の披露目に来たみたいな『黒いトランク』を書いたのだろう。両者相通ずるものを感じる。
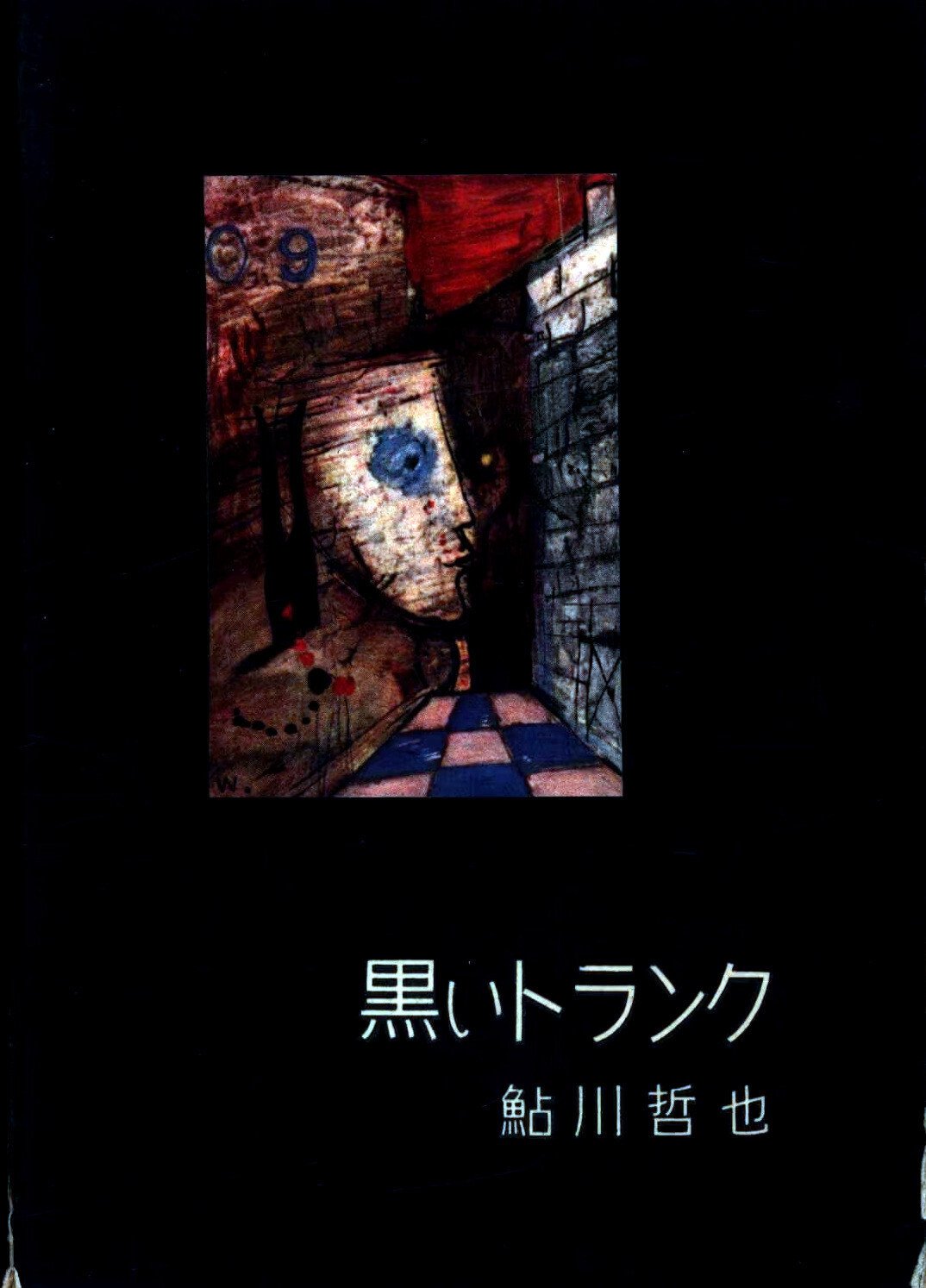
「最後の『トレント最後の事件』:探偵の退場と人間の登場」で書いたが、いわゆる本格ミステリーは第一次世界大戦直後に生まれた。『樽』はまさにその時代のとば口、1920年に発表された。
クロフツは大戦後に病気療養を強いられ、その時期にこれを書いたというのだから、執筆は出版前年の1919年と考えていいだろう。しかし、作中の時間は1912年の春に設定されている。第一次世界大戦は1914年7月28日~18年11月11日なので、大戦後に、戦前を振り返って書いたことになる。
小津安二郎が1949年に『晩春』を撮った時、描かれたのがあまりにも静謐な生活で、現実とかけ離れすぎ、まったくアクチュアリティーがないと批判した評論家がいたという。しかし、創作物というのは、その時代の現実を直接に反映しなければいけないわけではない。反時代的な世界を描くことは、それはそれで時代の表現である。
『樽』の静かさも、やはりクロフツの同時代に対する批判だったのかもしれない。まだ材料が乏しくて、明快に云えるわけではないが、「本格ミステリー」とは、戦争という「犯人のいない無秩序な大量殺人」への抵抗、嫌悪感の表明として、「特定の実行者による秩序ある人殺し」を提出しよう、という作家たちの集合無意識の産物ではないかと考えている。

ジェイムズ・エルロイという痛烈な経験をした眼で、本格ミステリーという、滅びたものへのノスタルジーから、このところ古典を読みつづけている。その意味では、『樽』にも昔のものらしい魅力はある。たんに、昔からアリバイ崩しが嫌いなので、その始祖とされる長篇も、やはりアリバイ崩しものの通弊をまぬかれるものではなかったと感じたにすぎない。
◎どうでもいい些細な疑問の壱
本を一冊読むと、最後まで解決できない疑問が残ることが多い。とくに、異なる時代や、異なる文化が描かれていると、それってどういう意味? と思ったまま解決できずに終わる事柄がけっこうある。『樽』にもあった。
『ロンドン、西区、トットナム・コート・ロード、西ジャブ街一四一 レオン・フェリックス様 ルーアン経由 長海路』それに『彫像』というゴム印が捺してある。
これは樽につけられた荷札の描写なのだが、中国の地名みたいな「長海路」というのがじつに面妖で、なんだこれは? だった。当然、原文を確認した。
‘M. Léon Felix, 141 West Jubb Street, Tottenham Court Road, London, W., via Rouen and long sea,’ with the words ‘Statuary only’ printed with a rubber stamp.
「長海路」はlong seaを訳したものだったのだが、残念ながら、このlong seaも意味がわからない。そんな海事用語は発見できなかった。long seaをウェブで検索したが、このクロフツのセンテンス自体がヒットしたりして(ほかに使用例がない可能性が示唆されている)、解決に至らず。

となれば、勝手に想像して書いてもかまわない、という許可証を得たようなものだ。よって、想像した。
郵便物に、書留だの、速達だの、via airなどという但し書きをすることがある。これを並行移動してこのケースを考えてみる。海運会社は重さと距離に応じて荷主に運搬料金を請求するに違いない。たとえば、国内の海上運送は、short seaと云われ、短距離運送の従量料金が設定され、外国への運搬とは区別される、と考えたらどうだろう。
クロフツは鉄道員だったそうで、こういう荷の運搬に無知だったはずがなく、むかしはlong seaという区分があったのだろう。それがその後変化して、何か異なる表現になってしまったために、ウェブで検索してもヒットしなくなってしまったのではないか。
◎どうでもいい些細な疑問の弐
樽というと、わたしはbarrelを思い浮かべる。しかし、クロフツの樽はcaskである。両者は異なるものなのか?
ウェブには、微妙な違いがあるようなことを書いているところもあったが、読んでみてもよくわからず、結論として両者交換可能、どんな場面でも、どちらも使える、ということだけ確認して、あとの細かいことは一晩寝たらきれいさっぱり忘れてしまった。

しいて云うと、barrelのほうが用途が広く、容量の単位でもあるし、樽状のもの、たとえば、銃の輪胴やペン軸のことも云うのに対し、caskは用途が狭く、樽以外のものを思い浮かべないのではないだろうか。
ひとつだけ、caskから連想する樽以外のものを思いだした。caskから派生したcasketという言葉がある。意味は、宝石箱のような小筐が第一義。そして、第二義は棺桶! クロフツはこのcasketへの連想を狙って、The Caskと命名したのだろう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
