
古典ミステリー初読再読終読:J・D・カー『魔女の隠れ家』後編
あかね書房「少年少女世界推理文学全集」収録のジョン・ディクスン・カー Hag's Nookは、児童向けなので『魔女のかくれ家』というように「隠れ」をかなに開いていたが、現在流通している訳題は『魔女の隠れ家』と漢字なので、ここからはこちらの訳題を使う。
もっとも、カーは戦前から訳出されているので、あかね書房版以前には『妖女の隠れ家』というタイトルもあった。ハヤカワ・ポケット・ミステリ(音引きをつけて「ミステリー」にしてほしいのだが、早川書房は「ミステリ」としている)収録のHag's Nookは「妖女」のほうだったと記憶している。

創元推理文庫も昔は「妖女」を使っていたのかもしれないが(記憶曖昧)、現今の新訳版は『魔女の隠れ家』である。そもそも、Hagを「魔女」と訳したのは、あかね書房版が最初ではないかと思う。それで、後年の訳題が変化したと考える。子供の時、「魔女のかくれ家」のタイトルで読んだ人間としては、「妖女」では別の本に感じてしまう。そういう世代に合わせて訳題が変化したのだろう。
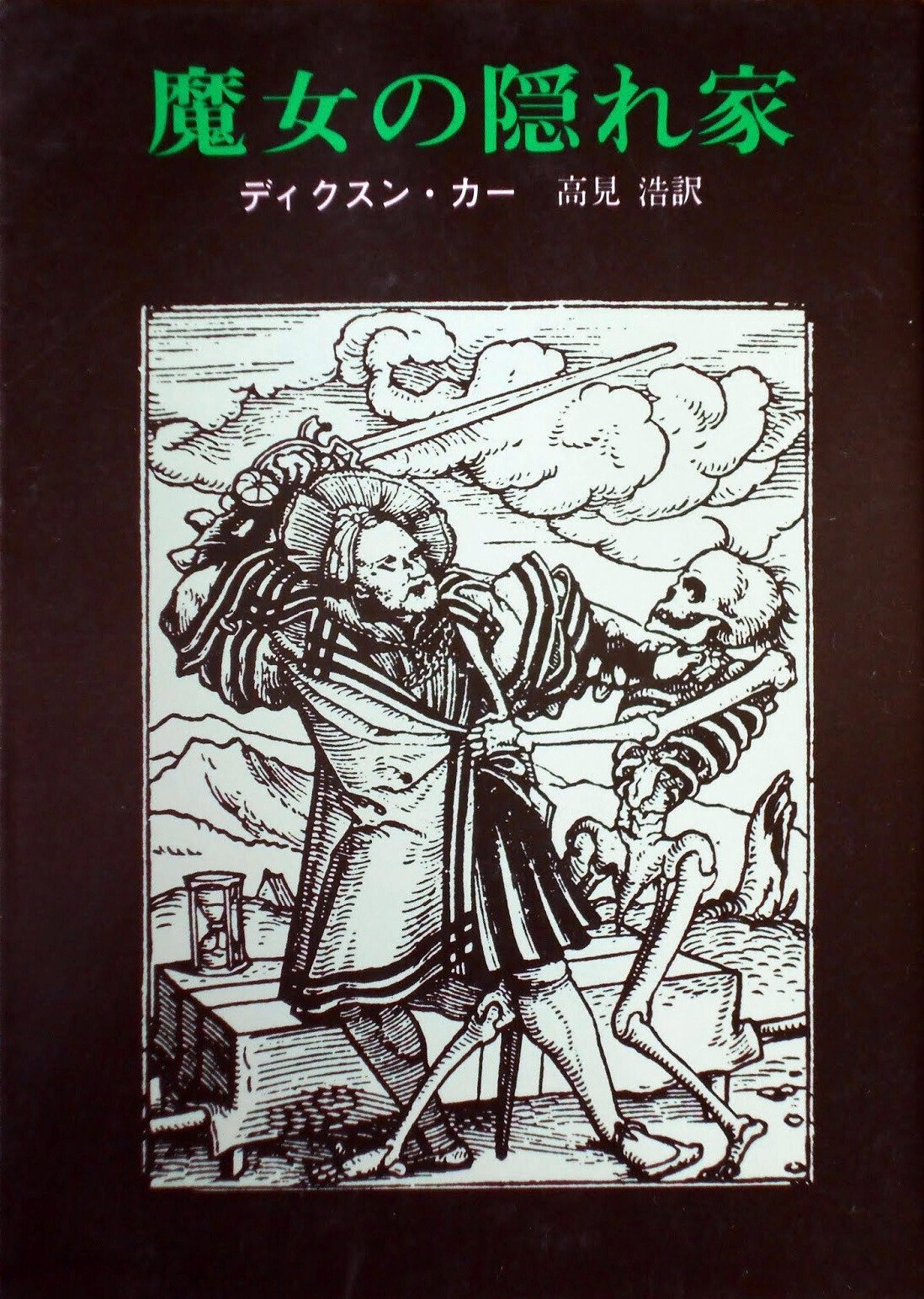
◎廃墟のお化け屋敷
子供の時、隣の隣のブロックに古色蒼然たる洋館があった。どういう由来の家なのか誰も知らず、人が出入りしているのを見た人間もいなければ、窓が開いているのも見たことがなく、子供たちは魔女の棲み家と云って、怖がりもしたが、興味津々で、なんとか中のようすを知ろうとした。
長じて建築好きになり、近代建築の写真を撮って歩いた人間としては、あれは戦前の建物の貴重な生き残りだったと考える。玄関ドアのまえに三段ほどの石段があったし、樫だったのか、頑丈な木の扉にはノッカーもついていて、小ぶりではあるが、まっとうな西洋住宅建築、タウンハウスの造りだった。破風や窓にも日本的な崩れはないgenuine and authenticな西洋建築だった。しかし、あれはやはり無住だったのだろう。魔女は棲んでいなかったに違いない!

そういう事情があったので、「魔女」の二文字だけで、本を開く動機としては十分なのに、あの装画の魔女のすごさ。あんなにワクワクしながら読みはじめた本は、その後、いくつあったか……久生十蘭『魔都』、中井英夫『虚無への供物』、半村良『石の血脈』など、わずかに指を折るにすぎない。

◎沼地の廃監獄と魔女伝説
十数年前に創元推理文庫版で再読しているのだが、すでにその印象は薄れた。そもそも、あれほど繰り返し読んだのに、いまでは、覚えているのはたったひとつの絵、「隠れ家」を凝視するギデオン・フェル博士とランポール青年の姿である。
英国留学中のアメリカ人学生タッド・ランポールは、担当教授に、この人に会ってみなさい、と云われ、リンカンシャーはチャターハムのギデオン・フェル博士の家に向かう(これがフェル博士のデビュー)。
チャターハムは、ロンドンの真北、リヴァプールとほぼ同緯度の大西洋岸の小さな町で(チャターハムという土地は実在するが、リンカンシャーではなくサレーにあるし、スペルも異なる。『魔女』のチャターハムは架空なのだろう)、かつて監獄があったが、いまは使われないまま廃墟になっている。

チャターハムは沼沢地帯にあり、湿気がひどく、そういう土地にありがちなように、怪奇な噂、言い伝えが多く、監獄は「魔女の棲家」と呼びならわされている、その昔、魔女と断定された女を絞首した場所を中心につくられたゆえの通称だが、その後、コレラの発生などのためにこの監獄は遺棄された。
ドイル『バスカービルの魔の犬』(大人の本では『バスカーヴィルの魔犬』などの表題になっている)にも沼地が出てくる。怪奇ムード醸成の常套手段なのだが、子供のわたしはバスカーヴィルの魔犬同様、この瘴気充ちるチャターハムという舞台にコロッとやられた。

その刑務所が建つ土地の所有者であるスターバース家の長は二代に渡って刑務所長を務め、二人とも首の骨を折って死んだ(とされている)。そして、スターバース家を継ぐ者は、二十五歳の誕生日の夜、ひとりで所長室に行き、11時から12時までそこで過ごしたあと、金庫を開け、そこにあるものを確認しなければいけないならわしで、ちょうど、ランポールはその代替わりの時にこの町にやってきて、その深夜の儀式を遠く見ることになる。
◎儀式の目撃者たち
フェル博士に勧められるまま、ランポールは博士宅に止宿した。相続のための「儀式」がおこなわれる夜、博士宅には、ランポールのほかに牧師もやってきて、ちょっと離れた元監獄の所長室を庭から見ていたが、博士から借りたスターバース家の記録類を読むために、ひとり二階の寝室のあがり、書類を読んでは、スターバースの若い当主が灯りをもって籠った所長室を望見する、というのを繰り返した。
ふと、ランポールが書類を読む目を監獄のほうに向けると、所長室は暗くなっていた。時刻はまだ十二時になっていない。不吉な予感に襲われたランポールは家を飛び出し、監獄へと走った。そのあとを牧師も追う――。

いつもは、書かないほうがいいことまで書いてしまうが、この『魔女の隠れ家』にかぎっては、ここでプロットを追うのをやめる。子供のわたしがこの物語に強く惹かれたのは、殺人事件の論理的解決ではなかったので、ここから先はそれほど重要ではないのだ。
◎情緒と論理の等価交換:怪奇趣味の効用
魔女は怪奇的趣向を盛るためのいわば装飾だが、相続のための不可解な儀式はきちんと論理的に説明されるし、探偵自身が、遠望ではあるが、犯行現場を観察している、というミステリーの王道を行く仕掛けが施されている。
人物の入れ替えも、本格ミステリー黄金時代の礎のひとつとなったフィルポッツ『赤毛のレドメイン家』(1922年)を思わせ、若きディクスン・カーの『魔女の隠れ家』は、彼の代表作ではないにしても、たしかな骨格を持つ謎解き物語ではある。
(敗戦直後、本格ミステリーの書き手として「再登場」した横溝正史は、謎と論理の物語に転じた最大のきっかけはディクスン・カーの諸作、とりわけ『プレーグ・コート殺人事件』だったことを繰り返し書いている。いずれもいわば作家たちの「共有財産」だから、あげつらうつもりは毛頭ないと断っておくが、『魔女の隠れ家』の不可解で非現実的な、それでいて論理的な相続のルールは『犬神家の一族』を想起させるし、探偵が遠望で事件を目撃するのは『不死蝶』を、入れ替えは『悪魔の手毬唄』や『不死蝶』を思いだす。正史自身が考えていた以上に、彼はカーと体質がよく似ていたのかもしれない。)

しかし、子供のわたしが惹かれたのはそこではなかった。装飾である怪奇趣味のほうだった。いまではその傾向は薄れてしまったが、子供の時は怪談好きで、テレビでも『ミステリー・ゾーン』(原題Twilight Zone)を怖がりながらよく見ていた。『魔女の隠れ家』よりあとのことになるが、『アウター・リミッツ』という、後年の『Xファイル』にちょっと似た怪奇ものも、いつもビビりながら、欠かさず見ていた。
◎装飾と本体、本質と周縁
うっかり、「装飾」などと雑駁なことを云ってしまったが、ここはひとつ考慮のいるところだ。
長篇小説というのは、ある「世界」をつくり、その世界に読者を引き込み、ある一定の時間、その「世界」で「生きる感覚」を壊さずに、保持しつづけることを目標としている、と考える。
むろん、たとえば、いわゆる「ヌーヴォー・ロマン」、ロブ=グリエ『時間割』をこの定義に押し込むのはむずかしいかもしれないが、そういう「文学潮流」「文学界の動向」なんていうものは、それこそ飾りであり、日々の泡、時とともにうつろう「モード」「ファッション」にすぎず、「物語」の核心部分は、そうした風見鶏の右往左往のようなものには影響を受けない。
以上の枠組から云えば、たとえばこの『魔女の隠れ家』の瘴気に充ちた沼地、コレラ禍で廃された古い監獄、魔女伝説といった怪奇的要素は、「世界」を形作る重要な道具立てであって、読者がその物語を「生きる」のに必要不可欠な主要構成物質ではないか。
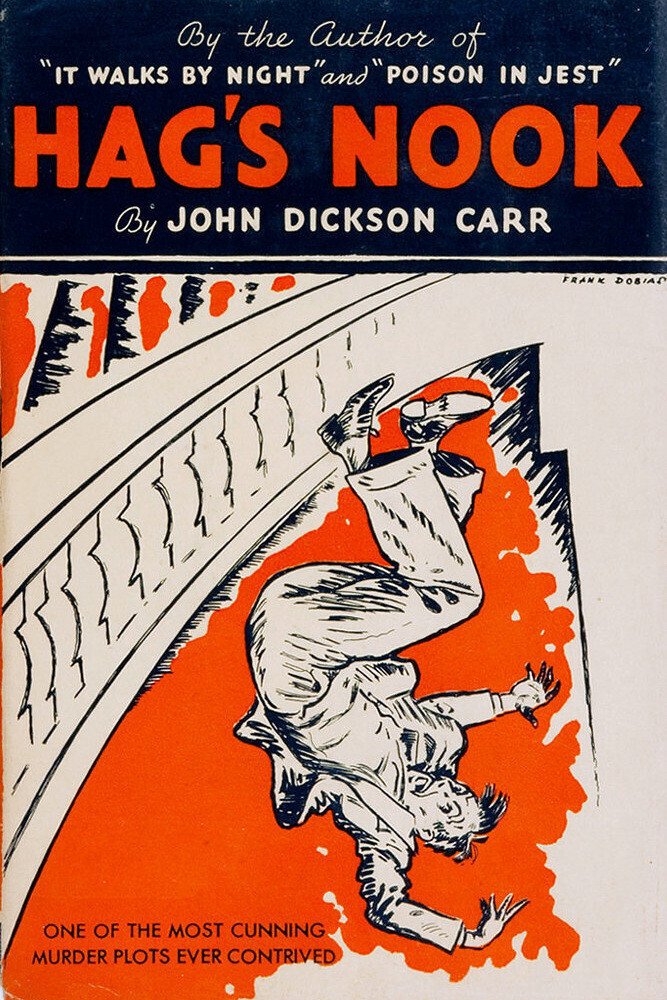
謎解き論理小説であっても、ただ謎を投げ出すだけでは誰も300ページの本など読みはしない。たんに犯罪があり、それが論理的に解決され、犯人が判明するだけなら、それはクイズであって、小説ではない。
探偵「小説」を成立させるのは、たとえば、スコットランドの古城であり、銀座の裏通りの酒場であり、瀬戸内海の小島であり、浅草六区の芝居小屋であり、そうした場の過去の曰く因縁、そこに暮らす人々の相貌である。時と場所と人を描く、という一般の小説となんら変わりがない。たんに、その「世界」に、犯罪とその論理的解決、という要素が追加されているだけだ。
◎「世界」をつくる、「世界」を見る
学生時代に読んだきりで、もうほとんど忘れてしまったが、フィツジェラルド『グレイト・ギャツビー』に、主人公が夜、愛するデイジーが暮らす対岸のロング・アイランドの灯をじっと見る場面がある。結局、ギャツビーを読んだ記憶はその一枚の絵に集約された。
同じように、『魔女の隠れ家』は、フェル博士とタッド・ランポールが、深夜、小高い丘にある廃監獄の窓の灯をじっと瞶める場面に集約され、わたしの記憶の中にしまわれた。ジョン・ディクスン・カーが子供に与えたものは、瘴気のぼる沼沢地の、魔女の隠れ家と云われる場所に建つ、古びた無人の監獄の、惻惻と迫る夜のたたずまいだった。

謎解き小説では、トリック、意外性、構成などの、小説の骨組の部分が重視される。それはそれで当然のことだろうけれど、顧みると、わたしがなによりもだいじだと感じていたのは、「世界」の構築、全体のムードだった。
どちらが鶏でどちらが卵かわからないが、『魔女の隠れ家』が提示した「世界」は、子供のわたしには素晴らしく魅惑的で、あのムードを味わうために、何度も巻を紐解いたし、わたしにとって、小説とは「ある世界を造形する行為」を意味するようになった。
『魔女の隠れ家』をカーの代表作などという人はいないし(江戸川乱歩は長文の「カー問答」のなかで、言及すらしていなかった。既読のものはすべてリスト・アップしていたので、執筆の時点で未読、まったく重視していなかったと思われる)、わたしだって、人にきかれたら、同じ怪奇趣味のあるものでも、たとえば『ユダの窓』あたりを代表作にあげる。

しかし、それでもなお、内々で過去の自分自身に問われたら、謎解き小説としてはせいぜいよく云ってもアヴェレージの出来かもしれないけれど、「世界」の造形に関する限り、やっぱり『魔女の隠れ家』がナンバーワンだよなあ、俺はお前のテイストを全面的に支持するぜ、と小学生の自分自身と握手して笑うだろう。
あかね書房版『少年少女世界推理文学全集』全20巻の配本が終わった時、わたしは小学校五年生になり、大人の本を読むようになっていた。「推理」の言葉に惹かれ、また、値段が安かったこともあり、つぎに読んだ本は創元推理文庫のJ・G・バラード『沈んだ世界』だった。
そのつぎは、ジャン=ポール・ベルモンド主演の『ある晴れた朝突然に』に感銘を受けたせいで、やはり創元推理文庫収録、ハドリー・チェイスの同題原作という妙な方向に曲がったが(映画のように面白くはなかった)、六年生の時にちょうど配本がはじまった岩波の新装「漱石全集」を買ってもらい、メインラインに乗った。

『少年少女世界推理文学全集』は本の虫人生の出発点であり、全20巻の中でもっとも強い印象が残ったのはジョン・ディクスン・カー『魔女のかくれ家』だった。
◎英国のアメリカ人
最初は子供向きにリライトされたエディション(ただし、いま目次を見るかぎり構成は原本に忠実だったと思われる)、大人になってからは創元推理文庫のエディションを読んだので、今回は原文を読んでみた。今年はじめには、『ニューゲイトの花嫁』(The Bride of Newgate)も原文で読んでいるし、『帽子蒐集狂』と『皇帝の嗅煙草入れ』は原書と訳書と行ったり来たりしながら読んだ。
昔から、カーの翻訳はひどいという評判が高く、じっさい、わたしが若いときに読んだ邦訳も難渋するものが多かったのだが、原書を読んでみて、翻訳者の方々が苦労したのも無理はないと、いくぶんか同情した。
カーはアメリカ人だが、処女作出版後、英国に渡り、英国を舞台にしたミステリーを多数書いた。アメリカ人であることは強く意識していただろうし、古色蒼然たる舞台づくりを好んだせいもあったのだろう、カーの文章は過度に英国的で、古い言葉、古い言いまわしにあふれている。異国の地に過適応してしまい、英国人以上に英国的な英語を書くようになったのだと思う。
米国英語で育った人間には、カーの行き過ぎた英国英語はしんどい。『ニューゲイトの花嫁』も『魔女の隠れ家』も、読了にはひどく時間がかかった。たとえば、エド・マクベインやアーサー・C・クラークのような「平易な英文」などではないのだ。

馴染みのない単語が多くて頻繁に辞書を引かなければならないし、ときおり、えーと、と考え込むような構文も出てくる。忙しい翻訳者、粗忽な書き手が、エラーを連発したのも無理はない。いまならば、意味の通らない文章は校閲部に指摘されるだろうが、おそらく、昔は校閲など入らなかったのだろう。翻訳者には好かれないであろう作家だ。
◎魔女対妖女、Witch対Hag
カーはHagを使っているが、魔女にはWitchを使うことが多いのではないだろうか。一応、両者の違いを調べた。
例のエニシダの枝かなにかでできた箒に乗って空を飛んだり、大鍋でスープをつくったりする、魔法を使う女という意味の「魔女」はWitch。
それに対し、Hagは超自然の力を持つモンスターであったり、たんに年を取って人間離れした相貌を持った老婦人を云うこともあるそうだ(年を取ったJoni Mitchellの壊れた声が大嫌いで、いつも「気味の悪い魔女声」と云っているが、この場合は、Witchは不可、Hagを使うべし、ということになる!)。
Witchは人間であるのに対し、Hagは人間とは限らず、人外の化物も指すという違いがある、のだそうだ。
しかし、カーの『魔女の隠れ家』で語られるのは、中世の魔女裁判の定義での魔女であり、どちらかというとWitchである。思うに、カーにとっては、Hagのほうが英国的響きが感じられたから、一般的なWitchの代用として言い換えたのではないか。意味、定義ではなく、あくまでもニュアンスのレベルでの判断だと想像する。
