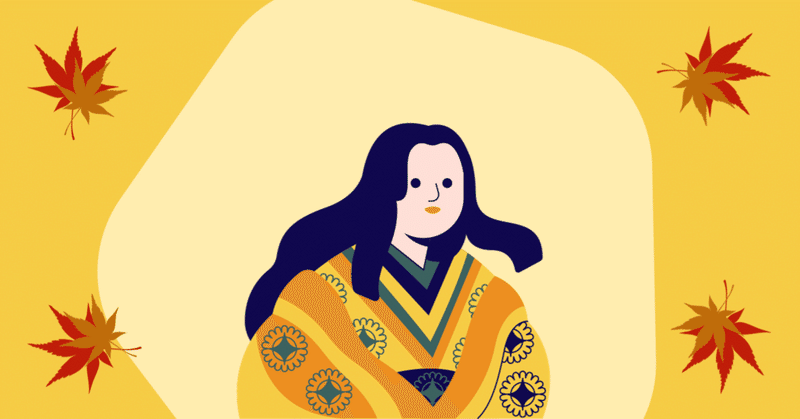
ジェンダー表象で読む『光る君へ』18回
NHK大河ドラマ『光る君へ』。紫式部を主人公、もう一人の主人公に藤原道長を据え、平安時代の世相と政争を描く本作は、5/5に第18回の放送を迎えた。
本稿では今回の『光る君へ』を、ジェンダー表象の角度から読み込んでいく。
まひろの憧憬—誰でも政治のできる国
冒頭、まひろ(紫式部)の親戚、藤原宣孝が邸宅を訪れる。太宰府帰りの彼は中国(宋)の商人や役人から聞いた話をまひろに披露した。
「宋には科挙という制度があり、これに受かれば身分が低くとも政に加われるそうだ」
それを聞いたまひろは、身分を超えて機会の与えられる国があるとは、と目を丸くする。
場面は転じ、中盤。大学で試験勉強に励むまひろの弟、惟規が帰省する。惟規が、学生の間で白居易による「白氏文集」が流行っていると話すと、まひろはこれに大いに興味を示す。
「読んだことない」
「白居易が、民に代わって時の為政者を糾しているものなんだよ」
まひろが父や惟規に頼んで「白氏文集」を読もうと熱望する、という一幕だ。

これら二つのシーンからは、まひろがもはや単なる勉強・文学好きではなく、民衆が政治に加わり、その恩恵を得られる世の中を作りたいという民主主義的理想を抱く、政治的主体であることを読み取れる。
まひろの社会への課題意識は直秀(友人の散楽師。宮殿から盗んだ財物を庶民に配った咎で処刑された)の死、農家の娘たねへの文字の教授、疫病によるたねの死…を経て強くなっていったものだが、その思いが宋、科挙のことを聞いたことで一段大きくなったのが今回だ。
かと言って、まひろを「リベラルで政治的な、ふつうの女とは違った男勝りな人物」などにしないところが、「光る君へ」の良いところだろう。
宣孝から宋の話を聞く一幕で差し込まれた、お土産の口紅をさすシーンの役割はそこにある。
本作は女性の活躍を描くフェミニズム的作品ではあるが、強く逞しい女ではなく、当時の社会の規範の内側にあるひとりの女性の政治的理想と邁進を描いている。現代の女性にも「強くあれ、ひとりで抗え」というより「強くなくとも、抱いた違和感を大事にしよう」という風な、より連帯感のあるメッセージを送っているのではないか。
道兼の死 —父という呪縛を越えて
第17回の終盤、関白である藤原道隆が没した。新たな関白に任ぜられたのはその弟、道兼だ。彼の成長と、死とが描かれた今回、改めてその変遷を読み取ってみよう。
道兼と言えば、父親からの覚えの良い道隆とのギャップに苦しむ姿が印象的なキャラクターだった。父からの愛と信頼に飢える激情家で、青年期には頭に血が昇ってまひろの母親を殺害。父の権力でそれを揉み消してもらって以来、一族の汚れ仕事を任される損な役回り(天皇に毒を盛る、天皇を唆し出家させるなど)を担っていたが、いざ父が没して次の関白になったのは憎き兄、道隆だった。

出世叶わず、妻子にも見捨てられ、道兼の生活は荒れたが、弟である道長が彼の心を救うことになる。
もう父の幻影に悩むことは無いのだ、という道長の言葉を受け、道兼は彼と共に「真に民のための政治」を志す。内裏の私財に過ぎない宮殿の多額の費用をかけようとした道隆を諌めたり、疫病に苦しむ庶民のために私財を投げ打って救小屋を建設したりといった行動からは、道長のその理想を垣間見ることができるだろう。
(呪術的性格の強かった当時の政治において、租税の役割は今でいうお賽銭のようなものだった。それゆえ「祈り」の精度を高められそうな宮殿改修に予算が割かれ、民衆の生活を実際に向上させる疫病対策などは後回しにされていた。道長は租税の再配分を通して、それを変えようとしているのだ。)
さて、道兼が関白として口にした台詞は少ない。少ないながらも、彼の人間観の変遷を感じさせるには十分なものばかりだった。
道長とのやり取りで見られた、
「父上に、もはや恨みはない。されど、あの世の父上を驚かせるような政をしたいものだ。まずは諸国の租税を減免し、新規の荘園を停止しよう」
という言葉は特に印象的だ。ここに彼の全てが詰まっていると言っても過言ではない。

まず、「父上にもはや恨みはない」という言葉。 父である関白、藤原兼家は当時において圧倒的な実力者であり権力者だった。その生前、藤原家の面々一人一人の運命を決定できた兼家は、まさに父権の象徴だった。
道兼はかつてその父権を引き継ぐことを目指し、父権の一機能として彼に従い、そして兄がそれを横取ったがゆえに父を恨んだ。その道兼が「恨みはない」と言うのは、彼が兼家=父権の呪縛から解き放たれたことの証左である。
そして「父上を驚かせるような政をしたい」。それがどんなものかというと、続く減税と荘園停止だ。政策として示されているのはいずれも庶民の負担軽減策で、道長の理想とする「富の再分配」と重なる。これは貴族制の中に閉じていた父=兼家には、たしかに思いつきもしない政策だろうが、その政策によって「驚かせたい」というのが絶妙に両義的だ。
富の再配分を実現したいという純粋な志であり、死した父に張り合おうとしてしまう、父権意識の残滓でもある。
別稿にて論ずる予定だが、「光る君へ」は貴族社会・男性社会の有害さと、それに対する抵抗を丁寧に描く物語である。
道兼が辿った変化は、まさに内在化したホモソーシャル規範の放棄である一方、感情面でそれに折り合いをつけきれない人間らしさも描かれており、誠実な描写がなされていたように感じる。
そんな道兼だが、関白就任後わずか7日でこの世を去る。疫病への感染が原因だった。咳き込む彼は念仏を唱えるが、いずれ自嘲的に
「俺は浄土に行こうとしておるのか?無様な…こんな悪人が」
と呟き、笑う。道兼の最期の台詞であった。
先週第17回では道隆の死が描かれたので否応なくそれと比べてしまうが、妻に看取られ、一家の行く末を祈り、かつて妻に送った歌を辞世の句とした道隆は、平安時代の貴族として極めて模範的な死に方をしたと言えるだろう。
その一方、暗がりでひとり己の罪を悔い、念仏すら中断した道兼。道長の影響から彼が抱いた貴族社会の常識への疑いが、その規範からの逸脱という形で死に様にも表れていると言えるだろう。
男性貴族を中心とする社会の特権性を端的に表現したキャラクターとして登場しながら、排斥の被害者としての面を描かれ、最終的にはそれゆえに自身の視野を広く民衆に開き始めていた道兼。
最期は民衆と死因を一にすることで、真に貴族社会の呪縛から解放されたのかもしれない。
諭す詮子と罵る伊周—ヒステリーの解体
今回サブタイトルである「岐路」に読み込まれているものの一つが、道兼の死を受けた、道長の昇進である。妻である定子の兄、藤原伊周を次の関白にしようと決めていた一条天皇が、関白を空位とし、実質的な内裏のトップを道長にするよう決定を覆すシーンは、藤原家の政争における岐路だと言える。
一条天皇のこの決定に至る背景には、彼の母であり道長の姉、詮子の言葉があった。

深夜一条天皇を訪ねた詮子は「どけ」の一言(厳密には2回)で守衛を払うと、関白時代の道隆がいかに横暴を働いたか、その息子である伊周を関白にすることがどれほど危険かを説いた。そして「自分のことなどどうでもいい」と断言した上で、一条天皇が操り人形にならないためには、我欲の無い道長こそが必要だと理に訴える。吉田羊の熱演が魅力を大いに高めたこの一幕では、詮子の(父譲りであろう)論理性と、我が子への強い思いとが豊かに表現されていた。
さて、そんな詮子と対比されるのが、直後のシーンで登場する伊周だ。道長に昇進人事があったと知らされた彼が、妹である定子のもとに「話が違う」と詰め寄る際、詮子同様「どけ」と人払いをすることで、二人の叫びは対比構造を明示する。
この「どけ」の発声にも見事な仕掛けがなされていて、詮子の「どけ」が大声というよりも鋭い声であった一方、伊周のそれはまさに怒声だった。
そして話の内容としても、その言葉は一条天皇に言うことを聞かせられなかった定子への罵声と、一条天皇を繋ぎ止めるための出産の強要であり、「産む機械」としての女を交換して男の絆の土台とする、典型的な家父長のイメージを表現している。
自分のことなどどうでもいい、と過去の藤原家の振る舞いと天皇に歩んでほしい道筋を示した詮子と、自分が関白になるために、と定子に出産を強要した伊周。鋭く放たれる「どけ」と、張り上げられた「どけ」。両者の視野の広さと感情を抑える力の違いが描かれたこれらのシーンで、筆者の脳裏によぎったのはフランソワーズ・エリチエの研究だ。
彼女はアリストテレスやダヴィンチを参照して、かつて存在した「男女の考える能力の差」にまつわる言説を以下のように分析する。
精液は骨に集まり、頭部に蓄えられ、次いで脊髄に沿ってペニスまでゆっくりと流れていく。(中略)男性の性的能力は、いわば、男性の知的能力の証である。この二つの能力は精液という同一の媒体を用いている。
ところが女性の頭には精液はなく、空になっている。(中略、子宮が位置を変えることから)子宮が女性の頭という空洞に入り込んでいることもあり、それは最も純然たるヒステリーの典型だとされる。
フランソワーズ・エリチエ(井上たか子、石田久仁子訳)
明石書店
考える力は男性にのみあり、それは精液に由来する。精液を持たない女性の頭の中は空っぽで、かわりに子宮がそこに入るので、感情をコントロールできずにヒステリーを起こすのだ、という理解が、少なくともルネサンス期まではあった、というのがエリチエの分析だ。
荒唐無稽だと思うだろうが、じっさい「ヒステリー」という語は「子宮」を意味するギリシア語ヒステラ Hysteraから来ており、感情の爆発と思考能力の不足とは、そのまま女性性とセットに観念されてきたのだ。
「光る君へ」第18回で明示的に対比された詮子と伊周は、こうしたヒステリーに関する言説を解体している。感情を爆発させ怒り任せに罵詈雑言を吐く伊周に対して、詮子は広い視野=思考能力を持つ者として描かれる。
ヒステリーを起こすのは女性に限らないし、思考能力があるのは男性に限らない。そうした静かで理知的なメッセージを、両者の対比に読み取ることができる。
画像出典
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
