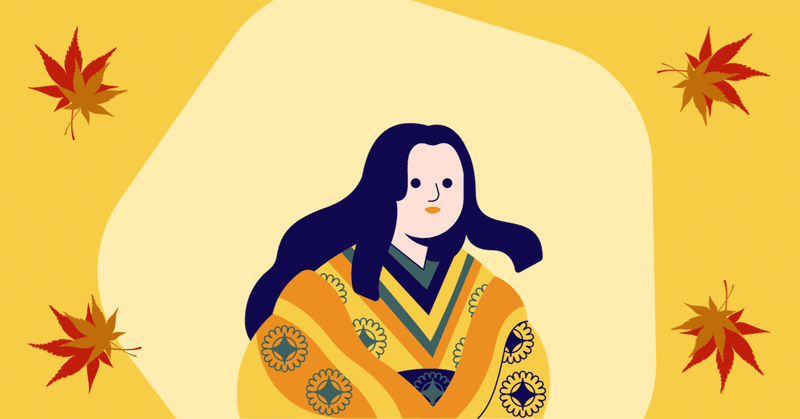
ジェンダー表象で読む『光る君へ』19回
NHK大河ドラマ『光る君へ』。紫式部を主人公、もう一人の主人公に藤原道長を据え、平安時代の世相と政争を描く本作は、5/12に第19回の放送を迎えた。
本稿では今回の『光る君へ』を、ジェンダー表象の角度から読み込んでいく。
まひろとききょう―ポストフェミニズムとの超克
まひろ(紫式部)には何人かの友人が登場している。放送時点で最も親しい友人のひとりがさわ、もう一人がききょう(清少納言)だ。彼女らとの交わりについて本作が示そうとしているものはなにか。さわの結婚、ききょうの仲介による朝廷への参内が描かれた今回、両者を比較してみたい。
まずはききょうとのこれまでについて。
第6回「二人の才女」で初登場したききょうは、まひろと共に藤原道隆の開く漢詩の会に参加する。学者であるそれぞれの父親に付き添う形で、上級貴族の面々が作る漢詩に対して講評を行っていた。おどおどとした様子で講評を伝えるまひろ、そんなまひろの言葉を「私はそうは思いません」とはっきり否定し自分の考えを堂々と述べるききょう。希代の二人の女流作家は実に対比的に描かれた。
まひろの父為時の在官中は、時折催される宮中での集まりで顔を合わせていた二人だが、為時の離職以来まひろと内裏との距離が開いたことから少し疎遠になる。この間、ききょうは藤原道隆の娘、一条天皇の中宮定子の女房に出世。時折まひろの邸宅を訪れては彼女に宮中での人間模様などを話す(愚痴る?)ようになる。

ここまで一貫して、ききょうには、「強い女性」のイメージがあてがわれている。自身の知識や才に基づいた物怖じしない発言と共に登場し、定子のもとに出仕を決めた際には「仕事の邪魔になるから」と夫と離縁。宮中で藤原斉信に言い寄られた際も「一度寝ただけでいい気にならないで」と言い放つ。演じるファーストサマーウイカが「キャリアウーマン」と呼ぶのが何となく腑に落ちるような、自分自身の成長のためには家庭も体裁も顧みない姿勢である。(本稿とは直接関係しないが、キャリアウーマンという語が、女性に家庭と労働の二者択一を迫る響きとともに使用されている現状には批判が必要である。)
第19回でもその「強さ」は遺憾なく発揮された。
いつも通りまひろと話していたききょうは、まひろが政治に関心を持っていることを知り、主君である定子がきっと彼女の話を面白がると考える。そしてまひろをつれて参内するのだが、ふたりが歩く廊下には嫌がらせのために画鋲が撒かれていた。
落ち着いた様子でききょうは「こうした嫌がらせは内裏では毎日のこと」とまひろに話す。
「でもそんなこと私は平気です。中宮様が楽しそうにお笑いになるのを見ると、嫌なことはみーんな吹き飛んでしまいますゆえ!」
高らかに宣言するききょうを背景に、画鋲を撒いているであろう女官たちのシルエットが映る。中宮定子との仲も深いききょうは他の女官からの嫉妬を集めているようだ。
そんなききょうの姿から連想されるのは、主君と忠臣の間に(あくまで理想像として)表象されがちな、ある種マッチョな封建的絆である。主君の喜びを自らの喜びとし、そのためであれば家庭も自分の血も犠牲にするという盲目的な忠誠心。
ききょうが背負う、男性的な「強さ」のイメージからは、少し前までの朝ドラヒロインと地続きである。
たとえば『カーネーション』の主人公、糸子。

同作の第二回のあらすじは以下の通りだ。
学校で糸子(二宮星)は一生糸で食べていけるようにという名前の由来を話す。担任教師の、将来は嫁として実家の呉服屋を盛りたてろという言葉に、糸子は、だんじりに乗るために大工になりたいと答え、みんなに笑われる。男子とケンカしたあげく、用務員に頭突きをして担任からきつく叱られても、まったくこたえない。父・善作(小林薫)の言いつけで、同級生・吉田奈津(高須瑠香)の家、高級料亭「吉田屋」に集金に行くことに…。
※太字は筆者による
男性のものとされていた祭事や職業への憧れ、暴力への傾向。「男勝り」というやつだ。年間2作が放映される朝ドラなので様々なヒロインが登場するが、糸子のような、社会の押し付けるジェンダー規範に抗う男勝りな女性、というキャラクターは一定数存在する。
こうしたキャラクターの造形や、2024年現在における「女性の活躍」という語の用法において念頭に置かれているのは、ポストフェミニズムである。詳細は省くが、新自由主義の台頭によって社会(政府)による個人への福祉が軽視されるようになった90年代以降、フェミニズムは「女性全体の権利」の回復というよりも、「努力した優秀な女性による経済的な出世」へと向かうようになる。これまで社会が女性に押し付けていた枷や、それに抵抗した歴史を否定し、個人の努力や性質による成功を至上の(市場の)価値とする、ポストフェミニズムの誕生だ。
『光る君へ』に視点を戻してききょうを見てみると、彼女を貫く価値観はきわめてポストフェミニズム的である。庶民の女児に文字を教えるまひろに「そんなことをしても意味がない」と言ったり、科挙の制度へ賞賛を示すまひろに「そんなこと(政)は殿方に任せておけばいい」と言うききょうの中には、「社会」が存在しない。自分が努力し、自分が出世し、自分の愛する定子が喜べばよい。
そのききょうと友人として接しながらも、やはり対比的に「社会」を見ているのがまひろである。庶民の貧しさと教育へのアクセスの無さに心を痛め、また政治に関われる者の特権性にも並々ならぬ疑念を抱いた上で、今回の放映では一条天皇に科挙の導入を提言した彼女は、貴族社会から庶民と女性を解放させようと奮闘する、ウーマン・リブの活動家だ。
ポストフェミニズムとその基底にある新自由主義は、個人による競争を最重視し、社会による福祉や連帯を透明化している。その過程には、ウーマン・リブへの反動も含まれ、こんにち多くの若者が「世の中に多くの価値をもたらしているなら男女は関係ない、したがって女性全体に対する抑圧は存在しないし、それに対する施策(ウーマン・リブ)は逆差別だ」という考えに陥っているのはまさにそれである。
このように、ききょう=ポストフェミニズムと、まひろ=ウーマン・リブとの間には思想的な対立・断絶があるのだが、『光る君へ』が優れているのはききょうをまひろからは理解できない存在として他者化するのではなく、まひろとの間に絆を持たせている点だ。
お互い異なる女性観、権力観を持ちながらも、緩やかに苦楽を共有する仲間。二元論的に善悪・優劣に囚われず両者の仲を描く本作は、ポストフェミニズムをも包摂する、現代フェミニズムの一種の理想系に迫っているのかも知れない。
まひろとさわ―階層を越えたユートピア的連帯
さわはまひろの父、為時の愛人?である「高倉の女」の娘である。さわと母親の家族関係は少し複雑で、さわは「高倉の女」が最初の結婚で授かった娘ながら、彼女が病気にかかり離縁したあとは父親の家で暮らしていた。再婚した父親と、腹違いのきょうだいとの暮らしに閉塞感を抱いていた彼女だが、産みの母親である「高倉の女」の今際の際に、彼女を看病する為時と、まひろに出会う。
ともに肉親を失った身ということもあり、さわは生まれて初めてできた友人として、まひろとの仲を深めていった。

さわとまひろとの関係を論じるにあたり、重要なのが第15回だ。ある日二人は石山寺に良縁祈願として参拝するのだが、向かう道中さわからの提案で、「もし良縁に恵まれなかったとしても二人で一緒に暮らしましょう」と約束を交わす。成人女性は婿を取るのが家のためであり、そのことが自身の幸せでもある、という観念が作中キャラクター(上級貴族や為時家の下女いと等)からも繰り返される中で二人の交わした約束は異性婚規範からの逸脱を宣言するようなものである。
石山寺に到着すると、「蜻蛉日記」の作者、藤原道綱母(寧子)と偶然鉢合わせる。「蜻蛉日記」を愛読していたまひろは、藤原兼家の愛人(妾)であった彼女から「自分は日記を書くことで、妾のとしての悲しみを救った」という言葉を聞く。寧子の言葉は、長年慕ってきた道長から妾になるよう言われ深く傷ついていたまひろの心情とリンクするものだが、その場にさわも居合わせていることが重要だ。

文学者としてのまひろに影響を与えていると言う意味で、寧子と麻尋の間には師弟めいた関係が仮想され、また母を亡くしたまひろに「私に娘がいれば」と語り掛ける寧子は、象徴的には母親の役割も担っている。そして同じく母親と死別し、今の家では前妻との子として腹違いのきょうだい達と暮らす孤独なさわも、寧子の「いたかもしれない娘」の可能性といえる。
ここで寧子がまひろとさわと共有するものは、男性に従属し、男性の性的対象とされる女性の困難である。権力者、兼家から関心を持たれたことは必ずしも寧子を幸せにしなかった。さわは父が「高倉の女」を見限り再婚したために母と同じ孤独を抱えることになったし、道兼と心を通わせたまひろでも、結婚相手に求める身分という規範に阻まれ二人は結ばれない。
規範の外側に自らを置こうとしているのが前章で論じたききょうだとすれば、この3人は規範の内側でもがいている。
一方で寧子とまひろは自己を表現する言葉を持ち、それによって「悲しみを救う」ことができるが、さわはそうした教養を持たない。文章を読み、自分で作る自閉的な時間を持つことは、社会規範の中で相対化され続ける客体から、自分なりの価値の中で絶対的な主体になるということでもある。したがって寧子もまひろもどこかマイペースというか、他人と自分を比べることなく心を守れているのだが、その手段を持たないさわは他者=男性からの評価でしか自分を位置づけられない。
そのことが端的に表れるのが石山寺での夜のことで、藤原道綱がさわにかける夜這いのシーンだ。「選ばれる性」としての規範を内面化させているさわの表情は満更でもなさそうだったが、道綱がさわのことをまひろと「間違えた」と口を滑らせたことで一転、失意に打ちひしがれる。行きの道中では男性に頼らないまひろとの暮らしを夢見ていた彼女だが、そのまひろとの間にある、男性にとっての魅力の差を可視化されたことで、まひろとも絶交してしまった。
規範の内側で同じように苦しむまひろとさわだが、ふたりの間には決定的な育ち、知識の差がある。
しかしその差を乗り越えようとするのがさわである。さわへの配慮を欠いた振る舞いを詫びるまひろから届いた手紙を、さわはすべて書き写したのだ。
今回冒頭では、父親の九州赴任にともない転居したさわから結婚を知らせる手紙がまひろのもとへ届く。最終的にさわは「家」に所属する妻として社会規範の一部に取り込まれたわけだが、それを自分の意志で解釈して他者に伝えるための言葉を得た。規範の中でこれから苦しむことがあっても、寧子と同様自分の心を救うための言葉を。ここにはききょうとの関係とはまた異なる連帯の形が示されている。違う方向の正義を抱えながらも同じだけの力を持つ者同士連帯するという形ではなく、力の差や階級を越えて社会全体に立ち向かおうというシスターフッドである。
このようにさわとの関係を読み込んでいくと、規範の外側で生きることのできる(ききょう的な)強さ以上に、規範の内側で悩む人々と心を通わせる弱さの面が強調されていることがわかる。さわや寧子の苦しみを吸い上げ、規範の解体へと向かっていく、まひろのこれからに注目だ。
画像出典
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
