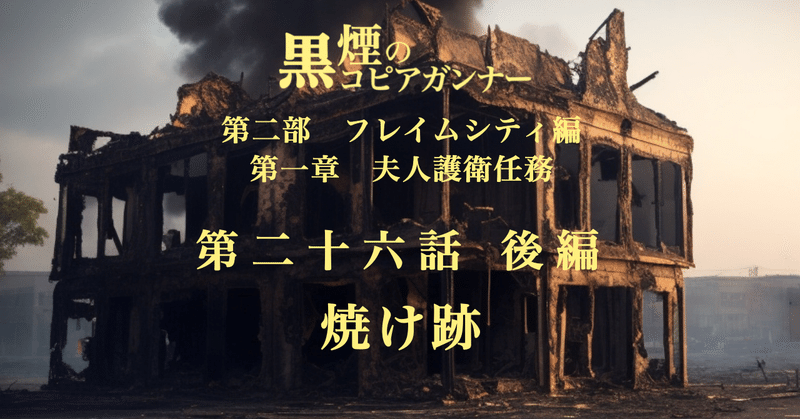
【連載】黒煙のコピアガンナー 第二十六話 後編 焼け跡
[第二十六話 後編]焼け跡
翌朝、すっかり元気になったアトラスは絶好調だった。
「使えそうな物は全部ここに一旦持ってきて! 復興に必要な道具は全部把握しておきたい!」
アトラスは、ギャバンが毎朝やっていた収穫物の集計の手順で復興に使える物資を中央広場に集めさせていた。
やけに元気で快活なアトラスに振り回される人達はその異常な明るさに戸惑った。
「アトラスさん、回復したと思ったらいつも以上に元気なのね」
「病み上がりでおかしくなってるんじゃねえの?」
ニッキーとジョンは特にこき使われまくっていて、アトラスに聞こえない所で文句を言っていた。
「ローディ! 君は何をやってるんだ! 寝てなきゃダメじゃないか!」
松葉杖をついて中央広場に来たローディをアトラスは追い返そうとした。ローディはパリスの迅速で適切な治療のおかげで一命を取り留めたが、傷口はまだ塞がっていなかった。
「俺は幹部直属部隊の一員です。寝ていられません」
「ほらほら、血が染みてきてる。ダメだよ、大人しくして!」
「ローディ!! もし傷口に菌が入ったらどうするんだ! 頼むから寝ててくれよ!」
ハーディは半泣きでローディを追い返す。
「ハーディ。何泣いてるんだ。俺は無事だぞ!」
「どこが無事なんだよ! お前は重傷者だ!」
「足以外問題ないのに休んでいられるか!」
「いい加減にしろよ! バカ野郎!!」
アトラスは弟達のケンカが始まってしまい、困り果てる。
「君達、仕事の邪魔するなら2人揃って学校に戻ってなさい」
「なっ……何で俺まで!?」
「アトラス兄さん……!」
「ハーディも気持ちが沈んでるなら少し休んだ方がいい。泣いてばかりじゃ仕事にならないだろ。ローディは絶対安静だよ。その傷、立って動けるのが奇跡みたいなもんだ。ちゃんと休んで傷が塞がってからでも君なら遅れを取り戻せる。そうだろ?」
「俺は……大丈夫ですよ……」
「すみません。休ませていただきます」
ハーディとローディは2人仲良く学校へ戻っていった。アトラスは気疲れで溜息をつく。
「なんかいつもと違うんだよなあ」
アトラスは体が妙に軽いと自分でも自覚していた。その分頭の中は空っぽだ。思考パターンをよく知るハーディとローディを説得するのにもいつもより時間がかかっている気がするし、言うべき言葉がすぐに思いつかなくなっている。体調不良で頭がぼーっとしたままなのだろうか。だが、体は異常なほど動くのだった。
アトラスは仕事に戻った。町の人達が町中を探して見つけ出してくれている使えそうな物を分類して並べ直す。そこへ、郊外まで足を運んでいた人達が手ぶらで駆け付けた。
「アトラスさん! 大変だ!」
「ジェシーとコーディが帰ってきた!!」
「ええっ!?」
アトラスは彼らの言う方角へ走った。
ジェシーを乗せた白馬のクリスティーナが見えてきた。コーディがクリスティーナの横を歩いて手綱を引いている。
「ジェシー!!」
アトラスは逸る気持ちを抑えきれず、まだ遠くて輪郭しか見えないジェシーの名前を呼んだ。
ジェシーからの反応はなかった。
「アトラス兄さあーん!!」
コーディが片手を振って叫び返してきた。
「コーディ!!」
アトラスもコーディの名前を叫ぶ。
アトラスが近くまで来ると、クリスティーナは止まった。
「ジェシー、無事か? 怪我してるのか?」
ジェシーの目は虚ろだった。無言でクリスティーナから下りて、アトラスの質問に答えることなくフラフラとどこかへと歩き出す。
「おい、ジェシー。どうしたんだよ?」
「アトラス兄さん」
ジェシーを追いかけようとするアトラスをコーディが止めた。その目はきつく何かを禁じていた。
「何かあったのか?」
「……はい。だけど、聞かないでください」
「何で?」
「俺の方からは言えません」
コーディの表情は明らかにただ事ではなかった。アトラスは何かジェシーが深く傷つく事態が起きたのだと察した。町の中心へととぼとぼ歩いて行くジェシーの後ろ姿をただ見守ることしかできなかった。
「おかしいな……ジェシーの考えてることはいつだって手に取るようにわかったのに……」
アトラスは呟いた。ジェシーはまるで別人だった。心を閉ざして、何かを隠しているようだった。
* * *
ジェシーはギャング病院に向かっていた。左腕の傷口を治療しなければいけない。包帯代わりに巻いたシャツの切れ端は既に真っ赤だ。傷口を縫わないと出血多量で死ぬ恐れがあった。
ギャング病院があった場所まで来たジェシーは、目の前の光景に立ち尽くした。外壁は焼け落ち、真っ黒に焦げた柱が残るのみだ。床も丸焦げの棚やベッドが放置されている。
ジェシーはギャング病院の中に入っていった。煤と灰まみれの床を踏みしめる。しばらく廊下を行くと、比較的焼けずに残っている部屋があった。
その部屋は措置室だった。ジェシーはところどころ焼け焦げのある棚から使えそうな針と糸を探し出す。包帯を解いて傷口を鏡越しに見遣る。乱れた金髪の奥から怯えた青い瞳が見つめ返してきた。
なんて無様な姿だろう。自分でもそう思う。思考は冷え切っていて、ただそんな感想がぽつりと浮かんでくるだけだった。どこか他人事のようだ。ジェシー・ローズという人間そのものが消え去り、思考するだけの何かが残ったみたいだった。
ジェシーは何度も深呼吸をした。糸を通した針を腕に刺そうとしている。麻酔はない。傷口を麻酔なしで縫われるところを何度も見てきたが、自分がやるのは初めてだった。
「はあ……」
ジェシーは針を刺せずに机に置いた。指先が震えている。こんな程度のことも自分1人ではできない自分が悔しい。他人の腕なら何度もやってきた。なのに、どうして……。
「ジェシーさん……?」
優しく甘い声がジェシーを呼んだ。ジェシーはその声に驚き、跳ね上がる。
「大丈夫ですか? 怪我をしていると聞いたので来たのですけれど……」
「来ちゃダメだ」
「どうしてですか?」
「来るな!」
措置室に入りかけていたパリスが足を止める。
「僕を見るな……!」
ジェシーは過呼吸を起こしていた。嫌な汗が噴き出し、目は焦点が合わない。椅子から転げ落ちるジェシーを慌てて飛び込んだパリスが受け止めた。
「ジェシーさん!!」
ジェシーは上の空で荒く呼吸をし続けた。パリスが措置室のベッドにジェシーを寝かせて誰かを呼びに行った。誰も来ないでくれ。1人にしておいてくれ。こんな姿は誰にも見られたくないんだ。大事な人ならなおさら、こんな姿を晒したくない……。
* * *
目を覚ました時、ジェシーはまだ措置室のベッドの上だった。
元小児科医の女医のサラ・ライカ先生がベッド脇の椅子に座っていた。
「落ち着いた?」
穏やかで温かい声がジェシーにかけられた。
「ライカ先生……」
「傷口はパリスが縫ってくれましたよ。あの子は手際がよくて本当に優秀ね」
ジェシーは見えなくても左腕の違和感が減っているのを自覚した。
「コーディから何かとても怖い経験をしたのではないかと聞いていますよ」
ジェシーはコーディを恨んだ。隠しておきたいことをベラベラ喋ったり、誰にも話していないはずのことをいつの間にか知っていたり、兄達は一癖も二癖もあって本当に気が休まらない。
「もしも打ち明けたいことがあるなら私でよければ聞きますよ」
ジェシーは考えた。傷が治療され、眠ったことで少し気持ちが楽になったようだ。ライカ先生はジェシーから視線を外してジェシーが話しやすいようにしていてくれていた。ライカ先生になら話せるような気がしたが、何から話せばいいのかわからなかった。
「僕は……もう、自分が嫌になりました……」
やっと出てきた言葉は自分を否定する言葉だった。
「僕は皆を助けたくて……なのに……僕は……」
「医者が聖職だと思っていたのね、あなたは」
「そうじゃない……これはそんなこととは全然違うんです……僕は……」
ジェシーの体は震えていた。あの時の恐怖と嫌悪感が押し寄せてくる。それを消し去るために自分がしたこともまざまざと思い出す。ジェシーは穢された。二度と洗い流されることのない汚辱がジェシーを苛んでいた。
「僕にはもう生きている価値がないんです……」
それがジェシーの思っていることの全てだった。
「何を言っているんですか?」
措置室の扉の前にパリスが立っていた。
「あなたに生きている価値がないなんて誰が決めたんですか?」
「パリス……」
ジェシーはもう声にならない囁き声で名前を呼ぶしかできなかった。
「あなたが何に怯えているのか私はなんとなくわかりますよ。でもそれが何だって言うのですか。あなたはこんなに必死に生き残って、私達がいるこの町に帰ってきてくれたのに、それに価値がないなんて誰が決められるのですか?」
パリスは泣いていた。ライカ先生は2人きりにするために静かに措置室を出て行った。
「お前に何がわかるんだよ……!」
「わかりますよ!!」
パリスはジェシーに抱き着いた。その柔らかな感触はジェシーの傷ついた心を優しく包み込んだ。
「あなたの存在価値を私が教えてあげます。あなたはバークヒルズに必要不可欠なギャングの幹部です。誰よりも強く、誰よりも優しく、誰よりも仕事熱心で、労力を惜しまない。人から恐れられ、同時に信頼もされる、私達町の皆の頼りになる存在です」
ジェシーの震えは止まっていた。パリスからは温かい感情が感じられた。消毒液の臭いが染み付いた髪はジェシーの髪と同じ香りがした。
ジェシーは腕を上げてパリスの腰に手を回した。パリスは促されるようにしてベッドに乗り、ジェシーの上に跨った。ジェシーの唇がパリスの唇に触れた。柔らかくて温かいパリスの体の感触がジェシーを包み込む。
ジェシーの頬にパリスの温かい涙が零れ落ちた。ジェシーはその涙で自らの穢れが洗い流されるように感じた。パリスはいつでもジェシーの危機を救ってくれようとしている。自分が大事にされていると感じるのは今のジェシーにとって、とても重くて、抱えきれないほど幸福なことだった。
あの男にもてあそばれた体でパリスの体を受け止め、あの男の首を絞めた両手でパリスの背中を優しく撫でる。ジェシーは何故だか罪悪感で胸がいっぱいだった。状況は何一つ変わっていないのに、パリスの行動一つで自分の気分が楽になってしまうことを許せない気がしていた。
皆さまに楽しんでいただける素敵なお話をこれからも届けていきます。サポートありがとうございます!
