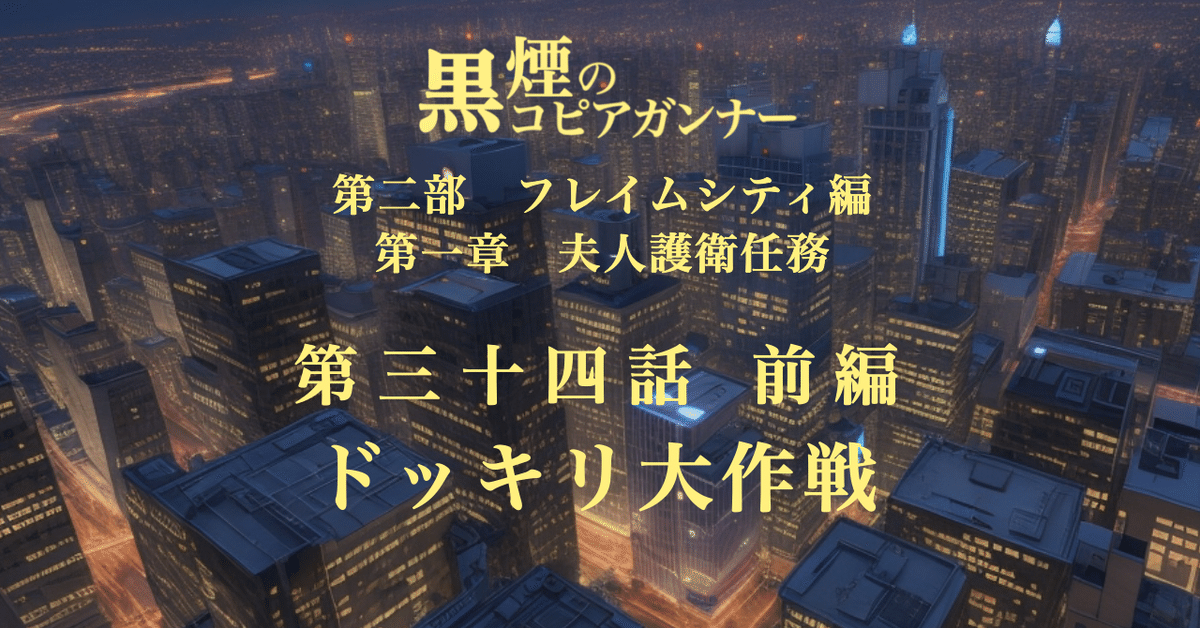
【連載】黒煙のコピアガンナー 第三十四話 前編 ドッキリ大作戦
[第三十四話 前編]ドッキリ大作戦
カズラ達一行がフレイムシティに来てから1ヶ月が経った。
計画通りにアンドリュー・イーデルステインの選挙応援パーティの会場となるホテルで清掃員と警備員の仕事に就いたパリス、ジョン、コーディは仕事をしながらホテルのバックヤードや警備の配置などの情報を仕入れてくる。
アパレルメーカーの工場で働くニッキーはフレイムシティの流行のファッションに詳しくなり、近所の酒屋で働くアトラスは酒の知識が豊富になっていった。
来た当初はバークヒルズの出身者だとバレやしないかとヒヤヒヤしていたが、だんだんとフレイムシティでの生活に慣れていく一行なのであった。
「ただいま~」
「腹減った~」
ジョンとコーディが警備の仕事から帰ってくるなりソファにどかっと寝そべる。
「ちょうどよかった。今、カズラさんとご飯食べに行こうって話してたとこなの」
ニッキーがダラダラしているジョンとコーディをソファにきちんと座らせながら言う。
「パリスは18時に退勤だからホテルまで迎えに行って、近くのレストランでディナーにしよう」
カズラがレストラン情報が載っている雑誌をテーブルに置く。
「何が食べたい?」
「肉!!!」
ジョンとコーディは2人同時に叫んだ。
* * *
そこから数日後。
ソウヤからジェシーの仕上がりが良くなってきたから見たい人は来てくれとの連絡があった。その日はたまたまニッキーとパリスが休みの日だったので、家事担当でアパートに籠り切りのカズラも含めた女性陣3人がウキウキとソウヤの邸宅に顔を出した。
「お嬢様とご友人方、よくぞお出でなさいました」
カズラとニッキーとパリスはメイドに深々と頭を下げて歓迎され、屋敷の中へと案内される。
「わあ、2回目でもやっぱり緊張するわ」
ニッキーが両手を握りしめて縮こまっている。
「ホテルで働いてると少しは慣れるもんですね。こんな大きなシャンデリアも」
パリスは以前よりもリラックスした様子だ。ニッキーは驚いてパリスをまじまじと見つめる。
「え、ホテルってこんな感じなんですか?」
「うん。お金持ちっぽい人が毎日宿泊に来るよ。最上階のスイートルームなんてのになると、私達ではとても目を合わせられないようなVIPが泊まってて、支配人が直々に挨拶に行ったりするの。そういう部屋は一流の清掃員が掃除を担当するから私はまだ行ったことがないよ」
「うっわ~、私なら緊張して倒れちゃいそう」
メイドがとある扉の前で立ち止まった。雑談していたニッキーとパリスも仰々しい扉を目の前にして黙り込む。
「ジェシーさんはこちらです」
メイドが体重をかけて重い扉をゆっくりと開ける。
昼過ぎの日光が射し込む明るい室内が見えてきた。部屋の中央に煌びやかな装飾の施された大きなテーブルがあり、その一角に華奢な女性が座っている。振り向くと、彼女は柔らかな笑みを浮かべて立ち上がった。
「ようこそお越しくださいましたわね。どうぞ、お掛けになって」
裏声に近い高めな声を聞いてニッキーとパリスとカズラはその女性がジェシーだと気付いた。
「ジェシーさん!!」
ニッキーとパリスは淑女の振る舞いをマスターしたジェシーに駆け寄った。
「すごーい! 本当に女の人みたーい!」
「おい、ニッキー。あんまりはしゃぐな」
ニッキーに腕を引っ張られてジェシーはイラついていつもの声のトーンに戻った。目つきもいつもに戻ってせっかくの美人が台無しだった。
「何で? こんなにすごいのに!」
「ったく、僕だって好きでこんな事してるわけじゃないんだぞ」
パリスはジェシーの髪型やメイクや服装、その全てに目を奪われていた。
「ジェシーさん、こんなに上品な薄紫色が似合うんですね。素敵です」
「あ、ま、まあな。カズラさんのワンピースを借りたんだ」
ジェシーはチラとカズラを見る。
「あぁ、いいぞ。別に。私は着ないからな」
「あ、ありがとうございます」
「ねえ、この格好でお出かけしてみましょうよ、ジェシーさん! 買い物しましょう!! 私、給料入ったから何でも買ってあげますよ!」
「ニッキー、勘弁してくれよ。君達に見られるのだって恥ずかしいんだぞ」
「ちょっとだけでいいから!」
ジェシーは女装して出歩くのを渋ったが、試しに街中を歩いてみることも必要なことだと思った。パーティ会場でいきなり人前に出たらどんなアクシデントに遭うかわからない。「じゃあ、ちょっとだけなら……」
ジェシーが小声で言うなりニッキーは飛び跳ねて喜んだ。
「やったー! アトラスさんが働いている酒屋に行きましょうよ。アトラスさんにも今のジェシーさんを見てもらいましょう」
「いいですね! きっとアトラスさんも褒めてくれますよ。ね、ジェシーさん?」
「な、何言ってるんだよ。パリス」
パリスもいつになく乗り気でジェシーは戸惑うばかりだ。
「ジェシーさんだって言わないで近づいてさ、後からバラすのなんてどう?」
「それ面白そう!」
ニッキーとパリスはもう決まった事のように話し出す。
「アトラス兄さんって酒屋で働いてるの?」
「そうですよ。お酒のビンって重いから最初は帰ったらすぐ寝ちゃうくらい疲れてたけど、最近はたくましくなりましたよね?」
「そうそう。帰りにお菓子買ってきてくれたりするよね」
「パン屋さんのレジ係の女の子と仲良くなって、廃棄のパンもらってきたりもしますよね」
「へえ、そうなんだ」
ジェシーはフレイムシティで元気に働くアトラスに胸の内がモヤモヤしていた。
「行こうよ。アトラス兄さんがどんな風にしてるのか見てみたい」
* * *
ジェシー、ニッキー、パリスはカズラが買った中古の車でアトラスがアルバイトをしている酒屋へ向かった。
真冬のフレイムシティをワンピース1枚では歩けないので、途中に寄ったアパレルショップでコートを買った。ついでに目つきでジェシーだとバレないようにサングラスも買った。
華やかにセットされた金髪、スラっとした体形を最大限に活かしたファッション、金色の装飾のついたサングラスをかけたジェシーは、スターがお忍びでショッピングに来ているような隠しきれない強烈なオーラを放っていた。
「着いた! あれがアトラスさんが働いてる酒屋ですよ」
ニッキーが車の窓に指先を押し付けて角の酒屋を指さす。
外壁全体を深緑色に塗られた店構えはシンプルで落ち着いた大人の雰囲気だった。
「行ってくる」
ジェシーが車を降りる。ニッキーとパリスがいたらすぐにジェシーだとわかってしまうので、ジェシーが1人で行く段取りになっていた。
ジェシーがハイヒールをコツコツと鳴らして歩き去っていく。
「わあ……」
「素敵……」
その後ろ姿にニッキーとパリスは見惚れていた。
店のドアを開けると、カランカランとドアにつけられたベルが鳴る。
「いらっしゃいませ」
店の奥からしゃがれた低めの声がする。レジ台の前まで行って店の奥を覗くと、白髪交じりの小太りの老人が棚の奥に手を伸ばしているのが見えた。
「おーい、アトラス。今、手が離せないんだ。お客さんの相手をしてくれないかね」
「はい、店長」
店長だというその老人がいる場所のさらに奥から若い男の声が聞こえた。姿は見えないが、ジェシーはそれがアトラスの声だと一発でわかった。
「今そちらへ行きますので、お待ちください」
アトラスはすぐにレジまで出てきた。白いシャツを着て、黒のサスペンダーでスーツのズボンを留めていた。蝶ネクタイは店の外壁と同じ深緑色だった。
「お待たせしました。今日はどんなものをお探しで?」
「いいえ、通りがかりに少し気になったものだから」
ジェシーは素知らぬふりをして高めの声で返事をする。
「そうでしたか。お酒はお好きですか? 好みを教えてくださればオススメをお出しします」
「ええ、そうね」
アトラスは何も気付いていない様子だった。ジェシーとしてはすぐに気付いてほしかった。昔、一度だけ姉のハンナのワンピースを着て会いに行った時はすぐに気付いてくれたのに、今回は見知らぬ女性に自分をよく見せようとするような張り切り方で活き活きと接客をしてくる。
「普段飲むのはワインですか? うちはリンゴ酒やピーチ酒などのブドウ以外の果物からできた果実酒も豊富ですよ」
試飲用のお酒の蓋を開けてプラスチックのカップにさっと注ぐアトラス。カップを差し出されたジェシーはそれを見ずに断る。
「いいえ、ごめんなさい。今日は私、これから予定があって」
「それは残念。どのようなご予定なんですか? ディナーのお約束でも?」
「そんな感じかしら。古くからの友人と食事をすることになって」
「ご友人とはいつからのお付き合いなんですか?」
「とても古いのよ、生まれた時から同じ町で育った仲ですから」
「それはとても深いご縁がおありなのでしょうね」
アトラスは得意げに話し続けながら、梯子を持ってきて棚の高い所に置いてある酒を物色する。その姿は楽しそうで何よりだった。
「そのご友人に男性の方はいらっしゃいますか?」
「ええ、男の方もいるにはいますけれど」
「でしたらこんなのがありますよ。年代物のウイスキーです。女性の方でも比較的飲みやすいタイプですよ」
アトラスが梯子の上から振り返ってウイスキーのビンをジェシーに見せる。ジェシーはサングラスを少し下げて、上目遣いにアトラスをじっくり睨みつけていた。
「あっ……えぇっ……!?」
アトラスは嗚咽を漏らしてさっと姿勢を戻して背を向けた。
「はあ、あったあった。ああ、いらっしゃい。お客さん。」
店長がウイスキーのビンを大事そうに抱えてレジに戻ってきた。ジェシーに軽い会釈をして、どかっとイスに座って店の電話に手を伸ばす。
「あー、ジェンキンスさん。ブルベット酒店です。お探しだったウイスキーがね、見つかりましたもんですからこうしてお電話差し上げたんですけれども。おぉ、そうでしたか。では明日お越しください。お待ちしております。では」
電話を切ると店長はイスに座ったままウイスキーのビンをタオルで磨き始めた。
数秒間、不自然な静けさが辺りを漂った。
「そうやってどの女性にも声をかけていらっしゃるの?」
ジェシーは女性のフリを続けた。
「いやあ、そんなつもりは……」
アトラスはジェシーの方を見ようともしない。今アトラスがどんな気持ちでいるのか想像してジェシーはニヤついた。
「ああ、そうだ。こっちの棚にはアケボシ国から仕入れた米酒なんていうのもありますよ。一度お試しになりませんか?」
アトラスは必死の形相で接客を続けた。はしごを下りてジェシーの顔を見ずに反対側の棚へと歩いていき、米酒のビンを探して持ってくる。
「まあ、米酒。そういえば、今日来る友人にはアケボシ国の方もいるんでしたわ」
ジェシーは近づいて米酒のビンにそっと手を添える。ビンを持つアトラスの手は震えていた。
「このお酒はどんな食事に合うのかしら。私、アケボシ国の料理は食べたことがありませんの」
「生魚の切り身をソイソースにつけて食べる料理がアケボシ国にはあるそうで、米酒はそういった料理に合うらしいですよ。僕も実はまだ食べたことがなくて、店長から教わった通りのことをお伝えしているだけなんですが」
「あら、そうでしたの。店長さんはお酒の知識が豊富でいらっしゃるのね」
ジェシーはサングラスを外してアトラスに笑顔を向けた。いい店で働いていて安心したことを伝えようとしたのだ。アトラスはジェシーの表情に何かを感じ取ったのか、引きつった笑顔から緊張感が消えた。
「今夜はお荷物になるのでしたら、お取り置きすることもできますよ。何か1本試してみてはいかがですか?」
アトラスはハキハキと接客をするようになった。ジェシーも酒に興味が湧いてきてアトラスの誘いに乗っかる。
「えぇ、そうね。なら、1本取り置いていただくわ」
「記念日とか、いいお酒が飲みたくなるようなことはありませんか? その日に合わせてラッピングしてお渡しすることもできます」
「記念日ね……」
「たとえば、誕生日とか」
アトラスがジェシーにニッコリと笑いかける。接客用ではなく、弟に向けられたいたずらっぽい笑顔だ。
ジェシーはアトラスが何かを伝えようとしているのだと感づいた。思考をフル回転させて思い当たる節がないか考える。そして、誕生日が近い人が身近にいるのを思い出した。
「そうね。もうすぐ誕生日の友人がいますわ」
ジェシーはなんだか照れ臭くなった。アトラスは自分の意図が伝わったとわかり嬉しそうだった。
「よかった。その人はどんなお酒が好みですか?」
「さあ、どうでしょう。まだお酒は飲んだことがないかもしれないわ」
「そうでしたか。まだお若いのですか?」
「ええ。去年成人したばかりで、お酒を飲める年齢ではあるけれど、勧めても飲もうとしなくて。不規則な仕事なので、酔いが残るとよくないと言って聞かないんですのよ」
「では、こちらのシェリー酒はいかがですか?」
アトラスが淡い金色のお酒を試飲カップに注いでジェシーに差し出した。ジェシーはそれを受け取り、口元へ持って行く。
「まあ、なんて甘い香り」
「でしょ? 女性の方に特に人気の一品なんですよ、それ。爽やかで口当たりがよくて、あまりお酒を飲んだことがない人でも楽しんでいただけるはずです」
ジェシーはシェリー酒を試飲してみた。さっと広がる軽い酸味を帯びた風味にジェシーは感動した。
「いいわ、これ。これにします」
「では、1本お取り置きですね。お渡しはいつがよろしいですか?」
「3月3日にお願いしますわ」
「かしこまりました」
アトラスは新しいシェリー酒のビンを持ってジェシーをレジへと案内する。レジの機械を片手で手早く操作して会計へと入った。
「友人が気に入りそうなお酒が見つかってよかったわ」
ジェシーは代金の受け渡しをしながらなおも話し続ける。アトラスは現金を受け取りレシートが出てくるのを待つ。
「大切なご友人ですか?」
「それはもう、もちろん」
ジェシーはフワフワした気分で話していた。アルコールが回ってきたのもあるだろうが、いい買い物ができて素直に嬉しかった。
「私は最も信頼できる人だと思っていますわ。誰よりも私のことを理解してくれるんです。本当に大事な人なのよ。私にとっては」
ジェシーのその様子を見てアトラスも満足げな表情をした。思いがけず兄の優しさに触れて、酔ったジェシーは舞い上がってしまいそうだった。
ジェシーが店から出てくると、車のシートを倒してグダグダしていたニッキーとパリスがシートを起こしてジェシーが車に乗り込むまでを見守った。
「どうでしたか? ジェシーさん」
「うん。すごく意外だった」
「何が? ジェシーさんだってすぐ気付いてくれたんですか?」
「アトラス兄さん、楽しそうに働いてるね。バークヒルズにいた頃とは全然違うじゃないか」
カズラが車を走らせる。ニッキーとパリスはアトラスの変貌ぶりを面白おかしく話し出した。ジェシーはそれを聞き流しながら、薄暗い酒屋の店内を見えなくなるまでじっと見つめていた。
* * *
2週間後。
アトラスが帰宅すると、安アパートの壁全体に紙の装飾品が貼りつけられていて、ホームパーティの準備が整っていた。
「おお、今日は盛大だね」
アトラスも帰りに買った誕生日ケーキの箱をカズラに渡してコートをかけに寝室へ行く。
「もうすぐ主役が帰ってくるから、皆早くこっち来て!」
ニッキーの指示で玄関に集められた一同はクラッカーをそれぞれ1個ずつ持たされた。後ろにはジェシーがアトラスの酒屋で買ったシェリー酒を持って立っている。
「せーのでクラッカーを引っ張るんですよ。いいですね? コーディさん、そのヒモあんまり触らないでください。暴発しますよ!」
「え、そうなの!?」
ニッキーが張り切ってパーティを取り仕切っている。コーディはクラッカーのヒモから手を放してじっとした。
しーんと静まり返った玄関。やがて、ドアの鍵が開けられて本日の主役が入ってきた。
「ただいまあ」
「パリスさん、ハッピーバースデー!」
「ハッピーバースデー!」
パリスの上空にクラッカーが放たれた。
「きゃあ!」
クラッカーの音にパリスは目を丸くして驚いた。色とりどりの紙のテープがパリスの頭に乗っかった。
「え、誕生日? わっ、何これ……!」
パリスは自分の誕生日であることよりも得体の知れないカラフルな爆発物への驚きが勝っていた。
「さあさあ、パリスさん。ジェシーさんからとびきりのバースデープレゼントがありますよ。どうぞこちらへ」
ニッキーがパリスを中へうながす。リビングの手前でジェシーがラッピングをされた細長い物を持って立っていた。
「パリス、誕生日おめでとう。これ、君も気に入るんじゃないかと思って……」
パリスはプレゼントを受け取った。
「これって……?」
「この前アトラス兄さんに選んでもらったシェリー酒。君にあげるよ」
パリスは頬を紅潮させた。ジェシーがそんな事を考えていたとは露ほども思っていなかったのだ。
「ありがとうございます! 一緒に飲みましょう!」
パリスは早速シェリー酒を飲もうとリビングへと足を踏み入れる。すると、目の前にはフライドチキンやグラタンなどの料理がズラッと並んでいた。
「わあ、こんなにおいしそうな物がたくさん。ありがとうございます!」
パリスは振り返って弾けるような満面の笑みでお礼を言った。パリスの嬉しそうな顔を見て満足した一同はわらわらとリビングに戻って食卓についた。
「冷めないうちに食べようぜ」
「俺もう腹減った!」
「お酒開けるヤツどこに置いたっけ?」
「大人はシェリー酒。ジョンとニッキーはまだ未成年だからオレンジジュースだよ」
「今日もオレンジジュースかぁ」
ニッキーが残念そうにしているが、アトラスはニヤニヤしながらオレンジジュースのビンを掲げる。
「ニッキー、今日のはいつもと違うよ」
「何がですか?」
「今日のはマラキア産プレミアムオレンジジュース」
「プレミアム!?」
それぞれのグラスにシェリー酒とオレンジジュースが注がれて、乾杯をして食事が始まった。
「シェリー酒あまっ!」
「何だこのチキン! うめえ! うますぎる!」
「あんまりがっつかないでよね、ジョン」
「お前ら、ケーキもあるの忘れるなよ」
コーディがシェリー酒の味に驚きの声を上げる隣で、ジョンがフライドチキンを両手で持ってかぶりついている。ニッキーはグラタンを自分の小皿に取り分けながらいつも肉ばかり食いつくすジョンに睨みを利かせている。賑やかに飲み食いする皆の楽しそうな姿をパリスは幸せそうに眺めていた。
「どうだ、パリス? その……味は……」
隣に座っていたジェシーが不安そうに聞いてくる。視線はパリスのシェリー酒のグラスに注がれていた。
「とてもおいしいです。ジェシーさん。私のためにこんなに素敵なプレゼントをしてくれてありがとうございます。嬉しいです」
「そうか、よかった」
ジェシーは晴れやかな表情になった。
その日はパリスの今までの人生で一番の思い出の誕生日になった。こんな幸せがいつまでも続けばいいのにとパリスは心から願った。パリスにとって最も大切なジェシーという存在がこれからもこんな嬉しそうな笑顔で隣にいてほしいと思っていた。
「よし、僕も食べよう」
ジェシーがフォークとナイフを持ってフライドチキンを1個自分の皿へ置く。その所作には一切の無駄がない。潜入任務のためにソウヤの邸宅でテーブルマナーも一通り身に着けた。それだけでジェシーの本気度が窺い知ることができた。
皆さまに楽しんでいただける素敵なお話をこれからも届けていきます。サポートありがとうございます!
