
NASA Strategic Design Studio③:浴びて、浴びて、浴びまくれ!〜リサーチ編〜
こんにちは。みかどです。三角と書いて、みかどです。
実際にプロジェクトでどんなことをしていたのか、そろそろ書いていきたいところなのですが、ここで大事な情報を一つ。授業が始まった最初の週末に派手に利き腕を骨折しました。元々の調子に乗りやすい性格にニューヨークという土地属性が付与された結果、右上腕骨をシュパっとスライスしてしまいました。後日日本で撮ったレントゲン写真は、ちょうどすき焼き用にネギを斜めに切った時のあの様相を呈していました。残りの14週間、この使い物にならない利き腕でどう留学生活を乗り切っていくのだろうかと、楽しみでなりませんでした。こんなことも起こるんですね、さすがNY。
そんな右腕をチープなブラックマジシャンのように仕立てあげた状態で(ファンクショナルブレースというらしい)、リサーチへと突入しました。
動き出す前に動き出す。
リサーチはさながら、Damien NewmanのDesign Squiggleそのものでした。

「何について調べる?」というところから始まり、あっちへ行ったりこっちへ行ったり。途中で先生に茶々を入れられ、さらに皆で迷走したり。大海原を漂流しているような感覚です。異質なクルーが乗り合わせた船に羅針盤を与えていくのがストラテジック・デザイナーの重要な役割の1つなのだろうな〜と、前述のClaraや先生のMarkをみてて思うところでした。
何はともあれ、プロジェクトは文脈理解のためのリサーチから始まります。ここでいきなり各人の流儀が出るのですが、コンサルでいうところのDay0的なリサーチをやっている生徒とそうではない生徒に分かれます。NASAほどの人気のある授業でも、事前に少しでもリサーチをしている人は半分もいなかった気がします。プロジェクト開始前の過ごし方に色が出るよな〜と思いつつも、もしや事前のインプットは授業での情報の受け取り方にバイアスがかかるからあえて避ける、などの崇高な哲学を持っているのかな?と自己処理しました。
かく言う私も大したリサーチはしていなかったのですが、宇宙ビジネスに関する本やレポートを読んだり、中田あっちゃんの宇宙ビジネス編を見たり、宇宙兄弟でモチベーションを上げたり、全地球史アトラスを見て自身のちっぽけさを嘆いたり、くらいは前段でやりました。(全地球史アトラスはストラテジックデザインに関わる人は必聴でもいいんじゃないか?)
ある程度仮説がある状態で検証的にリサーチをするというのが自分のこれまで生きてきた世界だったのですが、デザインスクールでは「仮説はバイアスだ」くらいのお話も出てきました(別の授業ですが)。どの程度まで仮説を持った上でデザインプロジェクトに臨むべきかはなかなかジューシーなトピックだと思うのですが、これはまたの機会に譲ります。
”浴びる”リサーチ。
いきなり脱線しますが、この”浴びる”リサーチという表現、よくないですか?仮説のない状態で行う土壌作りのような調査です。元BCGでリサーチのプロである田中志さんがビザスクのリサーチセミナーで話されていて、素敵すぎるので拝借しております。(浴びる・磨く・口説く、このリサーチの切り方めちゃ好きだ)
まずはリサーチテーマを決めるためのリサーチが始まりました。皆がどうスタートさせればいいのかとあくせくする中、早速、名指揮官Clara(前回の記事で紹介済)がアレクサンドロスが如く皆を導きます。何について調べてもいいと言われても、全くの制約がない状態では人間は動き出せないのですね。仮でもいいので標的を定める。さすれば矢は前には飛ぶのだ。と、重要なことを改めて思い知りました。

兎にも角にも、スタートを切るためのPromptが必要です。Clara指揮官の元、
General Background of ISS
History of National Labs
ISS - What happens after 2030?
この3つを準備し、15人がそれぞれが好きなテーマについて翌週までに調べてくることになりました。この調査は、そもそも今NASAってどういう文脈に置かれているんだっけ?を解きほぐすためのものですが、ソースやフォーマットなどは自由です。コンサルプロジェクトのようにワークプランを立てた上でGo!みたいなことにはなりません。(もっとも、コンサルの方々にとってはプロジェクトが始まる前に調べていて当たり前、みたいな内容なのでしょうが。)
ここで少しだけ背景を補足しておきます。NASAが中心となり運営されているISS(国際宇宙ステーション)は2030年にその役目を終えることが決まっています(当初の設計寿命は2016年までだったが何度か延長されている)。その後、スペースステーションは全て民間に委託され、NASA他その他機関は一部スペースを民間から間借りする、という運用が想定されています。年間約40億ドルかかっているメンテナンスコストを、深宇宙(月や火星など)の探求に回すというのが主な理由です。人類を再度月へ送り込み月面基地を作り、そこから火星に有人調査をするアルテミス計画という凄まじい構想があります。そっちへリソースを割きたいのです。(↓こちらの動画、お時間がある方は見てください。人類の野望に感動します。戦争やめて、宇宙行こう。)
また、ISS・NASAと共に重要なアクターであるISS National Lab(以下NL)というものがあります。ISS内の米国区間に設けられている国立の研究機関です。NASAは宇宙探査そのものを目的としており、NLは宇宙空間での実験室を政府機関他、民間企業、学術機関へ提供しているプラットフォームというイメージです(マイクログラビティという地球上に存在しない特殊空間での実験が可)。実際に、P&G、addidas、ノバルティスといった名だたる企業が研究で活用しています。
今回のお題は、NASAに限定せず、産学に開かれたNLもリーチできるデバイスとして考慮せよ、ということでNASAのみならずNLについても調べることとなりました。(この時点でまだ去年のブリーフだったので、なぜそんなに先生はNL押しなのかと皆理解に苦しんでいました。)
面白かったのは、皆のMiroへの吐き出し方。グラフィックデザイナーのとある生徒はマインドマップ的に思考を展開しており、

一方では、ひらすら文章で記録していくパターンの生徒もいます。(おそらくジャーナリストのMichael)

Chat GPTのレスポンスをそのまま貼り付けるだけの輩もいます。(結構、います。)

リサーチ段階のMiroは基本的にカオスです。同じ桶にいろんなものをぶち込んでみて、ふつふつと発酵するのを待ちます。
Miroの好きなのは、こういう風に(↓)好き勝手にリアクションを残せるところ。メンバーの人となりも見えるし、コメントきっかけで発酵が進むことも。
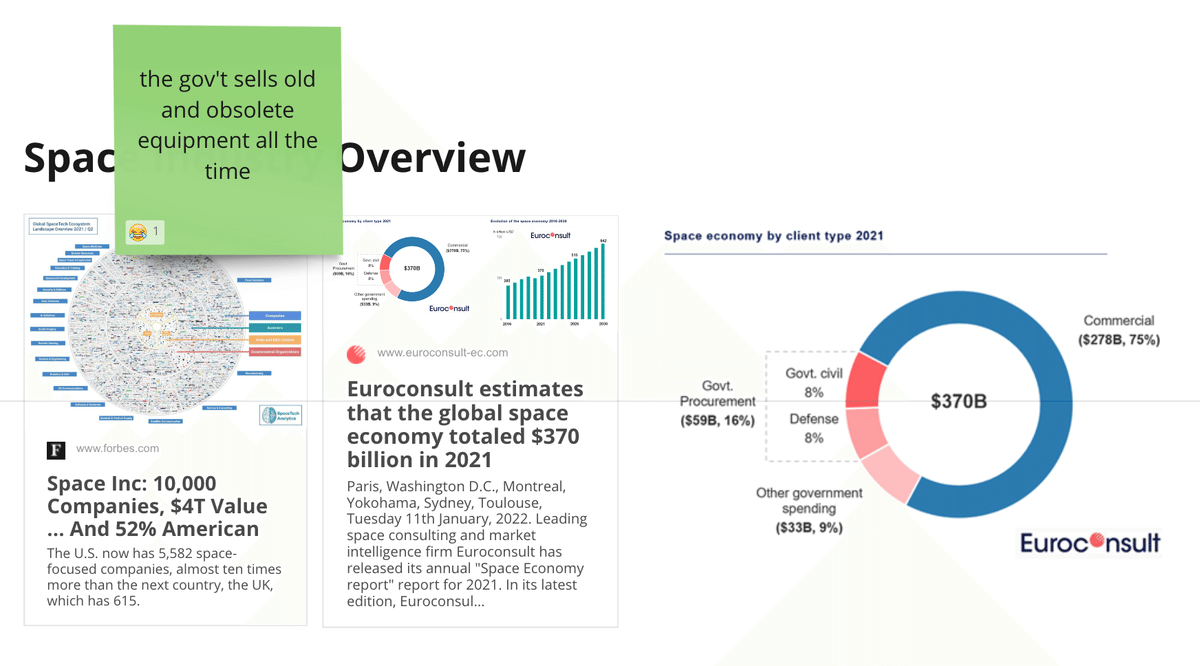
炸裂するClaraのファシリテーション
ある程度皆が文脈を共有できたところで、興味のあるテーマをすり合わせていきました。(事前のリサーチをやっていないと興味の湧くテーマすら出てこない状態になる)
ここでまたもや異彩を放つClara。皆が話している間にMiro上にこんなボードが出現します。

そして、皆各々に興味のあるテーマを投げ込んでいきます。
ペタペタと貼った付箋がどこかへ持っていかれる、そう思っていると隣でClaraが似たテーマの付箋を集め、名前をつけています。重複するものは統合したり、グループが大きくなると逆に分割したり。皆のアイデアがお手本のように整理されていきます。その後、各人が興味のあるカテゴリにvoteして、3つに絞り込みました。(既にデザインプロジェクトを経験している生徒はこういうプレーがサクッとできてしまう)

Economy・Health・Community
何だかそれっぽいキーワードが出てきましたよ。付箋には、
・What will the lunar economy look like?(月の経済はどのようなもの?)
・What if babies were born in space? How would they develop?(もし赤ちゃんが宇宙で生まれたら?どのように成長する?)
・Are we still using bills or coins?(まだ紙幣や硬貨を使っている?)
などのエキサイティングなトピックが湧出しています。これを14人相手に一人でやってのけちゃうのがClaraでした。ここからいくつか問いを選んで、チームに分けて機会特定、アイディエーション、プロトタイプして終わりじゃん!というのは浅はかすぎる考えだったと、その後のMarkとのディスカッションで思い知らされるのでした。
We’ve done a lot!Yeah!Let’s hang out!皆そんなテンションでしたが、翌週から沼の中の沼に沈められることになろうとは・・・
次回以降はほぼ哲学の授業です。ではまた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
