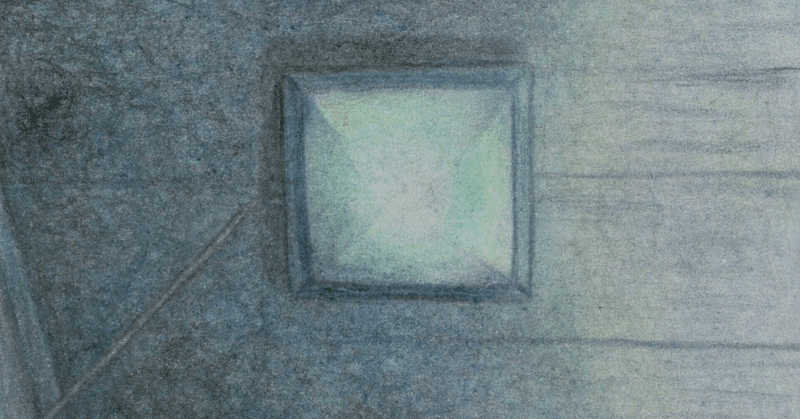
日が昇る四畳半【小説】
【あらすじ】子どもの頃、家族の誰とも血縁関係のない“おじい”がうちの四畳半に住んでいた。おじいはいつの間にかいなくなっていて、父も母もそれには触れなかった。大学生になって実家を出た。それからあまり実家に寄り付かなかった。そんなある日、家族が誘拐事件の容疑者として警察に捕まった。両親に誘拐されたのはーー僕。
①四畳半おじい
子どもの頃の話。
僕は、四畳半の部屋に住むおじいと仲がよかった。その部屋の襖を開けるとおじいはニカって笑って僕を迎え入れてくれた。
家族の中の誰とも血のつながりのないおじいがウチの一室にずっと住んでいた。誰とも関わらず、僕とだけ話すおじい。母がなんとなくおじいの分もご飯を作って、おじいの住む四畳半にそれを届けるのが僕の役目だった。
「今日は、おでん?おじいカラシほしいって絶対言うよ。」
「じゃあ、お皿の端っこにくっつけて持っていって」
「うん」
母は、おじいの好みの食べ物はなんとなく把握していて、おじいのためにわざわざ作るものもあって、おでんもそのうちの一つだった。父は魚の練り物が嫌いだから、おでんなんぞは匂いからして毛嫌いしていたのであったから。ん?…なんぞなんて言葉…初めて使ったな…。それと、もうひとつは、フキの煮物だった。父はフキの繊維質や食感が嫌いであったから、母はわざわざおじいのために作っていたのだ。
「おじい」
四畳半の部屋の襖を開ける。
「おお、あきちゃん。」
おじいは、にっこにっこして僕を見る。たばこの煙を吐き出しながらだ。
「ごはん」
「ありがとう」
「おでん」
おじいの前にお盆を差し出すと、タバコを咥えてお盆を両手で受け取る。
「こりゃうまそうだ、おっ」
「カラシもある」
「ぬかりなしだな」
「そ。ねえ僕もここでご飯食べたい。」
「ん?」
「だめ?」
「そりゃ、父ちゃんが悲しむだろ」
タバコを消して、お茶をひと口。それから、おでんのはんぺんを箸で切って口に入れた。白飯を口に放り込んでお味噌汁を飲んで、今度は大根を箸で切って口に入れる。
「美味いな。」
「うん。お母さんのおでん、僕も好き。」
「大根に出汁がしみしみだ」
よもや、母とおじいに何か、深い関係がありはしないかと探りを入れたくなった。
「ねえ、おじいって何者?」
「知らなくていい」
おじいがご飯を口にしているのを眺めている。美味しそうに食べるから、僕の口の中までおでんの味がしてくる。
「秋芳ー、ご飯だよー。」
母が僕をリビングから呼ぶのが聞こえて、
「おじい。後でまたね。」
「おお」
おじいの部屋からリビングに戻る。
おじいにはちゃんとした家がないから、この家を仮の住まいにしているんだと、父から聞いたこともあった。
でも、おじいがウチの四畳半に住んでいるのはもうひとつ理由があったように思う。
いつもは、母も父もおじいの部屋に近づかないのに、夜中に目が覚めた時に、2人の声がおじいの部屋から聞こえてきた。おじいのいつもより少し低い声も一緒に聞こえてきた。僕と話す時と雰囲気がまるで違う。怒りを含んだような話ぶりだった。
「だからあんたら夫婦、虫唾が走るほど嫌いだよ」
おじいは父と母が嫌い…。
「生駒さん、秋芳はいつ俺に返してもらえるんだ?」
え?
「それは…秋芳は…」
父が言葉を詰まらせている。どういうこと。
「良い加減にしてくれよな。菜告をバラバラ死体にしたのもお前らで、秋芳をそのまま誘拐したのもお前らだ」
「…比嘉さん、お願いこのまま…。」
母が泣いている。僕は話を聞きながら、よくわからなくて、夢なんだと思って目を閉じた。
翌朝、父と母はウチにいなくて、おじいがリビングにいた。
「おじい…。お父さんとお母さんは?」
「仕事が早いんだって。あきちゃんには朝ご飯にパンでも食べさせてって。」
「パン…ふーん。」
おじいは別にいつも通りって感じで。ただ、父と母がいないだけだった。
僕はいつも通り学校に行って、いつも通りに過ごして、いつも通りに帰ってきて、四畳半の襖を開けた時、いつも通りじゃなかったのは、そこに、いつもニカって笑う、おじいがいなかったこと。部屋の中はそのままで、おじいだけがいなくなっていた。
仕事から帰ってきた父と母は特段気にする様子もなく、いつも通りの父と母だった。だから、僕はおじいのこと全然聞けなくて…。
でも、四畳半の部屋はずっとそのままだった。
実家には大学に進学してから帰っていない。
「あきー。」
秋夜さんは、僕をそう呼ぶ。アルバイト先で出会ったひとつ年上の気の良い先輩だ。
「今日、バイト終わったら、飲み行かない?」
「良いですね。お酒強くないですけど…。」
「俺もそんなに強くないけど。」
秋夜さんが連れて行ってくれたのはバーだった。
バーなんて大人な寄り道をするとは思っていなかった。このお店のメニューにある中で知っているお酒は、ビールとハイボールとレモンサワーくらいだった。
「シュウが友だち連れてくるの珍しいね」
「この子、秋芳って言って、俺と同じで名前に秋って字が入るんだ。」
「そっか、あきくんね。よろしくね」
バーテンダーの人と秋夜さんが楽しそうに話しているから、僕は、「はじめまして。よろしくお願いします。」と言ってニコニコ微笑んだ。
バーと言っても、オシャレな人しかいないわけじゃないし、テレビがついていて、TBS NEWSがずっと流れていた。音は消してあるけど、なんとなく現実離れしない感じだった。
「あき、何飲む?」
「えっと……。」
メニューを見てもよくわからなかった。
だから1番上に書いてある
「ソルティドッグを…」と言ってみた。秋夜さんはクスッと笑う。
「それね、グレープフルーツだよ。」
「あ」
僕はグレープフルーツは、好きじゃなかった。秋夜さんはそれを知ってる。
「ビールにしよう?ドイツビールおいしいよ」
「あ、じゃあ。ビールをお願いします」
バーテンダーさんが、冷蔵庫を開けている間に秋夜さんに手を握られた。前々から少し感じていた。秋夜さんは、きっとそうだって思っていた。だから、なんの抵抗もない。
「ごめんね。あき。」
「いえ。」
「俺、少し汚いこと考えてた。」
「……もったいないです。なんで僕なんですか。」
「ふふ。なんでかな」
秋夜さんは背が高くて、顔が整っていた。モデルみたいだなってずっと思っていた。反対に僕は背が低くて、子どものような顔をしている。2人並ぶと、差が歴然で少し恥ずかしいとさえ思っていた。
目のやり場は、垂れ流されているニュース映像。字幕スーパーで、18年前の殺人誘拐事件に終止符。被疑者を特定、身柄を福島県警に送検。と文字が浮かんで消えた。
「はい、ビール。」
バーテンダーさんが僕と秋夜さんにビールを出してくれるのをありがたく受け取って、それでも気になってテレビを見ていた。
送検される被疑者は男性と女性。顔は隠しているけど、体形に見覚えがありすぎて鳥肌がたった。
名前の字幕には、生駒晴朝(52)、生駒実布由(48)。
「あき?」
嫌な汗が背中に流れる。なんで…そんな…。
「顔色悪いね、大丈夫?」
「…大丈夫です。」
ビールの味もわからないまま飲み進めた僕は酔いが回るのが早くて、何を話したかも覚えていない。
②18年前のこと
カーテンの色がブルー。
僕の部屋ではない場所で目が覚めた。レモングラスの香りがして頭が冴えていくが少し気持ち悪くて起き上がれなくて横になっていた。これが二日酔い。人生初めてだ。
「あき、おはよう。」
秋夜さんが、声をかけてくれて、ようやくここが秋夜さんの部屋だと分かった。
「ごめんなさい、僕…。」
「止めなかった俺も悪いよね。ごめんね。」
秋夜さんがペットボトルの水を渡してくれた。Tシャツが僕の服じゃないと気づいたのは起き上がったこの時だった。
「あき、吐いたから服洗濯したよ」
「重ね重ね、ごめんなさい」
「いいよ。」
スウェットズボンも、おそらく秋夜さんのもの…。
「秋夜さん、学校…。」
「今日は俺、午後から。あきは?」
時計を見ると10時だった。
「えっと。…僕もです。」
「良かった。サボらせたかなって、ちょっと心配だった」
僕の横に座って、頭をわしゃわしゃ撫でる。
「僕、シャワーも浴びてないし…あっ、歯も…。」
「歯磨きは、バッグから歯ブラシ出してやってたよ。おもしろかった。あきって、無意識で歯磨きできるんだね。でも、たくさんズボンにこぼしてたから洗濯したよ。」
「迷惑ばっかりかけてる…」
「俺、そういう手のかかる子、嫌いじゃないんだよね。」
秋夜さんは優しくて。昨日手を握られてからなんとなく、僕は受け入れている。
「ごめん、あき。俺ね、あきのこと好きなんだ。昨日、匂わせたから、変な飲み方させちゃったのかな。本当にごめんね。」
違う。あんな飲み方をしたのは…。
昨日、テレビで見たニュース映像を思い出す。父と母が警察の車輌に乗っていた。18年前の事件…。18年前、僕は2歳。だから、記憶が無くて当然。
「秋夜さん。僕も秋夜さんのことは好きです。秋夜さんの気持ちには追いつけないかもしれないけど。大切です。」
「…それ。友だちとして…だよね。」
秋夜さんの恋人としての気持ちに、僕は抵抗がない。だから、受け入れようと思う。
「…あの、たぶん違います。」
「無理しなくて良いよ。」
「無理してません。キスしましょう?今、歯磨いてからキスしても良いですか?」
自分で何を言ってるのかよくわからない。普通こんなこと言わないよなって思うと恥ずかしい。見た目が子どもすぎて女子からは弟扱いしかされなくて恋愛をしたことがなかった。
秋夜さんは、吹き出して笑い始めて、分かったよって、言いながら僕にキスをした。唇が唇と重なったのも、舌を絡ませたのも生まれて初めてで、恥ずかしい気分になった。耳まで熱くて、体もジリジリしてくる。
「どう?あき。」
「…え…っと、その。」
「恥ずかしい?」
「はい」
耳を触られて余計に恥ずかしくなる。秋夜さんの顔をちゃんと見られない。心臓がドクドク鳴り始める。
「本当に良い?俺と付き合ってくれる?」
首を縦に振った。初めての恋人は、同性。これからのこと全てを受け入れる覚悟もした。
「ありがとう」秋夜さんが僕のおでこにキスをして、首筋にもキスをした。くすぐったくて、恥ずかしい。
「大事にするからね、あき。」
恋人って、こんなに優しいものなのか。
頼って良いものなんだとしたら僕は僕のショックを秋夜さんに共有してほしいと、わがままな気持ちを勝手に抱いた。
「秋夜さんにだけ、聞いてほしい話があります。」
「…何?」
「今夜、また来ても良いですか?」
「バイト終わってから?」
そうだ、秋夜さんとはバイトで会うんだ。
「…はい。」
「いいよ。」
秋夜さんの部屋でシャワーを借りて、秋夜さんの服を借りて2人でモスで朝食兼昼食を食べて、電車で途中まで一緒に行って別れた。
アルバイトは6時から。
小さな料理屋。僕はホールで秋夜さんは厨房。アルバイトは賄を食べてから始まる。それを作っていたのは秋夜さんだった。秋夜さんは料理人になりたくて、大学も管理栄養士の学科だった。
「あき、味どう?」
この日の賄いは、カツ丼だった。甘めのつゆで煮込まれて卵でとじてある。
「好きな味ですがグリーピースは…嫌いです…。」
「それは、あきの好き嫌いだから。」
いつもニコニコしている秋夜さんが少し拗ねたように見せてすぐにニコニコし始めた。
「残されたらショックだから全部食べて。グリーピースもね。」
「…う」
賄を食べ終わってホールに入る。
僕は、なかなか常連のお客さんから可愛がられていて、いつも高い日本酒を頼んでくれるおじさんも僕を気に入っていた。
だからかどうかは知らないけれど、女将さんも僕を可愛がってくれていた。
ホールに入る前に、今日のおすすめを全部覚える。魚にお肉、旬の野菜を使ったお料理、デザート。お客さんは、結構おすすめを聞いてくるから。
「あきちゃん、比嘉さん来てるわよ」
高い日本酒を頼んでくれるのは、比嘉さんでいつもカウンターで親方と話しながら、お刺身には天明とか、天ぷらには十四代とか。なんか決めている感じだった。
「いらっしゃいませ。比嘉さん。」
僕が声をかけると、ニカって笑う。実家の四畳半にいたおじいに似ているって僕は勝手に思って、勝手に慕っていた。
「今日はもう、結構食べたんですか?」
「まだだよ。お刺身と天明はやってた。あきちゃんのおすすめあった?」
「ふふ。僕のおすすめですか。今日は…あ、たらきくが入りました。ポン酢和えか天ぷら」
「いいな。ポン酢和えもらおう。会津娘を合わせようかな。」
「はーい」
僕が、返事をすると比嘉さんはなんだか楽しそうな顔をする。年の頃なら70くらい。おじいは、あの頃、たぶん、60くらいだった。
僕が注文を厨房に出す頃、親方と比嘉さんが話すのが聞こえてきた。
「親方。18年前あった事件の犯人、今更捕まったみたいだね。」
「…ああ、あの、母親が殺されてバラバラ死体で見つかって、子どもは誘拐されて見つかってなかったっていう…。」
「そうそう。18年、…かかったもんだ。」
「とはいえ、子どもは見つかってないんでしょ?」
「…らしいね。今、生きてたら20歳。」
「うちの、生駒くんくらいか。」
「ああ、あきちゃん、20歳なの?」
「なったばっかりかな。」
「そう」
比嘉さんは、いつもは暗いニュースの話はしない。その犯人が、僕の父と母であることは絶対に知られたくないと思った。
厨房の秋夜さんが、僕のそばに来た。
「あき、注文は?」、
「…たらきくのポン酢和え。」
僕の顔を覗き込む。
「ちょっと休む?なんか変。厨房の中イスあるよ。」
秋夜さんがいつも通りに優しくて心が破れ始めて目から涙が流れる。
「あき?」
「う…うっ。」
「おいで」
厨房の勝手口から秋夜さんと一緒に外に出た。
「落ち着いて。どうしたの?」
「…必ず、必ず、後で話します。」
秋夜さんに抱き締められる。このままが良いと、僕のわがままが秋夜さんの背中に手を回した。
「ゆっくり息して。大丈夫。とにかく、今は落ち着いて。」
「ありがとう…ございます。」
少しずつ、息を整える。落ち着いてきた頃、頭をくしゃくしゃ撫でられた。
「今夜、たくさん話して。あき。」
「…はい。ごめんなさい」
秋夜さんが僕の頬まで落ちた涙を手で拭き取った。
「仕事できる?」
「はい。」
「いい子」
背中をぽんぽん叩いて僕を落ち着かせてくれる秋夜さんに、僕は安心していた。
夜10時には、料理屋が終わる。後片付けをしてバイトを上がって、コンビニでビールとかポテトチップスとか買って秋夜さんのアパートに戻ってきた。
「あき。おいで。」
秋夜さんがソファーに座って僕を呼ぶ。僕はその声に導かれて秋夜さんの前に立った。
話すのが少し怖い。
何から話せばわかりやすいだろう。
「あき、昨日から少し様子が変だよ。」
僕の両腕を掴んで秋夜さんが言った。
「秋夜さん…あの。」
「うん。」
秋夜さんに話して、他人に話を広げられるかもしれないなんてことはどうでも良かった。父と母のことを話して、秋夜さんが僕のそばからいなくなってしまうことの方が怖い。
「…昨日、ニュースで見たんですが。」
「うん。」
目に涙が溜まってきて、テレビの映像を思い出した。秋夜さんが僕をまっすぐ見つめている。
「…うう。ああ。うっう。」
堪えきれず泣いてしまった。
「あき、座って。」
隣に座ると、背中をさすってくれる。
「…泣いてしまうほどのことなんだから、落ち着くまで待つよ。俺に話したいって思ってくれたの、嬉しいから。」
ショックを共有してほしいなんて勝手なわがまま。秋夜さんに押し付けて良いんだろうか。
「僕、知らなかったんです。18年前の事件。」
「…18年前…あき、2歳?」
「はい。」
「…知ってる方がすごくない?」
「そうですか。」
「うん。俺も知らないことだと思う」
頭をゆっくり撫でられて話せるような気分になってくる。
「…母親の殺人と子ども誘拐事件があったそうです。」
「あ、……今日、親方と比嘉さんが話してた…」
「はい。」
僕の手が震え始める。秋夜さんがその手を握る。
「昨日、両親が警察の車に乗ってる映像がテレビで流れていました。名前も。」
「え」
「母親を殺し、子どもを誘拐したのは…僕の両親です。」
秋夜さんは、僕に驚いた顔を一瞬見せた後、僕を抱き締めた。
「18年前の事件ですが、僕は子どもの姿を見たことがありません。だから、きっと両親は子どもを殺してしまったんです。」
「怖かったね。」
「ずっと、ずっと知らなかった。ずっと、何事もないように、ずっと両親は僕に隠していたんです。僕はどうしたら……」
秋夜さんは、泣き続ける僕の涙を何度も拭いてくれた。
「何もしなくて良いよ。あきは今まで通りでいい。」
「大学、行けなくなります。きっと。両親にお金払ってもらってるのに。」
「そっか。ごめん。俺が何とかできることじゃないね。でも、話なら聞くから。俺はあきの味方だよ。」
秋夜さんが抱き締めてくれた。
「秋夜さん…」
「あきはひとりじゃないよ。俺がそばにいる。」
「ずっといてくれますか?ずっと離れないでいてくれますか。」
僕は秋夜さんを求めてしがみついた。四畳半に住んでいたおじいのように突然いなくなったらどうしようって不安だったから。
「大丈夫だよ。」
秋夜さんが優しく僕を包んで、泣いて疲れたからか少しずつ眠くなるのを感じた。
③真実
秋夜さんに話をした日から1週間。
僕の住むアパートに警察が来た。
「生駒秋芳さん。一度、DNA鑑定を受けてほしいんです。」
そんなことを言われて唾液の採取を受けて、髪の毛を何本か提出した。僕の知らないことが始まっているように思った。
学校の友だちには変化はなかった。相変わらず立ち位置はみんなの弟で可愛がられ役。
「あっきー。メロンパンあげるー。」
そう言って、女の子たちに囲まれたり。きっと、この中で、僕が犯罪者の息子だって気がつく人なんていないんだろうと思うと安心できた。でも、来年度からは在学できるかわからない。
バイトは、ちゃんと決まった時間に入って、ホールにいる間は両親の事を忘れた。比嘉さんは、3日にいっぺんからほぼ毎日来るようになった。
珍しく比嘉さんが個室を予約していて、僕は女将さんに接客をするように言われた。
「ご注文お伺いします。」
「あきちゃん、中に入って。」
部屋の中に入ると、手招きされて比嘉さんのそばに正座した。
「これ、あきちゃんにあげるね」
差し出されたのは分厚い封筒だった。
「これ…」
「200万円。来年度前期分。余ったら生活費ね」
「え」
「…あしながおじさん、してあげるよ。まあ、顔がわかっちゃってるから、それとは違うか。」
背中に嫌な汗が流れた。
「なんで…」
「お家大変でしょ?」
秋夜さんが比嘉さんに話した?いや、そんなわけがない。秋夜さんを疑うなんて…僕は最低だ。
だけど、なんで比嘉さんが知ってるんだろう。僕が困惑していると比嘉さんが話し始めた。
「俺、昔。あるうちの四畳半に仮住まいしてたんだ。東向きで日が昇るのがよく見えた。」
「え」
「その家主が、娘を殺した犯人で、孫は誘拐してそのまま育てていた。さも自分の子どものように。長かったよ、1年死に物狂いで探したんだ。浮浪者のふりをして近づいて、家に住み着いたんだ。奥さんは料理が上手だった。おでんが美味くて、フキの煮物も上手だったな。」
僕の母と似ている。
母は料理が得意だし、おじいのためにおでんとフキの煮物を作っていた。
「あきちゃん。」
「はい。」
「ここで、あきちゃんがアルバイトしてるなんて、俺たち縁があるよ。随分と良い子に育ったことは生駒夫妻に感謝しなくちゃいけない。」
比嘉さんが、実家の四畳半に住んでいたおじい?だとしても、比嘉さんが言っていることがよくわからない。
「18年、長かったね。他人のふりをして、実の孫と過ごす7年も長かったけど、離れてしまった10年はもっと長かった。あきちゃんの顔を見て、子どもの頃とさほど変わらない顔立ちに鳥肌が立った。」
肩を掴まれて、怖くて目に涙が溜まっていく。
「…おじい?」
「そうだ。四畳半にいたおじいだ。」
「実の孫って…」
「俺はあきちゃんのじいちゃんだ。」
そんなわけない。おじいはただの他人だ。父が言ってた。仮にうちにいるだけの他人だって。
「警察が来ただろ?DNA鑑定を受けろって。俺が頼んだ。結果が出たんだ。俺とあきちゃんは血が繋がってる。」
DNA鑑定を受けていた事を忘れていた。なんのための鑑定なんだろうって思いながらもただ従っただけだったから。
涙が溢れて視界が歪む。
「生駒夫妻の事を通報したのも俺だ。あきちゃんが大人になるのを待ってた。菜告は戻ってこない。でも、あきちゃんは……」
「なんでお父さんとお母さんがそんなことするんですか?僕は……お父さんとお母さんに誘拐された?…わかんない。比嘉さんの言うこと全然わかりません。」
200万円の入った封筒を比嘉さんに押し返した。
「受け取れません。信じません。」
頭の整理がつかない。
「これは、あきちゃんのための金だ。ちゃんと受け取りなさい」
強引に押し付けられて、受け取るしかなくなった。こんなあり得ないことが。
今まで僕は全くの他人に育てられていたということ。わがままし放題で、他人に無邪気に甘えてきたということ。
その他人が、僕を誘拐した犯人だということ。
バイト帰り、秋夜さんの部屋に来た。
今日は、秋夜さんはバイトに入っていなかった。
「あき?元気ないね。」
僕はソファーで横になる。顔を覗き込まれた。
「…秋夜さん、僕、自分がわかりません。」
「そう。」
頭を撫でられて甘えたくなる。
「明日、早いですか?」
離れたくないと強く服を握った。
「明日、午後からだよ。あきは?」
「3限からです。」
「そう」
秋夜さんの僕を見る目は優しい。
「俺も横になりたいな。あきと一緒に。」
「え」
「あっち行く?ベッド」
思っていた以上に早い。…でも、良い。甘えたい。現実がなんだかわからないから、おかしくなりたい。手を引かれるまま、ベッドに行った。先に仰向けに寝かされた。
「あき、泣きたいなら泣いて良いよ。」
「秋夜さん…。」
秋夜さんが隣に寝転がる。
「俺ね、あきが可愛い。辛い顔されると助けたいの。ねえ、あきは1人じゃないよ。」
抱きしめられた。温かい。ほっとする。頭を撫でられて、力が抜けていく。
「僕、秋夜さんがいてよかったです。」
「良かった。そう言ってもらえて。」
だけど、これから起こるであろうことが怖い。秋夜さんにしがみついた。手に力が入って震える。
「あき…」
秋夜さんの唇が僕の瞼に触れた。
「怖いことがあったから俺んとこ来たんだよね。たくさん甘えて良いよ。」
唇が重なる。舌が絡まる。頭の中が真っ白になる。何も考えなくて良いって、言ってくれてるように思う。耳を齧られて背中がゾクゾクしてくる。呼吸の仕方がわからない。
「かわいい。」
「もっと。」
「ん?」
「僕をぐちゃぐちゃにして」
涙が溢れて止まらない。
「どうしたの?」
秋夜さんが困惑するのがわかる。申し訳ないけど気持ちが収まらない。
「おかしくしてほしいんです。何も考えたくないから。秋夜さんしか…こんなことお願いできないから。」
苦しくて耐えられない。その気持ちを押し付けようとする僕は汚い。恋や愛がないような気がする。ただ、縋る場所を見つけただけの汚い頼り方。
「…ごめんなさい。秋夜さん。ごめんなさい。」
子どもみたいに泣いてしまう。秋夜さんはやっぱり優しくて、抱きしめてくれる。
「あき…俺といる時だけ、全部忘れて良いよ。」
服の中に秋夜さんの手が入って素肌に感じる暖かさが呼吸を乱す。誰にも触られたことがないところに少し秋夜さんの指が触れただけで体が反応する。
「あき、本当に良い?」
「はい」
秋夜さんに、返事をする。今までしたことがないこと。僕はこの日初めてセックスをした。秋夜さんに全部任せて委ねて。秋夜さんを受け入れて、掻き乱されて頭も体もおかしくなって、僕の現実を忘れたかった。
無我夢中でわけがわからなくて。
ただ、乱れるだけ。
それだけで良かった。
④正義の悪意
久しぶりに実家の玄関に鍵を通した。
玄関に、壁に人殺しって張り紙がたくさん貼ってある。こういうの、どういう気持ちで書いて貼るんだろう。理解できない負の感情。
玄関を開けて家に上がる。飾られた花が枯れて植物の死ぬ匂いがする。水っぽさを少し含んで臭い。花瓶を手にして台所に向かった。
枯れて腐った花をゴミ箱に捨てて濁った水を流しにあけた。臭い。花瓶を覗き込むと、水垢がこびりついていた。水道の水と食器用洗剤を流し込んで、流しを洗うスポンジでゴシゴシ擦った。
流しの三角コーナーのゴミは水分が抜けているのにどこから入ったか分からないショウジョウバエが取り囲んでいる。近所の人間たちと同じだ。頭に来てアルコールスプレーのスプレーを外して中身を全て三角コーナーにぶちまけてやった。ネットと金網をすり抜けて排水溝に流れていく。
こんな意味のないことしてもどうしようもない。
洗面所に行って手を洗った。ハンドソープを余分につけて。
洗濯物がドラム式の洗濯機に入ったままになっているのが見えて洗剤を注入口に入れてスタートボタンを押した。
東向きの四畳半の部屋。
襖を開けてみた。部屋がそのまま。おじいが吸っていたタバコの箱もそのまま置いてある。ライターも。父と母は、なぜおじいの娘を殺したんだろう。2歳の僕は、何をしていたんだろう。
リビングの方からガラスの割れる音がする。心のやり場のない人が、ここなら何をしても良いと決めつけて何かを投げつけたんだろう。外から、人殺し!と大声で叫ぶのが聞こえてきた。
「…ふざけんなよ」
ふと声が漏れた。
外野が騒ぐな。お前たちに関係ないだろ。
そんな怒りの気持ちが込み上げてくる。
おじいがよく座っていた場所に座ってみる。
考えてみればおじいに怒られたことが一度もなかった。他人だから、怒る理由もないけど。おじいの吸っていた、マルボロ。箱に残っている数本から1本出して火をつけてみた。肺に煙を入れる。
おじいがいなくなったのは10歳の頃。たばこの匂いでお爺と話したことを思い出す。
小学校1年の春。入学式が終わった後、おじいに教科書を自慢した。
「あきちゃんが楽しみなのはどれ?」
「こくご?…字、書くやつ。」
「字を覚えたら本をたくさん読むと良い。人の心の動きがたくさん書いてあるから、優しい人になれるよ。」
「んー、僕…本苦手。あんまわかんない。」
「おじいも一緒に読んであげるから持っておいで」
そう言って、その通りにまずは教科書に載っている物語から読解してくれた。文字が読めても内容を汲み取るのが苦手だった僕は、おじいの解説で納得することが多かった。
本以外にも分からないことはおじいに相談した。父や母に怒られてもその場で理解できず、泣きながらおじいの部屋に逃げ込んだ。その度におじいは理由を話してくれた。それが分かれば僕は納得できて、謝ることもできた。
僕は今、理解していないし納得していない。
タバコの灰を灰皿に落として、部屋を見渡した。おじいは、もしかしたらこの部屋に住むことで、父と母に罰を与えていたのかもしれない。浮浪者のふりをして近づいたと言っていた。
もし、父も母もおじいの正体を知っていて住まわせていたのだとしたら…。脅されて一緒に住むしかなかったのだとしたら…。
ドラム式洗濯機のアラームが鳴るのが洗面所から聞こえた。洗面所に行って、洗濯機から洗濯物を出して、2階に上がった。僕の部屋の隣が洗濯物を干す部屋だから。洗濯物を部屋干しにして部屋から出る。そういえば隣の部屋は、入ったことがなかった。西向きにドアがある。父が時々出入りしているのを見たことがあった。きっと父の部屋だったんだろう。…特に何もないだろう。
僕は、ドアノブに手をかけて、ドアを開けた。西陽で眩しいほどに部屋は照らされて観葉植物が窓の陽を浴びていた。机にはサボテンに多肉植物やアガベ。アガベは数種類。みっちりとあった。そういえば、父は観葉植物マニアだった。特に好きなのはサボテンだった。
一度、リビングでスーパーボールを飛ばして遊んでいたら、小さなサボテンの鉢に当たり、倒してしまったことがある。盛大に砂をぶちまけて父に怒られた時も、おじいがどうすれば良いのか一緒に考えてくれた。結論は、部屋ではスーパーボールで遊ばないと誓い謝って許してもらうで、それは正解だった。その後、父は父で、大事な観葉植物は全て僕の目につかない場所に隠してしまった。
それがこの部屋だったのかと申し訳ないが少し笑ってしまった。
実家から、おじいが吸っていたタバコとライターを持って出た。リビングには立ち寄らず、投げ込まれたであろうものはそのままにして。
父と母が、罪を犯すだろうか。人に恨まれるような人には思えない。何かの間違いなのではないかと思う。
僕の足が向かったのは警察署で、面会を申し入れると、母とだけ面会ができるという。父は取り調べ中だと教えてもらえた。
アクリル板の向こう側に現れた母。
「…秋芳。」
母の声は少し掠れていた。顔色は悪く目の下にくまがあった。
「ごめん。秋芳。」
僕の顔をまっすぐ見ながら謝る母。
「お母さん、……何があったの?」
「秋芳には……本当に申し訳なくて。」
「うん。」
「秋芳の本当のお母さんは、菜告さんて言って。」
「うん。」
「私たちが駆けつけた時にはもう、…たぶん亡くなっていて。」
「…え」
母の話を聞いていけば、菜告さんは交通事故に遭い、それは所謂ひき逃げで、父と母は事故現場を目撃した。
それは、夜10時ごろ。母は念願だった赤ちゃんをその日の昼に流産していて2人は五月町の病院から自宅に向い、国道4号線を父の運転する車で走っていた。数メートル後ろから煽り運転をしてきた車を避け追越車線に入ると、その車は、その先の信号が赤になっているにも関わらず猛スピードで直進。横断歩道を渡る親子連れをひき逃げし仙台方面へ走って行った。父と母は、近くに車を止め駆けつけるが、事故にあった菜告さんは腕や脚がちぎれ、顔の半分はわからなくなっていた。
菜告さんのそばに倒れていたのが僕で、僕はその時、頭を打って意識を失っていた。
「じゃあ、…殺してないってこと。」
「…でも私たち、その時通報してすぐ秋芳だけを連れてその場を離れてしまったの。」
「……え」
「私たち」
母が涙を流す。震える手で顔を抑えた。
「…子どもが欲しかったの。」
母は、ゆっくり話し続ける。
父と母は、僕を自分達の子どもと偽り、夜間救急へ連れて行った。僕は偶然にも保育園の通園鞄を持っていて、その中には、僕と保護者の名前の書かれた連絡ノートが入っていた。僕の名前を知るのは容易なことで、年齢も誕生日もすぐに確認できた。保険証こそないものの、診察を受けることはでき、僕は助かったのだ。
「ずっと、ずっと隠していてごめんなさい。菜告さんをひどい目に…見殺しにして…秋芳を誘拐した…。
こんな風に、あなたを苦しめてごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。
一生をかけてあなたを幸せにしたかった。だけど、こんなことをした私たちを、許してなんて言えない。ごめんなさい。ごめんなさい。
一生償います。ごめん。ごめんなさい。ごめんなさい。
秋芳。本当に…。」
肩を震わせて、俯いて鼻を啜り涙を流しながらごめんなさいとばかり謝る母を見て、僕は涙を堪えた。
抱きしめて、良いよ、大丈夫って言ってあげられないのが悔しい。許すも何も、父と母に大事にしてもらったんだ。僕は他人なのに、そうやって、18年家族でいてくれた。
「…お母さん。」
僕の呼ぶ声に母が顔をあげる。
「僕は、今だって幸せだよ。」
「秋芳…」
母は声を上げて僕の名前を呼びながら泣いた。
「ウチに帰んなくてごめん。お母さん。」
強がって、にっこり笑って見せた。本当は泣きたいけれど。ここで泣いたら、お母さんが泣き止んでしまうから。僕は、どんな背景があっても、父と母を恨むなんてできない。誘拐されてできた偽りの家族であっても、僕には大切な人たち。
「お父さんにも、僕は幸せだって言っておいてよ。でさ、また、集まれたらウチでお母さんが作ったご飯食べさせて。」
母は、ただ僕の話を聞きながら頷いて。
時間が来て、母は警察官に両手を縛られて立ち上がった。
「秋芳、ありがとう。」
涙目でも少しだけ笑ってくれた。
僕は、右手を挙げた。
「またね」
重い扉の奥に母が消えた。
僕は少し眺めて、少し泣いた。
⑤僕は味方
大学の学食で友だちとお昼を食べる。
5人で囲むテーブル。最近、隣に座る幸樹と僕の向かいに座る由奈が付き合い始めて、他の2人も盛り上がっている。僕の身に何が起きているか、この中の誰も知らない。
「あっきー、チョコあげる。」
そう言って、僕の左手を軽く握って斜め前の沙耶ちゃんがチョコを手のひらに置いてくれた。こういうのもしかしたら、ドキッとするんだろうけど、なんともない。一応、僕はにっこりして
「ありがとう。沙耶ちゃん。」と言って受け取る。僕は、ポケットからミルキーを出して、沙耶ちゃんの左手をミルキーでつんつんする。
「お返し。僕好きなやつ。」
隣の愛花が、
「あきって、あざといよね」って笑った。
「何が?」って、上目遣いで聞くと「それ!」って少し強く言われた。
「かわいいからやめな。勘違いされるからね。」って。よくわかんないけど。でも、普通に可愛がられてる。大学が、実家から少し離れていて良かったと思う。もし、知れたら友だちじゃなくなるかもしれない。
「あっきーには彼女とかいてほしくないなあ。」
沙耶ちゃんが、僕の顔をじっと見ながら言った。
「なんで?」
幸樹が僕の代わりに聞いた。
「あっきーのこと、好きなん?」
愛花も揶揄うように言う。
「いや、そうじゃなくて。なんか、あたしたちの弟が大人になってほしくないって言うか。彼女に彼氏らしく接してるの想像できない、いや、したくない。」
勝手なこと言われても。僕だって、恋人はいるのに。
「つか、女興味ある?あっきー。」
幸樹が、僕の頭をわしゃわしゃしてくる。秋夜さんのは嬉しいのに、ちょっと嫌だ。
「んー。」
チョコレートを口に入れて、考えるふりをした。
「あっきーには、純粋でいてほしい。」
由奈までそんな風に言ってくるから、ますます弟キャラから抜け出せない。
「大人にならないでね、あっきー。」
頭に秋夜さんとしたことが浮かんでくる。僕は、みんなとちょっと違う。水を口に含んだ。
「でも、背の高いイケメンはありじゃない?」
沙耶ちゃんが真正面から言ってくるから、胸がドキドキし始めてくる。ウチのことも知られたくないけど、僕が秋夜さんとお付き合いしてることもこの中の誰にも知られたくない。
「多様性の時代だし。あきがそうでも、俺は応援するけど。」
「応援?幸樹があきの彼氏になるってこと?」
由奈がそう言うから幸樹と目が合うけど、なんか違う気がする。
「いや、俺は由奈がいるからごめんね。」
一言も喋らない方が墓穴を掘らなくて済みそうな気がする。
「…あき?怒った?」
愛花が少し心配そうだった。首を横に振った。
「こんなことくらいで怒んないよな。あき。」
こんなこと…恋愛対象が同性が良いと言われたことくらい?ってこと。…別にどうでも良い。
「うん。」
「絶対汚れないでよ。あっきー。」
沙耶ちゃんは、僕のこと弟以上の扱いはしないんだろう。
「うん。」
「それでこそ、私たちの弟!」
てか、同い年なんだけど。でも、僕を可愛がってくれてるのがわかるから、これで良いって思う。そうこれがいい。楽だし。
学校が終わったら、秋夜さんと会う約束をしていた。2人ともアルバイトを休みにしていた。
待ち合わせは駅で、服とか見たりしようって。僕の事情を知るのは秋夜さんだから、一緒にいるとほっとして安心する。
「あき、服いつもそんな感じ?」
オーバーサイズのシャツを襟を後ろにひいて着ている。Tシャツも少し大きい。パンツは黒で少し細くてくるぶしまでの丈。アディダスのスニーカーを履いていた。バッグはポーターのボディバッグ。
「変ですか?」
「いや、かわいいなって。」
僕の顔が赤くなるのがわかる。他の誰かに言われてもいつもの弟キャラの方の意味だと思うけど、秋夜さんに言われるとくすぐったい気持ちになる。もしかして、これが恋なのかな。
「あき、自分のサイズわかってるなって思う。」
「僕は、秋夜さんみたいな感じ、憧れます。」
秋夜さんはチャコールグレーのジャケットに白いTシャツ、黒のデニムに黒いスニーカー。背が高いからかっこいい。
「僕なんか一緒に歩いていいのかなって。」
「俺、一緒にいたいんだけど。あきは嫌なの?」
優しい顔だけど、少し怒ってる。
「いえ、嫌とかじゃ。みんなが見てどう思うのか…自信なくて」
「みんなって?俺たち、そんなに見られてる?」
「あ」
「ね?周りなんか関係ないよ。」
「はい」
何も考えず、普通のカップルみたいに堂々と歩けば…秋夜さんの左手に僕の右手で触れてみた。すぐに僕の右手は秋夜さんの左手に捕まって、
「手冷たいね、あき。あったまるまで握っとくわ。」
なんか、照れくさいけど、恥ずかしさはなかった。
服屋さんで、冬服を試着したり、値段を見て悩んだり。日常の時間が流れて、申し訳ないと思う。
父と母は今頃、裁判所で18年前の事件の真実を話している。僕は、大事な人たちの運命の日にその場に行くことを選ばなかった。
行けばきっと、どうにもならない現実に押しつぶされるから。2人はきっとやってもいない罪を背負うことになる。重い判決が下されるかもしれない。いくら弁護士がいても、18年前のひき逃げ事件の真実を明確な証拠を出せる根拠がないのだ。
「あき、食べないの?」
秋夜さんとドトールに入った。バスのロータリーがよく見える。僕はミラノサンドと紅茶を半分残したまま、少し外を眺めてぼーっとしていた。
「食べます。」
「紅茶も冷めるよ。」
「飲みます。」
「どうしたの?」
秋夜さんは少し微笑みながら、僕を覗き込んでいる。
「話して。あき。」
「今日、裁判だったんです。」
「お父さんとお母さん?」
「…僕、行かなかったんですけど。大学で友だちと普通に過ごして、今、秋夜さんと会ってて…。目の前で結果を知るの怖くて。行かないって決めて。でも、僕も何か…。」
秋夜さんはコーヒーを口に含んだ。
「お父さんとお母さんの今のところの味方は、あきだもんね。力になりたいって思うのは、当たり前だよ。」
実家に貼ってあった貼り紙を思い出した。
「……僕、2人の味方なのか。」
「うん。」
2人が実家に戻る前に、悪意に抗おうと思った。実家の貼り紙を全て剥がそう。また貼られても、また剥がそう。
「ありがとうございます。秋夜さん。」
それに、比嘉さんに、本当のことを話そう。僕は誘拐されたんじゃない。保護された。それだけのことなんだ。2人は、僕をちゃんと育ててくれた。
「ん?」
じっと秋夜さんを見つめた。
「どうした?」
大切なことは、秋夜さんが気づかせてくれた。2人を守るのも、僕自身を救うのも僕なんだ。
「大好きです。秋夜さん。」
⑥お願いします
日曜日。学校もバイトもない。
実家の玄関に貼られた貼り紙を剥がしてゴミ袋に入れる。壁には卵とか、犬のフンとかも投げ付けられていて、笑っちゃうほどにひどい。防犯カメラを設置して犯人を割り出してやっても良い。これだって、立派な犯罪だ。父や母は、お前たちに何もしてないじゃないか。
「ずいぶん、ひどいな。」
聞き覚えのある声だった。振り返ってはっとする。
「比嘉さん…。」
「手伝うよ。あきちゃん。」
僕にとって、比嘉さんは戦う相手のはず。それで間違いないと思う。でも、比嘉さんにとって僕は孫。
「ゴム手袋、持ってないだろ?」
僕にゴム手袋を渡して庭の水道からホースを伸ばして、水をかける。
「こんなことは、望んでなかった。俺は俺の怒りだけ届けば良かった。知らないやつの同調なんか求めていない。」
僕は比嘉さんがブラシで壁を洗う姿を眺めてしまう。
「……おじい。」
比嘉さんの手が止まる。
「あ、比嘉さん。…ありがとう。……ございます。」
「俺が撒いた種だ。当然だ。」
こびりついた汚れが落とされていく。
「ホース持って。あきちゃん。」
「はい。え、あの。」
「持って。」
「持ってるだけ?」
「高いところ届かないだろ、チビだから。」
「ひどい」
比嘉さんは、僕に暴言を吐きながら、僕との距離を縮める。昔みたいに笑いながら2人で壁を掃除した。
外壁の汚れを探して家の周りを一周する。
「この部屋だったな。」
比嘉さんが東向きの四畳半の部屋を眺めて言った。
「四畳半の部屋、あの頃と同じです。変わってません。」
「朝日が眩しくてよ」
「東向きだから…ですか?」
「ま、そうだな。」
比嘉さんは、少しだけ昔を思い出すような顔をした。
「僕、誘拐されたんじゃないと思う。」
比嘉さんが僕の方を見るのがわかった。
「比嘉さんだって、ずっと見てましたよね。僕と…父と母…。」
比嘉さんが、家の壁を無言で綺麗な雑巾で拭き始めた。
「そこ汚れてませんよ、比嘉さん。」
「…」
なんで、何も言わないんだろう。
「比嘉さん…」
比嘉さんが黙々と壁を擦る。僕も、真似してみた。手が止まって、比嘉さんがその場にしゃがみ込んだ。
「…菜告は、帰ってこないんだよ。どうやったって、何が真実だって。お前の本当の母ちゃんは帰ってこないんだよ。」
「裁判、行ったんですか。」
「…行くしかないだろ。」
比嘉さんが、裁判で聞いたのは父と母の証言を元に、当時、事故現場の近くに住んでいた人に聞き込みをした結果と、18年前の死亡解剖から出てきたタイヤ痕から割り出した車体が、僕の父と母の乗っていた車と一致しなかったと言うこと。
「俺が菜告に会った時は、腕と脚がバラバラで顔が潰れて…。持ち物は、子どもの服と水筒。会社に行く時のバッグに……全部、血で汚れていたけど。持って帰れるものは受け取った。
アイツはひとり親だったから託児所にお前を預けていて、迎えに行った帰りだったんだ。託児所に問い合わせたけどお前はいなくて。
こんな形で家族を失った気持ちが、あんな幸せな奴らにわかるか…。わかるわけがないだろ!!
俺は、ずっと、恨み続けて…」
リビングの方からガラスの割れる音がした。
「人殺しー!!」
面白半分に誰かが、そう言って、もう一度ガラスの割れる音がした。中に誰かいたら、怪我をするかも知れないのに。よく平気でこんなことができると、怒りより呆れの感情が込み上げる。
「…あきちゃん、俺もアイツらと同じだ。」
比嘉さんが、そう言って立ち上がった。
「中、片付けよう。ごめんな。」
僕は、ポケットから鍵を出した。
「比嘉さんとアイツらは一緒じゃありません。」
僕は、外の窓から部屋を覗いた。
この部屋がこのままなのは、もしかしたら、父と母は比嘉さんがいつか戻ってくるかも知れないと思っていたのかも知れない。父も母も、僕に比嘉さんの話はしなかったけど。
僕の知らないところで3人は、何か共通の意識を持っていたのかも知れない。
「……おじい、父と母から、なんですぐに僕を取り返さなかったの?どうしてウチに住んだの?」
玄関に向かって歩く。
比嘉さんは、その間話さなかった。家の鍵を開けて中に入る。窓ガラスが割られ物が投げ込まれているのは、南向きのリビング。割れたガラスが危ないから仕方なく靴のまま中に入った。
「俺は持病があって、通院してる。」
投げ込まれた石を拾いながら比嘉さんが話す。
「17年前、奥さんとあきちゃんが、そこの待合にいたんだ。顔を見てすぐに分かった。ずっと探していた孫だって。あきちゃんはだいぶぐずっていて、奥さんは、けっこう困ってて。」
僕は、箒でガラスの破片を集めていた。
「近づいてあきちゃんの顔を見たいから、ミルキーを奥さんにあげたんだ。あきちゃんはミルキーが好きだから。奥さんは、にっこり笑って、これこの子好きなんですって。なんとも言えない気持ちだった。知ってるんだ、俺の方が。好物も、好きなキャラクターも、全部。名前を聞いたら、やっぱり秋芳だった。」
比嘉さんは、リビングを片付けながら、話し続けた。
僕はその頃、極度の人見知りで、母にくっついてばかりいた。比嘉さんは、何度か母を見かけ、家を特定できたという。
それから、ウチに住むまでにはさほど時間はかからなかった。でも、比嘉さんは。
「あきちゃんをすぐに返してほしいと言うのは無理だと思った。」
僕は、比嘉さんをじっと見つめた。
「あきちゃんは、生駒さんに懐いていて幸せそうだった」
比嘉さんは、大きくため息をついて。
「生駒さんたちに、問いただした。あきちゃんの本当の名前は、比嘉秋芳だろって。2人は、俺がそう言うとあっさり認めた。」
肩を震わせ、何かを堪えるようだった。
「生駒さんたちは、俺に縋るように言ってきた。どうしても、子どもが欲しかった。この子が、可愛くて仕方がないって。俺だって…俺だって、あきちゃんのこと…初孫で…。」
僕は、少しだけ比嘉さんに近寄って、もう少しだけ近くで話を聞こうと思った。
「だけど俺も。このウチで、家族を取り戻した気分になってたんだ。…家族の夢を見せてもらってたんだ。…憎んでいたはずなのに。」
「おじい…。」
声をかけると、比嘉さんは僕を見つめた。
「僕を探してくれてありがとう。」
僕は、こんなにも愛されているんだと少しだけ嬉しい気分になっていた。
本当の母が亡くなって、それでもどんな形であれ、僕を愛し育ててくれた人たちがいて。
「僕、みんなが好きです。」
「…あきちゃん。」
「おじいも、父も母も。比嘉さん、苦しむのもう終わりませんか。菜告さんは、きっと、おじいが恨んだり憎んだりすること望んでないと思います。」
「…」
「僕の本当のお母さんって多分そういう人だと思うので。」
本当の母が、どんな顔をしていたか全く知らない。どんな性格の人だったかも、どんな声で話すのかも。でも、父と母をきっと許してくれると信じてみる。
「比嘉さん、お願いします。父と母を許してください。」
僕は深々と頭を下げた。
⑦日が昇る四畳半
僕は裁判所の証言台にいる。
背後の傍聴席からの視線が、なんとなく怖い。こんなにたくさんの人に見られたのは初めてだ。少しだけ後ろを見ると比嘉さんと目があった。
比嘉さんは、父と母を許すと言ってくれた。でも、それには条件があった。僕が当事者として証言台に立って父と母がしてきたことをきちんと話すことだった。
「生駒秋芳さん、あなたは、18年前、生駒夫妻により、事故の現場から連れ去られていますが、その頃のことは覚えていますか。」
弁護人から質問を受ける。これは、事前の打ち合わせをしていた。たしか、覚えていないと正直に言っていい質問だ。
「覚えていません」
「では、質問を変えます。監禁や暴行を受けた記憶は?」
「ありません。」
傍聴席が騒がしくなる。洗脳されてるとか、嘘言わされてるとか。そんな声が聞こえてくる。
「では、生駒夫妻からあなたがされたことで、記憶に残っている嫌なことは。」
「ありません。」
「では、命の危険を感じたことは。」
「ありません。」
僕は、ずっと、ありませんしか言ってない。
「裁判官、このようなことから被告は、…連れ去り略取 誘拐を行ったものの、当事者に対し、明らかな損害を与えたものではありません。よって、負傷した児童を保護し、保護者が現れるまで安全を確保し続けたと言えると考えます。」
傍聴席が騒がしくなる。ふざけんなとか、世間を舐めんなとか、そんな言葉が飛び交っている。僕はこれで良い。父と母が無罪になれば良い。早く終わってほしい。
「裁判官。意義を申し立てます」
検察官が、手を挙げた。
「被告側の弁護人の質問は、極めて抽象的であり、当事者である秋芳さんの具体的な話が全く聞けていません。私からも質問よろしいでしょうか。」
裁判官が許可をする。僕はこの人とは何も打ち合わせをしていない。
「簡単な質問です。あなたはいつから、生駒夫妻からお父さん、お母さんと呼ばされていますか?」
そんなの、わからない。気がついたらそうだった。
「答えられない?」
言葉が何も出てこない。
「なぜ、“保護された”と思い込んでいるんですか。」
質問に答えられない。
「あなたがされたことは、紛れもなく誘拐です。あなたが意識を失っていたのは生駒夫妻にとって好都合だったと言えるでしょう。当時、あなたを診察した医師によれば、あなたには記憶障害があった。母親と父親の顔を見ても反応がなかったそうです。2歳の子どもが、全くの他人に何か反応すると思いますか?ただ、あなたは、自分の名前や年齢なども言えなかったことから、医師は記憶障害と、診断したそうです。」
そんなこと、今聞かされてもわかるわけがない。
「ここから、生駒夫妻からあなたへ洗脳が始まったと考えられるでしょう。自分たちを、お父さん、お母さんと呼ばせ、あなたを養子にし、さも普通の家族のようにして、あなたを支配下においた。立派な拐取ではないですか?それでも、保護されただけと言えますか?」
なんて言えば良い?どうすれば良い?
被告人席の父と母を見た。僕に申し訳なさそうな顔をしている。そんな顔見たくない。もっと堂々としてほしい。何も悪いことやってない。僕を18年、ずっと育てて、反抗期も高校受験も、大学受験もずっと、ずっと支えてくれて味方になってくれたのは父と母なんだ。
今度は、僕が…僕が味方にならないと。
本当の親じゃない。でも、親だ。家族だ。考えろ、なんて言えば良い。なんて発言すれば僕は2人の家族でいつづけられるんだ。出てこい言葉。おじいが読解してくれた本…思い出せ…心、気持ち、今の僕の中にある言葉……なんでも良いガチャガチャみたいに出てこいっ!
「……親ガチャってあるじゃないですか。」
僕の口から思ってもない言葉が出た。ちょっとあせるけど、落ち着いたふりをする。
「僕、大当たりしたなって。」
検察官が、
「質問に答えてください。」
って詰めてくる。
「答えてます。……たぶん、多分ですけど、救急車待ってたら、僕、死んでたかもしれない…ですよね?てことは、助かる方法で助けてくれたってことですよね?え?なんかダメなんですか?」
傍聴席から、どよめきが起こった。アタオカじゃね?とか、イカれてるとか。それ、お前らじゃん暇人。って軽口叩きそうな気分をグッと押し殺した。
「ずっと、優しくしてもらってました。父にも母にも。僕がイライラして八つ当たりして二人とぶつかっても。必ず受け入れてくれました。だから、世間がどう思うかは知らないけど、僕の親ガチャは大当たりでした。これからも、僕は父と母と家族でいたいです。」
父と母に目を向けた。母は涙を流していて、父は真っ直ぐに僕を見ていた。
「いつもありがとう。こんなことしか言えなくてごめんね。」
傍聴席が、ずっとうるさくて、後ろを見れなくて比嘉さんの様子を伺えなかった。どう思っただろう。約束を守ってくれるだろうか。
裁判が終わって結果が出た。
父と母の罪は略取 誘拐罪。無罪にはならなかったものの、執行猶予がついた。でも、実家への嫌がらせはやむことがなく、防犯カメラを設置して、証拠として警察に届け出た。早く嫌がらせが終わってほしい。父と母が、帰ってくるから少しの間だけバイトを休んで実家に泊まり家の周りと中を片付け続けた。窓ガラスは直すのには時間がかかるから、まだガムテープを貼ったままの状態だ。
比嘉さんも時々、うちの様子を見ては、一緒に掃除を手伝ってくれる。
「イタチごっこってやつですよね、コレ。」
「早く飽きてくれればいいけどな。」
比嘉さんとは昔の話をしたり、大学の話をしたり。僕の将来を一緒に考えたり。それに、比嘉さんの持病の話も少しだけ。そんなに悪い病気じゃなくて、様子を見れば良いらしい。比嘉さんが病院の診察券を見せてくれた。ずっと、根気よく通ってるからボロボロだって、そう言った。
比嘉さんの下の名前は東生(のぼる)で、初めて名前を知った。
久しぶりのバイトの帰り、秋夜さんと2人でバーに来た。
僕が裁判で頑張ったからって、ご褒美らしい。何も頑張っていないから、なんだか申し訳ない。
「お父さんお母さん帰ってくるのはいつ?」
「明日の…僕が学校の時間です。」
「これからは実家にちょこちょこ帰ってあげなよ。」
頭をわしゃわしゃされた。
「…なんか、いない時行くのは良いけど、いる時に行くのは急にどうしたの?って感じしませんか?」
「良いじゃん、実家でしょ?」
「んー…。」
「ん?」
「いや…。」
「俺も行って良い?」
「え」
「あきの実家。」
「ダメです。絶対ダメです!」
「じゃあ、アパートは?」
「ダメに決まってます!」
「なんで?」
「散らかってるから。本当にダメです。秋夜さん家みたいなカッコいい部屋じゃないし。お見せできません!」
「……つまんないなー。」
「つまんなくありません!」
「なんて?」
顔を近づけてくるから、胸がドキドキしてくる。
「近い!」
「良いじゃん」
絶対に酔ってるから、この人酔ってるから!
「あき…って。」
「え」
「やっぱかわいいな。」
恥ずかしくて照れ臭くてどうして良いかわからない。
「あき、今日ウチに持って帰るね。良いよね。」
「え、そんなの聞いてないですよ。」
僕は、親のことで大変だったけど、この人の言葉に救われたのを思い出す。その時に大好きだって言ったことも。
「あき、俺のこと大好きなんだよね。」
耳元で言われるから、息がかかって背筋がゾクゾクする。だけど、僕はやっぱり秋夜さんを受け入れていて、その場から離れようとは思わない。
「あき、まだまだ多分大変だけど、なんかあったら頼って良いからね。」
「…ありがとうございます。」
「アパートの部屋、掃除してあげようか?」
「大丈夫です、それは。」
「そう。…困ってないの?」
「それは困ってないです。」
僕のアパートは、とても狭い。
東向きに窓があって、日中でもまあまあ暗い。だから、あんまり人を呼びくない。どうせ日中は使わないから選んだ部屋だし。だけど、お風呂とトイレは別々だ。そこそこ綺麗でまあまあ広い。そこは自慢できる。
でも、朝日がよく見えるのは気に入っている。
子どもの頃おじいがいた四畳半を思い出すから。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
