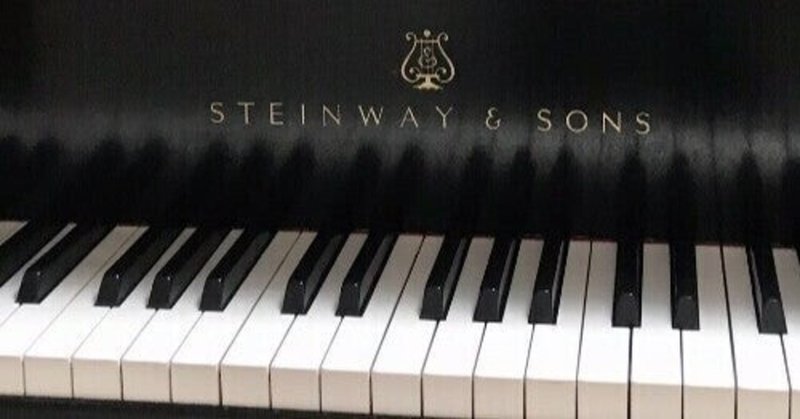
外山雄三を讃えて#17 ブーニンとのモーツァルト、ショパン
(これはときどき私が出すクラシック音楽ネタです。マニアックです。それでもよいと思われるかたはどうぞお読みくださいませ…)
この「外山雄三を讃えて」というシリーズも、果たして今は何回目なのかわからなくなりました。2021年6月に16回目を書いているのをいま確認しましたので、おそらく17回目かと思うのですが、もうどうでもいいです。今回は、私が学生時代から聴き続けているCDのご紹介です。スタニスラフ・ブーニンのピアノ、外山雄三指揮、NHK交響楽団によるモーツァルトのピアノ協奏曲第23番とショパンのピアノ協奏曲第1番です。われわれの学生時代は生演奏を除くとCDかラジオなどを聴くしかなく、しかも外山雄三のCDなどというものは限られており、このようなものも繰り返し聴いたのです。でもこのCDは「当たり」でありまして、いまも繰り返し聴く、いいやつです。
これは1986年8月8日の昭和女子大学人見記念講堂でのライヴ録音であり、プログラムからして最初に序曲などが演奏された可能性はあると思いますが、なにしろブーニンが主役の録音ですから「外山雄三を讃えて」というシリーズで取り上げるのもアレかなと思いながらのご紹介です。
当時、ブーニンは19歳と書いてあります。ジャケットはブーニンがピアノを弾いているところですが、19歳には見えず、もっと老けて見えます。もっとも外国人の年齢はよくわかりませんけれども。これから35年が経ち、ブーニンが独自路線みたいなのを歩んでいるらしいことはなんとなく知っています。たまに聴く演奏が、かなり独自路線だったりしますね。その片鱗はこの演奏からもうかがえます。
とくにモーツァルトの協奏曲ですね。ピアノの先生が「モーツァルトをぜったいにそういうふうには弾いてはいけない」と言いそうな弾き方をことごとくしているという演奏で、「自由に、やりたいように弾いている」という感じの演奏です。それで、不自然な感じはしません。まだブーニンも19歳で、「独自路線がほどほど」だった感じに聴こえますね。私は熱心なブーニンの聴き手ではありませんが、このモーツァルトは好ましいものに聴こえています。
オーケストラはかなり情けないです。第2楽章でのフルートの1拍間違えと、その復帰のしかたの非音楽的なことは情けないです。このフルーティストの名前はたぶん挙げられるのですが、もちろんやめておきますね。第1楽章のホルンのクライマックスでのハイE(高いミ)を出すところも外しております。以下のは想像に過ぎませんが、こういうところで厳しい外山雄三がここでホルンをにらみ「外すなよ!」と圧をかけて、かえってホルンは緊張して外した、ということも考えられます。こういうとき、外山雄三はプレッシャーをかけるので、オーケストラが萎縮しているのではないかと思う演奏がときどきあります。オーケストラをうまく乗せて演奏させるストコフスキーとの違いがあります。それぞれの良さですが、オーケストラプレイヤーとしてはストコフスキー・タイプの指揮者のほうがありがたいですよね…。以上、単なる想像でしたが、当たらずとも遠からずではないかと思います。
ショパンのほうは、ブーニンの独自路線はさっきのモーツァルトほどではないように思え(ただし私はこのCDを聴きすぎてショパンの協奏曲第1番はこの演奏が基準になってしまっているのもあると思いますが)、しかし、非常に聴きごたえがあります。外山雄三のつけかたも、なるほどと思わされる面もあり、さすがという感じです。
さきほども書きましたが、オーケストラは頼りなく、どうも1980年代のN響は、ほかの録音を聴いても、あまりうまくなかったらしいことがわかります。同じ時期では、都響(東京都交響楽団)がずっとうまいですね。
なお、YouTubeには、ブーニンと外山雄三指揮のピアノ協奏曲の、お世辞もいいとは言えない演奏がアップロードされていたりしますので、そういうのはご覧にならないでいただきたく思います(笑)。
ほんとうに駄文でごめんなさい。このへんまでです。失礼いたしました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
